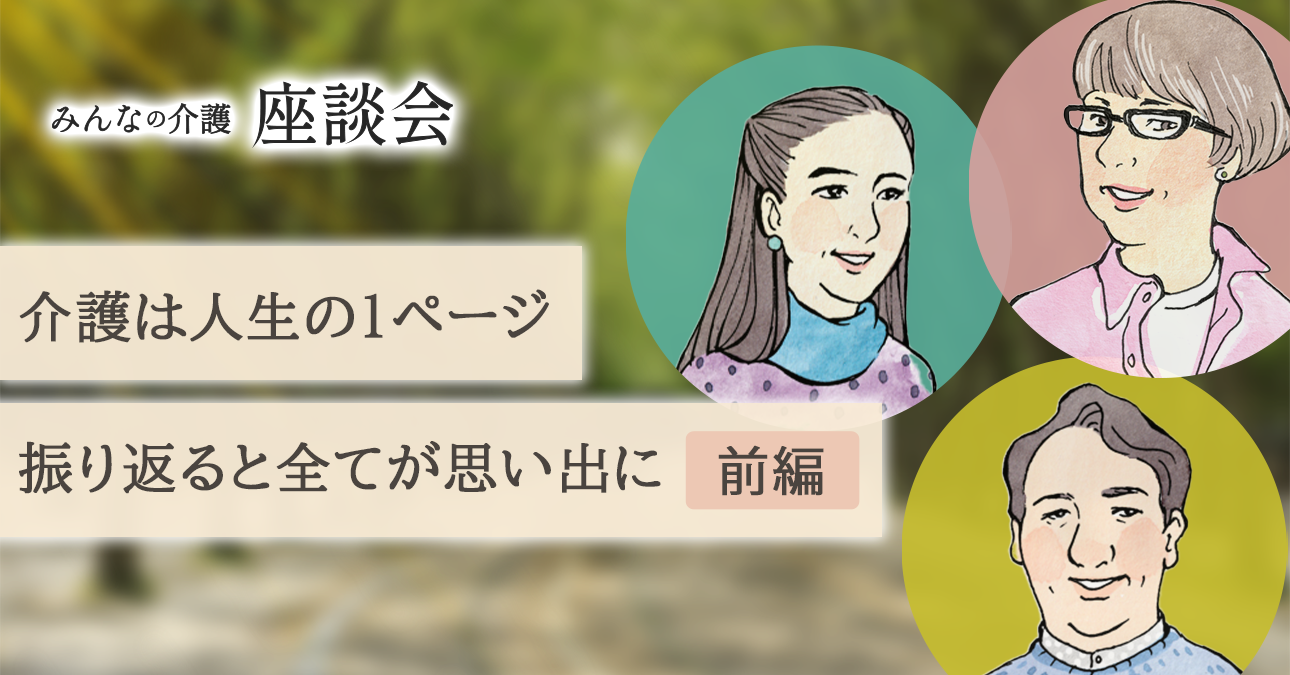
今回のテーマは「家族回」。介護に家族で向き合ったある一家の皆さまにお越しいただきました。今後の介護のあり方について参考になるかもしれません。
この記事に登場するみなさんのプロフィール(敬称略)
義母が亡くなるまで、主な介護者として在宅介護をしていた。同居する孫も含めた多世代家族をリードする存在で、義母の介護も家族一丸となって取り組むような家庭を築く。介護をしていた期間にはいろいろと“思うこと”もあったが、今となっては良い思い出になっている。
会社員。生まれたときから祖母と暮らし、共働きの両親の代わりに面倒も見てもらっていた。祖母の介護が始まると長男の立場から、祖母の意見、父の意見、母の意見を聞くことが多くなる。祖母の介護生活のときは、仕事が多忙で休むことが難しく、祖母が亡くなってから「もっといろいろしてあげたかった」と後悔を感じている。会社勤めでも介護にもっと専念できる「システム」が必要だと考えている。
ライター。通所デイサービスで介護職員として勤務していた経験を活かし、介護・福祉系のライターとして活動中。15年前に脳梗塞で左麻痺になった自身の父や、認知症になった義祖母の自宅での生活のサポートをする。在宅介護で経験したことや、母や夫の家族の悩みや話を聞くうちに、家族を介護することは「介護者の気持ちに寄り添うこと」も必要だと強く感じるようになる。
介護生活が始まったときのこと
みんなの介護(以下、―――)
ご家族で介護のご経験をされた「佐山さんご一家」にお集まりいただきました。
佐山さんにとっては義母、ひろしさんにとっては祖母、あけみさんにとっては義祖母である、としえさんのお話を主にお伺いできればと思います。
まずは自己紹介をお願いできますか。

佐山
佐山です。結婚生活と同時に義母と一緒に暮らすようになりました。
あるとき、お義母さんが介護が必要となるほどのケガをしてしまい、要介護3の認定を受けました。それからはデイサービスを利用するようになり、92歳で検査入院先の病院で亡くなるまで在宅介護をしてきました。80歳ぐらいから認知症の症状が見られるようになりましたが、私も認知症の知識がないし、どうしていいのか分からなくて……。周囲の協力を得ながら介護生活を続けていました。
お義母さんが認知症になる前は、ケガや病気で入退院を繰り返していましたが、しばらくしてから話していると「あれ?」と思うことがあったり、お母さんの行動面に違和感を覚えることがあったりするように。
病院で検査をしたら、認知症と診断されたんです。とつぜん認知症になったわけではなく、“徐々”に症状が見られるようになっていました。
舅姑との同居生活は、佐山さんが結婚されたと同時に始まりました。結婚してからは同じ屋根の下で暮らし、自分の親よりも長い時間生活を共にしてきました。
約15年間、デイサービスを利用しながら佐山さんが姑さんの介護をしてきたそうです。
――― ありがとうございます。ひろしさん、自己紹介をお願いできますか。

ひろし
52歳、会社員です。母が言うように、祖母の認知症は徐々に始まりました。当時、祖母の様子がおかしいと思っていましたが、仕事の忙しさから「家」のことはノータッチだったので、いつから認知症になったかという記憶があいまいです。
あるときから物忘れなどが激しくなってきて、おかしなことやつじつまが合わないことを言い始めたり。たぶん、足のケガをして入退院を繰り返したことも、認知症が進んだ原因の一つなのかな、と思っています。

佐山
転倒して足を骨折したときから、お義母さんの介護が始まったよね。
家族で食事をしていた飲食店で転倒してしまい、救急車で病院に救急搬送してもらったんです。そこから、入退院を繰り返す日々が始まりました。自宅から病院までは距離があったんですが、家族や親類などみんなで「ほぼ毎日」お見舞いにも行ったんですよ。
佐山さんのお義母さんの転倒による骨折から始まった介護生活。自宅から片道2時間ぐらいかかる場所の飲食店での出来事だったそうです。救急搬送先の病院で、お義母さんの入院が決まりました。退院するまでの約1カ月間、飲食店の近くの病院に毎日、往復4時間かけてお見舞いに行っていたそうです。仕事が忙しかったひろしさんも時間を見つけ、何回も車でお見舞いに行ったそうです。
――― ありがとうございます。それではあけみさん、自己紹介をお願いします。
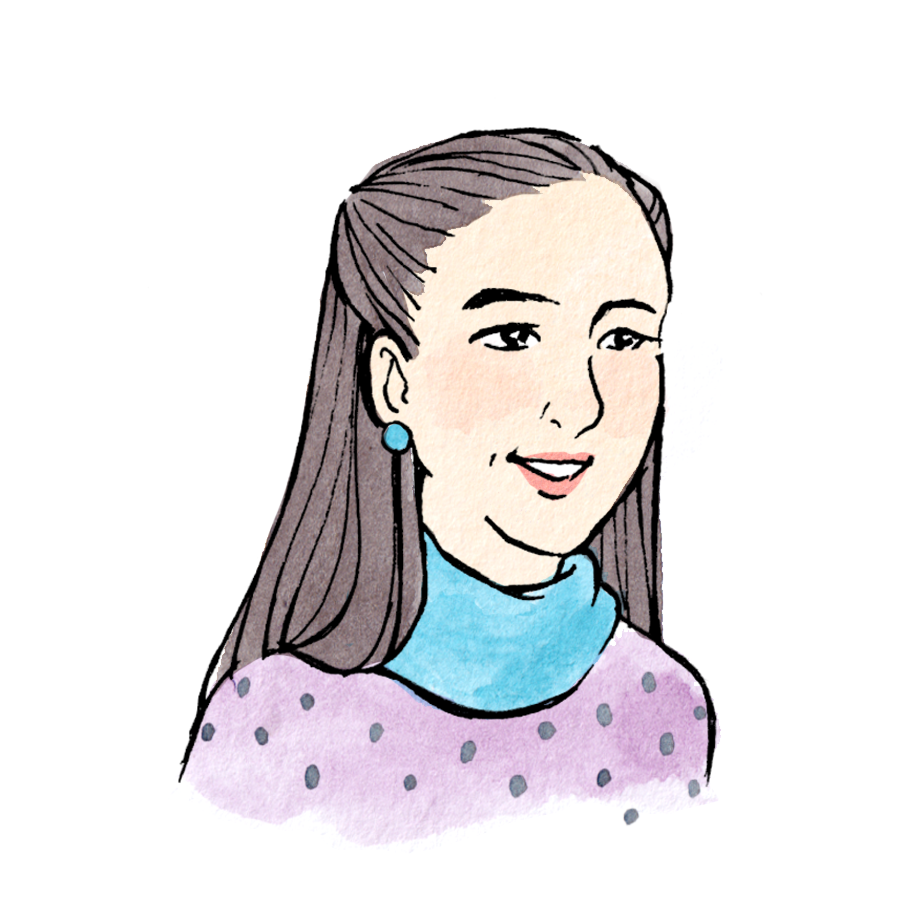
あけみ
ひろしの嫁のあけみです。嫁ぐ前は、デイサービスで職員として勤務していました。結婚してからはずっと、夫の実家で同居をしています。夫の祖母である「おばあちゃん」に私が出会ったときは88歳でした。
デイサービスで勤務していたときには、「おばあちゃん」よりも若い方でも歩行が難しい車椅子の方やトイレで立ち上がるにも職員の介助が必要な方もおられました。「おばあちゃん」と私が出会ったときは入浴以外ほぼ一人で自立してなさっていたんです。手先も器用な方だったから、認知症を患っていても進行はゆっくりだったのかもしれません。
結婚される前は、都内で介護のお仕事をされてきたあけみさん。義祖母が認知症を患っていても、「とてもしっかりしている」と思ったそうです。あけみさんがお子さんを妊娠しているときには、前職の経験を活かして手先が器用な義祖母と折り紙や手芸などして過ごしていたそうです。
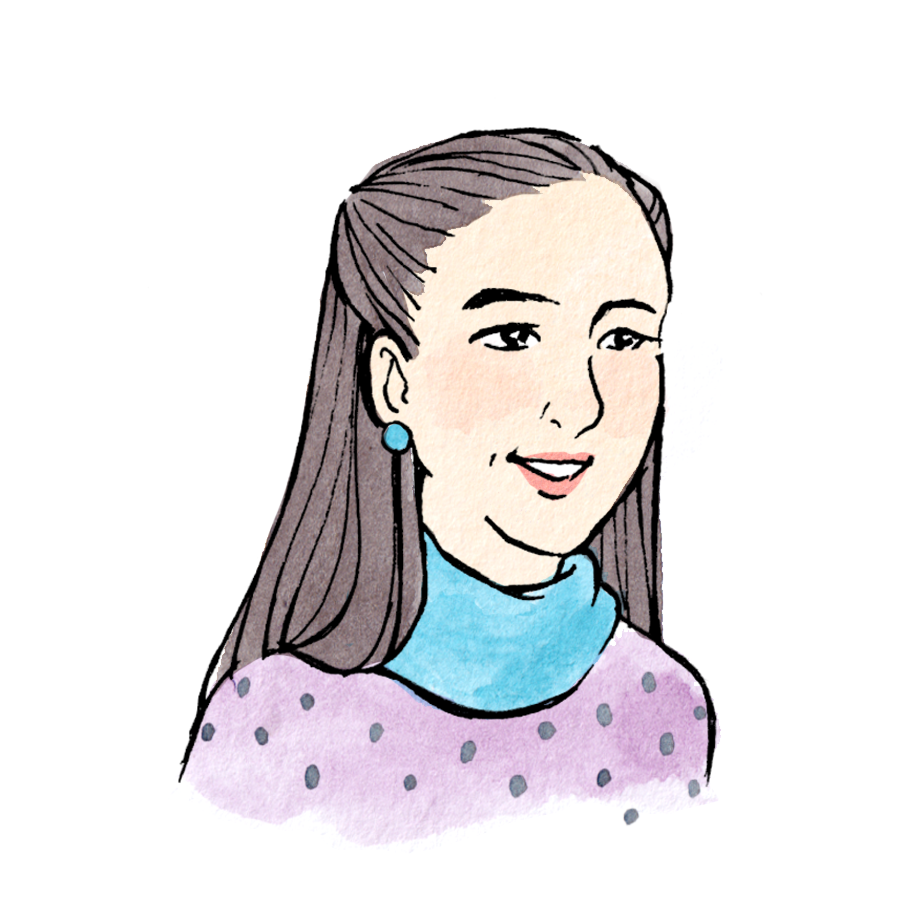
あけみ
「おばあちゃん」も転倒したときのケガから介護生活が始まりましたが、私の実家の父もそうでした。もともと左半分麻痺の体でしたが、自立して歩行はできていました。ですが去年、自宅のトイレに行った際に転倒してしまって。かかりつけの総合病院に行って、念のためにケガ以外も検査をしたら水頭症の診断を受けて即入院。
実家までは距離があるので、電話で父と一緒に暮らす母からいろいろ話を聞きました。母によると、よく失禁もしていたようで水頭症の症状があったようです。
認知症の原因となる疾患の特発性正常圧水頭症は、頭に脳脊髄液が溜まる病気です。溜まった脳脊髄液は脳を圧迫し、さまざまな病気の症状がでてきます。
――― お父さまは水頭症の手術をされたのでしょうか。
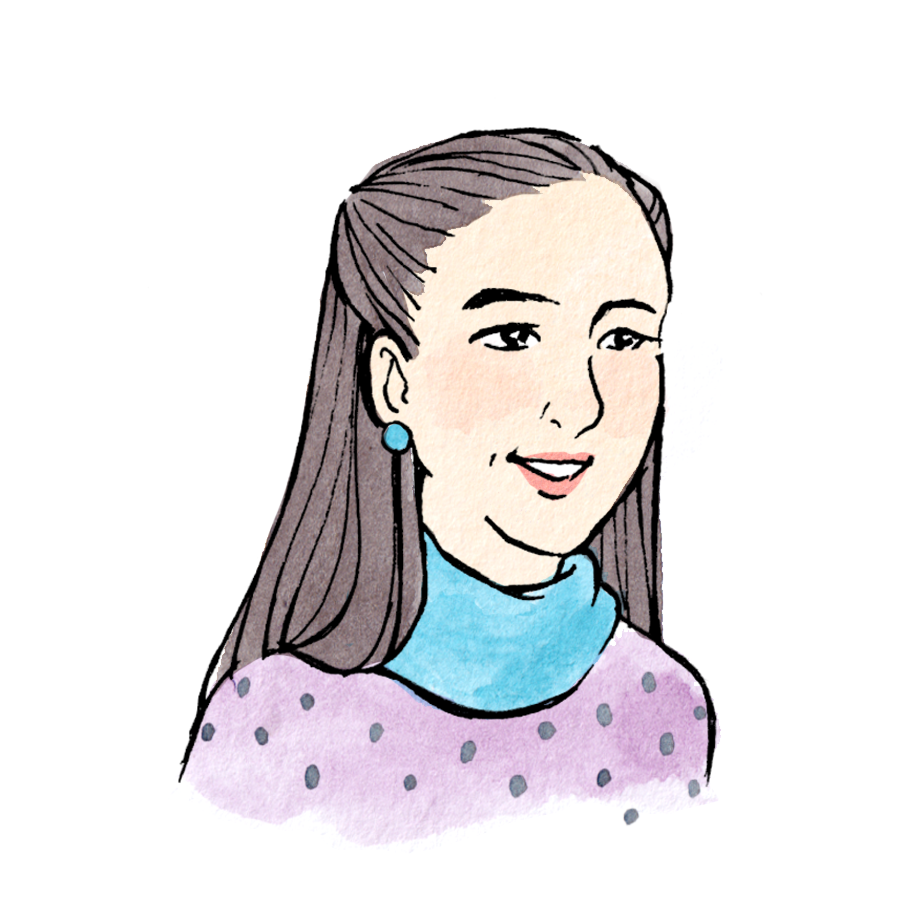
あけみ
はい。手術は2時間にも及び、無事に終わりました。要介護認定4の診断を受け、週に2回リハビリ付きのデイサービスを利用するようになりました。ですが術後は歩行も遅くなり、物忘れもひどくなったようです。母が「ここに座って待っていてね」と言ってもすぐに歩き回ってしまい、目が離せないと電話でよくこぼしていました。
退院後は父の介護のサポートは母以外に一緒に暮らしていた兄もしていました。再び退院してから1カ月後、父は入院しました。脳以外にも肝臓、腎臓の状態も悪化し、父は私が想像していたよりも悪い状態だったようです。
息子に会いに素足で1Kmも歩いたとしえさん
――― としえさんがケガで入院をされた後のお話をお伺えますか。

佐山
ケガで入院して1カ月後には、自宅近くの病院に転院し入院していました。入院しながら足のリハビリを受けていました。ケガをしてしまいましたが、当時まだ70代後半だったこともあり、退院してからの介護も大変ではありませんでした。

ひろし
ケガをきっかけに、入退院を繰り返すことが増えて認知症も進行していました。そこからの介護の日々は、祖母と一緒にいる時間が長い家族は大変だったと思います。
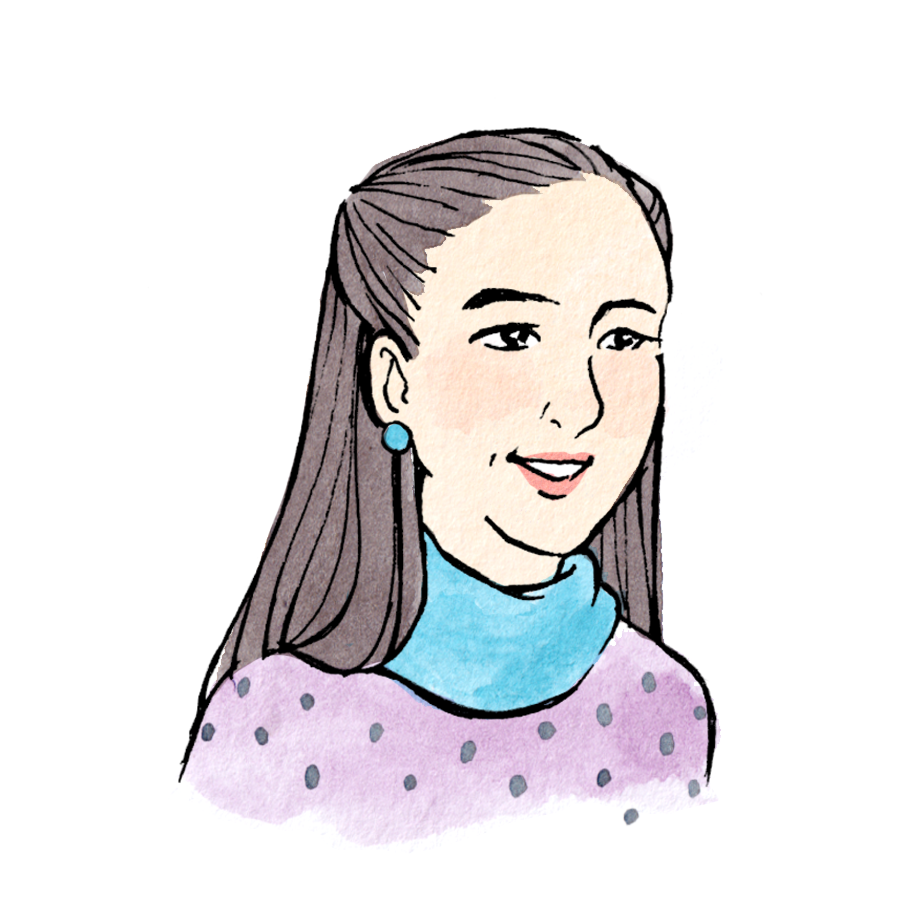
あけみ
私が嫁ぐ前のことですが、80代前半で認知症を患ったばかりの頃は、足腰がしっかりしていたと思うので大変なこともあったのかなと思います。
――― 大変だったと感じられたことをお聞かせください。

佐山
そうですね。目を少し離した隙にお義母さんが、夫の兄弟でお義母さんの末っ子でもあるお宅に歩いて行ってしまって……。靴をはかずに行ったのか、途中で脱いでしまったのかはわかりませんが、「素足」でお宅に着いたようです。ご家族の方に足を洗ってもらったそうで。
田んぼ道もあるけど、大きなトラックも通る道路もあるから道中、事故に合わなくて本当によかった。お義母さんにとって、一番末の子供だから、心配になったのかもね。
自宅から1km以上ある道路を靴をはかずに、自身のお子さまのご自宅に突然歩いて出かけてしまったとしえさん。「一人歩き」する方の事故やケガが増加していますが、佐山さんがおっしゃるように、出かけてしまうことには理由があるのではないでしょうか。
「物盗られ妄想」と家族の対応
――― 「一人歩き」のほかに、認知症になってからの介護のエピソードを教えていただけますか。

ひろし
「お金がない」とか「自分の物がなくなった!」ってよく言っていたよね。そして、物を盗んだとされたのは、いつもお母さんだったよね。世話を焼いてくれて顔をよく合わせる間柄だからこそ、「物盗り犯」になっちゃうのかな。

佐山
そうなんだよ。いつも自分でお金なんかをしまっても、しまったことを忘れてしまったり、しまっていないのにしまったと思い込んでいたりして。ないことに気づくと、私はいつも犯人に仕立て上げられて……。認知症とわかっているから、あまり強くも言えない。だけど「お金は盗まれてないよ。自分でどこかにしまったのよ」と伝えても、私が盗んだとずっと思われていました。

ひろし
何度も犯人扱いされたんじゃ、祖母が脳の病気だとわかっていても、いい気分にはならないよね。特に、一番介護をしてきている身としては。
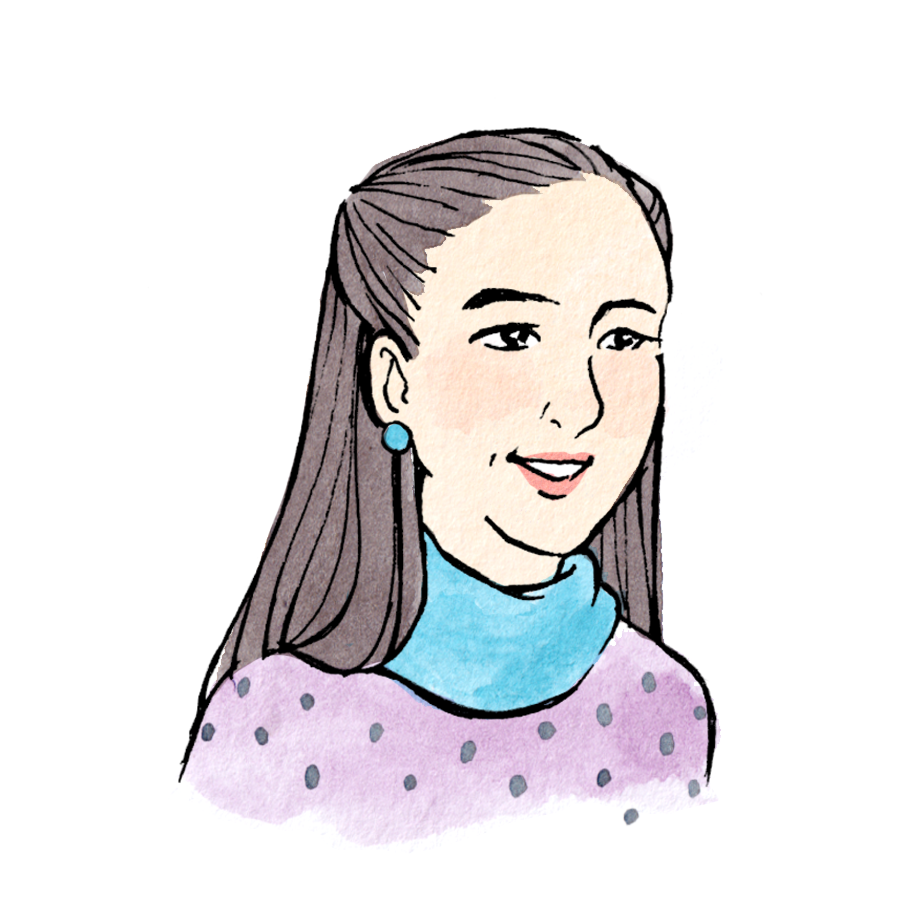
あけみ
私も「おばあちゃん」から「銀行の預金を息子夫婦に全部盗られた」とよく聞いていました。物盗られかなと、気楽に思いながら夫に「『おばあちゃん」がこんなこと話していたよ」と日常的に話していました。デイサービスでも認知症の方の「物盗られ」はよくあることだったので。
その次の日、おかあさんから「おばあちゃん」の物盗られのお話と説明を受けました。そうですよね、認知症の症状をよく知らないと「家族でお金を使い込んじゃったのかな……」と思われてもおかしくありませんよね。

ひろし
親戚とかいろんな人に「勝手にお金を引き出された」って話をしちゃうんだよ。認知症のことを知らない方が聞いたら、私たち家族がお金を下ろしていたり、盗んでいるように思われてしまって困りました。いろいろな方に言っていたようなので、訂正もできませんでした。

佐山
お金がない、通帳がない、印鑑がないということはよく言っていたよね。本人以外の人間がお金を引き出すこと自体そんなに簡単ではないのに。本人が同席しないと難しい場合もありますが、だからと言ってお義母さんの預金を下ろすことはなかったのよ。
2021年に高齢者の金融取引について金融機関の指針が打ち出されました。成年後見人制度を利用しなくても、銀行は認知症を患っている方の親族にも、限定的に引き出しに応じる考えになっています。
この指針が打ち出される以前は、それぞれの銀行で認知症の方の預金取引の対応が異なっていました。
としえさんの利用していた銀行では、認知症になったご本人と親族などが同席し、認知症になった経緯の説明といった「手間がかかる」手続きが必要だったそうです。
反対に、成年後見人以外の人は預金を下ろせないといった対応が厳しい銀行もありました。

ひろし
何回も犯人扱いをされて、何回も違うと言っても祖母が理解することは難しいし……。
――― 「物盗られ妄想」がみられるようなとき、どのような対応をしていましたか。

佐山
私に「盗られた」と言っているお義母さんは、自分でも認知症だからと理解しているけどね。何回も言われちゃうと私も感情的になっちゃうよね。強く言うとお義母さんも感情的になってしまうし。
ですから、お義母さんの話をとにかく聞くようにしたり、私を盗んだ犯人だと思い込んでいるときには、家族の別の者がお義母さんの対応をしていました。

ひろし
家族は人の物を盗ったりしないので、祖母が「ない」と言っている物を一緒に探してました。「何を探しているの?」と聞いても「アレがない、アレがない」と言って、祖母は一人でも探し続けてしまうので「今日はデイサービスに行ってきたの?」とか「テレビにタレントの〇〇さんが出るみたいだよ」というふうに他のことに意識を向けるように声をかけていました。

佐山
深夜になにかガタガタ音がするなと思って、お義母さんの所に行くとタンスを開けて探し物をしていたときもありました。「アレがない」と言って探しているときは、本人もアレが何かが分からなくなっているときもあるようです。
――― 大変な思いを当時はされていたようですが、他にもエピソードがありましたら伺えますか。

佐山
入退院を繰り返しているうちに、「息切れがする」とお義母さんが言い出したことがあって。病院で検査をしたら、タバコを吸っていた影響からか次第に肺も弱くなっていたようです。自宅でも在宅酸素療法を取り入れてました。自宅では酸素発生機といった機械を利用して酸素を送り、病院などに外出のときは携帯用の酸素ボンベを持って行きました。
外出時、ボンベの酸素や機械の電池の残量の確認は大変でした。ボンベ自体は業者の方が定期的に自宅に来てくださり、交換してくれるのですが、空気残量や携帯用の酸素ボンベの乾電池のチェックは自分たちがしなくてはいけなかったので。
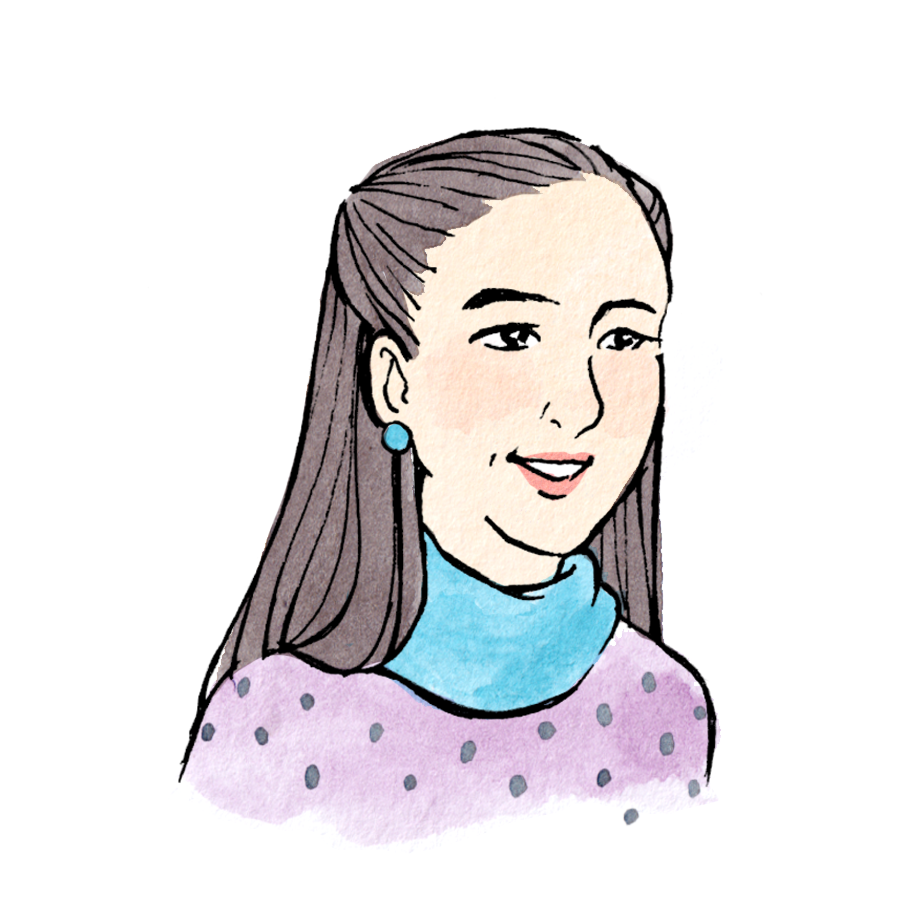
あけみ
私も病院に一緒に行ったのですが、携帯用のボンベのアラームを気にしていたことを覚えてます。おかあさんが、小まめにチェックしていたのが印象的でした。
あと、「おばあちゃん」は自宅ではトイレに一人で歩いて行っていたんですが、あるとき、鼻に付けている酸素を送るチューブを抜いてしまって。

佐山
酸素用のチューブは長く、おばあちゃんの部屋からトイレまで届くほどでした。トイレへ行くときにじゃまだったのか、お義母さんが取ってしまったようです。部屋に戻ってきて鼻にチューブを戻さずに寝てしまったこともありました。
気づいたときはチューブのチェックをしていたけど、ときどき「もう行くの?」と思うくらい頻繁にトイレへ行くときがありました。
20分〜30分位に一回の割合だったかな。そうなるとトイレに行くたびにチェックはできなくて……。チューブを抜いてしまって危ないからといってトイレではなく、お部屋にあるポータブルトイレの利用も考えましたが、自分で歩いてトイレに行けることもありポータブルトイレは利用したくなかったようでした。

ひろし
たぶん、漏らすのが嫌で「少ししたいな」と思うとチューブを抜いてトイレに行っていたんだろね。

佐山
そうみたい。普段は“リハパン”も履いていたし漏らしても大丈夫なんだけどね。気分的にそのままトイレに行かずに漏れるのは嫌だったみたいだね。
介護は一人で抱えなくていい
――― 介護中はさまざまな問題が起きたと思いますが、としえさんの認知症のことをどなたかに相談されましたか。

佐山
お義母さんの担当のケアマネージャーさんに相談したり、地域包括支援センターで相談にのってもらいました。地域包括支援センターとデイサービスが併設されていたからは相談後にお義母さんと一緒に帰宅したり、お義母さんがデイサービスに行っている間に相談しに行ってました。
地域包括支援センターの職員に相談して気持ちも軽くなった佐山さん。介護者の相談ができる場所が一つでもあると、心の支えになるようです。
――― 介護生活を「乗り越えられた」理由を教えていただけますか。

佐山
夫のお姉さんにも協力をしてもらっていたんです。お姉さんの自宅に1〜2カ月ぐらいお義母さんが宿泊したり、出かけるときに一緒に連れて行ってもらったりしました。食事だけ頂きに行ったりして、お義母さんもずっと家にいるより、気分転換になったようです。
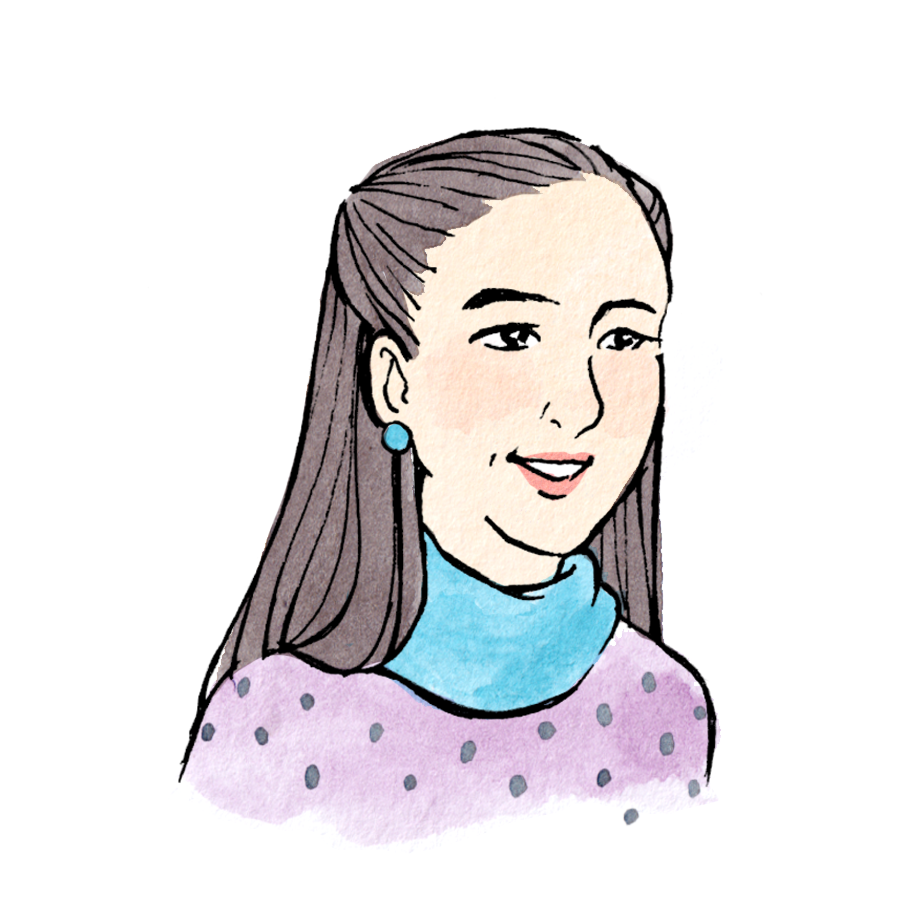
あけみ
私と夫で「おばあちゃん」をドライブに連れて行ったり、お花が好きだったので自宅近くのフラワーパークに行ったり、気分転換になることをしました。
出先では車いすでの移動もありましたが、とても喜んでいただけたようです。記念に撮った「おばあちゃん」と夫の二人が映ったツーショット写真を気に入ってくれたようで、今でも飾ってありますよ。

ひろし
親戚みんなの力を借りたり、我が家は妻が介護関係で仕事をしていたからできたこともあるのかもしれません。ですが、できないときには「できない」と言って、一人で頑張らなくてもいいんじゃないかなと思います。
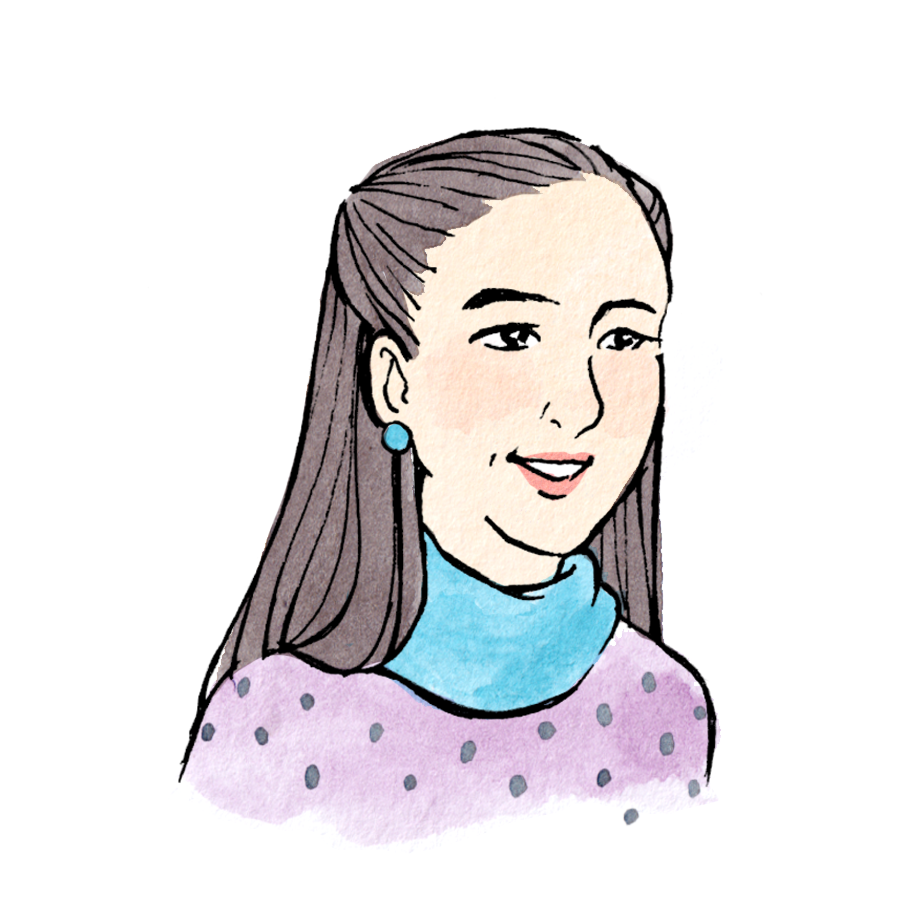
あけみ
たしかにそうですね。おかあさんは、そういう意味では周りの人の力を借りることが上手な方だと思います。私が嫁いでから、子供も生まれて総勢7人で暮らしていました。
家族の誰かが「おばあちゃん」を見守る中で、2歳だった子供も曽祖母と一緒に折り紙やお手玉をしたりしていました。多世代が集まる家庭の中で認知症の「おばあちゃん」も、ひ孫のお守りという仕事があって生活にハリが出たようです。そこに行きつくまで家族を引っ張っていったおかあさんは「さすがだな」と思いますね。
周囲の力を借りる。介護に限らず悩みがあると、一人で問題を抱え込むこともあります。佐山さんご一家のみなさんは、親戚の方も含め一丸となって、としえさんの介護と向き合ってこられたようです。
――― あけみさんは介護のお仕事をされてきたそうですが、自宅でご家族の介護をするのはどうでしたか。
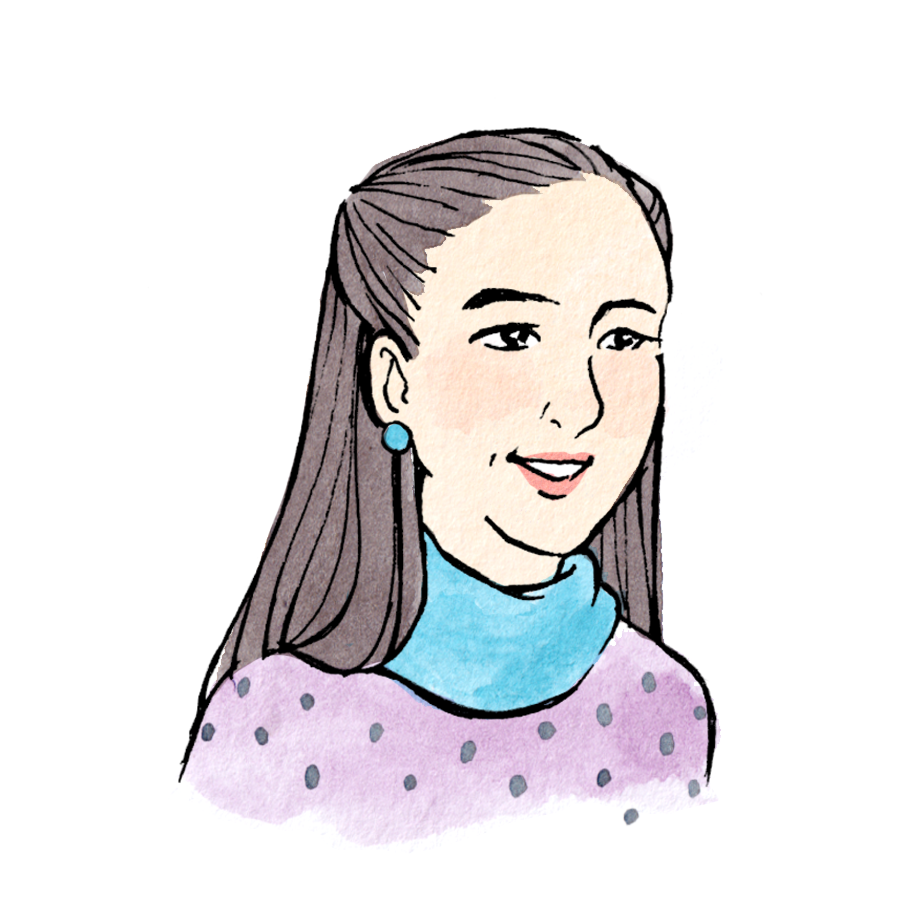
あけみ
デイサービスで介護の経験があり、自分でも経験があるし「大丈夫だろう」とは思っていました。
たしかに、介護の技術的なところは仕事での経験を活かせましたが、毎日を共にするとなると話はまた別ですね。デイサービスに通われている方は、自宅で見せる顔とは別の外の顔を持っているようです。自分と同じデイサービスに通われている方や、職員にも気を使われる方も多くいらっしゃいます。自宅だと介護者は自分の子供だったり、孫だったりしますよね。
認知症を患っているといっても、親、一番の年長者としてのプライドがあります。こちら側の話を聞いてくれないこともありますし、周りに説得されても感情的になってしまうこともありますよね。家族では納得しないことでも、第三者に言われて納得することも多くありましたよ。仕事で認知症の方や介護を必要とする方を見てきましたが、自分の家族に介護を必要とする者と一緒に生活することは別だなと感じました。
――― 第三者の意見で納得されたエピソードを教えてください。

ひろし
祖母が「入院したくない」とよくもらしていました。ですが、医師に「入院です」といわれると、おとなしく入院に同意していましたね。第三者の存在は大きいですよ。

佐山
お義母さんとは自分の親より長く接しているから、自分の子供のように接してもらいました。だからこそ、親のプライドが出て私と意見が衝突してしまうこともあったんだと思います。
頼れる存在が認知症になるということ
――― 頼れる存在のとしえさんが認知症になられたときどのように感じましたか。

ひろし
わたしが生まれてきたときから一緒に暮らしてきた頼れる存在の祖母。認知症になって一緒に話しをしていると会話がおかしくなったり、たまにですが「だれだっけ?」と私の顔を見て言われたときはショックでした。
話や行動面が普通のときは普通なんだけど、たまに「アレ?」と思うことがあったんですよね。仕事であまり介護に携われなかったのですが、なぜか家族の中では一番私のことを信頼して好いてくれていました。
父親の子供の頃と間違えて記憶していたりはしていましたね。妻に「ひろしは小さいころに家の畑でできた野菜を、売りに行ってくれた」と父の子供の頃の話なのに、私の体験のようにしてよく話していたそうですよ。
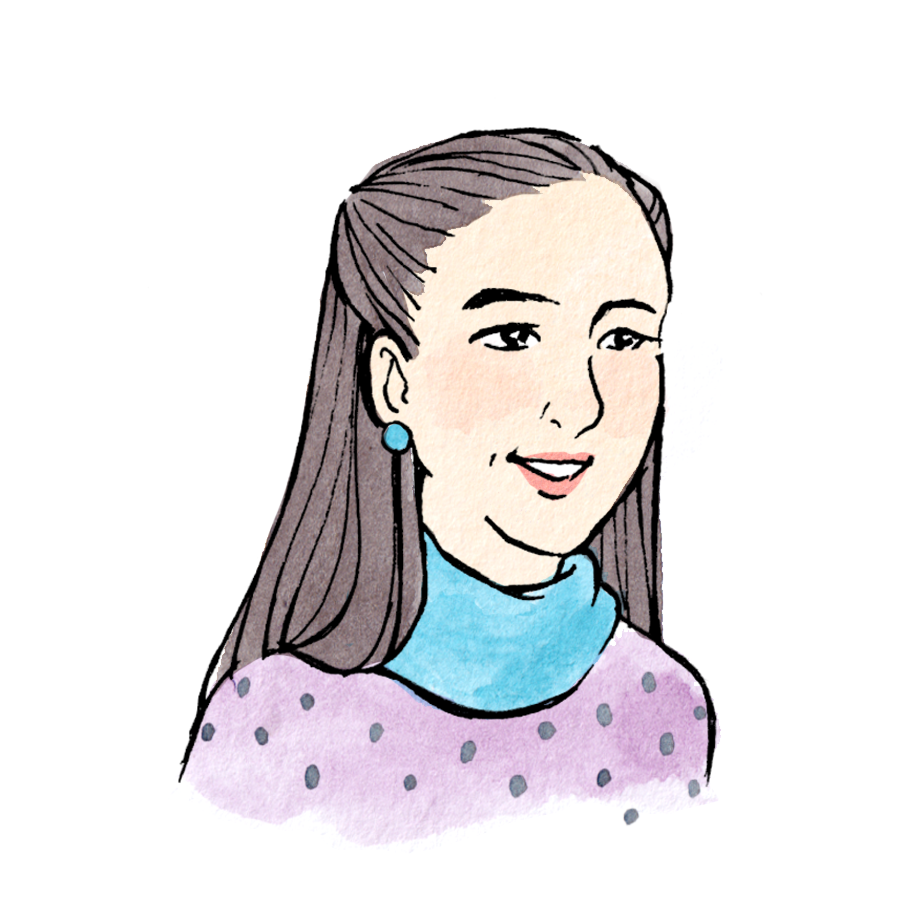
あけみ
「おばあちゃん」はよく「信用できるのはあのこだけだ」と夫のことをそう話していたものね。家族に物を盗られたり、預金を勝手に引き出されたと思っていたから夫が心のより所になっていたのかもしれません。「おばあちゃん」は介護生活が始まる以前は、ご自分でうどんやおそばを粉から打って作ったり、お魚もおろしてお刺身にしたりして家族に振舞っていたそうです。
夫も子供の頃、保育園まで「おばあちゃん」が運転するバイクに乗って登園していたそうなので、“行動派”でしっかりとしていた方が認知症を患ってしまったからこそのショックが夫にとって大きかったと思います。

佐山
私が嫁いだときは、お義母さんはまだ48歳という若いお姑さんでした。自営業を営んでいる家に嫁いだので仕事のことや、本家としてのあり方……いろいろなことを教えてもらいました。子供が全員成人になって子育てが終わり、やっとこれから自分の時間ができると思っていた矢先の介護生活。でも、お義母さんの症状は軽い方だったから、大変だと思ったことはないですよ。
お義母さんの母親はもっと大変だったみたいで、便をいじってしまったりいろいろあったようですし。

ひろし
ショックだったけど、祖母が認知症になって、自分にもできることはなにかないのかと考え始めました。でも、介護をすると言っても何ができるのか、何をしていいのか分からなかったんです。仕事も忙しく介護のことを勉強したり、調べたりすることができなかったです。
家族が介護を必要な状態になったら、一人で抱え込まずみんなで支え合いながらサポートをしてきた佐山さんご一家。
いつ起こるかわからない「家族の介護問題」。もしかしたら明日、急にサポートが必要になる方が家族から出てくるかもしれません。後編は、佐山さんの話を通して仕事と介護の両立などのお話をお聞きします。

取材・文:中島順子
「みんなの介護座談会」へご参加頂ける方を募集しています
「みんなの介護座談会」は読者の皆さまに参加して頂く新企画です。皆さまの日々の介護に対する思いをぜひ座談会で語ってください。
以下のフォームより、ご応募をお待ちしております。
参加フォームはこちらをクリックしてください



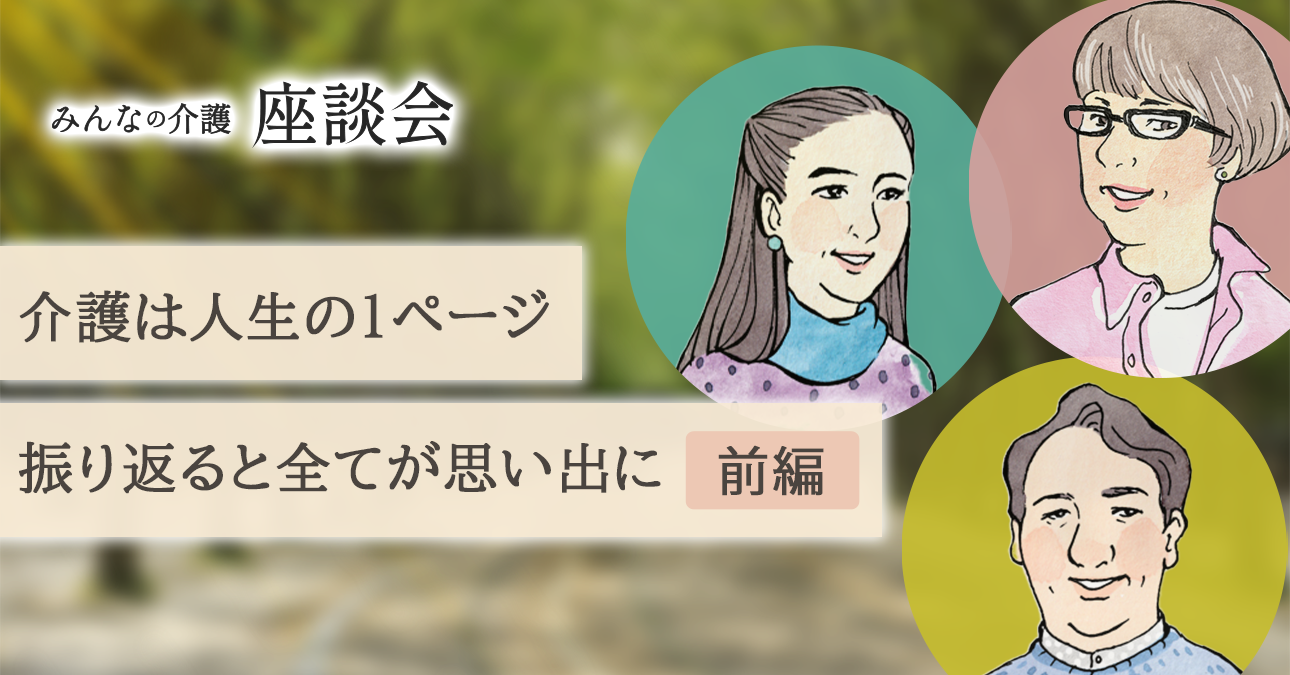
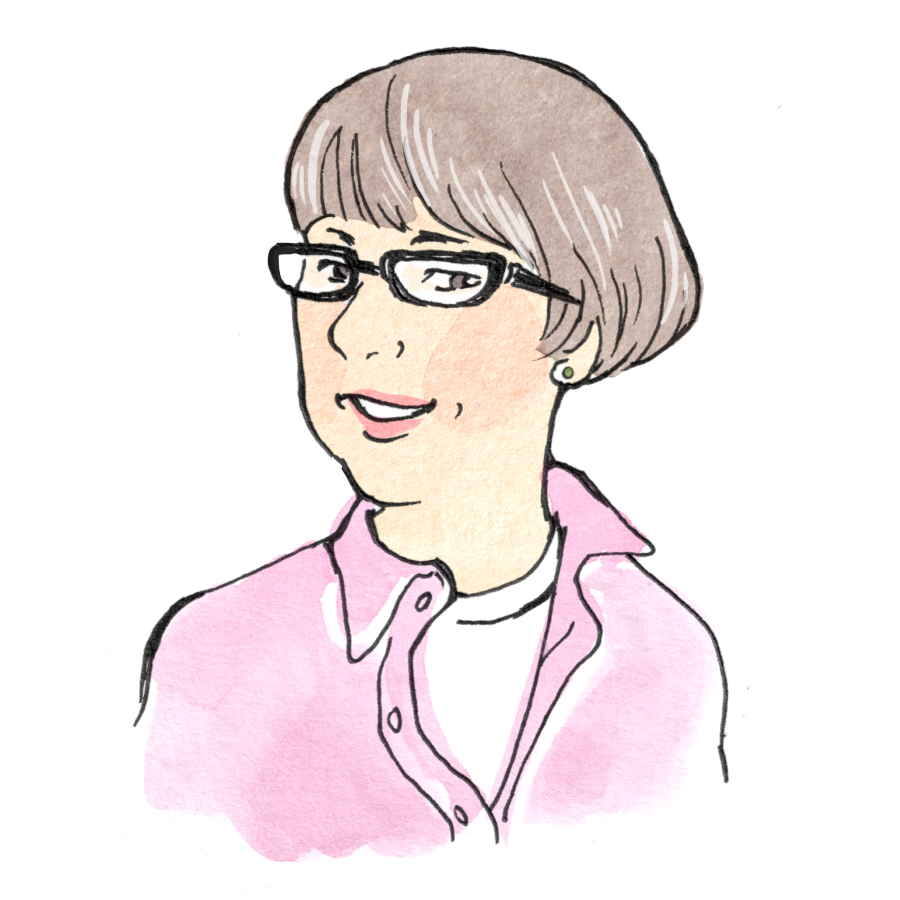
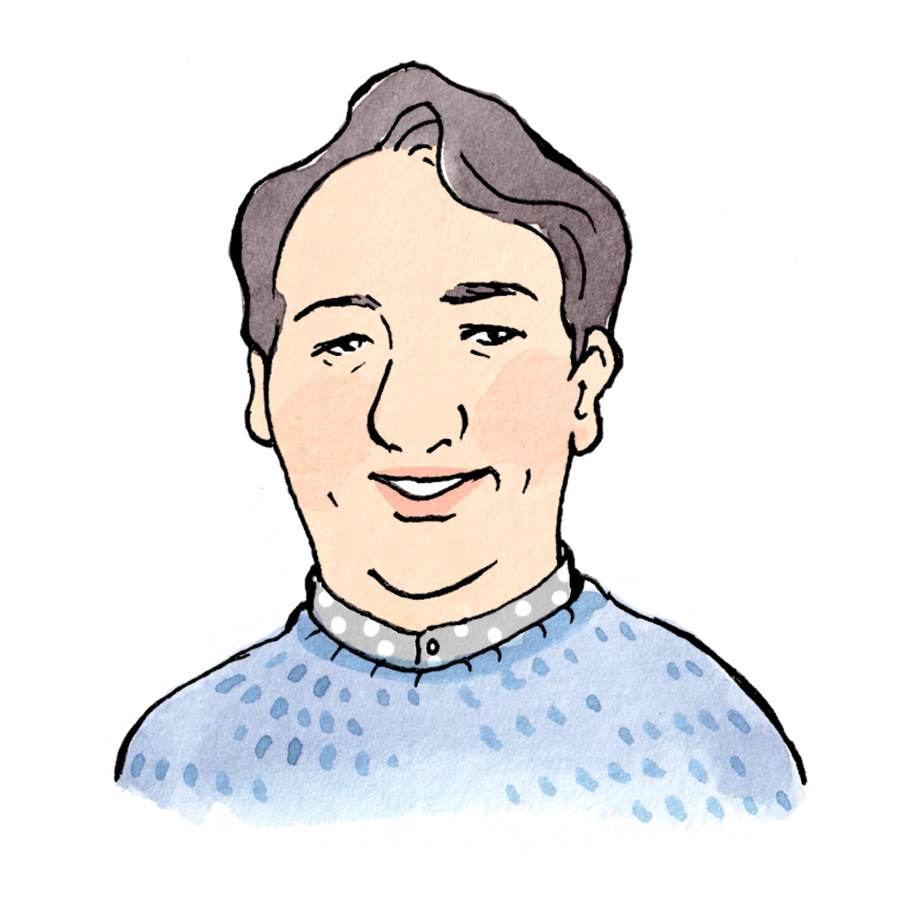
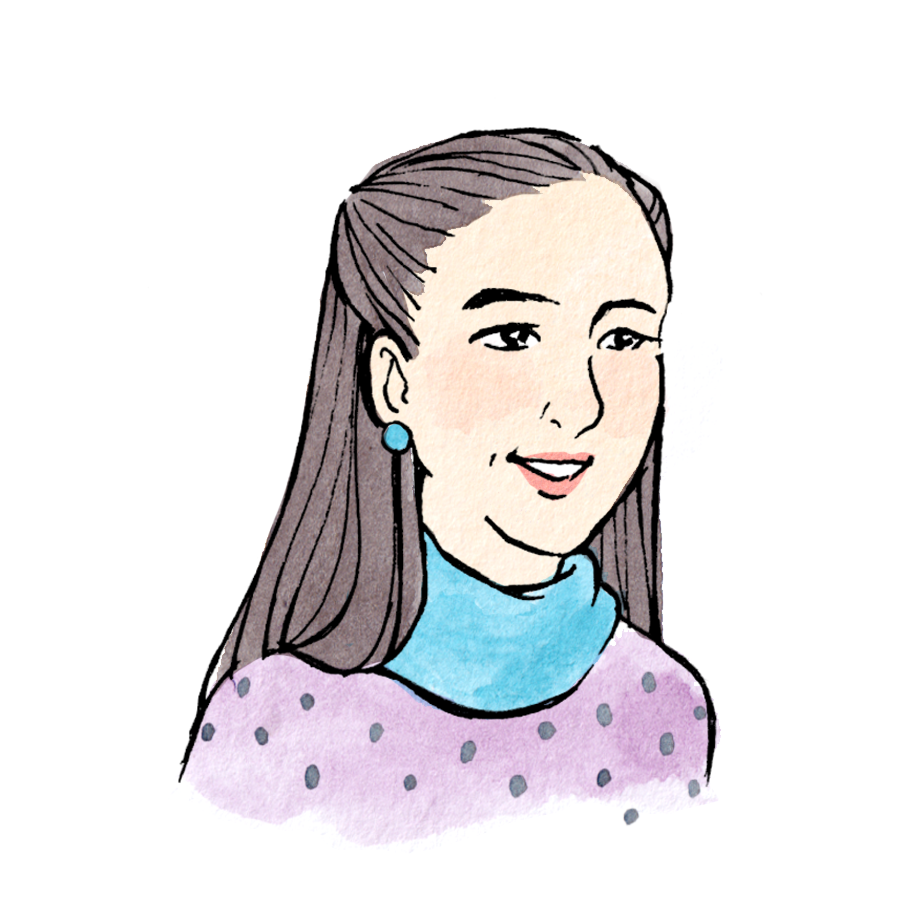
 佐山
佐山 ひろし
ひろし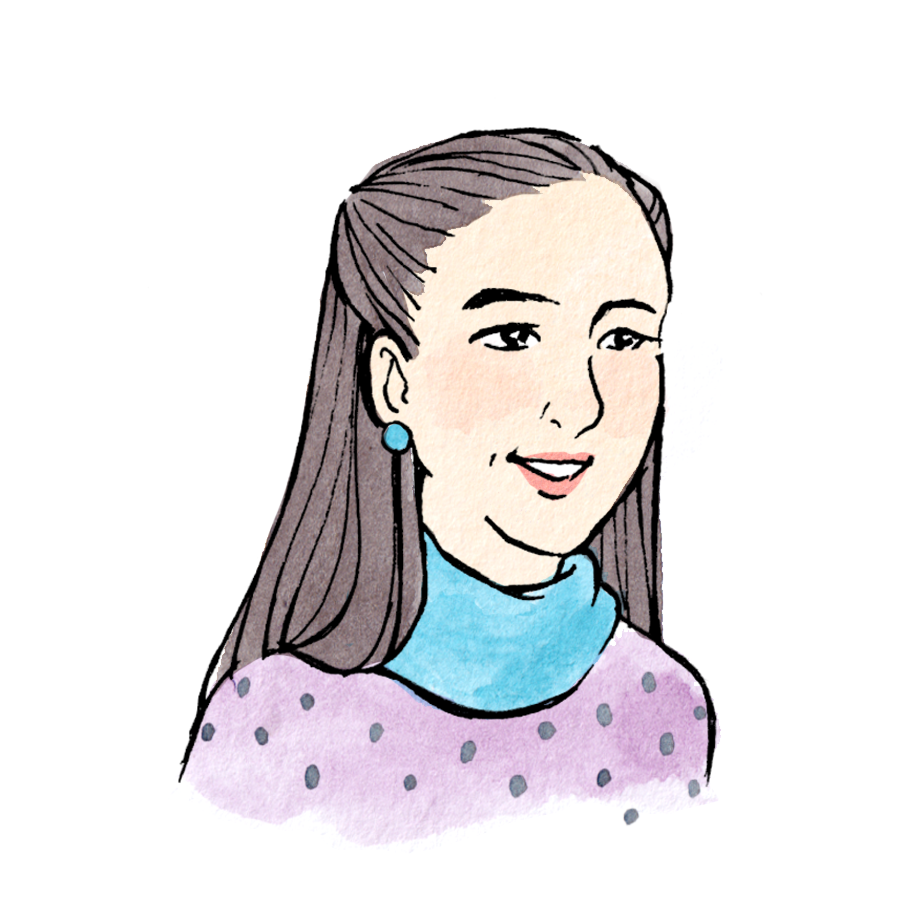 あけみ
あけみ