前編では、在宅介護の辛さやご苦労を伺いました。「血のつながった肉親なのに体に触れるのが辛い」……生々しい経験談に参加者みなさんが共感を寄せる場面もありました。後編では、施設入所についてもお聞きします。
この記事に登場するみなさんのプロフィール(敬称略)
50代のライター職。夫と2人の子供と実母と同居。実父を5年前、自宅で看取られた。実母は91歳、要介護1、認知症があり、週3回デイサービス、2ヶ月に1度2週間のショートステイを利用。
40代、医療事務のパート勤務。23年間母と同居。母は、3年前から転倒が増え2年前入院、要介護4が認定。母の認知症を認めない父の暴言が続き、昨年8月特養に入居。介護者の家族会にも定期的に参加されている。
50代、サービス付き高齢者住宅のフロント業務に従事。近隣で暮らす独居の祖母の在宅介護を実母と共に孫として支え、施設探しも行った。祖母(99歳・要介護4)は、有料老人ホームに入居し昨年施設でご逝去された。
入所を考えたタイミング
祖母の入居先探しをされたという高橋さん。プライドが高くてデイにさえ行けていなかったそうです。

高橋
母は自分ではなく、祖母を優先に考えて介護をしていました。周りから「もう限界だから施設だよ」と言われても、「私はまだやれている」と言っていた母。でも、結局、母が倒れてしまった。
母が倒れ、もう「まわらなく」なりました。これが入所の決め手です。
施設選びは「慌ててすると大変だった」と、高橋さんは当時を振り返ります。

高橋
祖母が転んでしまい入院することとなったのですが、リハビリ施設へ移る前に「今日明日中に、この数か所から決めてください」と病院から言われてしまいました。「1回見とこう」と、2つ施設を急いで見学しましたが、昼食の様子を見て「この施設はだめだな」と思いました。
食事にこだわる祖母。見学先の昼食は、魚肉ソーセージの炒め物。扉でなく、カーテンでオープンするトイレ……ちょっとにおったりする。スタッフからの挨拶もなく、施設にいらっしゃる方も覇気がなくてぼおっとされていた。
「ここに祖母を入れたら、さらに進むんじゃないか」と慌てて病院が選んだ施設ではなく自分たちで探しました。病院側に言われるがままではなく、自分の目で見なくてはと痛感しました。
――― 「見学」の重要性がわかります。

高橋
ただ私たちには、時間がありませんでした。母は「大変だから病院から言われたところに入れよう」と言いましたが、私はそばで見ていて「ほかにも施設はある、もうちょっと探そう」と母に助言し一緒に動きました。
結果、病院が選んだ施設じゃなく家の近くの見学済みの施設へ行ってもらいました。当事者である母は、病院側にあせらされてしまうと思考が止まってしまったんでしょうね。期日があるので、病院の言い分は分かる。でも家族としては、きちんと、自分の目で確認して納得できる施設を選んだ方がいいと思います。
「今」が一番落ち着いていると話す井下さん。在宅介護をいつまで続けようと考えているのでしょうか。

汚い処理は「女」がするもの

井下
母は、きつい時代を経て、今一番落ち着いている何年間です。まだ入所は考えていません。ただもう91歳。便はもれる。垂れ流しではないけど、間に合っていない。普通の布製パンツではだめで常時リハパンツです。痔もあり、下痢もひどい。今は、トイレに本人が行けているから何とかなっています。
ベッドに「どん」と粗相をされたら、もう無理ですね。トイレの汚れは掃除をすればいいけれども、ベッドでされたら……どうなるんだろう。ぞっとします。
“淡々”とお母様の排泄介助もされていた橋本さん。どんな様子だったのでしょうか。

橋本
大人の場合、しもの御世話をしようとしても、暴れることもある。子供やペットとは量も違う。寝返りを打つと、こんな所、あんなに所にうんちがついている。見つけては拭いて見つけては拭いての繰り返しです。
うちの両親は認知症になる前から仲が悪くて一緒の寝室ではありませんでした。3階に父、2階に母、1階に娘である私たちが暮らしていました。母が粗相をして部屋を汚すと、父がちゃんと見てくれていて私に知らせるので、私が掃除に行っていました。……昭和の男は、便の掃除なんてしませんから。
私には、弟がいます。娘が母を見て、介護をするのは当たり前。「男である息子はみなくていい」というのが我が家の考えでした。「汚いことは女がやれ」と言うわけです。
ご主人の協力を得て在宅介護をされている井下さん。「これだけは夫に頼めない」と思うことがあるそう。

井下
トイレが汚れたら夫が掃除をしてくれて「汚れていたから掃除しておいたよ」と教えてくれるような人です。 さすがに、夫に母のお尻をふいてもらうようなことはやらせられない。夫婦ならともかく、妻の母のしもの世話までさせられない。
座談会参加者の皆さんは口々に「井下さんの旦那様ならやってくれそうじゃない」と言います。

井下
でも、彼には悪い。私がいやなの。罪悪感を覚えてしまう。そこまでは申し訳なくてやらせたくない。
母は、平気で便座を汚しています。尿や便のふきあげはまだ自分でやれているが、脱いで便座に座るまでに、まにあわなくて便が出て自分で座ってしまう。床に落ちたうんちに気づかず、ベッドまで戻るので、たどった道が分かる。
便のふきあげができなくなったら、自分が変わりに母の便をふくのは無理です。だって爪も切れないくらいだから……。

高橋

井下
このあいだね、いわゆるモビコール(慢性便秘症治療の薬)を処方してもらったの。便秘だから。そうしたら、とんでもなく効きすぎて“すごい”下痢になってしまったの。痔ももっているから、いきむと大変。破裂しちゃう。
トイレに「いきまないでください」と張り紙をしたら、本人がパニックをおこしてしまいました。トイレでぎゃあぎゃあ大騒ぎ、張り紙をはがしてしまった。叱られたと思ったのかな?
施設入所についての悩みもつきません。井下さんは思いを吐露します。

井下
一番わからないのは、「いつふんぎりをつければいいのか?」ということです。 私は、母が自分の足でトイレに行けなくなったら入所と考えている。 なぜなら我が家は狭くて、部屋で車いすで生活できても、トイレまでいけない。 トイレに入るまでに車椅子が通れない細い廊下があり、人が介助できない。 トイレにいけなくなったらおしまい。
でもその状態で施設を探し始めて入所まで3ヶ月くらいかかっちゃったらどうしよう。

橋本
行く行かないは関係なく、今から探す。それしかない。断るのは簡単だから。

井下

橋本
うちは家族がバラバラでピンチでした。慌てて特養申し込んだから、井下さんは、落ち着いている今から探しておいた方がいいと思う。
自分が入所に向けて動いたのは母の入院中です。 母がろっ骨を骨折し、6か月間リハビリ入院していた時、大親友がアドバイスくれたんです。親友も、父の介護をしている子だったから経験があったんでしょう。
「何に」困っているか発信を
――― このサイトをご覧になっている介護中の方へ、皆様から最後に一言いただけますか?

高橋
自分が困っていることはそれぞれ違う。 困っていることを言う、聞いてもらえたらいいと思う。 自分が何を困っているか発信しないと、手を差し伸べにくいから。声をあげていってほしいな。

井下
結局介護は親子関係の続きですよね。 そこを分からないで始めると無茶苦茶苦しい。
介護が始まったからといって親子関係が変わることはありません。 自分が好きじゃない親の介護は苦しいもの。 自分と親との関係性をきちんと見つめたうえで、するかしないかを考えてほしいです。
同居の時にきちんと考えればよかった。 単純に長子だから自分が親の面倒をみなくてはと同居してしまった。 失敗したと思っています。 切れないんです、親子関係は。 そこに苦しめられていると思いますね、 自分のことばかり責めている。

高橋
いや、井下さん違うよ。
感情がないから入居の際はすっと決められるんじゃないかしら。 みんな葛藤している、葛藤しないご家族なんていませんよ。 家がいいっていってる祖母を施設に入れて、そこに世間体もあって苦しみました。 それをばさっと「私無理だから行ってね」と言える強さが井下さんにはある。 “線”がひきやすいんじゃないかしら。

井下
その言葉がとってもうれしい。 サ高住の話を具体的に聞けて、そういう風に対応すればいいと思えました。

橋本
介護ってエンドレス。 終わりがみえれば頑張れる、でも終わりはみえない。
自分は同居介護でしたから、結構隔離されている世界でした。 自分の人生、自分を大切にしてほしい。 助けを求めてほしい。 お金がなくても、助けてーって周りにいってほしい。
自分の人生楽しみながらであれば、介護は出来る。 母がおしっこをもらしても、部屋に咲く花の美しさに心がほっとすれば、介護する相手にも優しくできていました。 介護する相手は鏡。うまくできると思う。なるべく人を頼ってほしい。情報をたくさんもらって、私はそういうのたくさんもらって、仕事に出ていました。
遊びだと罪悪感あるけど、人に介護してもらって遊びなんてなんだろうと思う。だけど仕事は違う。私働いているし、子供を食べさせなければいけない。仕事に出ていると、介護のことを忘れられました。
もしお仕事を持っていて可能であればやめないでいた方が、自分を保てていけるんじゃないかなと 仕事があってカフェの仲間に助けられたから母の介護ができたんだと思って、周囲に感謝しています。
壮絶な介護経験を淡々と話してくれた橋本さん。まだ在宅介護渦中である井下さん。そして介護職としても働いてこられた経験から優しい視点で話を聞いてくれた高橋さん。3名の方のお話を聞かせていただき感謝しています。 ありがとうございました。

取材・文:上垣 七七子
「みんなの介護座談会」へご参加頂ける方を募集しています
「みんなの介護座談会」は読者の皆さまに参加して頂く新企画です。皆さまの日々の介護に対する思いをぜひ座談会で語ってください。
以下のフォームより、ご応募をお待ちしております。
参加フォームはこちらをクリックしてください




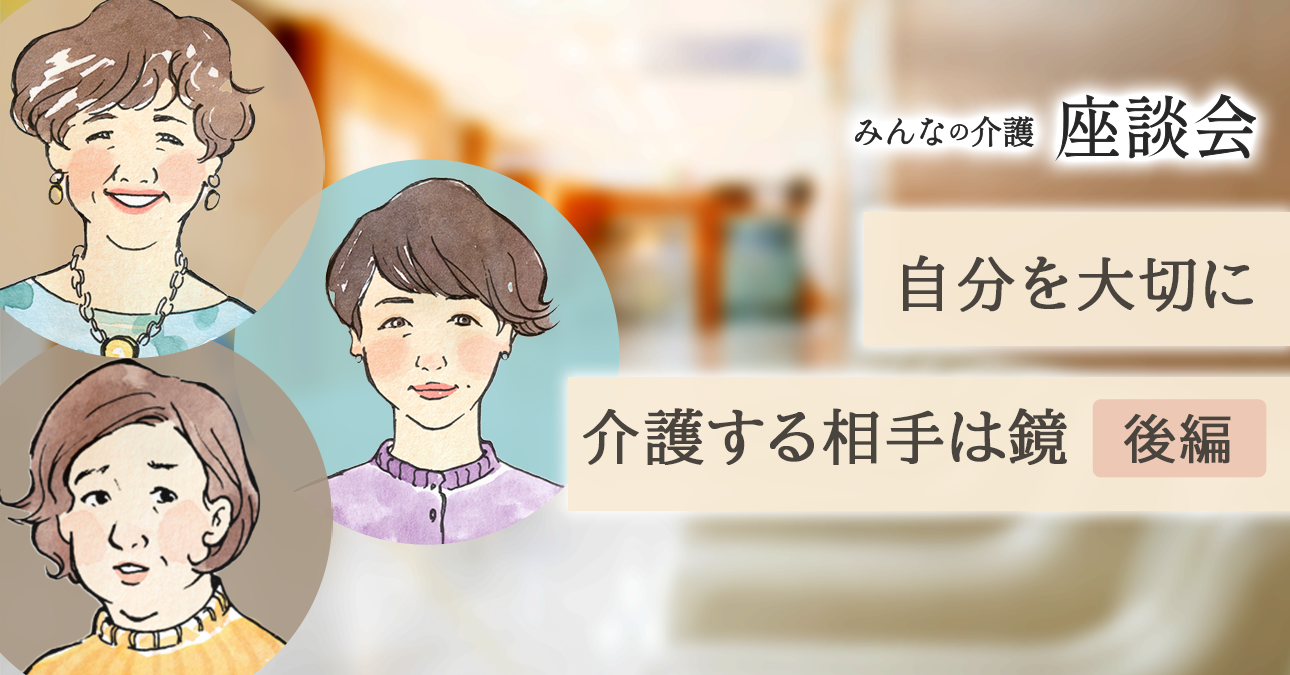



 橋本
橋本 高橋
高橋 井下
井下