今回の「みんなの介護座談会」は、妻、娘、嫁とそれぞれ立場が違いますが、認知症となったご家族を介護したみなさまにお集まりいただきました。「認知症」といっても、その介護はひとそれぞれ。施設入所に対する考え方などを伺いました。
この記事に登場するみなさんのプロフィール(敬称略)
夫の介護のために介護離職。親子ほど歳の離れた夫が、健康診断で認知症の診断を受ける。判明当時は小学生と中学生だった子どもを抱え、働きながら在宅介護をすることに。夫の症状の進行は早く、暴力・暴言などからデイサービスやショートステイから利用を断られるようになる。在宅介護を続ける覚悟でいたが、過酷さが増す日々に、受け入れ可能な施設や精神病院を探す。2022年に入所先のグループホームが見つかる。現在は要介護3。
自営業。夫の転勤で東京へ転居。1年程経過したころから、地元・九州に住む母親に変化が出始める。転勤当初から頻繁に電話をしていたことで母親の異変に気付き、診断を受けたところ、アルツハイマー型若年性認知症と判明。東京←→九州の遠距離介護を続けていたが、父親を1年がかりで説得し、両親を東京に呼び寄せる。「通い介護」となるも、父親が限界を迎え、2016年に母親が特養に入所。現在、母親は発語も難しくなり、要介護5。
マンガ家。10歳以上年上の夫の姑が認知症になり、マンガ家の傍ら、在宅介護を約10年間続けていた。姑が車椅子生活になったことを機に、特養へ入所してもらったが、姑は半年後に入所先で死去。看護師免許を持っていることもあり、姑が施設に入所後、当時お世話になった現場の人たちへの「恩返し」も込め、グループホームで働き始める。グループホームでは、看護師としてではなく、現場のスタッフとして2022年まで働いていた。
夫が、母が、姑が、認知症に!
みんなの介護(以下、―――) まずは、みなさまが「直面」されたご家族の介護について、お話をお聞かせいただけますか。

小林
親子ほど年の離れた夫が認知症を発症したのが60代でした。進行も早く、暴言や暴力、幻覚などの症状が現れて、5年前から本格的に介護をするようになりました。
できることならば在宅介護で頑張りたかったのですが、私と2人の子どもだけで介護していくことが難しい状況となり、2022年からグループホームに入所しています。
小林さんの旦那さんの認知症の症状は、“警察沙汰”になったことがあるほど、暴言・暴力がひどくなっていきました。デイサービスやショートステイの利用も断られるようになってしまったのです。
在宅介護が難しくなるも、「受け入れてくれる」施設がなかなか見つからなかったといいます。「やっとのこと」でグループホームを探し出しましたが、“大黒柱”が認知症となり、月に約25万円の施設の費用が掛かる日々は、中学生と高校生の子どもを抱え、介護離職をしている山口さんにとっては、金銭的に厳しいものがあるそうです。
――― ありがとうございます。続いて、山下さんお願いします。

山下
もともとは九州に住んでいたのですが、結婚した翌年に夫が東京に転勤となり、私の家族と遠く離れて暮らすことになりました。その1年後、私の母が57歳のときにアルツハイマー型の若年性認知症という診断を受けました。
父はもともと東京出身なので、2011年に両親を東京に呼び寄せました。両親が上京するまでの数年間は、東京と九州を月イチくらいで行き来する遠距離介護をしていました。
東京では両親の家に「通い介護」をしていましたが、父が倒れ、母の症状が進んだこともあり、2016年に母は特別養護老人ホームに入所しました。
認知症の進行が進むお母さんとそれを支えるお父さん、そして自身が遠距離介護を続けていくことに限界を感じたという山下さん。何かあればすぐに駆け付けられる「近く」に移り住んでもらうように、約1年かけてお父さんを説得したそうです。
――― ありがとうございます。それでは、坂本さんよろしくお願いいたします。
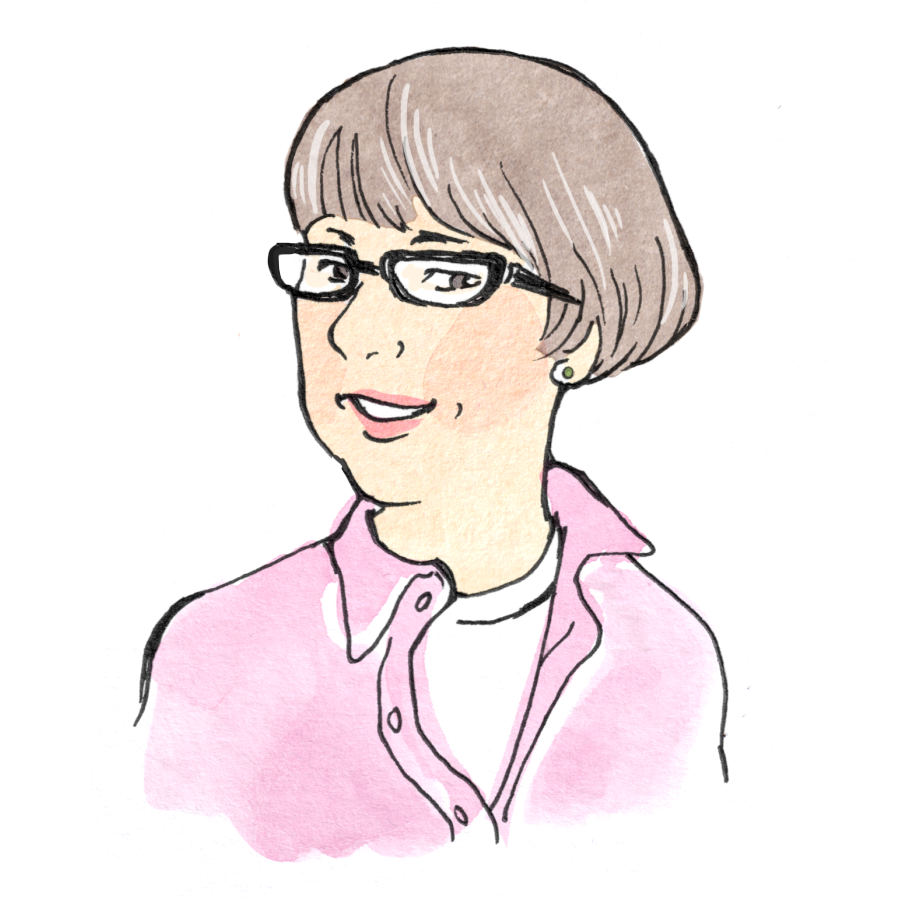
坂本
私も小林さんほどではないけれど、夫とは10歳以上歳が離れているため、結婚当初から姑は「かなり」の年齢になっていました。その姑が認知症になり、約10年間、在宅介護をしていました。姑が車椅子生活になったことを機に、特別養護老人ホームに入所してもらい、その半年後に姑は入所先で他界しました。
私は看護師の資格を持っています。姑の介護で多くの介護職の方にお世話になった恩返しがしたくて、姑が施設に入所したタイミングから2022年まで、約6年間グループホームのスタッフとして現場で働きました。
マンガ家を続けながらお姑さんが施設入所後に、介護現場で働き始めたという坂本さん。仕事を通じて、介護について考えさせられるような貴重な経験をたくさんされたそうです。
――― 坂本さん、ありがとうございました。それでは、さらに詳しいお話をお伺いさせて頂ければと思います。
なかなか認知症だと気づくことができなかった
――― 三者三様にさまざまな状況ですが、「ご家族が認知症になった」という共通点があると思います。ご家族が認知症だとわかったときの心境や、進行していく症状への戸惑いなどがありましたら、お聞かせください。

小林
うちは「ひょんなこと」から夫が認知症だとわかってしまって。
夫が1年に1回の健康診断を受けに病院に行ったのですが、その病院から「住所も言えないし、呂律が回っていない。脳の病気かもしれないから、奥さん来てください」と電話がありました。そこで、いきなり脳の検査や認知症の検査をして「ご主人は認知症ですね」と言われたのです。
――― そのような形で発見される“ケース”もあるのですね。山下さんはどのような経緯で、お母さんが認知症だとわかったのでしょうか。

山下
私は母と遠く離れて暮らすようになり、ちょくちょく電話をするようになったんです。電話口で「なんとなくいつもと違うな」と感じる回数が増えていきました。両親はドライな夫婦仲だったのかもしれませんが、同居している家族に母の変化をもう少し早く気づいて欲しかったですね。「怒り」まではいきませんが、すごく歯がゆい思いがありました。
でも、父は「現役」で働いていたし、同居していた妹も日中は働いています。変な話ですが、離れて暮らしている私が母と一番話しをしていたので、気づけたのかもしれません。

小林
私も夫と一緒に住んでいましたが、全然、気づきませんでしたよ。だから、認知症という診断結果に「えー!」という感じで。
今、思えば、その1年前くらいから、やたらと夫婦喧嘩が増えたり、料理好きの夫が料理をしなくなって子どもたちの世話をお願いしたときにコンビニ弁当を食べさせていたり……もしかしたら、そのあたりが「前兆」だったのかもしれません。
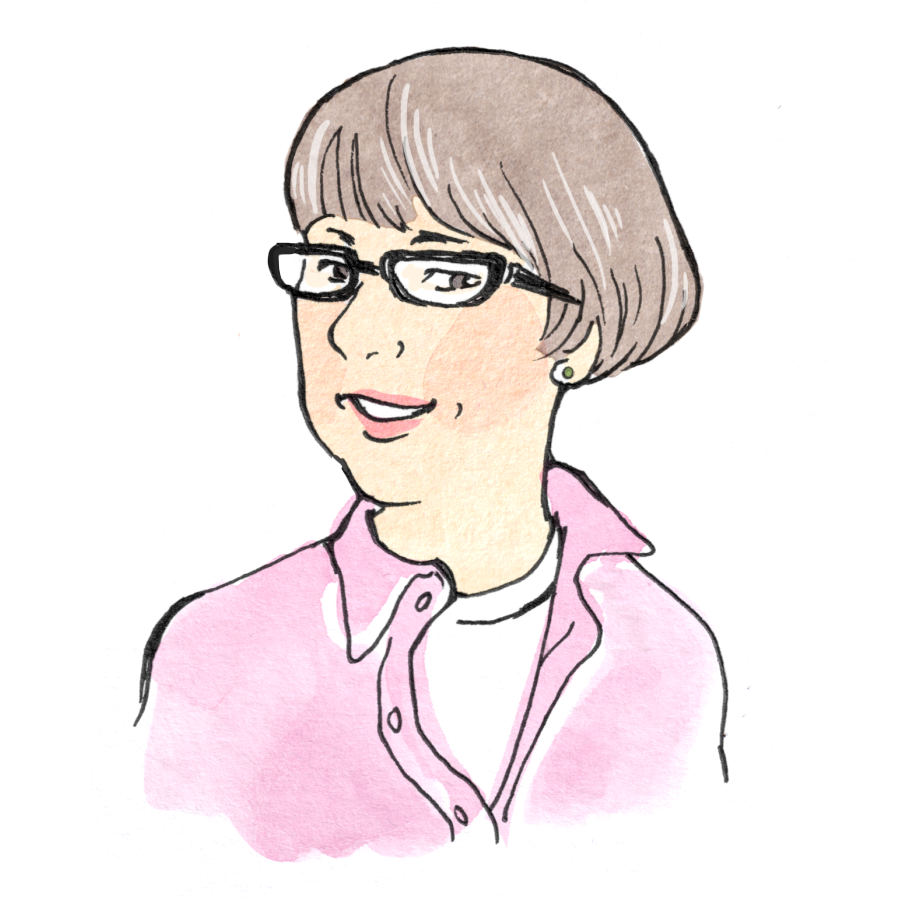
坂本
小林さんの旦那さんと山下さんのお母さんは、まだお若いということもあり、周りが気づきにくかったのかもしれませんね。
私の姑の場合は、年相応に緩やかに認知機能が衰えていくという感じでした。認知症の「教科書的」というか、床暖房に隠した下着が臭ってきたり、もの取られ妄想で「通帳がなくなった」と言い出したり……。お二人のお話を聞いていて、グループホームで働いていたときの方が教科書的でないケースの方が多くて、大変だったことを思い出しましたね。
――― 小林さんは、旦那さんが認知症だと「突然」判明しましたが、当時のことを伺えますか。

小林
健康診断で何の心構えもなく、認知症と診断されたあとは「ケアマネジャー? デイサービス? なんだかよくわからない!」「どうしよう、どうしよう」と、日々に対応にしていくことで精一杯で……。
私はガンで両親を亡くしています。そのときも命をなんとか助けたくて医師を探し回ったのですが、夫についても「なんとか夫の症状が良くならないだろうか」と、夫を診てくれる医師はいないか、良い治療法はないかと必死に探し回りました。

山下
私は、病院探しといっても、東京にいて付き添うことができないので、まずは父に近所の掛かりつけ医に連れていってもらいました。
ただ、そこではうつ病と診断されました。そのあともいくつかの病院に行ったのですがハッキリしなくて。「やっぱりおかしい。大きい病院に行った方がいい」という私の「勘」で、物忘れ外来のある大学病院に紹介状を書いてもらい、やっとアルツハイマー型の若年性認知症だということがわかりました。

小林
私も認知症の名医がいるという病院をいくつも回り、「こういう薬のパターンにすれば症状が少しは抑えられる」と言われればそれを試しましたね。
でも、夫には効果があまりありませんでした。そして「信頼できるこの医師でダメならばダメだ」「夫はもう良くならないんだ」と諦めがついた感じです。
山下さんは、お母さんが若年性認知症だと判明してからは、お母さんをできる限りサポートするために月イチで東京←→九州を行き来する「遠距離介護」となりました。
小林さんは、その後は現実を受け止めて、介護サービスを利用し、在宅介護をしていく覚悟をしたそうです。「悲しいな」「大変だ」と思うこともあったそうですが、日々の介護に忙殺されていきます。
「デイサービスに通う」という壁

山下
母も九州に住んでいたころに通っていたデイサービスは、70歳以上の方ばかりで年齢的に合わなかったようです。
認知症になった初期のころは本人の意思もあったと思いますが、だんだん症状が進行して、要介護3、4、5となってくると、母がどう思っているのかがこちらに伝わってきません。だから仕方ないと思って通っていたのかもしれないですね。そのあたりを「当時はどう思っていたの?」と聞いてみたくても、今はもう発語ができなくなってしまっていて……。

小林
夫はデイサービスの利用者や内容がどうこうよりも、「家でゆっくりしたいのに、どうして外に行かなければならないんだ」と自身の機嫌で行ったり、行かなかったりしたのが、とにかく大変で。行ってしまえば、そんなに嫌がることはなかったみたいです。
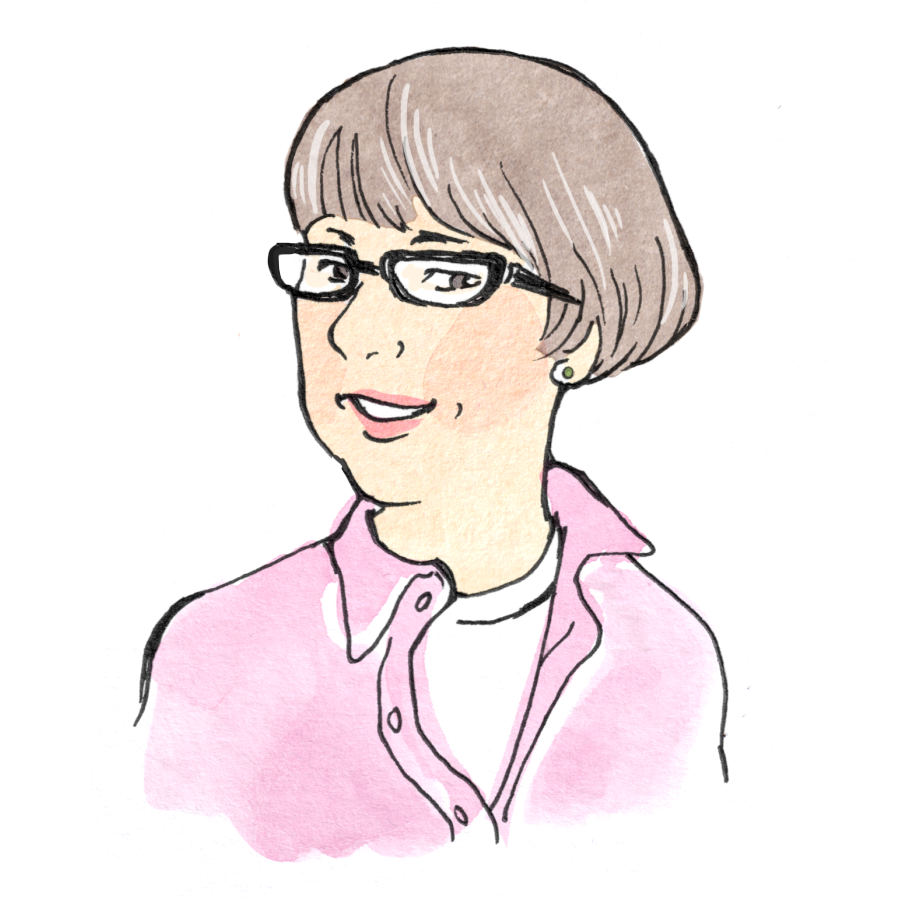
坂本
男性は家を出るまでが大変みたいですよね。姑はデイサービスに行くのを楽しみにしていて、送迎車が来るのを玄関先で待っていたのですが、お迎えの時間が10、20分遅れてくるのはザラ。スタッフの方に理由を聞くと、男性の利用者さんが行くのを“渋った”ということがよくありました。

小林
私は「行くよ!」と先にデイサービスの送迎者に乗って、夫が車に乗ったら反対側のドアからスッと出るみたいなことをやったりもしましたね。そうでもしないと車に乗ってくれませんでした。
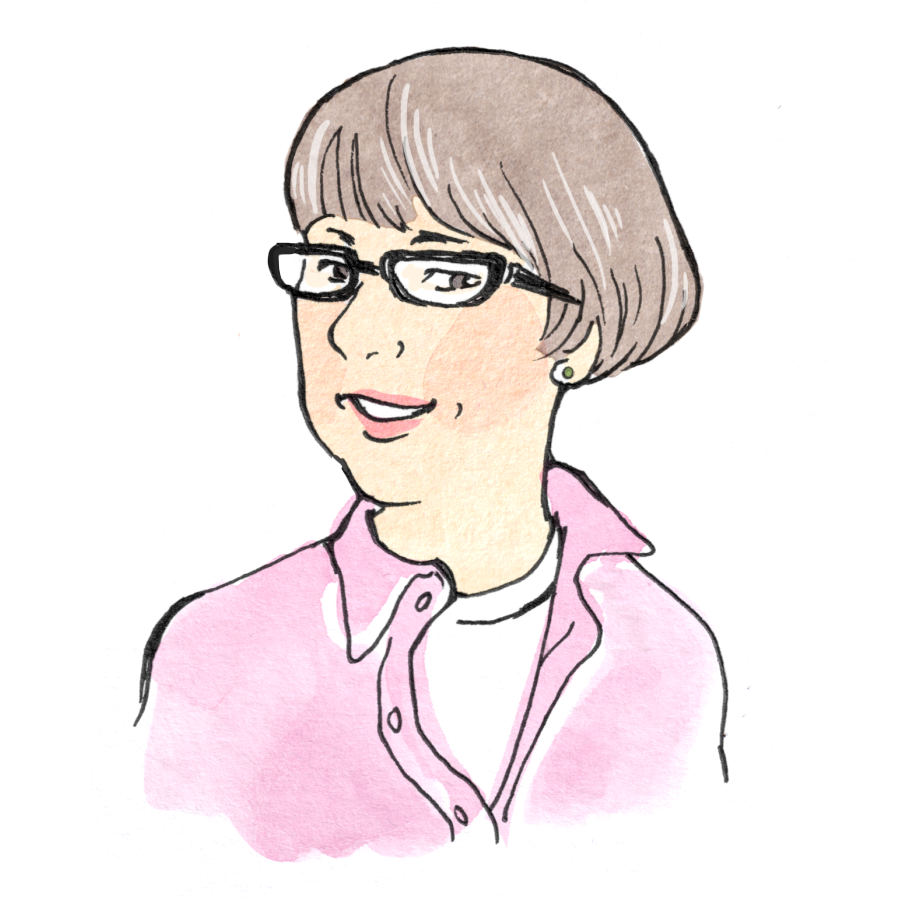
坂本
認知症の人と接するにあたり、いろんな意味でそういった演技が上手になりますよね。姑が「お財布がない!」と騒ぎ出すとたいてい私が先に見つけてしまうのですが、それで手にしてしまうと私が盗ったことになってしまいます。
だから、私が見つけたら姑の見つけやすいところにそっと移動して、それを改めて姑に見つけてもらう。「みつかって、よかったね」ということを繰り返していました。

山下
「お財布がない!」という話で思い出しました。基本的には母はおとなしい性格なのですが、もの取られ妄想がありました。お金を盗ったのは妹だと私に訴えるのです。私は母に「妹は盗っていないよ」と説明していたのですが、私が九州に帰っている間は、私が近くにいるという安心感からかそういったことが落ち着いていました。
認知症の方と接するときには、“やさしいウソ”や“演技”が大切だというお話があります。みなさんも認知症のご家族のために演技をされていたようです。
後半では、介護によってギクシャクした家族関係や施設入所に踏み切ったそれぞれの思いについて伺います。

取材・文:岡崎杏里
「みんなの介護座談会」へご参加頂ける方を募集しています
「みんなの介護座談会」は読者の皆さまに参加して頂く新企画です。皆さまの日々の介護に対する思いをぜひ座談会で語ってください。
以下のフォームより、ご応募をお待ちしております。
参加フォームはこちらをクリックしてください







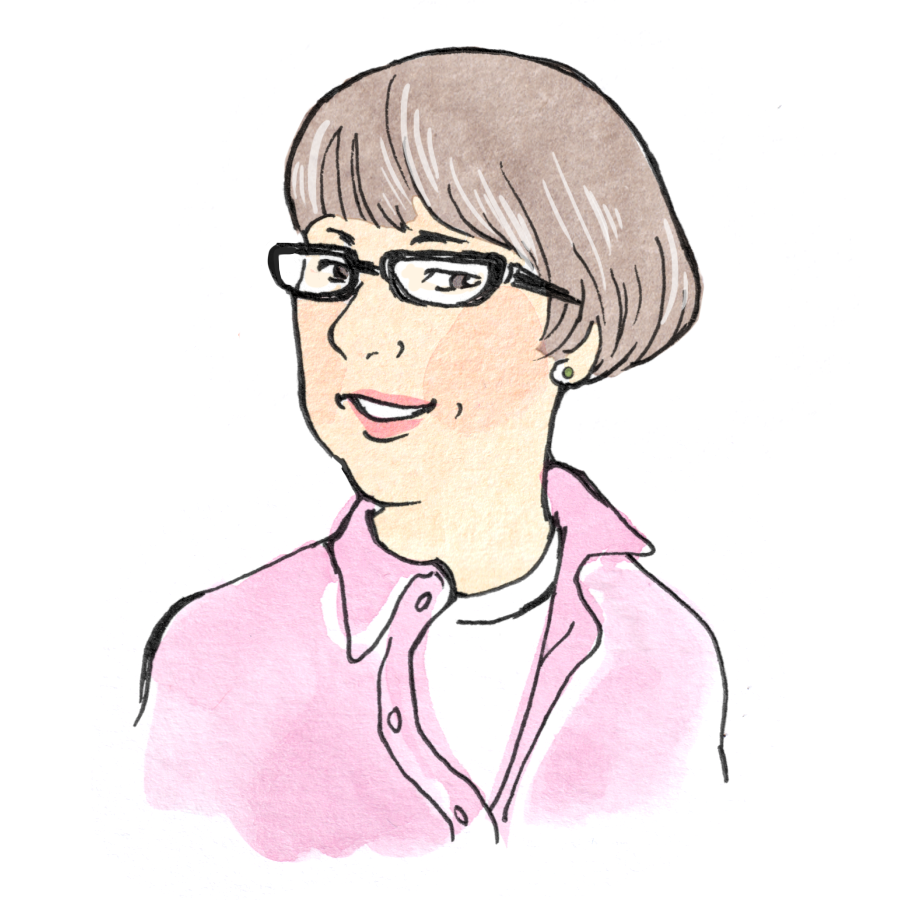
 小林
小林 山下
山下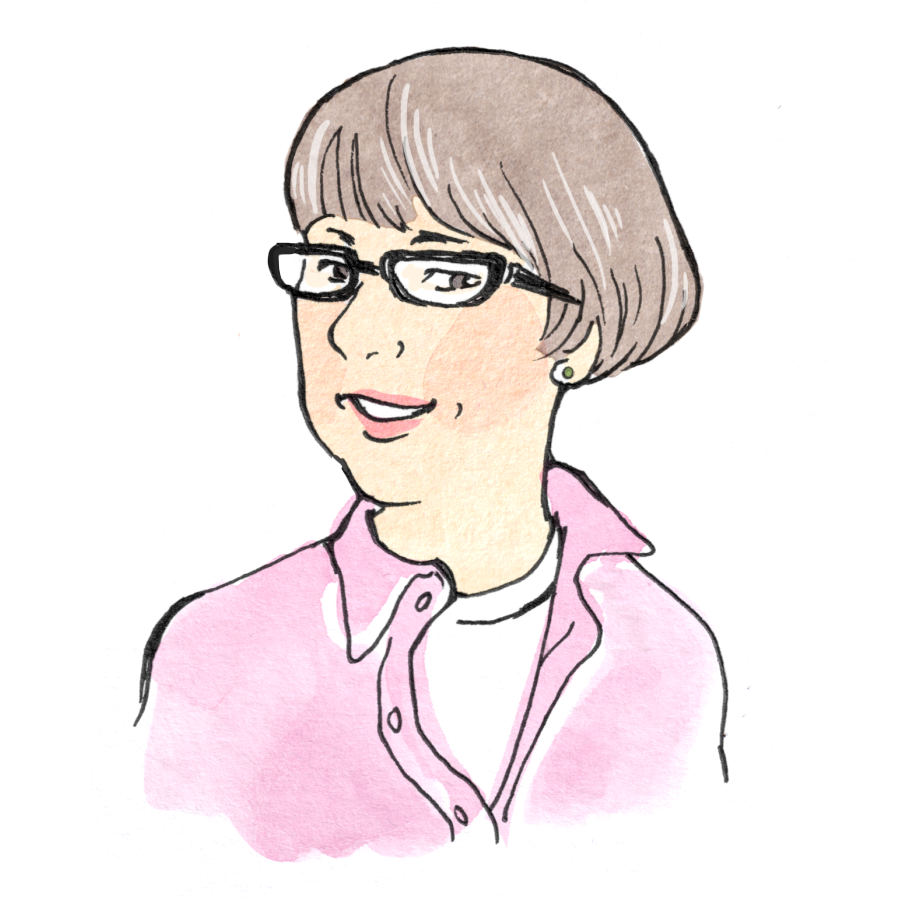 坂本
坂本