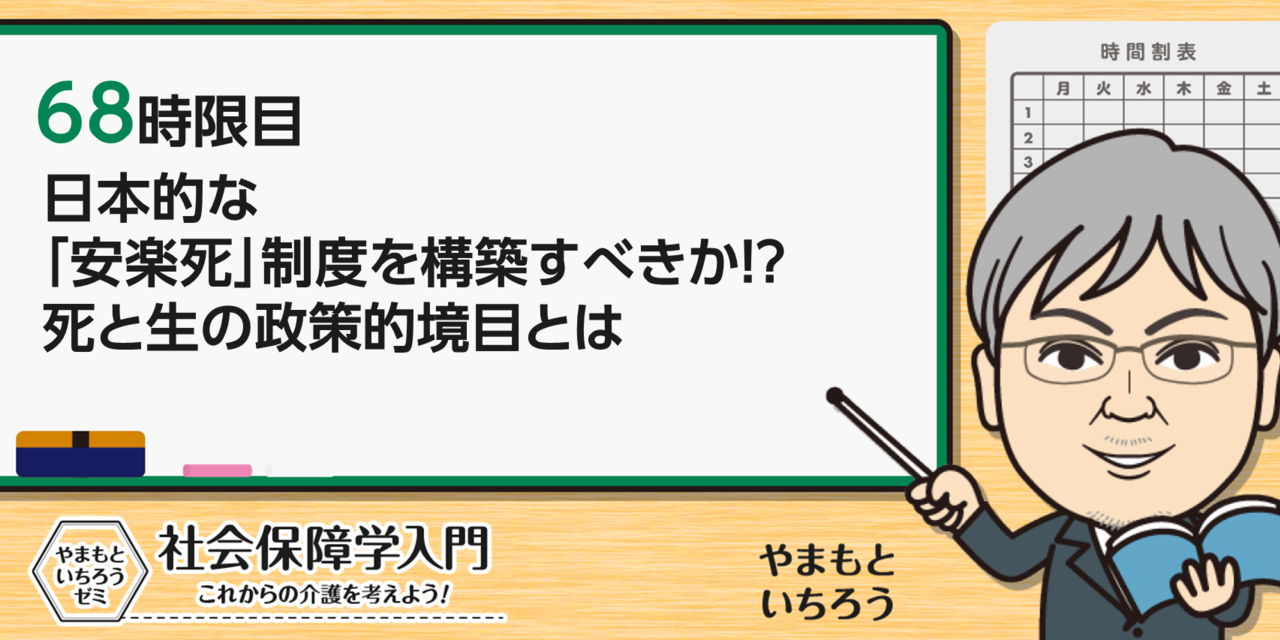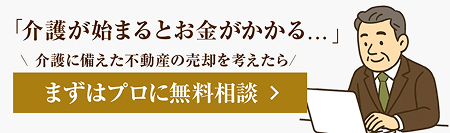社会保障論としての安楽死は劇薬であって、特に「何のための社会保障制度なのか」や「制度として死を望んだときの線引きを策定することは望ましいか」といった論点は、医療倫理から社会風習までさまざまな観点から語られるもので、国民全員が納得する回答などあるはずもない難題です。
今回は真摯に安楽死問題について考察していきたいと思います。
なぜ安楽死議論が行われるのか?社会保障との理念とのギャップ
そもそも、社会保障というのはその社会で暮らす誰もが安心して生きていける仕組みのことです。それはイギリス救貧法以降、人権思想と統治のあり方との根幹のところで議論することそのものが唾棄すべきものとして、安楽死についてはあまり語られてこなかった側面があります。
医療倫理の世界で言うならば、医療行為というのは命をつなぐことを一丁目一番地としており、積極的な救命を行うことが医療行為の大原則であるため、そこに対して行政・政策論として異議を挟むこと自体が望ましくないという空気があるわけですよ。
他方で、医療の現場や社会保障の実務を担う人たちからすれば、しばしばこれらの倫理と理念(プリンシパル)とを突き詰めていく狭間に、そう簡単ではない綺麗事として踏まえざるを得ない事件が多数存在することはよく知っています。
日本語に直訳すると「無益な治療」と「死ぬ権利」という、医療倫理や法哲学のある種の先鋭化であり対立する二項について、割り切れない現実に直面することになります。
この「無益な治療」は、医療倫理の世界では適正な医療活動を行うにあたっては、そのようなものは存在しないという建前から、医道として目の前に苦しんでいる患者さんがいたとしたならば、どのような状況であっても然るべき延命治療を行うことを是とすることを大原則としています。
ここには、苦しんでいる本人の意志は推定であって、おそらく生きていたいだろうという意志があることを大前提にしているので、この手の安楽死論争では定番となっている「自殺をしようとして死にきれずに苦しんでいる患者さんを医師は救うべきなのか」という論点からいろんな議論が発展していきます。
人権として認められる「死ぬ権利」。死の選択は許されるのか
この対極の概念として「死ぬ権利」というものがあり、生きていくことはもちろん人権として認められていて、政府は国民に対して等しく生存権を認めている一方、その生命の終わりを選択する場合に自己決定モデルとして死んで良しとするのかという問題に直面します。
これは、死にたいと思っている国民の「内面の自由」であって、自由権のど真ん中である一方、これに対して政府・行政が自殺してはいけませんと制限を駆けることは憲法で認められた国民の権利に対して政府が口を挟むのかという矛盾をもきたすわけです。
そして、先般物議をかもしたお笑い芸人の小藪千豊さんを起用した人生会議のポスターにおいて、特徴的な議論として、もしものときに備えてどのように対処するのか家族で話し合っておくことの大事さを伝えたはずが、あさっての議論になり炎上してしまったのも、また議論の成熟までにはまったくいたっていないのだなあと考えさせられます。率直に言って、このポスターは問題になったけれど、言ってることも問題提起も間違っておらんのです。
問題は、これらの議論が「不安を煽る」のではなく、語られなければならないことを避けて通っているに過ぎないことを浮き彫りにしていることです。
端的な例では、現在ほとんどの介護やペインコントロールの現場で、入所する高齢者や障碍者に緊急の事態が起きたときに積極的な医療を施すか否かを本人やキーパーソンに確認を取る作業をしています。下手をすると、長期療養型病院を標榜しているにもかかわらず、夜間救急対応できる医師や資格のある看護師を実質的においていないまま高齢者を多数受け入れている施設さえあるのではないでしょうか。
特に、重度の認知症や精神疾患を抱えていたり、病状の回復のめどが立たない重篤ながん患者さんなどを集めている施設は、本人の意志とは関係なく家族が「本人が亡くなるのを待っている」状態であると批判されることもしばしばあります。
しかし、徘徊やベッドからの転落の防止、食事や排泄の処置などもしなければならない在宅介護を、限られた親族が行うことの負担を考えると、過日より社会問題となっている介護離職や老々介護が一層重い問題として横たわることになります。
もっと言えば、これらの問題はどう解決するかというより、2042年ごろまで団塊の世代が次々と後期高齢者入りをし、高齢化問題はあと20年弱続く、これから悪化する問題だと覚悟する必要があります。
こういう高齢者対応の仕事に就いて、これから貴重な労働力として納税を担わなければならない若い世代を充当するのは、社会の生産性において本当に望ましいことなのか、議論にならざるを得ません。
もちろん、介護の仕事が尊いものなのは間違いないのですが、社会的生産性という観点からすれば、もはや社会に対して付加価値をもたらさず生産を担わない高齢者を、貴重な労働力で生き長らえさせることにどれだけの意味があるのか、という論点から否定されることがあります。
「国民には、生きたいと思う以上は、平等に長く生きる権利がある」とは言えども、それは自分の財産でできる範囲内のことをやるべきではないか、社会保障としてそこまでの負担をこれ以上担うことは困難になるのではないかという反論も出てきてしまいます。

海外では正面から議論が続く!スイスでは悪用ともいえる状況も…
これらの問題に正面から「死ぬ」「死なせる」という死に方の問題でカバーしてきた日本の議論とは別に、オランダ(安楽死政策;The Euthanasia Policy)やベルギー、ルクセンブルク、カナダなどで見られる積極的安楽死政策と医師幇助自死の適法化が進んでいるのは、制度的に命の選別につながりかねない危険なものであるとも見られます。
アメリカでも、バーモント州、カリフォルニア州、ハワイ州など割とリベラル色の強い地域でも医師の介在による自殺が一定の法制化をされるなど、実質的な「最後の手段としての医療行為」や「患者のオートノミー(自律)と尊厳を尊重」といったジュネーブ宣言の内容に対して、真っ向から反発するというよりは、生と死の線引きの概念を更新するといったアプローチで世界的に一般化していっているとも言えます。
端的に言えば、国民である患者さんが、どういう状況に陥って、本人の意志としても客観的にも生存の見込みがなく希望を持つことが合理的でないとなった場合に、制度的に安楽死を認めるのかといった線引きが必要となります。
ただしこれは、完全に認知の問題を抱えていたり、親族間で財産を巡る争いがあったり、逆に完全に本人の財産状況が危機的状況で治療に見合う支出負担が担えないなど、ちゃんとハードルをつくっておく必要はあるわけですよ。
しかし、現在スイスなどでの医療ツーリズムで、この安楽死をするためだけに生存の見込みのない高齢者や家族が現地を訪れ、死亡処理をして遺体だけ帰国させるという行為が横行しているとさえ言われている状況です。
悪く言えば、それだけ需要が見込める世界なのだとも言えます。私なんかは、倫理的にこれは悪夢でありディストピアなんじゃないのと思うのですが、ただ、法で認められる範囲内でせん妄や認知症による暴力、ベッドからの転落防止を防ぐためにベッドで拘束され寝かされるケースもあるのは紛れもない現実であって、制度がそれに向き合わないのもまた不誠実とも言えます。
長期療養中に体調不良をきたし、積極的救命を行わず、または行える体制を敢えて置かず、病院や施設の経営を保つためだけに長い入院期間を設定して死ぬのを待っているだけの医療や介護にどれだけの価値があるんですか、というのは、まさにこの安楽死の議論の根幹にあります。
正直、“吐き気”のするような論点を細かく詰めていく作業の連続であり、倫理や理想と現実との間にある溝にどう橋を掛けるのかという話で、私なんかは日本の高度成長を支えていまの恵まれた社会を構築した立役者である団塊の世代の最期にこれか、と思ってしまう面はあります。申し訳のない気分になります……。
高齢者や重篤患者、障がい者の方の生命の危機に瀕して、積極的な延命治療をしないことが許されるのであれば、安楽死も認められていいじゃないかという安易な議論にならないよう、しかし、生きる尊厳や死に方の問題にもきちんと立ち入って政策論争ができるよう期待したいところです。