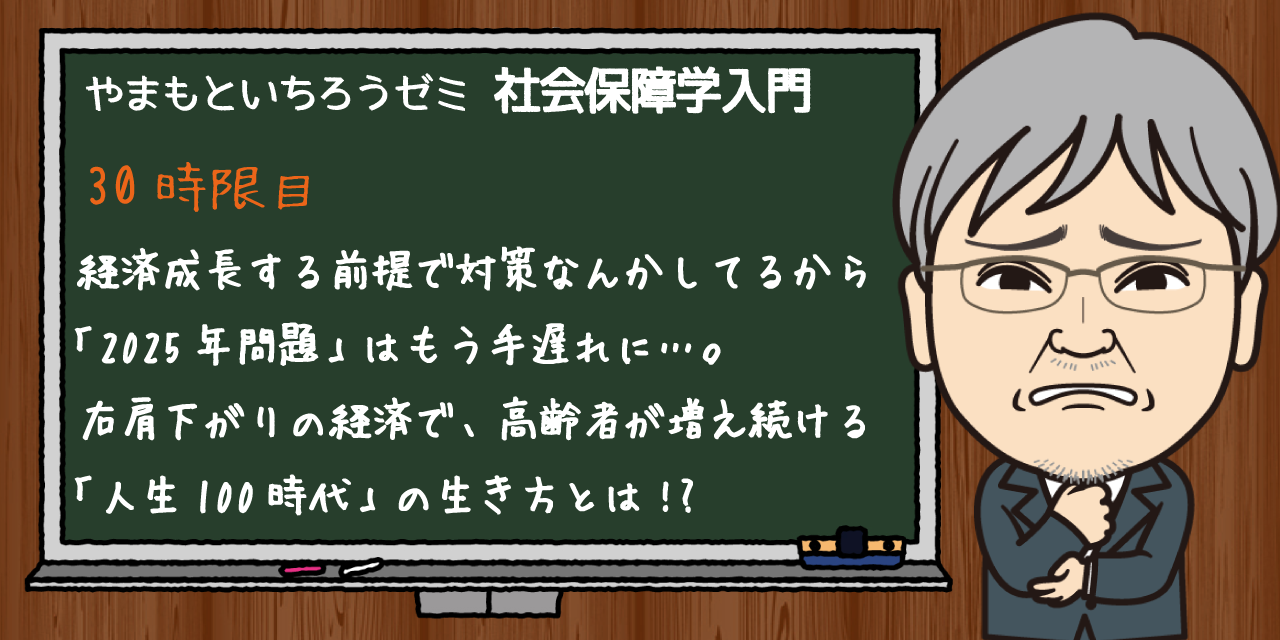「2025年問題」はまじでヤバいよと言うと「そんなことわかってるわ!」と言われがちですが、わかっていてもどうにもならないのがこの問題の本当のヤバさであるとも言えます。
だったら、政治家でさえもこのままじゃダメだとわかっているのに変えられない、この日本をどうにかしてしまう問題を、ヤバさだけでもちゃんと理解しておこうではないかと思うわけであります。
特に私と同年代の人たちにとっては、理想の穏やかな老後のイメージが悲しいほどに壊れていってしまうのです。
遂に「2025年問題」がやって来ますね
私の親も一気に老け込んで病気がちになってきました
私のような団塊Jr.のベビーブーム世代(1971年~74年生まれ)は、これから軒並み親の世代が後期高齢者の仲間入りするんですよね。
私の両親は一足先に75歳を超えて後期高齢者になりましたが、やはり80歳の足音が聞こえてくると、それまで元気に買い物に行ったり、銀行で振り込みをしたり、庭いじりをしていたのが、一気に老け込んで病気がちになります。
そして、一度大きな病気をして、あるいは階段で転んで骨を折ってからは、転がり落ちるようにダメになっていってしまいます。親の介護をしていて人が"しぼんでいく"姿を間近で見るのは悲しいことです。
それも、自分と血を分けた肉親が、あれだけ元気に笑い合い、尊敬したり怖れたりしていた父親、厳しいけど愛情を持って接してくれた母親が無表情になり、あるいは感情の起伏が激しくなり、記憶が微妙になっていくと、元気だった頃を思い返してさびしい想いを抱きながら車椅子を押すわけであります。
ああ、死んでいくんだなあと。
おそらくは、そういう想いを抱きながら親を見送ったみなさんも、また私の同世代で悲しい思いをこれからする人たちもたくさんおられるわけですが、社会全体からしますと団塊の世代は1947(昭和22)年~1949(昭和24)年生まれで、この約800万人が順調に後期高齢者に突入します。

後期高齢者の数は2015年で1,691万人、2025年には2,180万人、2055年にピークの2,446万人(日本人の4人に1人)となります。日本の社会や経済を支えた世代がごっそり引退から終活を迎える世代になると、これを支える社会保障費が問題になるのも当然と言えます。
国や自治体ではもう無理だからと
高齢者福祉は家庭にぶん投げられてしまった
この連載でも、高齢者が増えていくにあたって「今までのやり方の延長線上で社会保障を組み立てても解決しそうにない」という話は繰り返ししてきました。
積み上がる社会保障費、負担となる社会保険料、上がらない賃金、入ってくる外国人労働者、公的部門が賄いきれないので民間に、地域に、家庭にぶん投げられる高齢者福祉の実情…。
どれもが、これまで以上の負担を社会が担い切れない、国も財源が乏しいということで、働けなくなった高齢者は国や自治体もなるだけ面倒を見たいけどやっぱり家庭でお願いしますね、と押し返されたような格好です。
だからこそ、介護離職の問題や老老介護といったワードが飛び出してきて、さらには伴侶がいずれかは先に亡くなることで発生する独居老人だけでなく、そもそも結婚していない、家族もいないという「独身貴族」が「おひとりさま」を経て独居老人の仲間入りをするという事態に陥ってしまうのです。
今でこそ、お見合いなんてとんでもない、女性の社会進出は当たり前、自由恋愛でなければ結婚はしないという風潮も出てきました。
しかし、結婚適齢期に相手を見つけることができず、婚活競争に負けた独身男女が量産されてしまうことになると、いずれそういう人たちが高齢者になるときに「地域で介護を」「家庭に戻って」と言われたところでで誰も身寄りがいないし、地域に親しい人もいないという社会問題を容易に引き起こすことになります。
独身は気楽でいいねとのんびり言っている場合ではなく、生産性を引き上げ、社会とのつながりをどう維持する人生を日本人が送るべきかがまさに問われることになるのです。家庭と働き方とが問われるようになると、現代社会の自己決定権というのは個人の利得としては最大だけど、誰も救ってくれないキリギリス問題を起こします。

そこで、『働き方改革』なるワードが飛び出してきました。
もともとは、雇用・労働政策の柱として、ネットでは主にブラック企業対策も含めた雇用の流動化や残業時間の上限規制などが盛り込まれて、より働きやすい環境づくりに社会や企業が貢献すべし、という内容ではあります。
一方で、この働き方改革の主眼は、日本の人口動態の変化、つまりは年寄りが増えて労働者が減るので生産性を上げていかなければ激ヤバいという現状認識を(安倍政権が)強く持ち、そろそろガチで労働者をどうにかしなければ、増える高齢者と共倒れになりかねないと本腰を入れてきた結果がこれらの働き方改革である、とも言えます。
その働き方改革を進めるバックボーンとは、まさしく『人口の減少』と『人生100年時代』を迎えて、これらを『テクノロジーの進展』を含めた労働者の知的生産の促進、生産性の向上という未来志向で乗り越えていこうという、まあなんというか、ああそうですかという雰囲気のスローガンがあります。
とりわけ、私なんかは『人生100年時代』と言われてもいまひとつピンと来ないわけですが、つまりは「みんな長生きするので、子ども・学生時代、働く時代、老後」の3つのステージで人生設計をするのではなく、途中で大学行って学んだり、転職したり、老いても楽しく働いたり、とにかく年金をもらってゆるゆる暮らすんじゃなくて、畑に出たり、駅前の放置自転車を持ってったりしながら自分自身と社会に対して価値のある人生を長く送れや、という政府からの熱いメッセージであろうと思うわけであります。
知らぬ間に社会保障費は4兆円も削減!?
そりゃあ同じ人に40年間も年金を払いたくないか…
もともと年金制度や皆保険制度というものは、みんな頃良い年齢で亡くなる前提で、老人が基調で労働力が旺盛な時代に設計されたものであって、エンゼルプランが策定されるほどに人口減少が現実のものとして危機感もって捉えられなかった時代につくられた内容です。
当然、制度疲労を起こして支える労働者人口が少子化の進展で激減りするとは思ってなかったんでしょうね。
概要でいえば、この『人口の減少』は2025年に団塊の世代が75歳以上になること、2050年から2055年には人口の4割が高齢者(65歳以上)となること、そして2060年から70年には現在の労働人口が6割以下になってしまうことという、人口構成上の問題が大きくなっています。
一方で、合わせ鏡のように『人生100年時代』では、これはまあ希望的観測も込みではありますが、約半数の日本人が100歳以上まで生きる(かもしれない)ので、従来の65歳での引退、年金支給では毎年50万人近い日本人が40年以上もの期間で年金をもらいかねないぞという危機感があるのです。

当然のことながら、これらは今までどおりに潤沢に保健医療にお金が使えて、年金制度も国家財政も破綻しないというファンタジー気味の未来予測に基づいて、めっちゃ日本人が健康で長生きだったらヤバいということで設定されたバックグラウンドではあります。
さりげなく社会保障費は削られてきているので、保険医療に潤沢な資金を投じることは不可能なのが予算からも見えてきます。なぜか共産党系の赤旗がまとめた資料があるので例示してみますが、削らなければどうにもならない、とはいえ気になる項目がたくさんあります。
| 年度 | 内容 | 削減額 |
|---|---|---|
| 2013年度 |
|
1兆5,300億円 |
| 2014年度 |
|
4,000億円 |
| 2015年度 |
|
1兆0,650億円 |
| 2016年度 |
|
1,700億円 |
| 2017年度 |
|
1,900億円 |
| 2018年度 |
|
5,300億円 |
| 2019年度 |
|
3,870億円 |
| 合計削減額:4兆2,720億円 | ||
しかしながら、ここでいう『人生100年時代』のジレンマというのは、「右肩上がりの社会環境ではとっくになくなっている」のに「右肩上がりの経済や社会風土を前提として、法律や制度や政治が未来を予測している」ということに他なりません。
生産性を上げれば生産人口がたとえ1割減っても経済成長するのだ、と信じる有識者はほとんどいません。
経済成長は必要で、だからこそデフレ経済からの脱却や需要喚起のために異次元とも言われる金融緩和をし、日本銀行がアップアップになるまで日本国債を買い溜めていたりしますが、それもこれも日本経済がこれからまだまだ伸びていく前提で必要なことを全部やる、という右肩上がりの思想から脱却できていないところはあるのかもしれません。
必要なことは一人当たりの生産性の拡大であって、経済全体のパイがまたバブル時代のように伸びるとは思えないにもかかわらず、アベノミクスだ働き方改革だ、これからの日本人は100年生きるんだからずっと働いていれば働く期間が伸びて経済成長だ、プラス思考で日本人全員頑張れ一億総活躍だぞと言われているのもなかなかつらい気がいたします。
一番の懸念は、日本の政治家もみんなこのままじゃダメそうだということがわかっていることなんですよね。
なんで、わかってて無理のあるスローガンを掲げて、無理のある活力を日本人に期待して、無理に老人を働かせようとするのか良くわからんなあ…、というのが正直なところです。
【新刊情報】山本一郎が説く、介護をされる側も介護をする側も心に響く現代日本の生き方本
「ズレずに生き抜く 仕事も結婚も人生も、パフォーマンスを上げる自己改革」(文藝春秋)