高知県西南部に位置し人口約10,700人の黒潮町は、65歳以上の高齢化率が45%と高齢化が進み、南海トラフ巨大地震では最大震度7が予想され、最大で34mの津波が襲うと予測された地区もある。山間の地域も多く、土砂崩れや浸水などへの防災意識も欠かせない。地区防災計画づくりに取り組む松本敏郎町長に防災訓練の様子や災害時の高齢者避難について話を伺った。
監修/みんなの介護
【ビジョナリー・松本敏郎】
それぞれの命を守るために、
一人ひとりがベストを尽くす

南海トラフ大地震で想定される黒潮町の被害は最大震度7、最短8分で津波が町の沿岸部に到達、最大で34mの大津波に襲われると予測された地区もあります。一方、近年増加している豪雨災害や台風被害による浸水や土砂崩れは町の中山間地域に起こりやすい被害です。沿岸部と山間部で違う防災活動、南海トラフ巨大地震と豪雨・台風による土砂災害への対策方法を、住民の皆さんと相談しながら日々アップデートしています。
自然災害からそれぞれの命を守る意識を住民みんなで共有し、各自で何をすべきかを具体的な計画に落とし込んでいます。行政としては必ず逃げられる場所を用意し、そこに避難できるように住民の方々にはベストをつくしてもらわなくてはなりません。そのために、町全体での大規模防災訓練を年に2回行っています。
住民みんなで力を合わせ地域ごとに決めたルールに基づいて、一人ひとりが行動することで、犠牲者ゼロを目指すことができるようになります。黒潮町には61の地区がありまして、ほとんどの地区の区長が65歳以上です。黒潮町の65歳は町を担う現役の世代ですので、率先して地域を牽引し、防災への備えを実践してもらっています。
町ぐるみで行われる防災訓練
黒潮町では、自衛隊、警察、消防とともに行う町ぐるみの防災訓練を、毎年9月に行っている。朝8時の地震発生の告知放送で開始し、自治体ごとに決められた場所に避難する訓練を行う。また、11月には夜間避難訓練が実施されている。訓練への参加率は、2020年は昼間訓練が37.5%、夜間訓練が25.88%となっており、ここ8年ほどは目立った参加率の変化はなく、この状態をキープしている。
黒潮町の65歳以上の人口は約45%であり、防災訓練の参加者の約半分は65歳以上のシニア世代だ。とはいえ、黒潮町におけるシニアの防災意識は高く、防災訓練をスムーズに行うためのノウハウを各自が持っている。元気なシニアは決められた避難場所に自身で避難し、自分一人では避難できない支援の必要な高齢者は、自宅の玄関まで自力で移動する。玄関まで行くことができれば、後は地域の人々が補助して避難場所まで連れていく。高齢者が玄関外まで出ることで、地域の人たちが該当者を探すために家に入る手間が省け、避難時間が短縮される。

良い取り組みはどんどん取り入れる「まねっこ防災」
海に面した沿岸地域から山深い山間地域まで、黒潮町には61の地区=自治会がある。住民の防災活動を支援するため、町では全職員を61自治会に振り分けた地域担当制をとっている。避難計画は自治会ごとに違い、住民が何をすべきかも自治会によって判断される。最大34mの津波が襲うとされた想定の地区は、「共助」なしには犠牲者ゼロは目指せない。
区長をリーダーに、自治会ごとに防災計画が進められており、年に1回防災シンポジウムとして、先進的な自治会の防災計画が公開される。先述した「高齢者の玄関までの避難訓練」や、避難生活に必要な物資を衣装ケースに入れ避難場所に保管しておく「個人ボックス」など、町全体で取り入れたい取り組みが各自治会から発表されている。
良い取り組みをその地区だけに留め置かずに、町ぐるみでまねして防災意識を高めようという、「まねっこ防災」という意識も生まれてきた。ヘルメットをかぶったネコのキャラクターがコミュニティ防災計画についてガイドをする。黒潮町と京都大防災研究所が共同制作した動画教材も2021年9月よりネット上で公開されている。
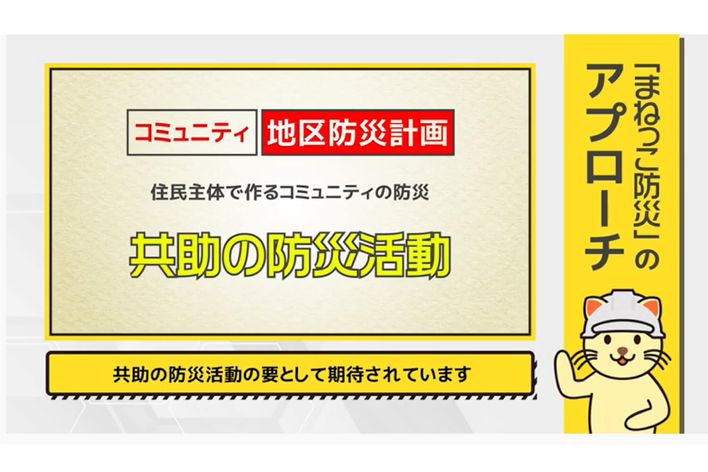
地区で力を合わせ犠牲者ゼロを目指す

町ぐるみの避難といっても、高齢者の避難をどうするかということが一番難しい。黒潮町の中学校では、地区の高齢者を連れて避難場所に逃げる防災訓練を行っています。子どもたちが「一緒に逃げよう」と声をかけることで、避難に消極的だった高齢者が積極的に避難行動をとるようになったという事例がよく聞かれます。
あきらめムードだった高齢者が「こんな立派な子どもたちがわざわざ私のために来てくれている。やっぱり一緒に逃げなければ」という気持ちを持つようになるんです。そして子どもたちとのふれあいを通して、「避難をあきらめない」から「人生をあきらめない」気持ちへとだんだんと変わってくる。高齢者の生きる姿勢までも変えてしまう力を持つ子どもたちは、町にとって非常に重要な存在です。
黒潮町では防災教育に力を入れています。町内の小・中学校は、防災訓練を年間で6回以上行っており、中には10回以上行っている学校もあります。また、保育所においては月に1回避難訓練をしなければならない規則があります。小さな頃から日常的に防災訓練を行い、防災意識が体に染みついた子どもは、間違いなくしっかりとした防災意識を持った一人の成熟した地域住民へと育ってくれます。そして、自分の子どもにも自分と同じ防災意識を持つように育ててくれるでしょう。
起こりうる自然災害に対して、自分の命を守ることをあきらめず、かつ地区で力を合わせて、犠牲者ゼロを目指していきたい。そのために何ができるか、何をしなければならないか。現在進行形で考えて、対策を積み重ねています。
保育所や小中学校の防災訓練の取り組み
黒潮町には小学校が8校、中学校が2校、保育所が4つある。学校だけでなく、地域ぐるみで防災訓練を実施しており、地域住民も子どもたちと一緒に高台や津波避難タワーなどの避難場所に向かう。中学校の防災訓練では、子どもたちが地域のおじいちゃんおばあちゃんの家を訪れ、手を引いて一緒に逃げる。「グラッと揺れたらすぐに高台へ」という意識が黒潮町の子どもたちには全員備わっている。

高齢者を防災訓練に参加させるため、
生きがいのある日常を
高齢者を積極的に避難させる気持ちにするためには、普段の生活を充実させなければならない。そして孤立させないことが必要だ。
地区の住民は地区全体で守るという住民の意識が、高齢者の「逃げることにベストを尽くす」という気持ちの変化を生む。地域にとってかけがえのないひとりの人間なのだということを高齢者に実感してもらいたい。そのために、黒潮町では高齢者一人ひとりに向き合い、粘り強くコミュニケーションをとっているほか、地域住民と高齢者がふれあうさまざまなイベントを画策している。「『防災』を合い言葉に、日常的な助け合いや地域コミュニティとしての強さも今まで以上に強くしていきたい」と松本町長は言う。
元気な高齢者は町を支える現役世代
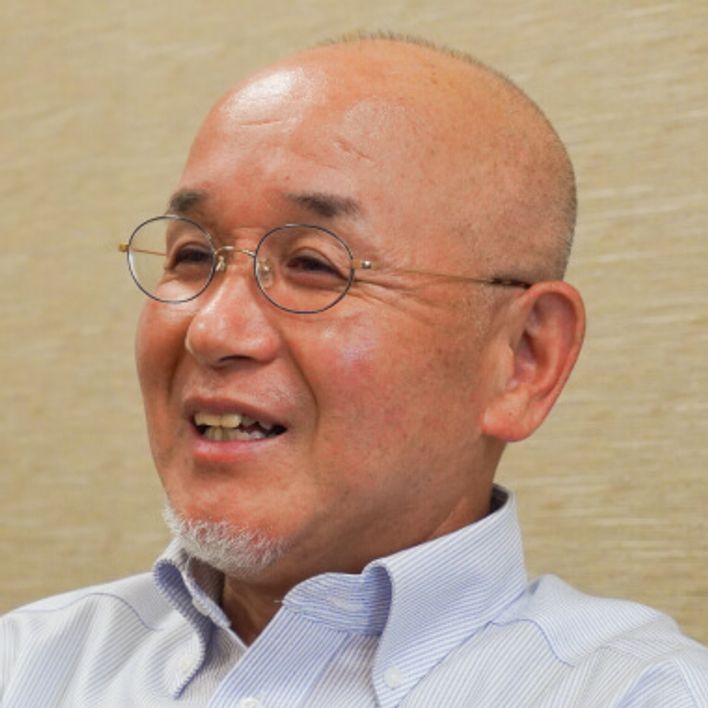
黒潮町では高齢化率が45%を占めております。65歳以上といっても、町内には元気でしっかりしている人たちが多く、福祉サービスを受ける側ではなく、町を支えてくれている重要な世代です。自分の生活を支えているのはもちろん、積極的に地域社会への貢献活動もしてくれています。ちなみに私も今65歳です。黒潮町では65歳はまだまだ若い世代になりますから、老け込んでいたら笑われてしまいます。
過疎化・高齢化が年々進む黒潮町では、劇的な若返りは見込めませんから、高齢者といっても年齢に関係なく、健康な人が町を支えなければなりません。元気に楽しく暮らしていくため、健康寿命を延ばす取り組みを町をあげて行っており、高齢化率の割に元気な人が多いと感じています。
健康寿命を延ばす「三世代ふれあい健診」や「健康体操」
黒潮町では、2005年から高知大学教育研究部医療学系臨床医学部門と連携した「三世代ふれあい健診」を行っている。夏休みの3日間、小学生がスタッフ側に立ち、65歳以上の住民の方の筋力・体力測定を行う。孫や近所の子どもたちに、良いところを見せようと、それに向けて体力づくりに励む高齢者も多いのだという。体力測定後には、医師からのアドバイスも受けられる。
ほかにも、町では8年ほど前からケーブルテレビ局と一緒に食生活改善推進員が出演する食生活改善のためのレシピ番組や運動指導士考案の健康体操番組などを放送するなど、住民の健康寿命を延ばすための取り組みを積極的に行っている。

介護保険料を月額500円下げることに成功
楽しく毎日を過ごすため、健康寿命を延ばすことに住民の意識が向かった結果、黒潮町では2021年度より3年間、介護保険料を月額500円下げることに成功した。
町では町内に6箇所ある地域福祉の拠点施設「あったかふれあいセンター」を中心に、住民の連帯意識を高め、健康寿命を延ばす取り組みを今後も行っていく予定だ。自然豊かな高知県の中でも、海あり山・川ありの何でも揃った豊かな自然が自慢の黒潮町。
「災害への緊張感を持ちつつ、山歩きや、海や川で魚を釣ったり、黒潮町ならではの環境の良さを生かした取り組みを考えていきたい」と松本町長は結んだ。

※2021年9月21日取材時点の情報です
写真:黒潮町提供



 この記事の
この記事の