島根県雲南市を拠点に、キーワードを「おせっかい」とする新しい「健康づくり・まちづくり」の輪が広がっている。今回紹介するのは、「コミュニティナース」と呼ばれる人々が地域の人々の日常生活に入り込んで、心身ともに健やかに暮らすためのお手伝いをする活動だ。この斬新な地域での活動について、発起人である矢田さんにお話を伺った。
監修/みんなの介護
【ビジョナリー・矢田明子】
コミュニティナースの取り組みで
病気になる前に「気づき」を与えたい

勘違いされることも多いのですが、「コミュニティナース」というのは肩書きではなく、私たちの「活動の在り方」です。一方的にこちらからケアを提供するのではなく、地域の人々と一緒になって、1番身近な場所から、「楽しいこと」「うれしいこと」「元気になれること」を実践していく。そういった在り方をコミュニティナースと呼んでいます。
この活動を始めたきっかけは、看護学生時代に知った「コミュニティナーシング」という考え方でした。医療施設ではなく、地域の中に看護できる人がいて、何気ない暮らしの中で健康づくりのアドバイスをするというものです。
一般的に、病院は病気になったときにはじめて行くものであって、ふらっと気軽に行けるところではないじゃないですか。だからこそ、病気になる前に「気づき」を与えてあげたり、体調の相談に乗ったりできる人が、地域にいた方がいいと思ったのです。
最初は店先などでの健康相談から始まった
矢田さんがコミュニティナースを始めたのは、看護学生時代だ。そのきっかけのひとつが、お父様ががんで亡くなられたことだったという。
「父が亡くなったのは、私が26歳のときでした。体調を崩して病院に行くと、すでに全身にがんが転移していることが判明しました。それから数ヵ月で帰らぬ人になったとき、『もっと身近に健康について相談できる人がいれば状況は違ったのではないか』と思ったのです」
そんな想いを抱えて看護学校に進んだ矢田さんが、コミュニティナースという概念と出会ってから行動に移すまでに時間はかからなかった。入学した翌月には、地元の喫茶店や公民館などでアルバイトとしてコミュニティナースの活動をスタートさせた。地域の人々に積極的に話しかけ、健康づくりのアドバイスを始めたのだ。

「大学の教授や同級生には『やめなさい』と止められました。『まだ学生で勉強中の身だし、間違ったことを伝えて取り返しのつかない事態になったらどうするの』と。でも、私はこういう活動をするために看護師の勉強をしようと思っていたので、躊躇はしませんでした。最終的には、教授や友人も巻き込んで、みんなで実践することができたのです」と、矢田さんは語る。
「まちの健康ステーション」として取り組みが広がる
医療・福祉関係者だけでなく、異業種の人々と連携して「まちぐるみ」で活動を広めているところも、矢田さんが実践するコミュニティナースの特徴だ。例えば、地域の老若男女が集まる郵便局や美容院などを「まちの健康ステーション」と位置づけ、局員さんたちと連携して高齢者や要介護者のケアを進めている。

「病院や福祉施設の職員さんがケアするよりも、普段から身近に接している人が気遣ってくれるほうが、高齢者も安心すると思うんです。老人ホームのような施設は確かに社会に必要ですが、それが最良の選択ではないという高齢者もいます。やはり、それまで暮らしていたまちとのつながりが絶えてしまうからです。じゃあ、老人ホームのようなケア機能をまちが担保すれば良いのでないでしょうか。すべての高齢者に当てはまる訳ではないかもしれませんが、私はそういう選択肢もあったほうが良いと思っています」
異業種と連携して「おせっかいの輪」をまち全体に広めていく。医療・福祉を出発点に、矢田さんは、共同体としてのまちの未来像をみつめている。
コミュニティナースの活動は
チームとして推進していく段階に

始めは一人きりで行っていたコミュニティナースという活動ですが、今は「Community Nurse Company」という会社を立ち上げ、組織的にエリアを広げています。一人でやっているときも壁にぶつかってばかりでしたが、会社としてぶつかる壁はまた異なるものだということを感じています。
会社の代表としては、この活動を持続するために、ビジネスとして成立させることが大切だと思っています。また、仲間のモチベーションを保つために、目に見える形で成果を上げることも必要です。
そのために研修などを開催して、情報を共有しています。その際に私がずっと言い続けているのは「一人で完結させなくて良い!」ということです。学生時代に教授を巻き込んだ話とも共通するのですが、必要なのは一人で何でもできるスーパーパフォーマーではなく、みんなで助け合って補完させられるチームだということです。
私たちはスタッフの「ウィル(したいこと)」「キャン(できること)」「マスト(求められていること)」を大事にしています。このうち、「キャン」はみんなで達成すれば良いものです。そのために、いろんなスキルを持つ人々を集めて、「高齢者を含めた誰もが健やかで楽しく暮らせるまちづくり」というゴールに向かって邁進しています。
「ナスくる」では高齢者の「楽しい」を支援
矢田さんが「Community Nurse Company」の代表取締役として取り組んでいるのが、「ナスくる」というサービス。高齢者や要介護者が住む自宅などへ定期的に赴き、おしゃべりや趣味のお手伝いを通じて人間関係を構築しながら、心身ともに健やかで幸せな日常を送れるようサポートするというものだ。

「第二の親戚」のような存在を目指すこのサービスを通じて、矢田さんは「楽しいと思えることがいかに高齢者にとって大切か」ということに改めて気づいたという。
「利用される高齢の方々が、みるみるうちに元気になっていくんです。スマホで撮った写真をうれしそうに見せてくれたり、スタッフが自転車に乗っていると自分も買って乗ろうとしたり…。歳の離れた友だち感覚でスタッフと楽しく過ごすうち、気持ちが若返ってくるんでしょうね。それって、とてもすてきなことだと思いませんか」
行政と連携した新事業への挑戦も
矢田さん1人での活動から始まり、現在は会社組織での取り組みへシフトしている。スケールが大きくなり、コミュニティナースという活動の可能性が広がっていくと同時に、新たな課題も出てきているという。
「私たちの活動を何かしらのメディアで知り、自ら、雲南市に移住したいと申し出てくれた他地域在住の高齢者が数人いたんです。コミュニティナースのいるまちに住んで暮らしたい、と。非常にありがたいことです。でも、今の私たちは居住の面までお世話できる機能を持ち合わせておらず、残念ながら見送りすることになりました。居住面までカバーできるような体制づくりも、これからの課題だと思っています」
また、矢田さんたちは、内閣府と成果連動型民間委託契約(Pay for Success)を結んでいる。「地域おせっかい会議」によって介護予防の成果をあげることで、その成果に応じた委託費やインセンティブが支払われる仕組みだ。これは、ビジネスとして軌道に乗せられるかを判断する、大きな材料となる。

それぞれの「ウィル(したいこと)」「キャン(できること)」「マスト(求められていること)」を共有し、スタッフ一丸となってこの目下の介護予防という課題に取り組むことで、より豊かな「おせっかい」を追求している。
「ご近所づきあい」による社会形成で
地域の可能性を拡大していく
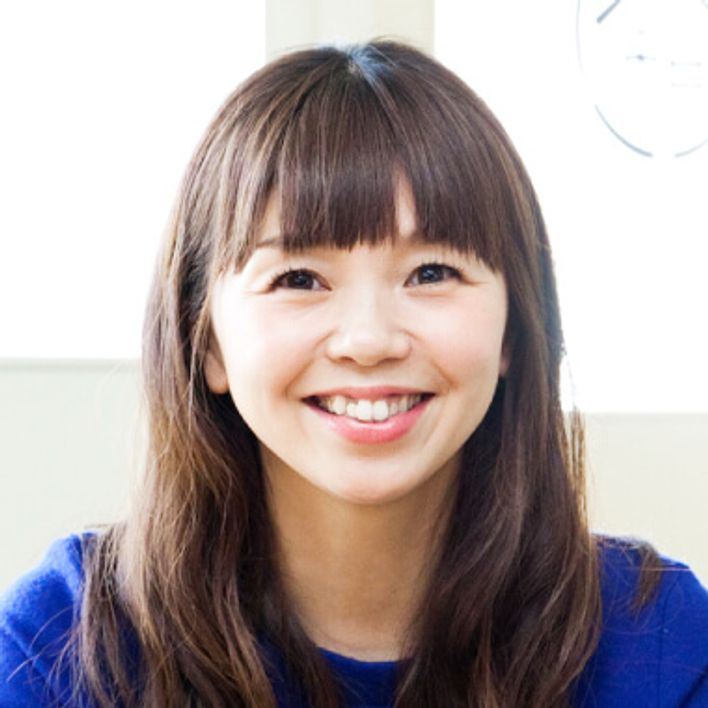
近年は、高齢者や要介護者だけでなく、子どもとその親にも目を向け、子育てしやすいまちづくりに貢献できることはないかと考えています。子どもたちを対象にコミュニティナースを実践するということです。2021年春には、小規模多機能型の子育てを実践する施設「地域まるごと子育て 縁」をオープンしました。
根底にある考え方は、やはり地域全体で子育てをするということ。家族だけではなく、高齢者を含めた地域の人々たちとのふれあいを通じ、子どもたちの可能性を伸ばしていきたい考えています。
こういうふうに言うと、「新しいアイデア」のように思われてしまうのですが、昔はどこにでもあった「ご近所づきあい」です。いつの間にかなくなってしまいましたが、まちにはもともと高齢者や子どもたちに「おせっかい」をする機能があったんです。
コミュニティナースという活動は、その機能を取り戻すためのもの。病院や福祉施設、学校に任せきりにするのではなく、「みんなでやればできる!」ということを、改めて感じてもらえればと思います。そういう意識を共有できているまちは、あらゆる世代にとって暮らしやすい場所になると思うんです。
「地域まるごと子育て 縁」がつながりの拠点に
地域の文化や自然を活かし、雲南市独自の子育てを実践する「地域まるごと子育て 縁」も、コミュニティナースと同様にユニークな取り組みだ。キーワードは「まちぐるみ」で子育てを行うということ。地域の大人たちと子どもたちが日常的に触れあえる機会を積極的に設けることで、まちのコミュニティをより豊かに育むことができる。

そうして育てられた子どもたちが大きくなったとき、地域の高齢者に「おせっかい」ができるようにすることを最終的なゴールとして見定めている。医療・福祉だけでなく、教育・育児の機能も「まち=コミュニティ」に復活させるという試みと言えるだろう。
地域のコミュニティの中で、子どもから高齢者、要介護者を含むあらゆる人々が縁をつなぎ、楽しく、健やかに暮らしていける。そんな共同体の機能が充実した「小さな拠点」の次世代モデルが目指されているのだ。
海外でも地域のつながりは注目を集めている
これまでの日本では、医療と介護をシームレスにつないで「最後の受け皿」をつくることが重視されていた。しかし、医療・介護機能を充実させながら、「コミュニティ=ご近所づきあい」を核としてとらえた社会形成が必要なのではないか。
そんな考え方が、矢田さんたちの活動の原動力となっている。そしてこの考え方は、近年、海外でも広まりつつあるという。
「少子高齢化が進んでいるのは世界的な問題です。日本はいち早くその壁にぶつかった国だと言われています。だからこそ、介護医療体制の充実がずっと図られてきた訳ですが、今、そのような『あり方』はターニングポイントを迎えています。私たちが実践しているコミュニティナースの活動が海外からも注目を集め始めているのは、その表れだと思うのです。病院や福祉施設への入院・入所によって高齢者のコミュニティを分断するのではなく、つながりを保ったままできることもあるという考えが広まっているのです」
矢田さんたちの活動は、懐かしくて新しい社会形成の重要なマイルストーンとなり得るかもしれない。
※2021年4月14日取材時点の情報です



 この記事の
この記事の