秋田県の県西部に位置する大潟村。人口の減少スピードが国内トップクラスの秋田県で唯一、消滅可能性都市を免れた自治体だ。かつてこの場所は、大きな湖だった。戦後まもなく干拓が行われ、大潟村は農業のモデル都市を目指して政策を行ってきた。村民のほとんどが農業従事者であり、現在はスマート農業や海外輸出へのチャレンジを行っている。今回は、2008年の着任以来、「開拓者精神」をモットーに村政に取り組んできた髙橋浩人村長から話を伺った。
監修/みんなの介護
【ビジョナリー・髙橋浩人の声】
55周年を迎える大潟村が目指すのは「農業のトップランナー」であること

大潟村は、常に農業のトップランナーであることを目指した政策を掲げてきました。この村は稲作が中心ですが、米は人口が減る分需要も減るだろうと言われています。
そこで今年で55周年を迎えるこの村は、次の100周年を目指して「農業チャレンジプラン」を制作しました。モデル農村としての特徴やこの村の資源を受け継ぎ、発展させることを目標に、「住み継がれる元気な大潟村」を目指しています。稲作中心で農業を行う村民がほとんどの状態から、今後を見据えて「しなやかで強く、競争力のある大潟村農業の創出」の基本方針をチャレンジプランとして定めました。
今回のプランは、「飛躍と持続を可能とする農業」「水田稲作農業の新たなチャレンジ」「大潟村発知識集約型農業の展開」という3つの視野から、今後の大潟村農業の振興を検討したものです。具体的には、次の50年を見据えた経営形態の模索、新たな高収益作目の導入、稲作の再構築、スマート農業の基盤作り、意欲ある人材の確保、環境創造型農業推進、村民全体の収入増などです。
厳しい時代に備えて新しい農業にチャレンジし続ける
秋田県では農業を行っている人口自体は多いものの、大潟村のように常に新しい農業へのチャレンジを村全体で行っているのはとても珍しい。
髙橋村長は、県内の農業高校から東京農大に進学。卒業後はアメリカ・オレゴン州にて農業研修を2年行い、大潟村へ戻っている。オレゴンでは、タマネギやジャガイモを中心に作物を育てていたそうだ。初めて体験する大規模な農業は、タマネギのタネを直蒔きするなどの気候に合わせた効率的な農業だった。
県内の農業地は、中山間地が多く、面積も小さく点在している。そのため、機械作業や運搬に苦労が多い。その点、大潟村は田んぼがまとまって平地にあるため、農作業がしやすい。
需要が減少して米の価格が下落することで、いずれは農業がもっと厳しくなると言われている。そのために村では、県立大学よりアドバイスを受け、この農業に適した土地で大規模な高収益作物としてのタマネギの導入や、将来的な共同で田畑を耕作する計画も企んでいる。
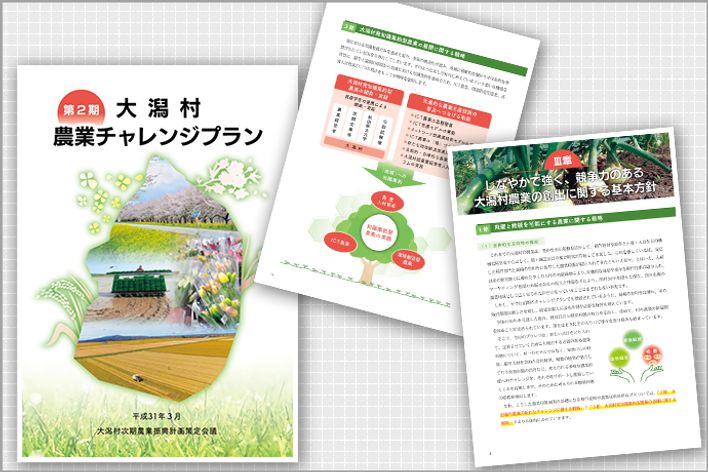
個人の田んぼのほか、大規模な畑を共同で経営する。村長の経験、恵まれた土地、そして農業のプロフェッショナルである村民が揃ったからこそできる試みである。
村民と良好な関係を築き、意見は積極的に取り入れる
1966年の第一次入植者募集から始まった大潟村は、大規模農業のモデルを築くため、県内外から入植希望者が集まって今の形になった。当初、入植者たちには、10haの農地が配分され、1975年の追加配分で15haとなった(現在は平均17haを所有)。
かつて減反政策(米の生産調整のため転作させること)や青刈り(作物を成育途中で刈り取ること)などで、国や村役場と、農家の歯車がうまく合わない時代もあった。しかしそんな時代を経て、今では良好な関係性を築きあげている。
村は農業や農村の未来を考え、チャレンジ力の強い開拓者精神を持った村民の意見をとりいれた政策を打ち出している。米の収穫は、1年で大体のサイクルが決まっていて収入は今も安定している。そのため、新しいことにチャレンジしやすいのも大潟村の特徴である。村長自身も今は公務があり、頻繁には難しくなってしまったものの、できる範囲で休日には田畑に出て作業をしている。
また平成20年には、以前にも協力関係があった秋田県立大学と連携協力協定を結び、村農業へのアドバイスや土地に合った作物の研究を行ってもらっている。
村の歴史や開拓者としての誇りを第三世代に受け継いでいく

私は小学校低学年まで、県北部の旧二ツ井町という場所で育ちました。そこから、家族で大潟村へ入植をしました。大潟村では、私の父親世代(今の70~80代)が第一世代として活躍。親の背中を見て育った第二世代は、村の歴史や開拓者精神を肌で感じて、親のあとを継いでこれまできました。
しかし、時代によって農業のあり方は変わって行かなければなりません。また、今の20~30代の第三世代へはどうやって開拓者精神を伝えていくかが、課題だと思っています。農家と言われる人たちは、経営者であり、親方なのです。
これからの世代の人たちは、経営も学び、国内にとらわれず、海外へも挑戦して行くことが求められています。その実現のためにプログラムを組むなど、高度な人材育成も行いたいと考えているところです。時代にあった新しい農村や農業のスタイルを構築することが、私の使命でもあります。
また大潟村には、海外からの人材を受け入れている農業法人があります。そこから斡旋された海外からの労働者に対しては、今後も地域の一員として頑張ってもらえるように、村全体でサポートしていきます。
若者を対象とする「高度人材育成」が来年からスタート
人口減少率が全国で一番高い秋田県でも、大潟村は減少率が緩やかである。それには、ほかと比べてもUターンする人がとても多いことが理由にある。村に高校がないため、村外の高校や大学への進学、就職などで首都圏へ出て行った若者が、村に戻ってきて親の後を継ぎ、農業に勤しむのだ。

職がないと故郷に戻れないケースが多いなか、収入や生活の安定性などを理解している大潟村の若者たちは、家業の農業を引き継ぐ。しかし第三世代ともなると、開拓者精神の引き継ぎが難しい。
村では開拓者としての自立心やチャレンジ精神を引き継ぐために、若者たちを対象とした「高度人材育成」を来年度からスタートさせる。農家として作物を育てる知恵や技術はもちろんだが、将来に備えた経営や販売方法を徹底的に考えてもらう。これからは、育てるところから売るところまでの知恵を得ることがとても重要だ。
丁寧な人材育成が村の未来に繋がると信じての政策である。行政が1人に対してそこまでの支援を行うのは、とても珍しいことだ。
海外からの人口も受け入れ、村の一員に
また大潟村は、村民みんなが入植者であるため、移住者や訪れる人に対しても抵抗なく接することができる。村では、働き手として移住者の受け入れもスタートさせている。
現在ではベトナムから6名が移住し、農作業に従事している。ここで働くことは、この土地での農業について知ることができ、村民とも密にかかわれるため学びの幅が大きい。さらに今年度中には、介護などの福祉の仕事に就くために、インドネシアからの移住者が3人来ることも決まっている。
外国人移住者には村の一員として生活してもらうため、村のイベントや国際交流協会と連携したパーティを開催し、村民と交流できる場所を作っている。さらに、移住者たちには村営住宅を1人1部屋貸し出しており、今後も移住者を受け入れていく予定である。
100年住み継がれる村を実現するために「農福連携」から海外進出へ

現在は方向性が同じだから、村の内部で以前のようにもめることはないと思っています。苦しい時代もありましたが、農業に対してトップランナーであり続けたいと思う心はみんな一緒。海外輸出へのチャレンジも、協力して頑張っていくつもりです。
そして、次の100年に向けて「住み継がれる元気な大潟村」を実現して行きたいです。若い世代を育てて、これからの時代どうやって農業で勝負していくかはもちろんのこと、「日本一元気な長寿村」の構築にも力を入れたいと考えています。
村役場の周りには、柿の木があります。これは高齢者グループ「老人クラブ」の方々が育てたもの。また、春に観光客が訪れる名所になっている桜並木と菜の花ロードは、高齢者グループ「耕心会」が栽培管理しています。農業は引退しても、彼らが長年培った知恵を生かして、柿や菜の花などを育ててくれているのです。
老人ホームに入居しているご老人たちが花の栽培に挑戦したり、植物の成長を眺め、咲いた花に感動したりすることは、認知症の改善などにも効果があると聞きました。このように、一人ひとりができることでかかわれるような村づくりが私の目指すところです。
「農福連携」で高齢者は地域貢献しつつ、認知症予防ができる
大潟村では農業と福祉の連携をするために、「農福連携」を総合計画のひとつに盛り込んでいる。高齢者の生きがいづくりや介護予防、障がい者の就労支援や、雇用の場づくりを目指している。長年農業に従事した高齢者の豊かな知恵と経験を活用して、社会参加支援を行う。

この村だからできる農福連携を目標として、農業の生産や景観、癒し、学習、交流を進めている。これを実現するために、農業者、高齢者、障がい者、大学、ボランティアの4者が連携して、ファームを管理運営している。これがきっかけで、ファームが地域の拠点となり、自宅や施設に閉じこもっていた高齢者が18名も地域活動に参加することとなった。
平成30年4月に畑を作るところから始まった計画だが、初年度にはもう栽培したかぼちゃを出荷するまでとなった。今後は、かぼちゃのほかに、タマネギやニンニクの栽培も予定している。高齢者の知恵を生かした、新しい農業のあり方のモデルケースとなっていくだろう。
特産品などを海外へ輸出する「田畑複合経営」への挑戦を
大潟村で作られたグルテンフリーのパスタ、マカロニ、米粉餃子、そして米が、オランダや台湾、香港へと輸出され、現地の人気商品となっているのだ。米の輸出は、国によっては販売できない場合があるが、加工品の販売は伸び続けている。国内に売ることだけにとらわれるのではなく、農産物や加工品を海外へ販売しようと力を入れている。
「いずれ米の価格は下がる」「農業は担い手がいなくなる」などと、農業は厳しい言葉ばかりを言われてきた。しかし、大潟村では決して現状に満足することなく、来るべきときに備えた政策を行っている。
稲作単体経営から田畑複合経営に転換し、稲作だけではないプラスαの付加価値をつけることを目指す一方、スマート農業などで効率化を図ってきた大潟村。村全体がまとまり、「農業のトップランナー」として同じ方向を目指すその姿勢には、かつての開拓者精神が受け継がれていると感じた。
※2019年10月25日取材時点の情報です
撮影:船橋陽馬(根子写真館)



 この記事の
この記事の