2018年11月、ロボットが給仕する近未来的なカフェが話題を呼んだ。ロボットを操作するのは、ALS(筋萎縮性側索硬化症)などの病気や障害で身体的なハンデを抱える人々だ。寝たきりの状態でも簡単に遠隔操作をすることが可能で、生身の人間のように注文をとったり飲み物を運ぶ姿はまさに「分身ロボット」と言える。しかし、ロボットが実現するのは便利さだけではない。“ロボットは人とつながるツール”と語る開発者の吉藤健太朗氏が目指すのは、“誰もが役割と居場所を持てる社会”だ。
監修/みんなの介護
【ビジョナリー・吉藤健太朗の声】
分身ロボットを通じて誰もが社会に参加できる

私は学生時代から電動車椅子やロボットの制作に携わっていますが、その目的は「孤独」を解消することです。テクノロジーだけでは人を癒やすことはできませんが、テクノロジーで人と人をつなげば孤独は解消できると考えています。
私が代表を務める(株)オリィ研究所が開発した「OriHime」(オリヒメ)は、カメラとマイク、スピーカーが搭載された身長20㎝ほどの遠隔操作型コミュニケーションロボットで、AIではなく人がパソコンやスマートフォンで遠隔操作して動かします。
オリヒメという名前には「織姫と彦星のように遠くにいても繋がっている」という意味を込めました。
このオリヒメは、身体的なハンデのある方だけではなく、育児や介護で出勤できない方のテレワークにも活用できます。オリヒメは操作する人の「分身」として、その人が行けない職場や飲み会、結婚式の披露宴の席にも行ってくれるのです。
ロボットカフェで未来型の就労支援
「いらっしゃいませ」
2018年11月、身長120cmほどのロボット「OriHime-D」(オリヒメ·ディー)が接客を務める「DAWN ver.β」(ドーン・バージョンベータ)が期間限定でオープンして話題になった。
SF映画のようなこのカフェは、吉藤オリィこと、吉藤健太朗さんが代表を務める、株式会社・オリィ研究所のプロジェクトである。
オリヒメ·ディーを操作しているのは、AIではなくALS(筋萎縮性側索硬化症)や脊椎損傷などの重い障がいによって外出が困難な人たちだ。自宅からパソコンで動かす分身ロボットたちはてきぱきとオーダーを取り、トレイに飲み物を載せて運んでくる。

カフェは2020年の常設に向けて準備を進めており、吉藤さんも「外出ができない方でもオリヒメ・ディーを操作すればカフェの店員として働くことができます。今回は試験営業ですが、十分に営業できるという手ごたえは感じています」と期待を寄せる。
オリヒメ・ディーは同社が開発する「OriHime」シリーズのひとつ。NTT東日本など既にオリヒメシリーズのロボットを導入している企業や大学は多く、福祉とともにビジネスやアカデミズムの場でもオリヒメたちは注目されている。
まるで、すぐそばにいるような感覚
オリィ研究所の入り口でもオリヒメが応対する。小さくて操作が簡単なこと、一見すると能面のような顔が特徴だ。オフィスのほか、全国の特別支援学校やフリースクールなどでも活用されている。
「オリヒメは行きたいところに行けない人にとっての分身」と話す吉藤さんが重視しているのは、ロボットそのものではなく日常のコミュニケーションだ。
「その場に本人がいなくても、オリヒメを通じていろんな人と『日常』を楽しむことができるんです。電話やメールは用事があるときだけしか使いませんが、『そこにいる』オリヒメは、普段の雑談や冗談も交わすことができます」

吉藤さんにとって、孤独とは「自分は誰からも理解されない、必要とされていないと感じて、孤独だと思ってしまっている状態」だという。
オリヒメを分身にすれば、身体的にハンデがあってもどこにでも行けて、誰とでも話せて、仕事もできる――吉藤さんの目指す孤独の解消につながる。
「我慢弱さ」は、新しい未来を作る出発点
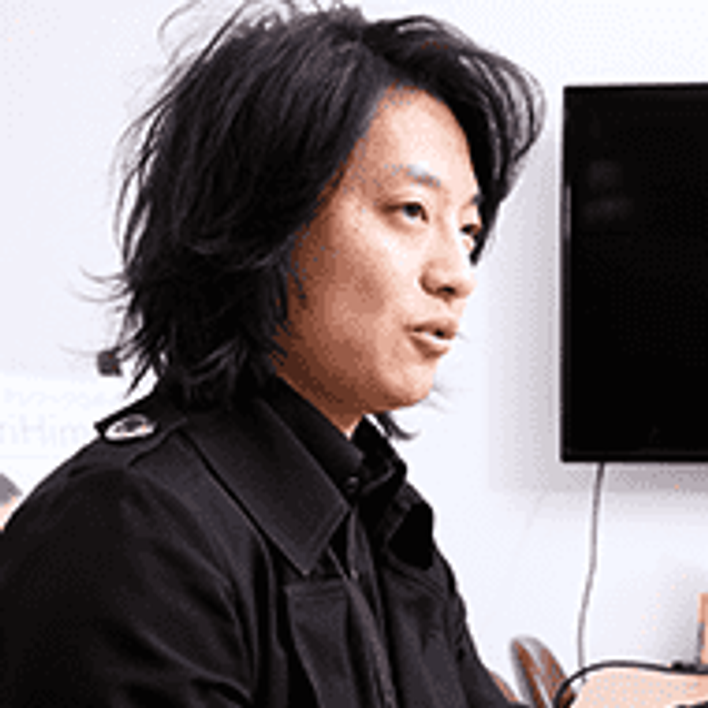
私は小さな頃から「我慢弱い」子どもでした。学校教育では「我慢強さ」ばかりを求めますが、そもそもなぜ学校の椅子と机は堅い木製なのでしょうか?朝から長時間座らなくてはならないのに…。制服も給食も、私にとっては納得できないことばかりでした。
でも、「こういうもんだから…」って諦める人がほとんどですね。電動車椅子の使い勝手が悪いのも、身体が動かない人が社会参加できないのも、「こういうもん」と言う。
私はそれをおかしいと思って、使い勝手の良い車椅子を考え、身体が動かない人の分身を作ってきたのです。車椅子でも自分の働く環境であっても、「こういうもんだ」と思ってしまうと先に進めません。
車椅子を健常者が開発するのも「おかしい」と批判されたことも何度もあります。私は車椅子を特別なものだとは思っていないので、バイクや車と同じように改良を重ねてきました。健常者もどんどん乗れば良いと思います。
自分自身もサイボーグ化する
自身をサイボーグ化して、もっと生活を便利にしたい、ラクをしたいと思うことが吉藤さんの創造の原点だ。2019年1月に上梓した著書『サイボーグ時代』(きずな出版)のテーマも「人間のサイボーグ化」である。
「コンタクトレンズも歯のインプラントも、便利に生活するためのものですよね。これを『障がいがある』とは言いません。同じような感覚で、健常者が胃ろうをつけてみるのはどうでしょう?手術も簡単ですし、苦手な食べ物は胃ろうから入れることができるので栄養も偏りません」
生活をより便利にするには、「我慢弱さ」は不可欠。ALSの患者さんにも「こういうもの」とは言わずに、ともに試行錯誤を繰り返してきた。
「病気で日に日にできることが減っても、できないことをテクノロジーでカバーすれば、病気や障がいがあっても人は前向きになれるし、未来を変えられると思います。だから、自分がまずしたいことを考えて、それができないハードル(障がい)をどうやったら乗り越えられるかを考えます。テクノロジーはハードルを越えるためのツールなのです」
吉藤さんはオリヒメ、オリヒメ・ディーの他に、眼球の動きを読み取る視線入力装置「デジタル透明文字盤」の「OriHime eye」(オリヒメ・アイ)も開発している。

これを使えば眼球しか動かせない人も、目の動きだけでオリヒメを操作できる。イラストのソフトを使って絵を描くことも可能だ。
誰もが「役割」を持てる社会に
サイボーグ化されれば、自分で自分を介護できる日も来るのか。
吉藤さんは、分身ロボットで自分自身を介護することをゴールとは考えていない。
「何でも自分でできることは、良いことでしょうか。マッサージとか、他人に何かをしてもらうのは普通に気持ち良いですよね」
そのうえで、介護されることを後ろめたく感じてしまう原因は、介護が『一方的な施し』のようになっているからだと指摘する。
「自分で自分のことができず、他人に何もしてあげられないから、申し訳なく感じるのだと思います。障がいがあっても、『自分が誰かの役に立てている』あるいは『他人に必要とされている』と思えれば、負い目は感じなくなると思います。介護の現場でも、介護される人が『ありがとう』と言われる環境を作れば良いんです」
ロボットカフェの構想もそうした思いがきっかけだった。
「私が秘書の番田雄太が操作するオリヒメに、『秘書なんだから肩をもんだり、コーヒーを淹れたりしてくれよ』と冗談を言ったのが始まりでした」
インターネットを通じて知り合った番田さんは、4歳で交通事故に遭って脊髄を損傷して首から下が動かず呼吸器もつけていたが、吉藤さんの「寝たきり秘書」として活躍、ともにオリヒメの開発や講演活動を続けていた。
「番田は亡くなりましたが、カフェは成功させて、いろいろな人たちが役割を獲得できる社会を実現したいと思っています」
テクノロジーは役割と居場所をつくるツール

私は小学校5年生から中学校2年生までの3年半の間、不登校と引きこもりを経験しています。あまり身体が丈夫でなくて病気がちで、それに他人と話すことが苦手な、いわゆるコミュ障(対人コミュニケーションを苦手とする人のこと)でもありました。
独りで部屋に閉じこもり、祖母が教えてくれた折り紙を折ったり、絵を描いたり、オンラインゲームに没頭したりしていました。
家族にも申し訳なく、学業の遅れも気になって、とても孤独で辛い日々でした。
でも、この頃があったから、今の私がいます。私のような孤独な存在を作らないためにロボットの製作やカフェの運営などを始めましたし、熱中した折り紙はロボットのプロトタイプ作りや初対面の人とのコミュニケーションにも役に立っています。
また、ゲーム内でキャラクターというアバター(分身)を通してなら会話もできることにも気づいたことは、リアルなアバター、つまり分身ロボットの製作を考えるきっかけにもなりました。
パニック障害や自閉症の子どもでも、オリヒメを通じてなら会話ができます。実際にオリヒメで授業に出たことで大評判になり、そのうちに本人が登校できるようになった例もあります。
10代で感じた孤独が今の自分をつくってくれた
吉藤さんが引きこもり生活を解消できたのは、お母さんが応募した「ロボット・コンテスト」の出場と優勝だった。もともとロボット製作にも興味があり、もっとロボットを作ってみようと、猛勉強して工業高校に入学する。
「あるコンテストで見かけた高校の先生が『奈良のエジソン』と呼ばれた方で、その先生に弟子入りして、新電動車椅子の開発に関わることができました」
多くのコンテストで受賞を重ねる一方、身体の弱かった吉藤さんは「自分は30歳までしか生きられない」と考えていた。亡くなるまでに「孤独を解消することに人生を使おう」と決意する。
「高校を卒業してから香川の高専に編入してAIの研究をしたのですが、やはり人を癒やせるのは人しかないと思って中退しました。人と人のつながりこそが孤独の解消に繋がると気づいたのです」
その後は早稲田大学創造理工学部に入学、さらにロボット製作を学ぶが、分身ロボットを作れる研究室がなかったため、当時借りていた六畳一間の部屋を「オリィ研究室」として分身ロボットの開発を進めることになる。「ない物は自分で作る」がオリィ流なのだ。
これからは仲間づくりに力を入れたい
「30歳までに…」と目標を追ってきた吉藤さんも現在32歳。ロボットカフェの常設化など、進行中の仕事も多いが、今後も「仲間を増やしていきたい」と意欲を見える。まずは「オリヒメ」の知名度アップだ。
「『オリヒメ』は多くのメディアに取り上げていただいていますが、まだ知名度が低く、ALSの患者さんに『もっと早く知りたかった』と言われることが多いです。より多くの方に知っていただいて、ALSで苦しむ人に選択肢を増やせればと思っています」

また、「それぞれが居心地の良いコミュニティを三つ以上持つこと」の重要性を挙げる。
「私は『居場所』をとても大切だと考えています。居場所が三つ以上あれば、一つくらいなくなっても大丈夫ですよね。居場所と役割があれば、生きていけると思います。テクノロジーは居場所や役割を得るためのツールなのです」
10代の頃に孤独と向き合い続けた吉藤さんが考える「孤独解消戦略」は、これからも多くのアプローチが期待できそうだ。
撮影:丸山剛史



 この記事の
この記事の