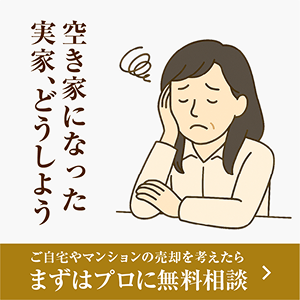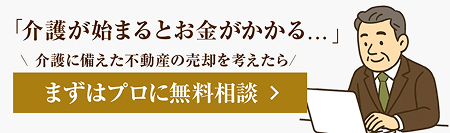梅原大吾「プロとしての仕事の基準は“したいか”ではなく“すべきか”どうかです」
2010年、日本で初めてプロのゲーマーとなった梅原大吾氏は、格闘ゲームの「神」と崇められるだけでなく、「The Beast」のニックネームで知られる世界的超有名人。「世界で最も長く賞金を稼ぎ続けているプロゲーマー」としてギネス認定を受け、2012年に上梓した『勝ち続ける意志力:世界一プロ・ゲーマーの「仕事術」』(小学館101新書)は多くのビジネスパーソンの支持を集めた。そもそも、プロゲーマーとはどういう仕事なのか。世界のウメハラに、まずはそのあたりから語っていただこう。
文責/みんなの介護
ライバルと切磋琢磨すること。仕事で腕を磨くためにはやはり必要不可欠です
みんなの介護 梅原さんは2010年にアメリカの企業とスポンサー契約を結び、日本人初のプロゲーマーになりました。2018年現在、日本でプロのゲーマーとして活動されている方はどれくらいいらっしゃいますか。
梅原 実は何をもって「プロゲーマー」と呼ぶのか、明確な基準があるわけではありません。つい先日、プロゲーマーのライセンスを発行する団体が誕生しましたが、今後どのように展開していくのか、先行きはまだ不透明な状況ですね。とはいえ、ゲームだけで生活できている人を「プロ」と呼ぶのであれば、僕の専門である格闘ゲームの世界では、ゲーム会社にゲーマーとして雇用されている人を含めて15人くらいでしょうか。
みんなの介護 プロの人がそれだけ増えたのは、やはり梅原さんがプロゲーマーとして生きていくための道筋を作ったからですね。
梅原 僕がプロになった当時、プライドを賭けて格闘ゲームに熱中している人たちは大勢いました。プレイヤーたちが大勢いたからこそ、僕も彼らと切磋琢磨しながら腕を磨くことができた。自分で言うのも何ですが、当時、知名度から言っても、影響力の大きさから言っても、僕がプロゲーマー第1号になることには、周りの人たちも納得してくれたと思います。と同時に、「自分もプロになりたい」と思った人も大勢いたはず。そうした人たちの中から、少しずつプロゲーマーが育っていったのだと思います。
みんなの介護 梅原さんはこのインタビューの直前まで、大会に出場するために台湾へ行かれていました。年間で何試合くらいに出場するのでしょうか。
梅原 僕の場合、年間で20~25試合くらいですね。
年間を通して自分がプレイするゲームのプロツアーに参加しています。大会で勝つごとにポイントが加算されていって、最終的に上位32名までが最後の決勝大会に出場できるシステム。そのため、その年のポイントの獲得状況によって、出場する試合数も違ってきます。ポイントを稼がなければいけないときは大会に出続けますし、決勝大会に出場できるだけのポイントが早めに獲得できれば、後半の大会をお休みすることもあります。逆に、ポイントが獲得できていたとしても、賞金を獲得するために、あるいは自分なりの技を探求したいときに、あえて大会に出場することもあります。
みんなの介護 大会が開催されるのは国内と海外、どちらが多いのでしょうか。
梅原 圧倒的に海外が多いですね。最も多いアメリカに続いて南米、ヨーロッパ、そしてアジアなど、世界各国で年間60試合以上開催されています。国内の大会はそんなに多くないんですよ。
もっと先に行くためには、もっと強い人と向かい合わなければいけない
みんなの介護 試合に出場していないときは、どんな活動をしているのでしょうか。
梅原 基本的には練習ですね。ゲームの戦術を練ったり、スキルを上げるための練習に時間を費やしています。
みんなの介護 1日何時間くらい練習するんですか?
梅原 2012年に初めて著書『勝ち続ける意志力』を出版するまでは、1日10時間以上練習していましたね。本を出してからは、今回のようなインタビューの仕事も増えてきて、練習する時間は減っています。今は平均して1日5?6時間でしょうか。もちろん、練習は長ければ良い、というものでもないので、本を出したことで悪影響が出ているとは言いませんが、たくさんの取材が入って忙しいときは、正直、もう少し練習したいなあと思うこともあります。
みんなの介護 練習はご自宅でされることが多いのでしょうか。
梅原 どこで練習するかは、「そのとき自分にとってどんな練習が必要か」で違ってきます。対戦会に参加することもあれば、一人で自宅にこもって練習することもあります。
対戦会というのは、本番の試合とは別に、プロゲーマー同士が月に数回集まって行われる練習試合のようなもの。現時点では、格闘ゲームはコンピュータより人間のほうが圧倒的に強いですから、自分が強くなるためには、できるだけ多くの強い相手と対戦する必要があります。そうやってプロ同士、切磋琢磨するわけですね。
ゲームは個人戦なので、みんな敵同士ではあるんですが、そうやって日本全体でレベルアップしておいたほうが、長い目で見ればお互いのメリットになります。相手がより強くなれば、その相手と対戦する自分もより強くなれますから。
そういった試合形式の練習が必要なときもあれば、独自に戦術や戦略を練りたいときもあります。そんなときは、一人で自宅にこもって、いろいろなことを試したりしています。
みんなの介護 現在、専門にプレイされているのは「ストリートファイター」ですね。
梅原 はい。試合では「ストリートファイター」しかプレイしません。かつては別の格闘ゲームをプレイしたこともありましたが、賞金総額やスポンサー企業の多さなどをみてもわかるように、「ストリートファイター」の大会が最も規模が大きい。それに僕自身、ずっとこのゲームを得意にしていました。そんなわけで、今は「ストリートファイター」1本に絞っています。
みんなの介護 ときどき、他のゲームを「プレイしてみたい」と思うことはありませんか。
梅原 子どもの頃はあらゆるゲームに対して「どんなゲームだろう?」とワクワクする気持ちがありました。しかし、プロになった今は「自分がプレイしたいかどうか」ではなく、真っ先に「プロの仕事としてプレイすべきかどうか」を考えます。

仕事中は目の前のことにぎゅっと集中していますが、問題を整理したいときには散歩などをしてそこから離れると良いですよ
みんなの介護 「仕事としてプレイする意味があるかどうかで考える」とおっしゃいましたが、ご自分の趣味としてゲームをすることはないのでしょうか。
梅原 プロゲーマーになって9年になりますが、この9年の間に趣味でゲームをしたことはもちろんあります。そのときどきに流行っていたゲームでしたが、どれも格闘ゲームではありません。
遊びでやっている分には勝たなければいけないというプレッシャーもないし、責任も感じませんから、ついついそれらのゲームに時間を取られてしまって、ふと気づくと、本業である格闘ゲームのプレイの質が下がってしまったことがありました。
そのとき痛感しましたね。「ああ、オレはもう、遊びでゲームすることは許されないんだな」って。それ以降、息抜きにゲームをするときも罪悪感を感じるようになったので、今では自宅で息抜きするときも「ストリートファイター」をやっています。
みんなの介護 趣味でゲームができないのは辛いですね。
梅原 ただし移動中に限り、スマホでゲームをすることはあります。「シャドウバース」とか、麻雀ゲームとか。シャドウバースは僕のスポンサー企業のゲームなので、ここでこんな話をすると宣伝しているようにとられてしまうようでツライですが、本当に面白いのでやっています。
みんなの介護 趣味でゲームができないとすると、自宅に帰って気分転換したいときには何をしているのでしょうか。
梅原 僕の気分転換になっているのは散歩ですね。仕事でゲームをしているときは常に追われるような緊張感を感じ続けているので、1人でぼーっと歩いていると、勝負の世界を忘れて心からリラックスできます。
歩くのは主に自宅周辺です。別に目的の場所があるわけではなく、街の風景をぼんやり眺めながら、最低でも1時間は歩きますね。夏の暑い時期には、できるだけ日陰を選びながら、ときには3、4時間歩くこともあります。
ぼーっと歩く、と言いましたが、実は歩きながら考え事をしていることも多いですね。性格的に、じっと座ったまま何かを考えるのは得意ではないので、何か考え事をしたいときに散歩に出かけることも結構あります。
もしかすると、散歩中はゲームしているときと同じくらい集中しているかもしれません。無我の境地というか、雑念をすべて振り払った状態で歩いているので。だから、どこをどう歩いたか覚えてないことの方が多いんです。
みんなの介護 散歩中もゲームのことを考えているのですか?
梅原 僕も一人の人間なので、ゲーム以外にも生活のさまざまなことを考えたりします。でもやっぱり、ゲームに関係することが多いかな。
ゲームに関して言えば、ゲーム画面を見ているときには絶対に思いつかないようなことを、散歩中にしばしば思いつきます。このときにあの技を出せばイケるんじゃないか、とか。そういうことは本当によくありますね。
みんなの介護 「物事に接近して見るだけではなく、時には引いて見ることも必要」ということでしょうか。
梅原 そうだと思います。ゲーム中は「ゲーム画面」という目の前のことにぎゅっと集中していますが、散歩をしていると、「ゲーム画面」から離れてより広い視野で物事を見ることが出来ます。特に、今抱えている問題を整理したいときには問題から離れて見ることが必要ですね。すると、「今まではこうだと思っていたけど、より広い視野で見ると、実はこうってことかもしれないな」と思いつく。実際に、そうやって新たな発想を思いついた時点で散歩を切り上げて帰ってくることも多いんです。
みんなの介護 気分転換としての散歩は、どれくらいの頻度で行っているのでしょうか。
梅原 ここ2ヵ月は海外遠征が続いていたので、散歩する時間が取れませんでした。木曜日に海外遠征に出かけ、翌週の火曜日に帰国して、1日休んでまた木曜日に海外へ、という繰り返しでしたから。
これだけ試合が続くと、さすがにストレスが溜まってきます。神経が高ぶり過ぎて不眠症気味になるし、気分まで落ち込んでしまう。勝負勘だけは研ぎ澄まされていきますが、それにも限界があって、疲れが蓄積してくると、今度は試合でのパフォーマンスが落ちてくる。何より、自分自身で成長が感じられなくなるのが辛いですね。
こうなることは自分でもわかっているので、そういうときは意識的に散歩する時間を作るようにしています。幸い、今度の香港遠征の後はしばらく国内にいられるので、帰国したらまず散歩をします。散歩することで、感覚や思考が平常の状態にリセットされるんです。
集中することと一歩引いて考えること。この2つがそろって初めて、自分は成長出来る
みんなの介護 ここ数年、ビジネス界では「働き方改革」が話題になっていて、「ワーク・ライフ・バランス」が重視されるようになってきました。梅原さんは一般人の趣味に当たる「ゲーム」をワークに選んだわけですが、現在のワーク・ライフ・バランスはどのようになっているのでしょうか。
梅原 自分では、ワークとライフのバランスがあまり良くないなと感じています。プロゲーマーは一般的な労働環境からすると自由な仕事ではあるけど、逆に言えば、自由に何十時間でも仕事ができてしまう。だから、「今日の練習はここまで」と自分で自分の仕事を打ち切らなければ、いつまで経っても仕事は終わりません。その決断がなかなか難しいですね。
僕がスポーツのプロであれば、話はもう少しわかりやすいのかもしれない。いくら練習したいと思っても、肉体的な限界があるはずですから。ところが、ゲームはスポーツのように肉体を酷使しません。練習しようと思えば、何時間でも練習できてしまう。僕は「世間から注目されている」というプレッシャーをいつも感じているので、たとえば練習を切り上げるとき、「今日の練習を本当にここで終わりにして良いのか?」「もっと練習しなくて良いのか?」といった強迫観念から逃れられないのです。
僕の場合、もしかすると、1日24時間「仕事中」の感覚になってしまっているかもしれません。それは良くないことだと自分でもわかっているので、気がついたときには、できるだけリラックスする時間を増やそうとしています。
みんなの介護 梅原さんはご自身の著書の中で「勝ち続けることは、成長し続けること」と書いています。また先ほどは、疲れてくると成長が実感できないので辛いとおっしゃっていました。勝負師である梅原さんにとって、「成長」はひとつのキーワードなんですね。
梅原 格闘ゲームの世界における「成長」には、①出来なかったことが出来るようになること、②知らなかったことを知ること、という2つの要素があります。
①については、主に手先の技術の問題になるので、反復練習によって出来るようになります。これは、プロのゲーマーなら誰でもやっていることです。問題は②。実は、知らなかったことを知ることのほうが難しいですね。ゲームに関する表面的な知識については、今はインターネットがあるので、比較的早い段階でほぼ出尽くしてしまいます。そしてこのレベルの知識は、誰でも簡単に手に入れることができます。
しかし、そういう知識を持っているだけでは、実際にゲームで勝つことは出来ません。勝つためには、そういった表面的な知識を自分なりにいくつか組み合わせなければならないのです。例えば、Aという操作とBという操作を組み合わせれば、Cという動きができるようになる、とか。こうした自分なりの発見をすることが、「知らなかったことを知る」という自分の成長になります。
みんなの介護 先ほど伺った「散歩の途中で気づくこと」にも、そういう発見が含まれているのですね。
梅原 まさしく、その通りです。
話は変わりますが、RPGの古典的名作に、仲間のパーティとダンジョンを探検するゲームがあります。後々のヒット作の多くに影響を与えたことで知られ、僕も子どもの頃、ずいぶんこのゲームで遊びました。
その当時、プレイヤーとしてずっと不満に思っていたことがあります。それは、戦闘でいくら経験値を積んでも、宿屋に一泊しなければレベルが上がらないこと。いちいち宿屋に泊まるのが面倒臭くて、「どうしてこのゲームはこんなややこしいシステムになっているんだろう?」と不思議に思ったものです。
でも、今考えてみると、僕にとっての散歩はその“宿屋”なんですよね。僕が目の前のゲームに集中して取り組んでいるとき、おそらく経験値はどんどん溜まっているはず。でも、そのデータ自体はバラバラで、自分で使いこなせるような形にはなっていない。それが、一旦ゲームから離れ、リラックスして散歩することで、データとデータ、知識と知識が有機的に組み合わさって、次に使える技として形作られていく。修得した技術や知識は、一旦寝かせることでより熟成し、より洗練されたものへと作り変えることができるんです。
集中することと一歩引いて考えること。この2つがそろって初めて、自分は成長出来るのではないかと思います。
負けた人が勝った人を恨んだり、嫉妬したり。そんなドロドロした部分にどうしても馴染めずに“勝負の世界から離れよう”と
みんなの介護 梅原さんは28歳で日本初のプロゲーマーとなる前、1年間ほど介護施設でヘルパーの仕事をしていましたね。介護スタッフからゲーマーに転身したのは、梅原さんならではの、まさに唯一無二の経歴だと思いますが、そもそもなぜ介護の仕事をしようと思われたのでしょうか。
梅原 それについてお話しするためには、僕の人生を十代の頃にまで遡らなければなりません。
僕が姉の影響で格闘ゲームに夢中になったのは10歳の頃。それからはゲームセンターに通い詰め、14歳で「ストリートファイター」ではほぼ無敵になり、15歳のとき全国大会で優勝。17歳で国際大会優勝、世界一になりました。
ところが世界一になっても、僕のことを知っているのは格闘ゲーム界の人間だけ。僕としては自分が有名になることで格闘ゲームの素晴らしさを世に広めたいと思っていたのに、全然そんな風にはなりませんでした。その後、いろいろな大会で優勝しても、状況はまったく変わらない。「世界最強の格闘ゲーマー」と言われても、その毎日はバイトしながらゲーセンに通うだけ。それで、ゲームの世界にいても未来はないと踏ん切りを付け、麻雀のプロになろうと決意しました。僕が23歳の頃です。
みんなの介護 なぜ、プロの雀士になろうと思ったのですか?
梅原 僕は勉強せずにずっとゲームばかりしてきたので、学歴もなければ資格もなく、おまけにコネもありませんでした。まさかそのトシから、野球やサッカーでプロを目指すわけにもいきません。
そんな自分が、腕一本で食べていくにはどうすれば良いのか。それで思いついたのが麻雀です。麻雀ならルールも知っているし、実際にプロも存在する。それに、ゲームをやってきた自分にとって、麻雀がいちばん身近なようにも感じました。
それから、雀荘に勤めながら2年半、麻雀に真剣に取り組みました。一応、腕には自信が持てるところまで上達しましたね。でも、それと同時に「何か違うなあ」という違和感もずっと感じていました。弱肉強食の勝負の世界だから、勝つ人がいれば当然、負ける人もいる。それで、負けた人が勝った人を恨んだり、嫉妬したり。そんなドロドロした部分にどうしても馴染めなかったのです。それである日、「もう、勝負の世界から離れよう」と決意し、すっぱり麻雀を辞めました。
麻雀を辞めたときは、両親も相当驚いていましたね。あんなに一生懸命取り組んでいたのに、そんなに簡単に辞められるものなのか、と。でも僕は、一度決めたら後ずさりしないタイプ。だから、辞めると決めたら麻雀には綺麗さっぱり何の未練もありませんでした。
ゲームや麻雀、飲食店などと比べ、介護は圧倒的に心地良かった。誰かによって競争させられることが一切なかったから
みんなの介護 麻雀のプロになることを止めた後、介護スタッフへと転職するわけですね。
梅原 麻雀を辞めた頃の自分は、勝負の世界に疲れ果てていました。勝ったら誰かに恨まれるし、負ければ自分自身の生活が苦しくなる。もう、そういう世界は懲りごり、という感じでしたね。
両親が医療の仕事に従事していたので、介護の仕事がどういうものかはある程度知っていて、親近感がありました。誰かと勝負することもなさそうだし、介護スタッフとして働いても良いかなと思ったのです。
みんなの介護 勤務先はどのようなところだったのでしょうか。
梅原 有料老人ホームでした。僕が受け持つことになった階は、全体の9割くらいが認知症のお年寄りでしたね。
麻雀の世界でも人生観が変わりましたが、介護の現場でも、やはり人生観が変わりました。僕の実のおばあさんも晩年は認知症を患っていましたが、特に介護の必要もなく亡くなっていたので、要介護のお年寄りに接するのは生まれて初めて。
そんなお年寄りの話を聞いてみると、「若い頃は社長だった」とか、「銀座の有名デパートで働いていた」とか言うのですが、そんな面影など、まるで残っていないわけです。「そうか、人は歳をとるといつかこうなるんだな」と、しみじみ実感しました。それまで、人生の終わりなんて想像も出来なかったのに、現実をいきなり目の前に突きつけられたようでしたね。
自分がまだ若いことに有難味を感じたし、歳をとってから後悔しないために、悔いのない生き方をしようと思いました。
みんなの介護 実際に働いてみて、介護の現場はいかがでしたか。
梅原 ゲームと麻雀の世界以外では飲食店などでもバイトしましたが、介護の仕事は圧倒的に心地良かったですね。それには、誰かによって競争させられることが一切なかったということが大きかったです。
僕は子どもの頃から、自分の意志に関係なく競争させられることが極端に嫌いでした。だから、点数を競い合う形での勉強が嫌いだったし、飲食店のバイトで「売上〇〇万円を目指そう」なんてハッパをかけられても、「オレには関係ない」と思っていました。ゲームのように自分の意志でやる競争なら良いけど、競争を強制されるのは勘弁、という感じですね。
その点、介護の仕事は競争とは無縁に感じました。仕事である以上、ある程度の効率は求められるのかもしれないけど、僕の経験では効率よりも気持ちや丁寧さが重視されたので、いつでも心穏やかでいられました。
確かに、給料が良いとは言えませんでしたが、時間もある程度融通が利くし、何より人に恨まれないどころか感謝される仕事ってなんてありがたいんだろうと思いましたね。下の世話にも抵抗はなかったし、お年寄りは優しい人が多かったので、それほどきついことも言われませんでした。とにかく、介護スタッフとして働いていた頃は、僕にとって居心地の良い時間でしたね。

介護よりきつい仕事はもっとある。それでも辞めていく人が多いのは「先が見えない」からなのでは
みんなの介護 その後梅原さんは、ゲームの世界にカムバックします。どのような経緯があったのでしょうか。
梅原 介護スタッフの仕事は充実していましたが、ある日友人に誘われて、リリースされたばかりの「ストリートファイターⅣ」をプレイしに、ゲーセンに行きました。すると、何年もブランクがあったのに、面白いように勝ててしまった。そのとき、ゲームの世界で自分はまだ特別な存在なんだと感じられたし、ゲームという得意種目を持っていることに感謝すべきだと思いました。だったら、介護の仕事を続けながら趣味でやるのも良いかなと思い、またゲームセンターに足を運び始めたんです。
それがどういうわけか、「あのウメハラがカムバックした」という形で海外でニュースになり、大きな大会に招かれて優勝します。それがきっかけとなって、アメリカのゲーム周辺機器メーカーからスポンサー契約のオファーを受け、悩みに悩んだ末、プロのゲーマーとしてやっていく決意をしました。介護の仕事にはやりがいを感じていたし、楽しくやらせてもらっていたので、プロゲーマーになっていなければ、今でも介護の現場で働いていたかもしれません。
みんなの介護 梅原さんは介護の仕事に対して良い印象を持っているようですが、介護の現場では今、離職する人が後を絶ちません。なぜ、辞めていく人が多いのでしょうか。
梅原 僕はそんなにいろいろな仕事を経験したわけではありませんが、肉体的にも精神的にも、介護よりきつい仕事はもっとたくさんあるんじゃないかと思います。にもかかわらず、介護の現場で辞めていく人が特に多いのは、もしかすると、「先が見えないこと」がネックになっているのかもしれませんね。
例えば、美容師の仕事もずいぶんハードだと聞きますが、本人に夢があれば、仕事が辛くても頑張れるのではないでしょうか。「将来は自分の店を持ちたい」とか、「カリスマ美容師として有名になる」とか、自分なりに明確な夢があれば。一方、介護の仕事では、なかなかそういう夢は持てないような気がします。
僕が介護の現場で働いていた当時でも、年配のスタッフさんは「この仕事をいつまで続けられるんだろう」と、いつも不安そうに話していましたね。多くの人は腰を痛めていて、それも辛そうだったし。僕は介護の現場に1年しかいなかったので、「競争のない仕事に癒やされた」という感覚しか抱きませんでしたが、もっと長く続けていれば、将来に不安を感じていた可能性はあります。もし、10年間仕事を続けたとして、仕事内容や給料がそんなに変わらなかったとしたら、僕も嫌になっていたかもしれません。
働いている人のモチベーション向上、ステップアップの道筋の明確化。評価に応じた昇給・昇格の約束は必須
みんなの介護 では、介護の現場から辞めていく人を減らすには、どうすれば良いでしょうか。介護スタッフ経験者としての、梅原さんの考えをお聞かせください。
梅原 ひとつ考えられるのは、働いている人の待遇改善ですね。頑張っている人がきちんと評価される仕組みを確立し、評価に応じた昇給と昇格を約束すること。働いている人のモチベーションも上がるし、○年後に主任、×年後にマネージャーに昇格という、ステップアップの道筋も見えやすくなります。
とはいえ、この改善策にもデメリットはあります。それは、上司の評価をめぐって、スタッフの間で競争が生まれてしまうこと。そうなると、仕事でも丁寧さより効率性が優先されるかもしれないし、職場の雰囲気もギスギスしてしまうかもしれない。僕自身の例で言えば、そういう競争原理の働かないところが介護の現場の良さだったのですが…。僕が働いていた職場でも、多くの人が競争することを好まない感じだったように思います。
みんなの介護 もしかすると、働いている人の性格によって、「働きやすい職場」の形は違ってくるのかもしれませんね。
梅原 もうひとつ言えることは、どんな仕事でも、長く続けれていればプラスの面に慣れっこになってしまい、マイナスの面ばかりが目につくようになること。その理屈でいえば、介護現場の穏やかな雰囲気にはいつの間にか慣れっこになってしまって、先が見えないことや働きがいのないことばかりが気になってしまうかもしれない。そうなると、働き方がきちんと評価されるシステムを導入する方が良い、ということになります。
人が人のお世話をする介護の現場では、競争するかしないかのバランスを取るのが難しいですね。これが介護とは無関係な一般の職場であれば、スタッフの働きぶりを正当に評価するシステムは絶対に必要なんですけど。そうでなければ、真面目に働いていても不真面目に働いていても、給料が変わらないことになってしまう。そんな職場は、やはり許されるものではありません。
前例がないプロゲーマーとしての“将来”を考えると、不安だらけで押し潰されそうになった
みんなの介護 先ほどのワーク・ライフ・バランスのお話で、プロゲーマーはプロスポーツ選手のように肉体を酷使しないので、いくらでも練習できてしまう、というお話がありました。とはいえ、ゲーム中は指先や反射神経など、肉体のさまざまな部位を使っていますね。年齢とともに肉体が衰えていったとき、プロゲーマーにもいつか“定年”のような日が来るのでしょうか。
梅原 僕は今、37歳。スポーツの種目によっては、とっくに引退している年齢だと思いますが、プロゲーマーの世界ではまだまだ現役バリバリです。僕が日本初のプロゲーマーになって今年で9年目。なんと言っても歴史の浅い世界なので、プロゲーマーが現役としていつまで戦えるのかは誰にもわかりません。僕としては、後進の人たちに「〇〇歳まで現役を続けられるんだ!」という希望を抱いてもらえるよう、できるだけ長く第一線で活躍出来ればと考えています。
みんなの介護 若い頃に比べて、肉体の衰えを感じることはありますか。ちきりんさんとの対談本(『悩みどころと逃げどころ』小学館新書)では、「肉体的な衰えを感じることはない」とお話しされていましたが。
梅原 正直言って、反射神経の衰えなどを感じることはないですね。ただし、気づかないうちに衰えている可能性はあります。「反射神経は年齢と共に衰えていく」と科学的に証明されているのであれば、自分が気づいていないだけで衰えているのかもしれません。
しかしその一方で、年齢を重ねるごとに確実に伸びていっている部分もあります。ひとつは経験値ですね。だからプラスマイナスゼロで、今はまだ第一線で戦えています。将来的に、マイナスの部分が大きくなっていったときには、僕も引退を考えるかもしれません。
みんなの介護 10年後や20年後など、ご自分の未来を想像することはありますか?
梅原 未来を想像するというより、将来に対して漠然とした不安を感じていた時期はありますね。2016年頃のことです。
みんなの介護 それは意外ですね。何か不安を感じさせるような出来事があったのでしょうか。
梅原 今思えば、生活に変な余裕が出てきてしまったからかもしれません。
2010年にプロゲーマーとなったときには、目の前のことに、とにかくがむしゃらに取り組んでいました。というより、目の前のことしか見えていませんでしたね。すべてが初めての経験だったので、自分がやるべきことに没頭し、毎日を全力で生きるしかなかったからです。
そうやって1年、2年、3年と過ぎていって、自分としてはずっと右肩上がりに成長出来ていると感じていました。ひとつの転機となったのが、2015年から2016年にかけて。それまで1社だったスポンサーがレッドブル・HyperX・Cygames、それからTwitchの4社にまで増えたのです。
それまでも、格闘ゲームの世界における僕の立ち位置は独特でしたが、スポンサーが増えたことで、自分がさらに特別な存在になったと感じました。それで、変な余裕が出てきたと同時に、変な気負いも生まれてしまったんですね。「自分はこの状態をいつまで続けられるのだろう」とか、「自分はゲーム業界に対してもっとやるべきことがあるのではないか」なんて考え始めてしまったんです。
そうやって立ち止まって考えてみると、自分の将来は不安なことだらけで、押し潰されそうになりました。当たり前ですよね。プロゲーマーとしてどう生きるべきかを考えようとしても、とにかく前例がないんですから。
未来のことを考え過ぎて守りに入ってしまっていた。もともとは明日のことなんて考えないタイプだったのに
みんなの介護 梅原さんが2016年頃に感じたという、将来に対する漠然とした不安は、どのように払拭されたのでしょうか。
梅原 実は、今日みたいなインタビューがきっかけだったんですよ。インタビュアーの人は僕より10歳以上年上でしたが、その当時僕が発していた「暗いオーラ」に気づいたんでしょうね。インタビューが、いつの間にか人生相談みたいな展開になってしまって。
そのとき、インタビュアーの人は言っていました。「自分はこのインタビューを終えると、1ヵ月先まで仕事がない。それでも、何とかなるものですよ。これまでずっとフリーランスで仕事をしてきて、将来に対して不安を感じることも多かったけど、たとえ仕事が切れても、不思議なことに、自分を必要としてくれる人が決まって現れる。結局、目の前の仕事に集中するほうが上手くいくと気づいたんです。だから、私はもう将来のことを考えるのは止めたんですよ」と。
そのとき聞いた言葉の一つひとつが、胸に刺さりましたね。そして、これからは将来のことを考えるのは止めようと思いました。
みんなの介護 今、私が聞いても、実に励みになる言葉です。
梅原 インタビュアーの人は、著名な書道家をインタビューしたときの話もしてくれました。
その書道家は、何事にも計画を立てて臨む人でしたが、数年前に生きるか死ぬかの大病をしたとき、「今まで立てていた計画は何だったのか?」と愕然としたそうです。どんなに綿密な計画を立てていても、ある日突然死んでしまったら意味がない。だったら、もう計画を立てるのは止めよう、そして1日1日を一生懸命に生きよう、と考え直したとか。その書道家は人生観が極端に変わってしまって、今では明日のことさえ考えないそうです。
それらの話を聞いて、自分がいかに守りに入っていたかがよくわかりました。28歳でプロゲーマーになって、大好きなゲームを仕事にしただけで感謝していたはずなのに、スポンサーが何社も付いたことで、この生活をいつまで維持できるのか、欲が出てしまったんですね。
それに気づいてからは、良い意味で「がむしゃらで無鉄砲な自分」を取り戻しました。僕は元々、明日のことなんて考えないタイプだったんです。将来どうなるかはわかりませんが、今はとりあえず快適ですね。そして、あのときインタビュアーしてくださった方には心から感謝しています。

将来を考えると目の前のことが手に付かない。だから、先のことを考えるのはもう止めた
みんなの介護 先ほど、「将来のことを考えるのは止めた」と伺いましたが、そうなると当然、ご自分の老後についても何も考えていないですよね(笑)。
梅原 すみません(笑)。○◯歳までに貯金して、××歳で引退して、△△歳で住宅ローンを払い終えて…といった人生設計はもちろん、老後についても、今は何も考えていません。
先ほどお話しした通り、ほんの少し考えたことはあるんですよ。将来自分はどうなるんだろうって。でも、そうやって考え始めた結果、不安のあまり目の前のことが手に付かなくなってしまった。これはゲームの競技者として、明らかにマイナスです。だから、現在のパフォーマンスを維持するためにも、「将来のことは考えない」と決めてしまいました。
みんなの介護 では、ご両親の老後について考えたことはありますか。
梅原 両親の老後についても、あまり考えたことはありません。まだ70代になったばかりで、頭も身体も元気ですから。2人とも真面目な働き者なので、蓄えもそれなりにあると思うし、経済的には放っておいても大丈夫なのではないでしょうか。とはいえ、父親にも母親にも世話になったことを感謝しているので、いざとなったら僕が面倒をみようとは考えています。
今思い出しましたが、僕は子どもの頃から、先を見越して行動することが苦手でしたね。もしも将来のことをきちんと考えていれば、もっとしっかり勉強したはずだし、真面目に大学に入って、就職活動にも真剣に取り組んでいたはず。そうしなかったのは、僕にとって、今やりたいことを我慢するのが難しかったからです。その結果、プロゲーマーとしての今があるわけですが。
みんなの介護 若手ゲーマーの人たちは、自分たちの将来についてどのように考えているのでしょう。梅原さんから見て、何か感じることはありますか。
梅原 プロになれるかどうかのボーダーラインにいる若い人たちは、真っ直ぐこの世界に入っていくべきか、迷っているように見えます。その迷いの原因は、「自分はプロとして本当にやっていけるのか」「自分には本当にゲームの世界しかないのか」という2つの不安ですね。特に後者の不安を払拭するのは、なかなか難しいのではないでしょうか。
僕の場合、麻雀とか介護とかいろいろな仕事を試してみて、「自分にはやはりゲームしかないんだ」と気づくことができました。だから今、とても快適です。自分であれこれ悩んだ末に、自分で納得した上で結論を出せたから。
一方、今の若手たちは、おそらくゲームの世界しか知らないはずだから、「いろいろ試した上で、やっぱりゲームの世界が好き」とまでは言えないはず。すると、これから先の人生で、「やっぱり○○の仕事に就いたほうが良かった」と後悔する場面が出てくるかもしれない。若手の人たちには、自分自身がしっかり納得できる形で、進むべき道を選んで欲しいと思います。
介護現場での経験は大きい。どんなことに対しても、“これは当たり前のことじゃない”という考え方が身についたから
みんなの介護 梅原さんは介護の現場も知っている希有なプロゲーマーです。ご自身の老後は考えないとおっしゃっていましたが、多くのお年寄りの老後を見てきて、何か思うところがあるのではないでしょうか。
梅原 介護の現場で働いた経験は、今の自分にとって大きなプラスになっています。どんなことに対しても、「これは当たり前のことじゃないんだぞ」と考えるクセが身に付きましたから。
例えば、普通に身体が動くことは、実は「当たり前」のことではありません。老人ホームに暮らしている多くのお年寄りは、思ったように身体を動かせませんから。そういう人たちを見ていると、普通に身体を動かせることは当たり前のことではなく、実は感謝すべきことなんだと気づきます。
誰かにサポートしてもらったときもそうですね。最初は「ありがたい」と思っても、サポートが2度、3度に及ぶと、いつしかサポートされることが「当たり前」になってしまう。でも、「これは当たり前のことじゃない」と考えるクセが付いていると、2度目、3度目もきちんと「ありがとう」と言える。そういうことって、実は人として大切なことだと思うんです。
みんなの介護 梅原さんはファンを大事にすることでも知られていますね。
梅原 自分ではファンのみなさんへの感謝を忘れないように心がけています。
海外の大きな大会に出場すると、「一緒に写真を撮ってほしい」「サインが欲しい」というファンの人が殺到します。多いときには、400?500人のファンが行列を作るときもあります。そんなとき、僕は写真もサインも断りません。時間が許す限り、ファンの人たちの要望には100%応えようと思っています。格闘ゲームが全然注目されていなかった時代に比べれば、これは当たり前のことではなく、本当にありがたいことだから。
みんなの介護 本当に断らないんですか。
梅原 断りません。もうすぐ試合が始まっちゃうというときはさすがに、「ゴメン、後でもう1回来て」と言いますが。
みんなの介護 いつまでも感謝の気持ちを忘れないのは、介護の現場で、終末期のお年寄りたちと接した経験が活きているんですね。
梅原 時々思うんです。プロのゲーマーにとって、一番怖いことは何だろうって。
例えば、今の仕事がすべてなくなって、昔みたいに経済的に苦しくなったとしても、それはそんなに怖くないですね。僕自身、贅沢に興味ないし、食べるものも着るものも、最低限のものさえあれば良いですから。
自分にとって本当に怖いのは、「あのとき、やろうと思えばやれたのに、どうして一生懸命やらなかったのか…」と後悔すること。これは人生の最期の最期まで、絶対に引きずると思う。
そんな風に考えるのも、介護施設で、多くのお年寄りたちの老後を見てきたから。もし要介護の状態となるにしても、人生を悔いなく生き抜くことができれば、「自分はやりたいことをさんざんやってきたんだから、まあいいか」と、穏やかな最期が迎えられるのではないか。なんて、ちょっと思ったりしています。
人生の最期の最期に「もう、やり残したことはない」と思いたい。そのためには、今この瞬間を妥協せず、精一杯生きなければ。そんな風に考えると、不思議と生きる気力が湧いてくるんですよね。
撮影:公家勇人
梅原氏とちきりん氏の対談本
「悩みどころと逃げどころ」が
大好評発売中!
稀代のプロゲーマー梅原氏と過去の賢人論。にも登場しているちきりん氏が”人生の探しかた”を明らかにする対談。日々の生活でやりたいことが見つからずに悩んでいる方、必読です。
連載コンテンツ
-
さまざまな業界で活躍する“賢人”へのインタビュー。日本の社会保障が抱える課題のヒントを探ります。
-
認知症や在宅介護、リハビリ、薬剤師など介護のプロが、介護のやり方やコツを教えてくれます。
-

超高齢社会に向けて先進的な取り組みをしている自治体、企業のリーダーにインタビューする企画です。
-

要介護5のコラムニスト・コータリこと神足裕司さんから介護職員や家族への思いを綴った手紙です。
-

漫画家のくらたまこと倉田真由美さんが、介護や闘病などがテーマの作家と語り合う企画です。
-

50代60代の方に向けて、飲酒や運動など身近なテーマを元に健康寿命を伸ばす秘訣を紹介する企画。
-

講師にやまもといちろうさんを迎え、社会保障に関するコラムをゼミ形式で発表してもらいます。
-

認知症の母と過ごす日々をユーモラスかつ赤裸々に描いたドキュメンタリー動画コンテンツです。
-

介護食アドバイザーのクリコさんが、簡単につくれる美味しい介護食のレシピをレクチャーする漫画です。