撮影当時の関口監督の心境は?
2ヵ月ぶりの母の入浴を素直に喜ぶ子どもたちに心を打たれた
認知症介護のエッセンスは、<予定非調和>あるいは<予定不調和>です。
2010~2011年当時、母の閉じこもりが進むにつれて、入浴も間遠くなることが顕著になってきました。
私自身も両股関節の手術前で、両脚にかなりの痛みを感じており、毎日入浴ができなかった時期でした。ですから、そんな私は、母に対して<何が何でもお風呂に入って>と、強く言える立場ではないと考えていました。
それでも、母の入浴をどうすればいいのか。
結局、このときは、母が入りたくなるまで待つしかありませんでした。母の記憶では、3日に1回ぐらいは入浴をしているということになっていたし、「冬だし、ま、いいか」というかなりアバウトな気持ちでしたよ。もし、私が潔癖症で毎日欠かさず入浴するような娘だったら、きっとイライラしたことでしょうね。
結局、介護は、介護する側とされる側の相性が大きいと思います。ただし、介護のプロには、<相性>とは、言ってほしくありません。どんな状況でも、どんな人に対しても対応できるような、認知症ケアの高度なスキルと判断力と実行力をプロの人たちには持っていてほしい。難しいことかもしれませんが…。
さて、入浴に関するさらなる母の問題は、母自身がリフォームを決めた新しいお風呂の沸かし方を忘れて、混乱しているということでした。確かにボタンがたくさんあれば、わかりにくいですよね!
ここで、息子の先人(さきと)の出番です。先人は、母と一番良い関係だったので、「彼の言うことだったら聞くかな…」と思いキャスティング(!)しました。
先人は、私の期待に応えて、一生懸命おばあちゃんに、どこのボタンを押せば自動でお湯が沸くのかを教えます。でも、そんな先人のひたむきさを、母は無残にも無視します。
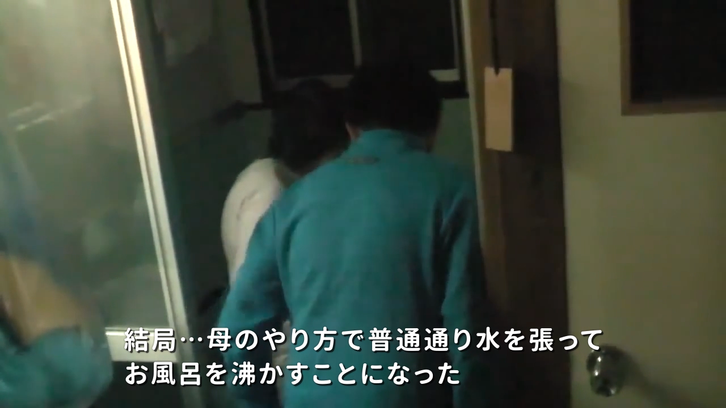
このシーンの素晴らしいところは、色々あっても子どもたち2人ともが、おばあちゃんが2ヵ月ぶりに入浴をしたことを素直に喜ぶところではないでしょうか。
子どもたちの邪心のない思いに、私は撮影しながら心打たれたことを思い出します。
そのとき関口監督がとった行動は?
息子と母のやり取り、子どもたちの反応をそのまま撮影した
私は、先人をキャスティングし、母とのやり取り、そして子どもたち2人の反応を撮影しただけです。
これは2009年の母の79歳の誕生日のシーン(「毎アル」オープニングのシーン)のときと同じですね。
つまり<今年はおばあちゃんの誕生日をやりました!>という言葉を投げかけたり、お風呂の説明に先人をキャスティングしたりするのは、私の監督としての役目。率先して仕掛けますが、そこから先に起こること、あるいは、起こらないことをそのまままるっと撮影するだけです。
そんな中で、母が入浴するまで待つ決断をしたり、自動で沸かせるお風呂でも従来のやり方で水を張る母を楽しんだりするということでしょうか。
特に今回は、先人が、どんなに言っても全く聞く耳を持たないおばあちゃんをあるがままに受け入れたこと。そして、おばあちゃんの久しぶりの入浴を姪っ子と2人で心底喜んだこと。この2点が重要だと思います。

関口監督から読者へ伝えたいメッセージは?
「平等に」は介護する側の都合。一方通行の介護になっていませんか?
この連載で、何回も書いてきましたが、介護は絶対に1人で背負い込まないということです。
特に子どもたちの存在は、重要です。時折、子どもたちを認知症の両親や祖父母から遠ざけるという話もよく聞きます。幼き子どもたちの貴重な人生体験なのに、どうして??
認知症を知り、恐れずに普段のまま接することを学ぶ機会を取りあげるのはよくありません。
先人は、誰よりも早く「アルツハイマーのおばあちゃんは、ゆるくなってとってもいい感じ」と母に伝えた子です。日々自信を喪失していた母にとって、どんなに勇気づけられた言葉だったことでしょう。しかも先人は、お世辞ではなく、本気で思っていたのですから、母の琴線に触れたことでしょうね。

介護をするときには、子どもであっても助けを借りるという姿勢が、大切だと考えます。しかし、どのように助けてもらうかを決めるのは大人(私)の役割であって、適材適所でなければいけません。介護される側を守ると同時に、介護する側も守らなければならない。今回、母にとって可愛い孫であり、かつ、母からの攻撃にも耐えられる素質を持っている先人をキャスティングしたのにも理由があるのです。
そうやって考えていくと、<親の介護は姉妹や兄弟で平等に担当しよう>というような浅はかな考え方や行動は、介護する側の都合のみで行う一方通行の介護であり、ときとして介護される側の反発を招くということも分かりますよね?そして、その反発が介護する人を深く傷つけ、追い詰めてしまうこともあるのです。



