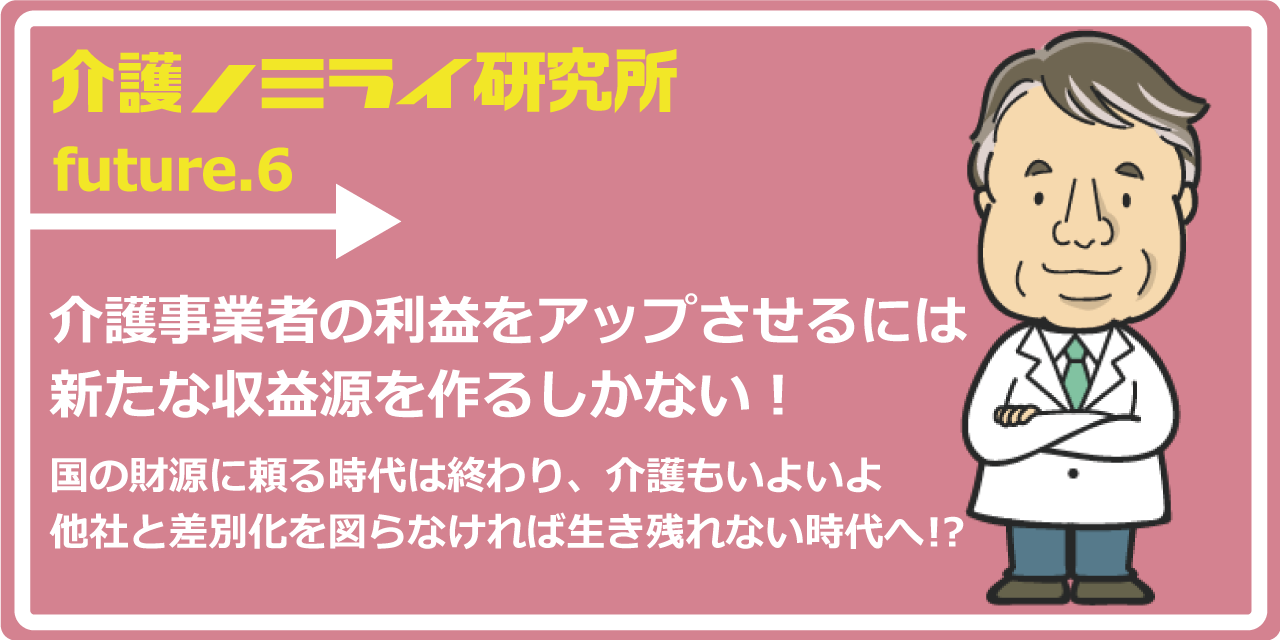酒井穣(さかい・じょう)です。前回の連載第5回「介護業界は人材不足問題よりも先に、まず職員の待遇改善に着手せよ!」では、非常に言いにくいことなのですが、「介護業界は労働生産性が最低(全63業界中63位)である」という事実を指摘しました。
労働生産性が改善されないままに働く人材だけが増えてしまうと、税収が減り、かえって日本の社会福祉が維持できなくなるというパラドクスが存在しています。
不足する人材をなんとかしないと日本の介護は大変なことになってしまいます。しかし、今の待遇のまま人材の数だけを確保しても、やはり日本の介護は大変なことになってしまうのです。
そこで今回は、経営学的な視点から「介護業界の労働生産性を高める方法(介護業界の売上を高める方法)」について考えてみます。
国の財源に頼る時代はもう終わり
このままでは事業者が倒産してしまう
いまさら確認するまでもないですが、日本において社会福祉のための財源は枯渇してきています。これに反して、介護を必要とする人々(要介護者)の数は、今後、爆発的に増えていくことがわかっています(2025年問題)。

この状況においては、利用者1人あたりの売上(国が決める介護報酬)は減らされていきます。しかし、1人の利用者につく介護職の数はそう簡単には減らせません。だとすれば、介護事業者の利益は今後、間違いなく減っていきます。
利益が減っていく企業で働く人材の待遇が改善することはありません。むしろ、現状維持ができれば上等です。しかしその現状はといえば、全63業界でもダントツで最悪なのです。
| 順位 (63業界中) |
業界名 | 平均年収 (万円) |
|---|---|---|
| 1位 | コンサルティング | 1,240 |
| 2位 | 総合商社 | 1,115 |
| 3位 | 放送 | 866 |
| 10位 | 医薬品 | 718 |
| 20位 | 生命保険・損害保険 | 669 |
| 30位 | 専門商社 | 606 |
| 40位 | 文房具・事務用品 | 562 |
| 50位 | コンビニエンスストア・人材サービス | 523 |
| 60位 | 家電量販店・ホームセンター・ディスカウントストア | 479 |
| 63位 | 介護 | 395 |
この環境において、介護事業者が生き残りながら労働生産性を高めるには、2つの方法しか残されていません。
- 介護職1人あたりが対応できる利用者の数を増やす
- 国の財源に頼らない新たな収益源をつくる
以上の2つの方法しか考えられません。
もちろん介護職1人あたりが対応できる利用者の数を増やすことは大切です。そのためには無駄な書類業務に代表される管理業務をITによって極限まで減らすことが求められます。ただ、この方法は、介護事業者が自分たちで努力すればどうにかなる話ではありません。ここはIT企業の担当すべき仕事になります。
そうなると、介護事業者に残されている道は、国の財源に頼らない新たな収益源をつくることしかありません。いわゆる保険外サービスの新規事業開発です。ここには(まだ)法的な制約があったりもしますが、今後は、規制緩和が求められます。さもないと、介護事業者の倒産が止められなくなるからです。
稼ぐ基本は“差別化戦略”
経営者にビジネスセンスが求められる!
これまでの介護事業者の経営は、国の介護報酬に依存してきたため、新たな売上を作ることではなく、利用者の獲得と維持に最適化されてきました。このため、新事業開発については、適切なトレーニングを受けていない経営者が多いという予想が立ちます。
そこで、一部の経営者にとっては釈迦に説法となるかもしれませんが、その基本的な考え方について、まずはおさらいしておきます。当たり前すぎて涙が出そうですが、軸となるのは差別化の戦略です。これをわかりやすく表現してくれているフレームワークがあります。

Harvard Business Review, April 2008
更新
このフレームワークにおいて、スイートスポットにはまるような商品を生み出すことが差別化の戦略です。これまでの介護事業者であっても、事業を行う地域という側面からだけは、スイートスポットを意識してきたはずです。
近隣に自分たちと同じ介護サービスを提供する介護事業者がいて、そのキャパシティーが地域の利用者の数を上回っていれば、とても経営になりません。実際に、競合の新規参入によって経営が立ち行かなくなった介護事業者の事例は枚挙にいとまがないでしょう。
実は、新事業開発の基本もこれと同じです。ただし、誰を競合とするのかが異なるだけです。新事業開発においては、同業種ではなくて、できるだけ異業種の仕事をターゲットにすることが基本だからです。
利用者のお財布(ワレット)の中身は限られています。それが急に増えることはありません。しかし利用者は、介護以外の目的にもお金を使っているでしょう。そうした他の目的のために支払っているお金を、自分たちの方向に向けることができたら(ワレット・シェアを高めることができたら)、介護事業者の売上を高めることが可能になります。
利用者から見れば、支払先が誰であっても、目的が達成されればそれで満足です。しかし介護事業者からすれば、それによって売上と利益があがるのであれば、ハッピーです。結果として、介護職の待遇を改善することも可能になります。
あくまでもアイデアですが…
介護業界は「コミッション」で生き残れる!
以下は、差別化の戦略に関する理解を深めるために描いてみた、私の妄想です。本当にこの戦略を実行する場合は、よりしっかりとした検討が必要なので、鵜呑みにしないでください。あくまでも考え方の筋道について理解してもらえたら幸いです。
まず、高齢者は、現役世代よりも、行動半径が狭くなることが知られています。結果として高齢者の買物難民が生まれているわけです。普通であれば、こちらから特定のお店まで足を運ぶことができないとき、デリバリー(宅配)に頼ることになるでしょう。
ここで、デリバリーを行っている業者の気持ちになってみてください。デリバリーをするための自動車、運転手、ガソリン代と、そこには様々なコストが発生します。結果として、家からあまり出られない高齢者に対して、すべての商品を安いコストで提供することはできないのです。

こうした状況を見越して、コンビニ各社は、現在、マンションの管理人室などへの出店を検討しています。高齢者がコンビニまで足を伸ばせないなら、コンビニのほうから高齢者に近づこうという戦略です。ついでにマンションの管理人業務まで受注できたら、コンビニとしては差別化の戦略が成立します。
さて…介護事業者は、そもそも普段から高齢者のところまで足を伸ばしています。そのコストは、すでに負担しているわけです。さらに、コンビニの店員よりもずっと、それぞれの高齢者の価値観についても理解しています。
まずは、トイレットペーパーや洗剤など、誰から買っても同じものであり、価格も変わらないのなら、そうした商品は介護職から買ってもらえるのではないでしょうか。
ここで、トイレットペーパーや洗剤などのメーカーからすれば、売ってくれる人にコミッション(手数料)を支払うのが当たり前です。その相手がコンビニではなく介護事業者になっても、本質的にはなにも困りません。いわば、リアル・アフィリエイトですね。
利用者の自宅で「あ、トイレットペーパーがそろそろ無くなりますね、次回来るときに持ってきますね、お値段はスーパーで買うのとかわりませんので」という介護職がいれば、利用者は助かるし、介護事業者にも正当なコミッションが入ります。
このとき、介護職が相手にするのは、要介護認定を受けている高齢者に限りません。マンションで暮らす利用者であれば、そのマンション全体の高齢者を顧客にすることも可能です。そうして、より多くの高齢者と関わっておくことは、将来の利用者確保にとっても有益なことでしょう。
もちろん、この対象となる商品はトイレットペーパーに限りません。たとえば、今の銀行の悩みは、ATMまで足を伸ばせなくなった高齢者からの「現金を持ってきてほしい」という依頼です。銀行からすれば、現金を届けにいくコストは持ち出しになります。誰かが代わりにこれをやってくれたら…という思いもあるでしょう。
究極的には、介護職を「いつも自宅まできてくれる信頼できる生活サポーター」として再定義することができたら、スーパーやコンビニ、銀行や保険など、様々な異業種をあらたな競合にすることが可能なはずです。こうしたあらたな競合には、時間をかけて個々の高齢者と向き合うというコストを負担する力はないので、自然とスイートスポットの創出ができると思われます。
本業の介護が儲からない!?
身近に本業が赤字のビジネスは意外と…
こうした話をすると、本業である介護が儲からない状態では、本末転倒であるといった意見をもらうこともあります。しかし、本業が儲からないというケースは、世界中に多数あることは知っておいても良いでしょう。
有名なところでは、プリンターがあります。プリンター本体は、場合によっては赤字でも販売します。その上で、インクカートリッジの価格を高くして、インクカートリッジを買ってもらうことで儲けています(最近は純正ではないインクカートリッジが増えており、少し事情が異なりますが)。
自動車メーカーも似ています。自動車本体は、その価格ではあまり利益が出ない構造になっているか、これも場合によっては赤字です。ただ、顧客には自動車を買ってもらうときにローンを組んでもらうことが多いでしょう。自動車メーカーは、このときのローンの金利で儲けています。
介護事業者が、介護という本業では赤字でも、その周辺で儲けることは、それほど悪いことでしょうか。当たり前なのですが、儲けるということは、悪いことではありません。先の妄想においても、利用者にとって本当に意味のあることでないと、決して売れません。
利用者のことを、そして高齢者のことを真剣に考えてきた介護事業者だからこそ生み出せる新たなサービスがあるはずです。そうした視点から、今一度、介護事業者のスイートスポットを考えてみてください。とにかく、競合としてはできるかぎり自分たちから遠く感じられる業界を設定してみることが肝要です。
私は、利用者の生活の満足度を高めることを通して、より大きく儲ける介護事業者が増えていくことを願っています。それが結果として、介護職の待遇を改善することにつながり、日本の介護を理想に近づけるものと信じています。政府関係者には、介護事業者がこうした方向にも発展できるよう、各種規制の緩和を考えてもらいたいです。
次回は、他の業界とビジネスという観点では別物と捉えられてきた、介護業界の「人材」について考えてみます。介護職員が稼げる人材になっていくのか、ぜひみなさんも考えてみてください。