介護職員のベースアップ等支援加算とは?制度のポイントと介護現場の“ホンネ”を取材
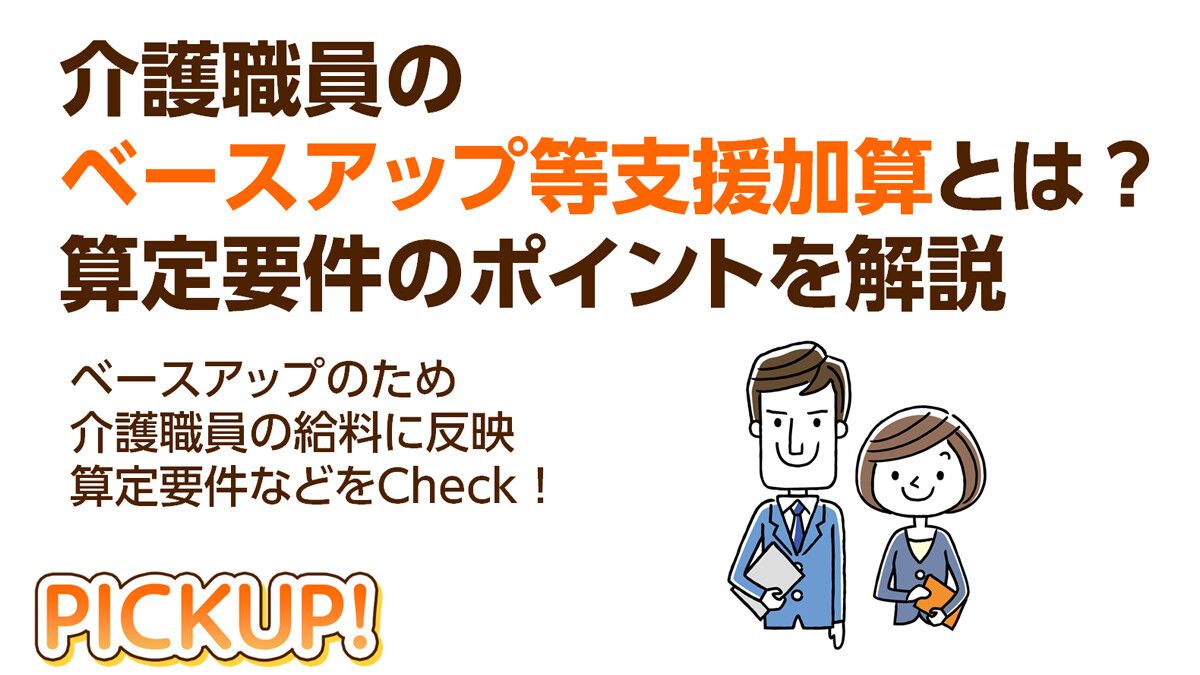
今年10月から新たな処遇改善加算がスタート
「ベースアップ等支援加算」とは?

今回のピックアップでは、2022年10月から始まった介護職「ベースアップ等支援加算」について解説します。
「ベースアップ等支援加算」の目的は、介護職の月給を約9,000円(約3%相当)アップさせることで、加算額は職員の給与に反映しなくてはならないという制度となっています。
注目すべき算定要件を見ていきましょう。
●処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
●加算額の3分の2は介護職員のベースアップ等(基本給か手当)に使用すること
これまでの「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」は、一時金(ボーナスなど)として全額支給することが可能でしたが、「ベースアップ等支援加算」では加算総額の3分の2以上を基本給、もしくは手当として給与に反映しなくてはなりません。
介護職の月給はどれぐらいアップするの⁉
「ベースアップ等支援加算」は、給付された報酬を「内部留保」として事業所に留めておくことができないことも大きな特徴です。
事業所の売上が上がれば、給付額も上がるので事業所の稼働率が上がれば上がるほど職員の給与に反映されることを意味しています。
実際に「みんなの介護」掲載施設の方々に取材をすると、「事業運営と給与の見直しのいい機会になった」という前向きな声が寄せられました。現場職員にとってはモチベーション・アップにつながっているようです。
一方で、必ず月給が9,000円増えるわけではありません。
加算はあくまでも「売上×加算率」で給付された金額を事業所内でさらに分配していくというシステムなので、事業規模が小さい事業所や複数の業態を持つ法人、分配対象となる職員が人員配置基準よりも多く在籍している場合には、給与に反映される額は少なくなることもあります。
そのため、月給9,000円アップを満額で達成できるかどうかは 「施設次第」という側面も少なからずあります。
実際、「加算対象外の事業所(居宅介護支援・福祉用具等)には支給できないので、給与のバランスが難しい」といった声だけでなく、「処遇改善に関する加算の種類が増えることで、事務処理が非常に煩雑になっている」といった“見えない負担”に対する不満もあがっているようです。
デメリットは利用者負担が増えること
「ベースアップ等支援加算」には利用者負担が増えるというデメリットもあります。
2月から行われてきた補助金は国庫を財源としていましたが、加算に移行されることで、社会保障費が財源となります。
例えば、利用者負担の増額分が月8万円の利用料だとすると、約80円程度に止まると見込まれます。「介護控え」につながるほど大きな負担とまでは言えませんが、わずかに負担が増えるのは事実です。
事業所の負担はどうなる!?
実際に介護事業所は今回の改正をどのように捉えているのでしょうか。介護現場の方々に“本音”を伺いました。
「なんとなく給与が上がるのでは?という期待感は実際あります。でも、日々の業務の忙しさが現場の一番の課題なので、配置・シフトの改善が実現して欲しいです」(兵庫県・施設職員)
「施設の経営者の立場からすると、正直、給与の見直しの良い機会になったと思っています。給与アップを実現できるように極力努力するつもりです」(兵庫県・施設経営者)
「職員の給与のアップ自体は良いことだと思います。しかし、制度全体としてはまだ整っていないと感じています。過去最悪のペースで介護事業者が倒産している中、職員の雇用の安定を守るには事業の安定も考えなくてはなりません。私たちは事業規模が小さいので、月給9,000円アップは正直なところ難しいです」(宮城県・デイサービス経営者)
制度の狙い
業態や規模によって、制度の恩恵を受け難い施設が生じていることは確かです。「加算となる場合、業績に応じて受給額も変動するため、ベースアップでのみ支給することは本来難しいのでは?」といった意見もあります。
「ベースアップ等支援加算」をはじめとした処遇改善は、介護職の満足度や魅力が高まり求職の幅が広がることが期待されています。「みんなの介護」では、今後も処遇改善について調査を続けていきます。





