小学生読者からの質問「認知症の方の暮らしが知りたい」専門家が回答
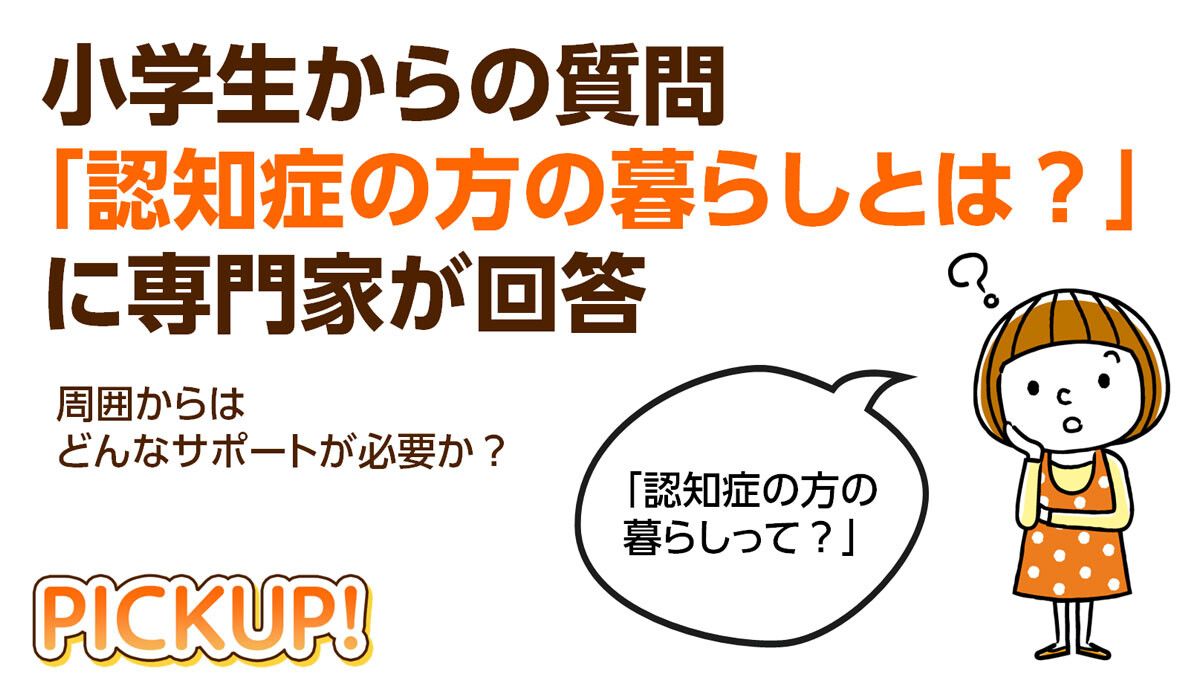
10月中旬、老人ホーム検索サイト「みんなの介護」にこんな読者コメントが寄せられました。
「小学5年の総合学習で『認知症の方の暮らし』を調べています。私は『認知症の方がどんな工夫をして暮らしていらっしゃるか』について知りたいです。できればそういった記事も作ってほしいです。何どぞよろしくお願いいたします」(11歳・女性)
「みんなの介護」ニュース編集部一同、こうして総合学習の時間にも読んで頂けて光栄です。
そこで今回は、「認知症の方の暮らし」と「ご本人が無理なく出来る、より良い暮らしのために有効なちょっとした工夫」について改めて取材をしてお伝えします。
「以前はできたことが、できない…」
まずは「認知症の方の暮らしが、実際にはどんな状況なのか」についてです。
一般社団法人千葉市認知症介護指導者の会で理事を勤める髙橋秀明さんは、認知症の方に意外な言葉を掛けられたそうです。
髙橋さん「ある施設で出会った認知症のお年寄りの方が『今の私は自分じゃない気がする。もの忘れがひどくて困っているだけど、私、おかしいよね?歳はとりたくないよ』と、仰ったんです。確かに、認知症の方の中には自分が病気という自覚が無い方もいらっしゃいますが、実際には自覚がある人も多くいらっしゃいます。自覚がある中で、自分の記憶が失われていくことや、自分が今まで出来ていたことができなくなるのはつらいですよね」

かつては、認知症というと「何もできない」とみられがちでした。また、周囲も「もしもの時のために何もさせない」といった接し方が一般的でした。
しかし、最近の研究で「認知症になっても暮らしの中で出来ることが実はたくさんある」ということが分かってきました。
認知症の方が苦手になることとは?
認知症を発症すると、特に記憶に関わる機能が衰えたり失われたりします。だからこそ、新しく物事を覚えたりすることが難しくなってしまうのです。
そのため、認知症の方が自立した暮らしを送るためには、記憶力をサポートするような工夫が有効です。
実際に認知症の方に取材をすると、さまざまな工夫をされていらっしゃいます。
- ・予定は、家族など身の回りの人と一緒にカレンダーなどに書くようにする
- ・物は、引き出しに見出しシールを作って貼ることでしまった場所を忘れないようにする
こうした工夫で、日常生活の困りごとを減らせるそうです。
また、「認知症ですので、ご協力をお願いします」と書いた紙やカードを持ち歩いて、いざという時には周囲の方に助けて貰えるように備えている方もいらっしゃいます。
「できること」と「できないこと」を思い切って分けるのが大事
記憶に関する能力が失われやすい一方、「体が覚えている」類のことは、認知症を発症しても衰えないケースが多いと言われています。
そのため、日常の動作はもちろん、自転車に乗ったり、お茶を淹れたり、料理を作ったりといった長年慣れ親しんできたことに関しては、認知症の初期段階では変わらずにできるケースが多いのです。
周囲の支援も受けながら、「自分なりにできること」にチャレンジすることは心身の充実のためにも重要です。
ただ、火を使う料理や車の運転など、万一の場合に自分や周りの人を巻き込んでしまう恐れがあることは思い切って止めたという方もいらっしゃいます。
「『できないことは、できない』と割り切って、自分なりにできることにエネルギーを使うことが大切だ」という声が当事者の方々から聞かれました。
地域の支援も積極的に活用を
認知症という病気自体が知られていなかった数十年前とは異なり、今では、認知症についてさまざまなことがわかってきました。
認知症について理解し、支援したいと考えている人が地域には必ずいます。また、発症された方も「認知症カフェ」などを訪ねれば、同じような境遇の認知症当事者の仲間を見つけられるようになってきました。

もしご自身やご家族など身の回りの方が認知症と診断された時には、地域包括支援センターなどに相談することがオススメです。
認知症は誰でもなりうる病気です。病気について理解が進み、当事者と周囲の方々がより暮らしやすい社会を実現できるよう、「みんなの介護」も力を尽くしていきます。





