著書『ゆかいな認知症 介護を「快護」に変える人』では、若年性のアルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症の当事者の方々に取材されていて、とても興味深かったです。
「はじめに」で触れられていますが、認知症の取材をされるきっかけになったのは、お兄様が「若年性認知症」と診断されたことなんですね。

今回のゲストはノンフィクション作家の奥野修司さん。奥野さんは認知症当事者の方々への丹念な取材を重ね、2018年に『ゆかいな認知症 介護を「快護」に変える人』を上梓しました。認知症になっても人生を楽しむ秘訣はあるのか。当事者の本音を徹底的に取材した奥野さんと漫画家くらたまで、認知症についていろいろと語り合いました。
「認知症の人の思いや本音を聞いてみると、実は家族が持っている情報が間違っているために、自ら介護を大変なものにしているのではないかと思うことがよくありました」。認知症当事者への取材を通して、ノンフィクション作家の奥野修司さんはそう語る。認知症の人たちは何を考え、何を感じ、何を望んでいるのか。病気になっても人生を楽しむ秘訣とは――。他者とつながりながら新たな人生を踏み出した人々を紹介する渾身のノンフィクション。
 くらたま
くらたま著書『ゆかいな認知症 介護を「快護」に変える人』では、若年性のアルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症の当事者の方々に取材されていて、とても興味深かったです。
「はじめに」で触れられていますが、認知症の取材をされるきっかけになったのは、お兄様が「若年性認知症」と診断されたことなんですね。
 奥野
奥野はい。2000年ぐらいに、兄が若年性のレビー小体型認知症と診断されたんです。2010年くらいからだんだん口をきかなくなっていき、亡くなったのは2013年でした。
ところが、兄が亡くなってしばらくして、「兄は本当に僕の言っていることがわからなかったんだろうか」と気になりだしたんです。僕は当時、終末期のがんの取材をしていて、患者さんから話もたくさん話を聞いていました。
僕自身が認知症に対して蔑視のようなものを持っていることに気づいたんです。すごく恥ずかしいことですが、家族も兄の認知症については周囲に言わないようにしていました。
有吉佐和子さんの名作『恍惚の人』じゃないですけど、「自分のきょうだいが認知症」というのは抵抗がありましたね。
 くらたま
くらたま家族が認知症って、やはり言いづらいですよね。
 奥野
奥野でも、がんも1990年代後半くらいまでは「恥ずかしい病気」だったんですよ。
 くらたま
くらたまえっ、そうでしたっけ?
 奥野
奥野昔はがんになるとみんな隠したんですよ。その頃まではがんは「遺伝する」とも言われていたんです。
 くらたま
くらたまそんな時代でしたか…。
 奥野
奥野1990年代の後半に入って、著名なジャーナリストや文化人が自分のがんについて体験談を書いて、それが読まれるようになりました。少しずつがんは遺伝ではないし、恥ずかしい病気ではないと知られるようになっていったんです。闘病する本人が一番大変なんだと。
 くらたま
くらたまそうなんですね…。
 奥野
奥野認知症も同じで、当事者が本を出したり、発信するようになったのは最近のことです。僕は、2011年の東日本大震災の取材もしているんですが、認知症のご家族がいる方は、やっぱり狭い仮設住宅でも隠されていましたね。
 くらたま
くらたま「認知症」という言い方も最近ですよね。昔は「痴呆」とか「ボケ老人」とかでした。
 奥野
奥野ストレートな言葉でしたね。でも、本でも紹介した丹野智文さんのように当事者として発信する人もいて認知症に対するイメージも変わってきました。
丹野智文さんは39歳で若年性アルツハイマー型認知症と診断されたけど、会社で勤務を続けて、出版や講演もされていますよね。
がんでも認知症でも、知らなければつい偏見を持ってしまいますが、当事者の言葉を聞いたら、ぜんぜん違うこともあるんです。
 くらたま
くらたま私も丹野さんと「くらたまのいま会いたい手帳」でお会いすることになった時、「果たしてコミュニケーションを取れるのかしら?」とすごくもやもやしていました。勝手に重篤な認知症をイメージしていたんです。
認知症の症状も人によって違うのでしょうけど、丹野さんはとてもお話も面白くて、楽しい対談になりました。
 奥野
奥野そうですよね。だから、いろんな認知症の当事者の方にそれぞれの立場から発信してほしいと、普段からお願いしているんです。
 くらたま
くらたま奥野さんのご著書には、認知症でいろいろな症状があっても日常生活はきちんとしている方が多くて、驚きました。
例えば「空間認知機能の障害」というのもはじめて聞きました。服の袖に手を通せないとか、お札をお財布に入れられないとか、そういう症状もあるんですね。
 奥野
奥野そうですね。本で紹介した山田真由美さんの場合は、若年性アルツハイマー型認知症なんですが、記憶障害はほとんどなくて、その代わりに「空間認知機能」に障害がありました。三次元の立体的な感覚がわからなくなるのだそうです。
僕もどういう症状なのかイメージがつかなくて、インタビューには苦労しました。
袖も腕も見えているのに、腕を通せないとか、吊るしてあるドレスは見えるのに、ソファーに置かれてしまうと見えなくなるとか…。何度も聞きましたけど、やっぱりわからなかったです。
 くらたま
くらたまお財布からお札を出せても入れられないって、どんな感覚なのか…。会話はできるんですよね?
 奥野
奥野山田さんは、よく話すし、よく笑いますよ。しゃべり始めると止まらないくらいです。
できないことにいつまでもこだわるのではなく、できることを大切にする。それが元気な当事者に共通するように思う
(『ゆかいな認知症 介護を「快護」に変える人』P25より引用)
 くらたま
くらたま不思議ですね…。
 奥野
奥野だから、僕は「認知症」と、「症」をつけてひとくくりにするのではなく、単に「三次元がわからなくなる障害」とすればいいと思います。山田さんは、この障害以外は普通に生活できているんです。
丹野さんも、短期の記憶が失われるという典型的なアルツハイマー型認知症の症状だけで、それ以外は普通です。
「認知症」という病名をつくってしまったために、無理に一つにすべてまとめられている気がしますね。
 くらたま
くらたま認知症というと、徘徊とか糞便をなすりつけるといった症状のイメージが強いから、どうしても「おそろしい病気だ」となってしまいますよね。でも、普通に生活できている方も多いんですね。
 奥野
奥野そうなんです。わかっていない人が勝手に決めつけてしまっているんです。例えば徘徊も、「目的もなくあちこちふらついている」とイメージされがちですが、最近では「徘徊にも理由がある」という研究があります。
たいていの認知症の方は、何か理由があって出かけて、帰り道がわからなくなっているだけなんです。
 くらたま
くらたまなるほど。
 奥野
奥野国内に重度の認知症患者を対象にしたデイケアが240ヵ所くらいあるんですけど、そのうちの1ヵ所で地元では徘徊で有名なある患者さんの女性に話を聞いたことがあります。
初日は全然会話になりませんでしたが、二日目は慣れてきたせいか、ぽつぽつとしゃべり始めてくれて、徘徊の理由も説明してくれたんです。
 くらたま
くらたまご本人は理由をわかっていらっしゃるんですか!?
 奥野
奥野そうなんです。彼女は「旦那や子どもが怒るから、むしゃくしゃした気持ちを抑えるのに、外に出るの。外は風が気持ちいいからスッキリするでしょ?」と話してくれました。これって、普通の人間の感覚ですよね。
もちろんご家族も意地悪をしているわけではなくて、トイレから出てくる時に水を流し忘れた時など「しっかりしてよ!」「なんでできないの?」と注意してるだけなんです。でも、本人はちゃんとやってるつもりなんですね。
なんで怒られているかわからないのだから、むしゃくしゃするのも当たり前です。それで突然家を出て、帰り道がわからなくなって、「徘徊」になっちゃうんです。ご近所の人が連れて帰ってきてくれて、玄関で「今日はいい風だったわ」とか言うそうですよ。
 くらたま
くらたまいい徘徊ですね。というか、それって「お散歩」ですよね。帰り道がわからなくなるのは家族からしたら大変ですけど。
要介護「4」「5」でもちゃんとコミュニケーションを取れるし、記憶も残っていらっしゃるんですね。
 奥野
奥野十分残ってますね。デイサービスに通えるくらいの方は、コミュニケーションはほとんど取れます。相手が取ろうとしないだけです。なかなかしゃべれないから仕方ないけれど、コミュニケーションは取れるんですよ。
 くらたま
くらたま私の父は、たぶん軽度の認知症なんですけれど、家族としては軽度でも「なるべく触れないようにしよう」となっているんですね。
でも、すぐ忘れるから、「その話、さっきも何回もしたじゃん!」みたいについ怒ってしまって…。
 奥野
奥野ご家族にとっては大変ですよね。何回も同じことを言わなければいけないし。
 くらたま
くらたま当事者が大変なのはわかるんですけど、家族がやさしい気持ちを持ち続けるのはけっこう大変だなと思います。
私は両親と離れて暮らしていて、実家には時々しか帰らないんですけど、父とずっと一緒にいる母を見てると、父への愛情が目減りしているのが手に取るようにわかるんです。母が父に「さっきも言ったでしょ?」「なんでできないのよ?」みたいなことを何度も言うんで、すごく悲しい気持ちになるんです。子どもとしては悲しいけれど、母の気持ちもわかる…。
 奥野
奥野認知症の当事者の皆さんは、「なんでできないの?」というのが、一番嫌な言葉だそうです。自分ができないとわかっているから、返しようがないと。
怒りは、認知症への無知が生むのかもしれない。それだけではない。認知症についての誤解が偏見を生み、認知症と診断された人の行動の自由を奪うこともある
(『ゆかいな認知症 介護を「快護」に変える人』P29より引用)
 くらたま
くらたまそうですよね。人にもよるんでしょうけど、母は妻だから、「注意すれば少しはマシになる」という変な希望がまだあるみたいです。
私は「そんなわけないじゃん」って言うんですけど、なかなか…。そういう言い方がよくないのはよくわかっているんだけど、父があまりにも何もできなくて…。
ご著書で、明るく楽しく生活している認知症の当事者さんがいらっしゃるのを知ることができたのはよかったです。身近に認知症の人同士で集まれる場があったら、もっと変わっていくのかなと思いました。
 奥野
奥野イギリスなどにはあるんですよ。サッカー場の選手の控室を借りて、認知症の人たちが集まってサッカー談義をするとか。日本には、あんまりそういうのはないですね。
 くらたま
くらたまないですよね。自分が認知症になったらと想像すると、同じ認知症の人といたほうがぜったい気楽だと思うんです。
 奥野
奥野この本でも取材している曽根勝一道さんという小学校の元校長先生も、そうでした。55歳くらいから物忘れがひどくなって、59歳で若年性アルツハイマー型認知症と診断されています。恥ずかしいからと病名を言わずに定年前に退職して、6年も引きこもっていた方です。
取材でお会いした時には引きこもりではありませんでしたが、ご自分は少しもしゃべらず、奥さんが代わりに話してくださるんです。本人の本音が聞けないと困るので、以前に取材していた竹内裕さんにお願いして対談していただくことにしました。竹内さんも59歳で若年性アルツハイマー型認知症と診断された方です。
二人で会ってもらったら、もう全然違いました。話好きな竹内さんと一緒に曽根勝さんもよくしゃべるし、楽しそうだった。竹内さんとは1時間の対談でした。その間、奥さんには買い物に行っていただいたのですが、10分ほど早く帰って来られたために、お二人の対談をカーテンの仕切りから聞くことになりました。すると、「あんなよくしゃべる主人を見たのははじめて」と驚いていました。
 くらたま
くらたますごく気持ちわかるなあ。そうですよね。「健常者」の家族に囲まれちゃって、「自分だけ認知症」ってなると、孤独になりがちですよね。
 奥野
奥野この本を書いたのは、「家族が認知症になったらこうなるよ」と知ってほしかったからでした。こういう本は、認知症の当事者は買うことはまずないですよね。ご家族が認知症になった人に知ってもらうことで、家庭の環境も変わると思うんです。
徘徊にしても、ただ何もわからなくてぶらぶら歩いているわけじゃないよとか、家族が理解すれば向き合い方も違ってきます。
人それぞれ性格が違うように、認知症であらわれる障がいは人によってさまざまだということです。障がいが十人十色なら、認知症をひとくくりに捉えるのではなく、当事者が何に困っているかをまず知ることが介護する家族にとっても基本になります
(『ゆかいな認知症 介護を「快護」に変える人』P279より引用)
 奥野
奥野例えばアルツハイマー型認知症の場合は、いろいろな症状がありますが、そもそも本当に「病気」なのかどうかもわかりません。ほぼ記憶障害だけですから。誰だって年を取ればもの忘れもひどくなりますよね。70、80代で記憶に難がない人なんているでしょうか?
日本人の平均寿命は、戦後の1947年では男性50歳、女性が53歳でした。それが今は80歳なんですから、僕らは「知らない世界」に入ってきているんです。だから、記憶障害といっても、本来は老化であって病気じゃないだろうと思います。
 くらたま
くらたま自然な老化現象に「認知症」という言葉が後からついてきたということですか?
 奥野
奥野記憶障害がひどくなって、「健常者」としての生活ができないから、「異質な人」に分類したのでしょう。何でもすぐに忘れるとか、トイレの水を流さないとかを「これは病気だ」と区分したんです。
単なる老化なのに薬を飲ませることも怖いのですが、「認知症」と診断されないと介護保険を使えないことも怖いですね。要介護認定をされないとデイサービスにも行けませんから、いろんな人と話すこともできなくなります。本当にそれでいいのかなと思いますね。
若年性認知症やレビー小体型認知症などは科学的に根拠がありますが、80代以上のアルツハイマー型認知症は本当に病気か研究したほうがいいでしょう。ただ、原因を探っても、見つからないと思いますよ。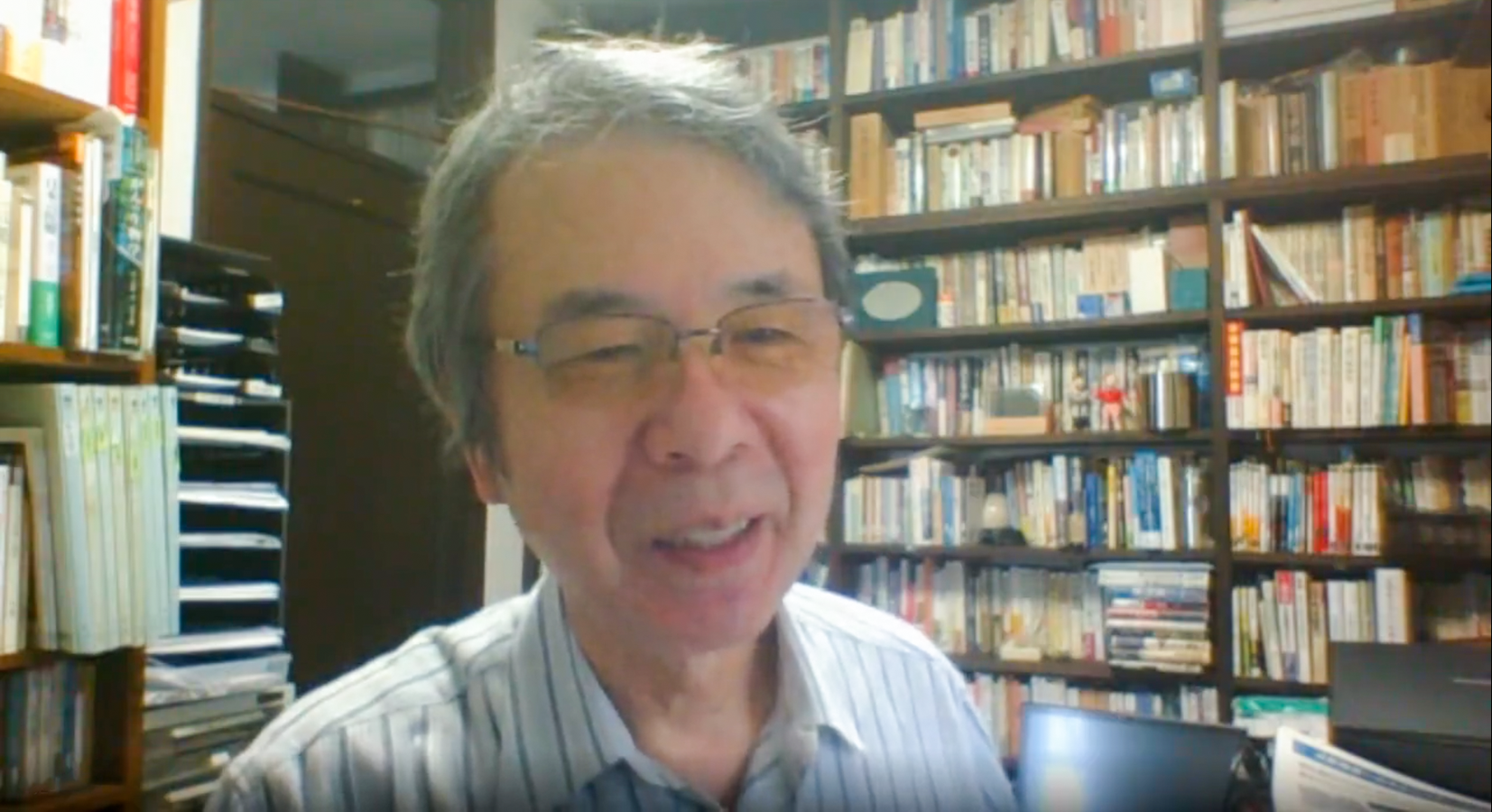
 くらたま
くらたま確かに、そうですよね。
 奥野
奥野あとは、先進国で日本だけ認知症患者が増えているのは、介護保険の問題もあると思います。知り合いの認知症専門医から聞いたのですが、いきなり家族がお父さんを連れてきて、「認知症と診断してほしい」と訴えるケースがあるそうです。
長谷川式認知症スケールで「認知症ではなく記憶障害」と診断されると、「認知症と診断されないと困るから、ほかを探します」と帰っていくというんですね。これは、要介護認定を受けないと、介護保険が適用されないからなんです。適用されないと気軽にデイサービスにも行けませんからね。
こういうことがあるから、僕は特にアルツハイマー型認知症については考え直さないといけないと思っています。
 奥野
奥野認知症に限らず、どんな症状・病気でも、「共生」が大事だと思います。共生って、そんなに難しく考えなくても、曽根勝さんたちのように「自分は認知症です」と言えば周囲も理解してくれるようになります。
あとは、自慢できる場があったらいきいきしますね。認知症の人も、「自慢する場」がほしいんです。
 くらたま
くらたま家族に冷たくされてもそこに行けばいいですもんね。お金が動けば、民間ももっと参入するんじゃないかと思うんですけどね。
 奥野
奥野体力のあるうちは、特に男性は働きたいと思いますよ。「人の役に立っている」と実感できるんです。
僕もよく訪れている東京・町田市のデイサービスに元植木職人のメンバーがいたのですが、ご近所の庭木の手入れをしてあげたら「ありがとう」と言われて、体が震えるほどうれしかったと話されていたそうです。
 くらたま
くらたま自分の存在を認めてもらえていると感じるのでしょうか。
 奥野
奥野そうですね。認知症に対する偏見みたいなのはまだあるんですが、記憶障害を除けば僕らとほとんど同じだと気づいてもらえればと思います。
「よく覚えられない」というのと、「認知症」とでは受け取る印象が全然違います。
 くらたま
くらたま私たちだって、「あの俳優さん、名前なんだっけ?」とか普通ですものね。
 奥野
奥野人の名前なんて覚えられないもの(笑)。 80代になったら当然だと思ったほうがいいと思います。

1948年、大阪府生まれ。ノンフィクション作家。立命館大学卒業。1978年から南米で日系移民を調査する。帰国後、フリージャーナリストとして活躍。『ナツコ 沖縄密貿易の女王』でに講談社ノンフィクション賞(2005年)、大宅壮一ノンフィクション賞(2006年)を受賞。『心にナイフをしのばせて』『がん治療革命』『魂でもいいから、そばにいて 3.11後の霊体験を聞く』など著書多数。共著として『丹野智文 笑顔で生きる 認知症とともに』などがある。