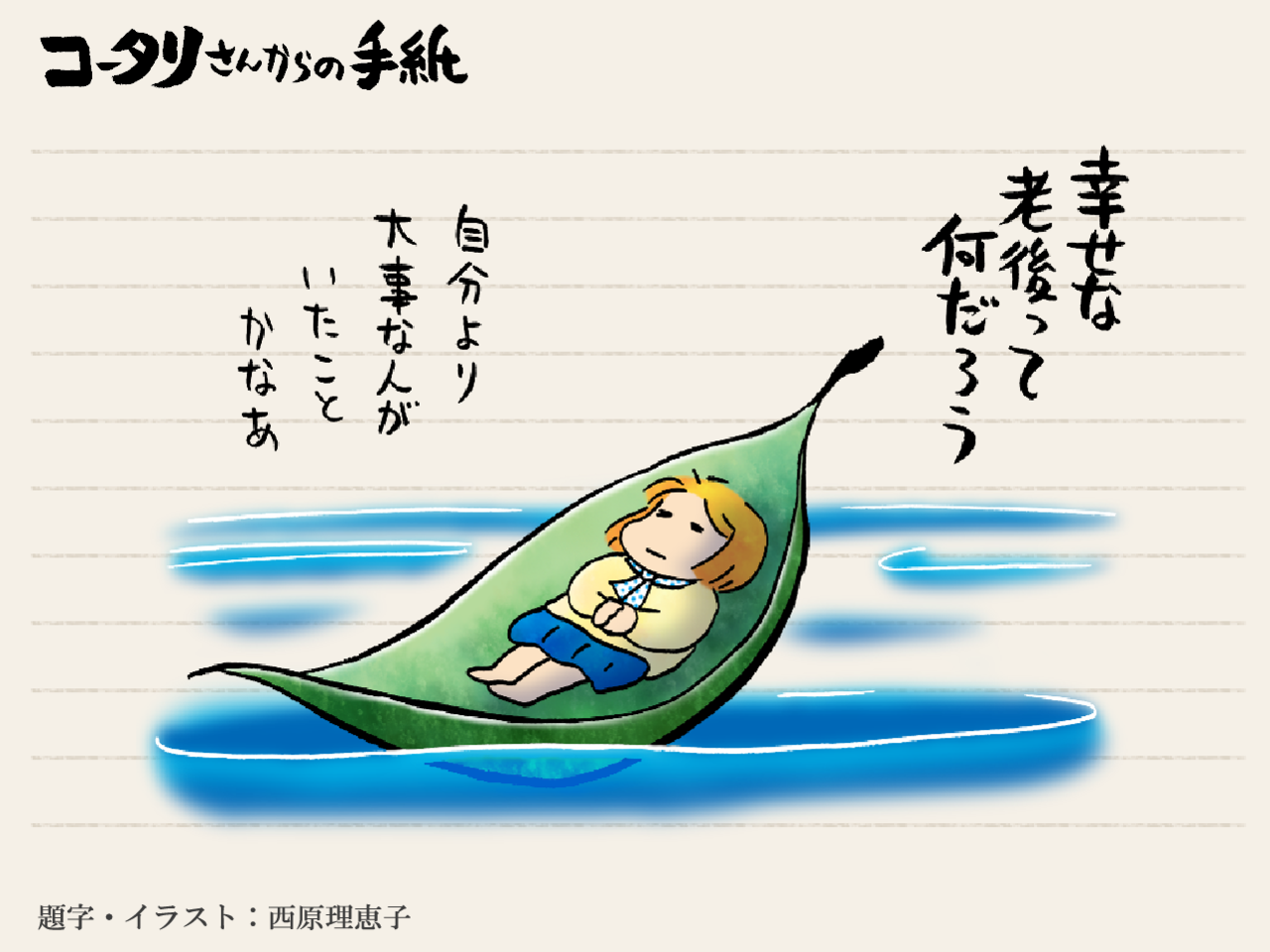幸せな老後ってなんだろう?異分野の人たちが
交流するカンファレンスに参加した
「幸せな老後ってなんだろう?」というカンファレンスが行なわれた。
そもそも老後って何歳からなの?いつが老後なの?ボクはそう思った。
老後の捉え方は人それぞれ。退職したら老後なのだろうか?それとも子どもたちが家から巣立ったら?
これから最新のシステムを渋谷で発信していこうという方々が、このテーマを題材に選んでのカンファレンスとは大変興味深い。

主催したのは「渋谷スクランブルスクエア株式会社」で、11月1日に開業する、渋谷の新たなランドマークとなるであろう大規模複合施設の運営会社だ。
その渋谷駅直結・直上となっている地上47階建てのビルの15階には、「SHIBUYA QWS(渋谷キューズ)」という共創施設ができる。
多様なバックグランドをもつ異分野の人々がそこに集い、芽生えた問いをさまざまな人や知識、技術を交差させる。
さらに、その問いから生まれた新たな可能性を実社会に飛び立たせる。
そんな可能性の種を生み出す空間だ。
連携パートナーとして慶應義塾大学や東京大学といった5大学や、さまざまな企業も参加している。
約2,600平方メートルという大きな空間のなかに、サロンやイベントスペース、プロジェクトベース、交流の場所などがあるそうだ。
これからどんな融合を見せるか楽しみだ。
今回は「SHIBUYA QWS」のオープンに先駆けて、今まで交差したことがなかったメンバーで「幸せな老後ってなんだろう?」をテーマに語り合うのだ。
登壇者にはVR旅行の登嶋さんもいる
幸せな老後を担っていく取り組みもさまざまだ
パネラーとして登壇したのは、年齢も30代前半から60歳過ぎまで、専門分野も幅広い以下のみなさんだ。
- 澤田伸さん(渋谷区副区長)
- 大石佳能子さん(株式会社メディヴァの代表取締役)
- 森田清子さん(カフェ「楽ちん堂」女将/イッセー尾形・ら株式会社の代表取締役社長)
- 登嶋健太さん(東京大学先端科学技術研究センター/稲見・檜山研究室)
- 南澤孝太さん(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科の教授)
パネラーのみなさんは、いま取り組んでいる「幸せな老後」になりうるであろう活動を紹介していった。

渋谷区副区長の澤田さんは、渋谷区がこれから行なっていく「シブカツ」についてお話された。
シブカツは、アクティブシニア世代の方がいつまでも楽しく元気に活躍し続けられるような、「学ぶ」「はたらく」「つながる」ことができるネットワークのことだ。
渋谷区にある大学のキャンパスで講座を受けられる「渋谷ハチコウ大学」や、スキルを活かせる場所を紹介するWEBサイトなど、高齢者へ提案する活動を紹介されていた。
株式会社メディヴァの代表取締役である大石さんからは、老人の施設や医療機関、在宅介護における新しい取り組みや提案についての話などを聞いた。
イッセー尾形・ら株式会社の代表取締役社長の森田さんは、主催するカフェ「楽ちん堂」で高齢者が中心のコミュニティーをつくり、子どもたちと交わりながら活動している話や、自身のパートナーを在宅介護して看取った経験も話された。
そして、東京大学先端科学技術研究センターの登嶋さんは、外出の困難な高齢者に「VR旅行サービス」を行なっており、それがどのような効果をもたらしているかについて話をした。
VR旅行サービスの活動には、ボクも端っこに参加し、そのVRを見ている。
入退院を繰り返して病院のなかで動けなくなったボクは、いつも一緒に活動している仲間が登嶋さんのワークショップを行なっているところを、遠隔で見ているだけで「社会に参加している」「つながっている」と実感できる。
この安心感と言ったらどんな治療にも勝る。
このようにVRの映像を高齢者に見せるだけではなく、その映像をつくるのもワークショップに来ているアクティブシニアのみなさんなのだ。
触覚を伝えてくれる装置も紹介された
感覚を補うという新しい治療方法を発見した気がする
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授の南澤さんは、これからの高齢化社会でみんながホジティブに生活していくことを目指した技術開発・体験などされているそうだ。
ボクが今回体験できて良かったと思ったのは、南澤さんが7年前に開発したという触覚技術を活用した装置だ。
その会場においてあったものは、装置と言っても実にシンプル。安価でできそうに見える。
装置がつながっている紙コップに、ビー玉をコロコロと何個か入れる。
そうすると、装置は音による振動によって触覚体験を記録し、別の場所で空の紙コップを持っている人に、その転がっているビー玉の触覚を伝えるのだ。
砂を入れれば砂をいれた感覚が伝わる。以前、その研究をニュースでも聞いたことがあるのを思い出した。
遠くにいても、実際の触覚に似た感覚が得られるわけだ。
物の重さや材質まで、実際にはない物でも触覚に置き換えることができ、音や匂いなども感覚で伝えることができる。
それならば、ボクのように脳の一部が壊れていても違う感性が補ってくれるのだろう。
補うという新しい治療法を見つけた気がした。
そもそも“老後”っていつから?もしかして、
大学生は60歳ぐらいだと思っていたりして…
登壇したメンバーは、思い思いに意見交換をする。どういう社会がのぞましく思われるかを、会場からの意見も参考にディスカッションした。
その日、観客は高校生や大学生から90代のシニアまでさまざまな方が集まった。
観客も、「自分の思う幸せな老後とは?」という問いの答えをカードに書いた。
それをもとに近くに座っている4人と意見を交わして、結果をカードにまとめた。
「老後を過ごすシェアハウスが普及してきているが、ある程度若いうちから共同生活していて、そのまま老後を迎えるというのはどうだろう?」とか、「いま自分の父が老後という世代なのだが、どう接したら良いか悩んでいる。年寄り扱いしても、若い人と同じでも、それはそれで問題がある」など。
ボクも近くにいた4人で意見交換をしたが、ボクよりちょっと上くらいの男性が「生涯現役・老後という観念は自分にない」という意見を出した。
さらに、「幸せな老後とは」という問いそのものにも、疑問を投げかけていた。
ボクは、ここに集まっている若い人たちは、そもそも何歳からを“老後”として考えているのかを聞きたかった。
「もしかして大学生は、60歳ぐらいだと思っていたりして」そんな考えもよぎった。
でも、その年齢に達した人たちは、決して老後だなんて考えていない年齢だろうなとも思っている。
ボクが考えた「幸せな老後」は、絵に描いた餅のようだ
でも、今の社会で実現すべきことだと思う
「幸せな老後」としてボクがイメージしたのは、若者と高齢者、男と女、障がいと健常などの隔たりがなく意見交換ができ、ともに働き、遊び、共存できる社会という漠然としたものだった。
それをカードに書きながら、「絵に描いた餅のようだな」とも思ったが、でも今の社会で実現しなければならないのはそういうことなんじゃないだろうか。
結局、さまざまな技術が発展しても、人と人のつながりや温もりがさらに必要な気もしてくる。
技術に寄り添う人間の姿が見えなければ価値はない。
1人の労働者が、2人の高齢者を背負っていかなければならない社会保障の時代がくるのであれば、働きたいと考えるシニアの方にもっとその機会があっても良いとは思う。
幸せな老後って、自分ができなくなってきたことをちょっと補ってくれる環境と、人の温もりなんじゃないかなと思ったりした。
結局いつも、最後は人と人だと思ってしまう。テクノロジーをつなぐのも人と人。
これは高齢者寄りのボクが考えた「幸せな老後」である。
取材協力:SHIBUYA QWS 公式サイト / facebook