前編では周囲の協力を得ながら、認知症を患った家族と介護をしていた佐山さんご一家の皆さんにお集まりいただきました。後編では会社に勤めている家族と、介護の話題を中心にお伺いします。
この記事に登場するみなさんのプロフィール(敬称略)
義母が亡くなるまで、主な介護者として在宅介護をしていた。同居する孫も含めた多世代家族をリードする存在で、義母の介護も家族一丸となって取り組むような家庭を築く。介護をしていた期間にはいろいろと“思うこと”もあったが、今となっては良い思い出になっている。
会社員。生まれたときから祖母と暮らし、共働きの両親の代わりに面倒も見てもらっていた。祖母の介護が始まると長男の立場から、祖母の意見、父の意見、母の意見を聞くことが多くなる。祖母の介護生活のときは、仕事が多忙で休むことが難しく、祖母が亡くなってから「もっといろいろしてあげたかった」と後悔を感じている。会社勤めでも介護にもっと専念できる「システム」が必要だと考えている。
ライター。通所デイサービスで介護職員として勤務していた経験を活かし、介護・福祉系のライターとして活動中。15年前に脳梗塞で左麻痺になった自身の父や、認知症になった義祖母の自宅での生活のサポートをする。在宅介護で経験したことや、母や夫の家族の悩みや話を聞くうちに、家族を介護することは「介護者の気持ちに寄り添うこと」も必要だと強く感じるようになる。
職場でできる? 家族の介護の話
みんなの介護(以下、―――)
前編では、としえさんの介護を通して「自分にできることを探したが、仕事も忙しくどうしていいのか困ってしまった」とひろしさんからお話がありました。
当時も会社にお勤めしてされていたそうですが、職場で介護の話があがることはありましたか。

ひろし
当時、職場で介護の話をすることはなかったですね。親や自分に近い存在の家族だったら少しはすると思いますが。
当時も現在も、介護の話題を会社でする人は少ないですよ。会社の食事会、会合などでもっと介護や育児問題などの話題になってもいいと思うんですよね。私の仕事の内容になってしまいますが、仕事に直接関係性のある効率性や生産性の話題が多くなりがちです。
「働く人間の背景にも目を向けた話題の話があがってもいいので」はと思います。
――― 当時、介護休業は取得されなかったのでしょうか。

ひろし
介護休業は取得しませんでしたし、取得しづらい雰囲気はありますよ。
「えっ?介護で休むの?奥さんや家族は介護をしていないのかな?」と、当時、男の私が介護を理由に会社を休んでしまったらそういう風に思われていたでしょう。
最近は介護と育児の休業の取得がしやすくなったようですが、身近で取得している方はいないですね。会社によるかもしれませんが、大きい企業や公務員だと取得しやすいイメージがあります。中小企業だとギリギリの人数で仕事を回しているので、介護休業でなくても休みづらいこともあるからかもしれません。
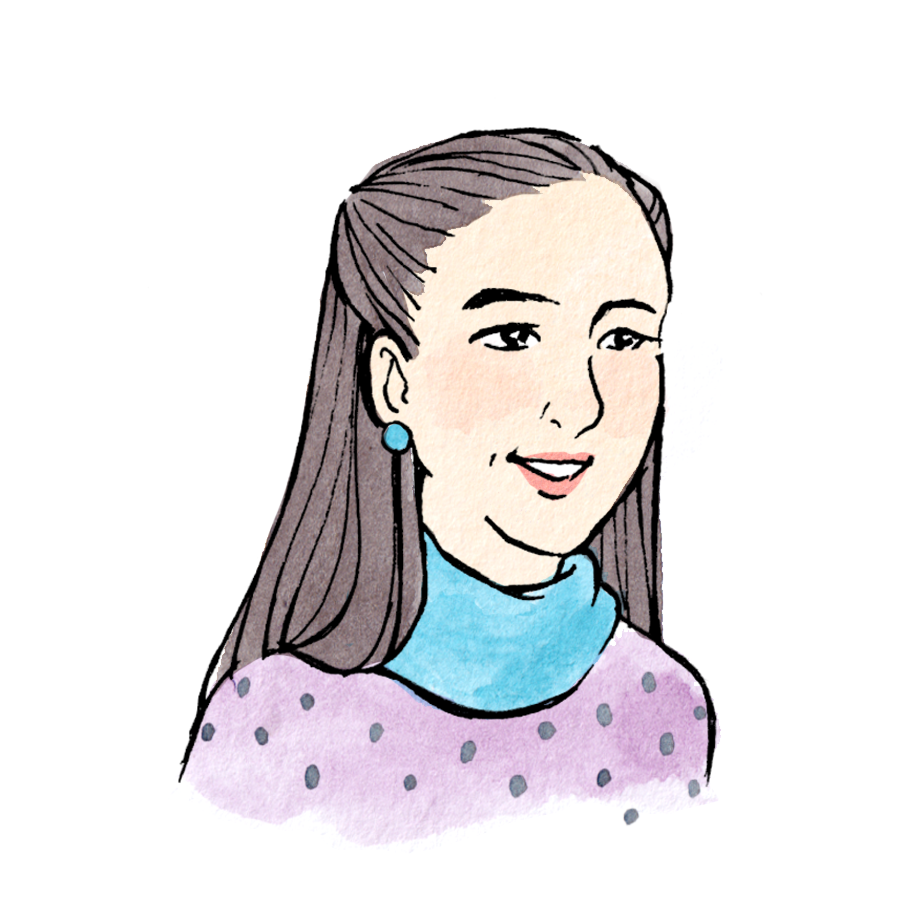
あけみ
たしかに正社員で働くと、休むことが“悪い”ことになってしまうことがありますよね。今は企業も改善してきていると思いますが、まだまだ介護休業を取得しづらい環境ですよね。

ひろし
介護の休業ではないのですが、自分の子供が生まれたとき妻は実家に帰省してました。ちょうどその頃、インフルエンザが流行していて妻の実家の者もかかってしまって。
妻と生まれたばかりの子供のサポートを出産で病院に駆けつけた私がそのまま退院後もする以外、対応がなくなってしまいました。妻の実家は自宅から遠かったので一週間程、会社を休みました。
その後、久しぶりに会社に行ったら、上司にすごく嫌な顔をされた苦い経験があります。話が介護からずれてしまいましたが、会社員が会社を休むことは難しい面があります。当時から法律が変わったようですが、介護で休むこともまだまだハードルが高いのではないでしょうか。
現在では、介護休業制度や介護休暇制度の施行により家族間で介護を必要とした場合、会社を休んだり休暇を時間単位での取得がしやすくなりました。介護による仕事の離職を防ぐことを目指し、介護をする労働者を守る制度になっています。
「育児・介護休業法」により該当するすべての労働者に認められている制度です。
――― 2022年に施行された介護休暇では、1時間単位で会社を休めるようになりました。数時間でも会社を休むのは難しいでしょうか。

ひろし
時間単位でも仕事に「穴を開ける」ことは難しいですよ。仮に仕事を休んだとして、「復帰後に自分の仕事があるのか……」と感じてしまいます。休んでいる間の給料の事も考えると不安です。
――― ありがとうございました。佐山さんの旦那様は自営業をされていたそうですが、介護へのサポートはどうでしたか。

佐山
自営業なので、会社勤めをされている方よりは時間を作ってサポートができたと思います。お義母さんを病院に連れて行ってもらったり、入院したらお見舞いにも頻繁に行ってもらったりしました。夫もお義母さんにはよく“尽くした”と思いますよ。普通に会社に勤めていたら、家族の介護のサポートは難しいと思います。

ひろし
よく、お母さんと祖母の間に入って話も聞いてくれていたよね。お母さんが言いづらいことは、お父さんが祖母に言ってくれたり。
仕事をしていても家にいる時間が多かったから、祖母とお母さんの両方に気遣いのある対応をしていました。心にも時間にも余裕があったのかなと思います。
――― ありがとうございます。あけみさんにもお話をお伺いしたいです。
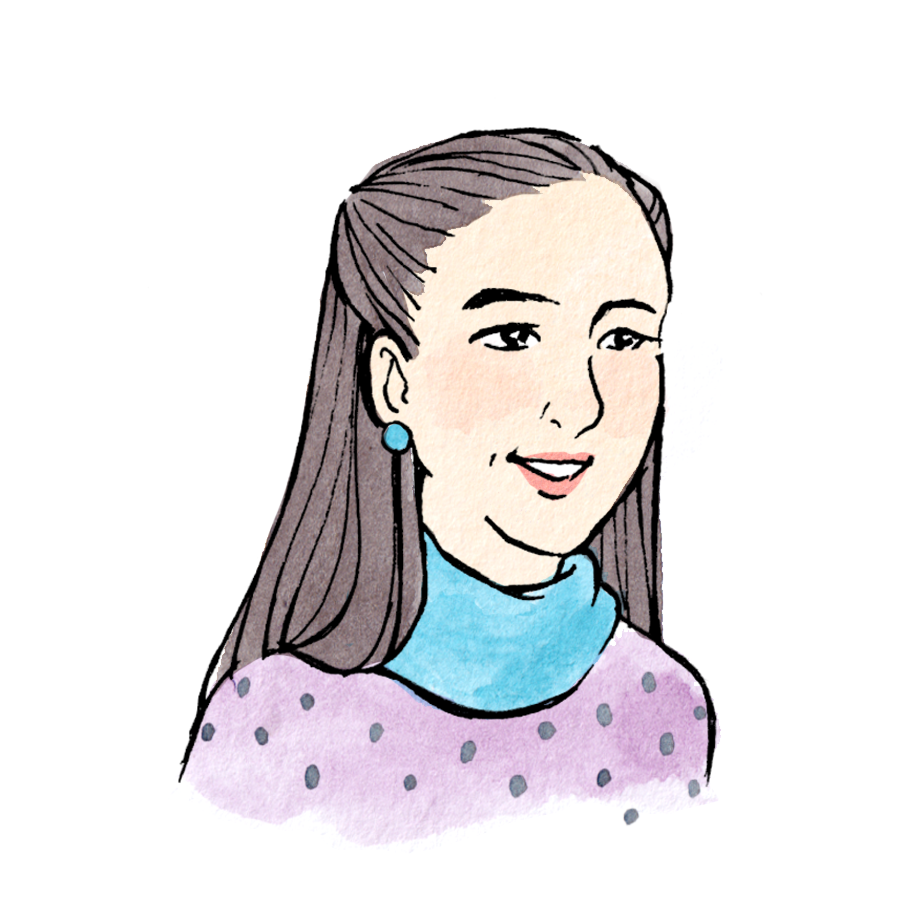
あけみ
私の実家の話ですが、父は60代で脳梗塞になりました。一命は取り留めはしたものの、後遺症として左麻痺になりました。
父は左利きで利き腕が麻痺してしまい、自宅に住んでいた私も病院に連れて行くなどサポートをしていました。その後、日帰りでは帰省できない地域に私が転勤となってしまいました……。
父の介護のサポートがあまりできなくなり、母と兄が主に介護をしていました。私の家も自営業で兄も父と一緒に働いてたから、父の支援がしやすかったのかなと思います。

ひろし
妻のお義父さんが70代で認知症になってしまったときも、サポートがあまりできなかったです。妻の実家も私たちの自宅からは距離があり、コロナの影響もあって簡単には行けませんでした。私たちもお義父さんの介護をしている妻のお母さんや、お義兄さんを手伝いたかったですね。
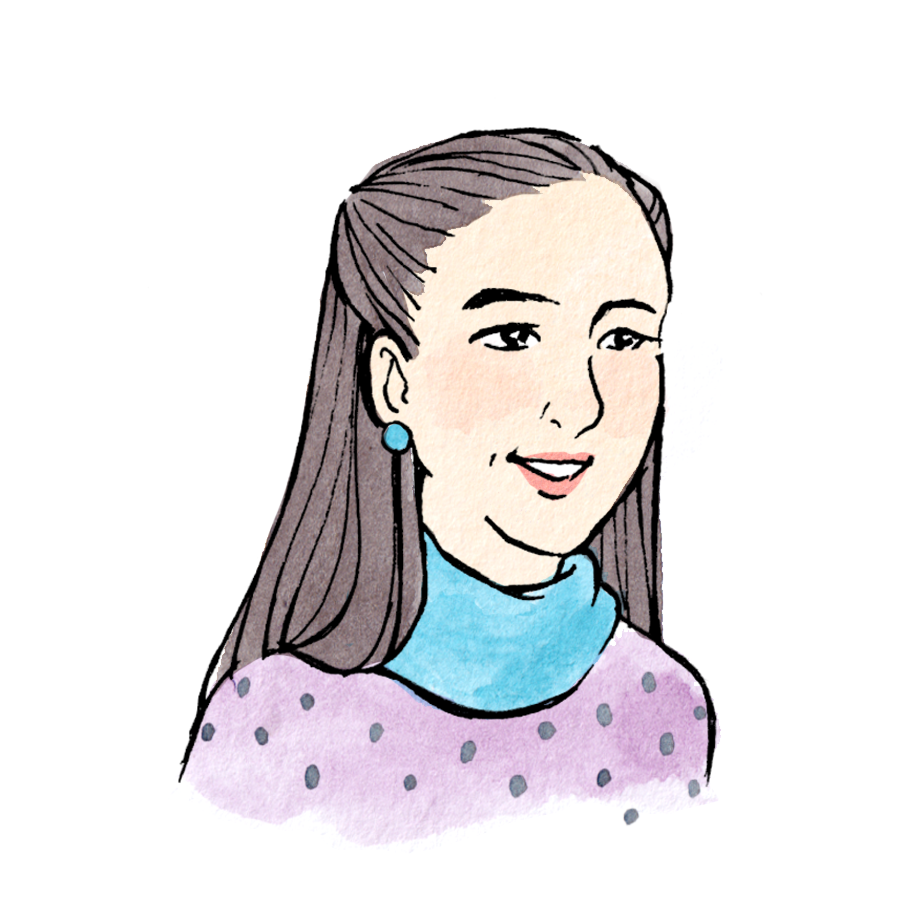
あけみ
父が認知症になったばかりの頃「お父さんがおかしくなってしまって。これから不安しかないです」と母からLINEがきました………。電話などで私もできる範囲で母の話を聞いたり、LINEで連絡を取っていました。介護の仕事では「高齢者の方の気持ちに寄り添いなさい」と言われますが「介護者の気持ちに寄り添う」ことも大切だなって思いました。
――― あけみさんのお母様とお兄様は、お仕事をされながら、認知症になったお父様の介護をしていたのでしょうか。
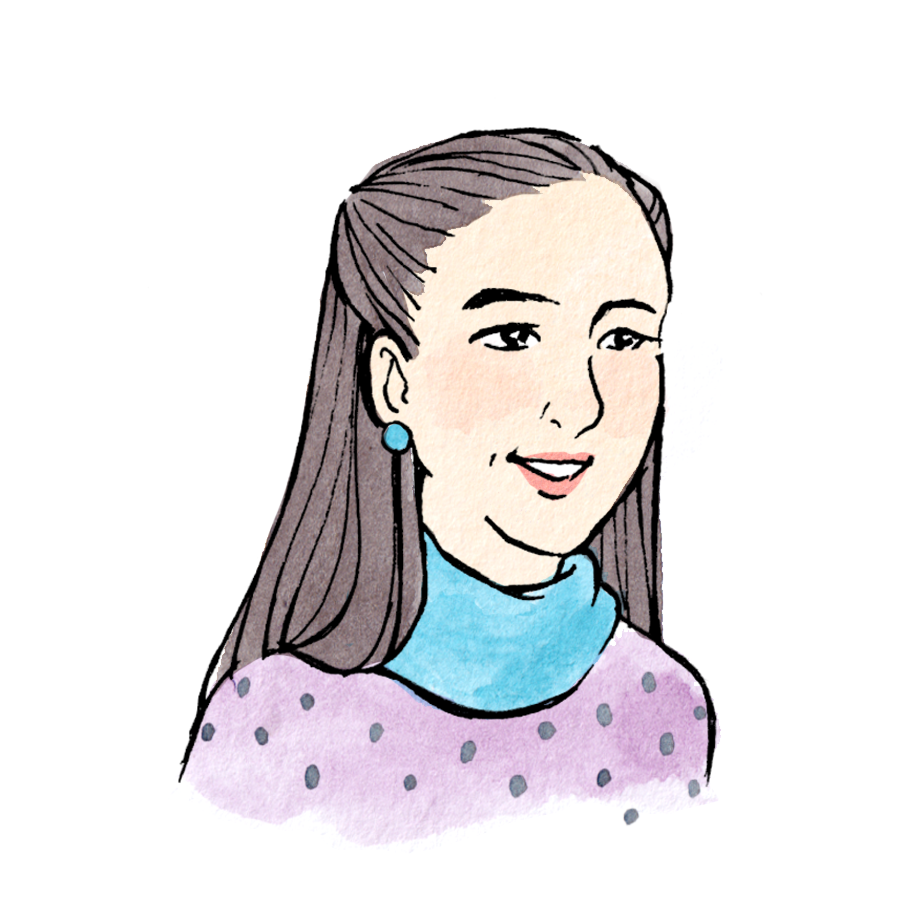
あけみ
昨秋、父は入院先の病院で老衰で亡くなりました。退院したら本格的な介護が始まるので、母は介護に専念するために仕事も辞めました。母の退職は年齢的なものもありましたが、一般的に見てもまだまだ介護離職はあると思いますよ。実家で営んでいた会社も、父の脳梗塞と不況のあおりを受けて廃業しました。
父が仕事を離れてからの再建は難しかったようです。兄はその後、左半分麻痺した父の支援がしやすいようにシフト制のアルバイトをしていました。アルバイト勤務にした理由は兄も40代の頃、脳の手術をしていて万全な体ではないという理由もありました。
――― ありがとうございます。介護に携わる時間が少なくても、介護をしている家族、または介護を必要としている方へサポートしたいお気持ちがよく伝わりました。

ひろし
今となっては祖母が亡くなって、いなくなってしまったからこそ、「もっといろいろしてあげたかったし、サポートをしてあげたかった」という気持ちが強いです。
母が祖母の介護を主にしていて、その姿を見て「大変だろうな」とは思いましたよ。たまに、祖母と家族が感情的になって口論になることもありました。認知症になった祖母や祖母のサポートをして疲れている家族、両方の姿を見てどうにかしてあげたいと思っていても、どう介入していいのか悩んでしまいました。
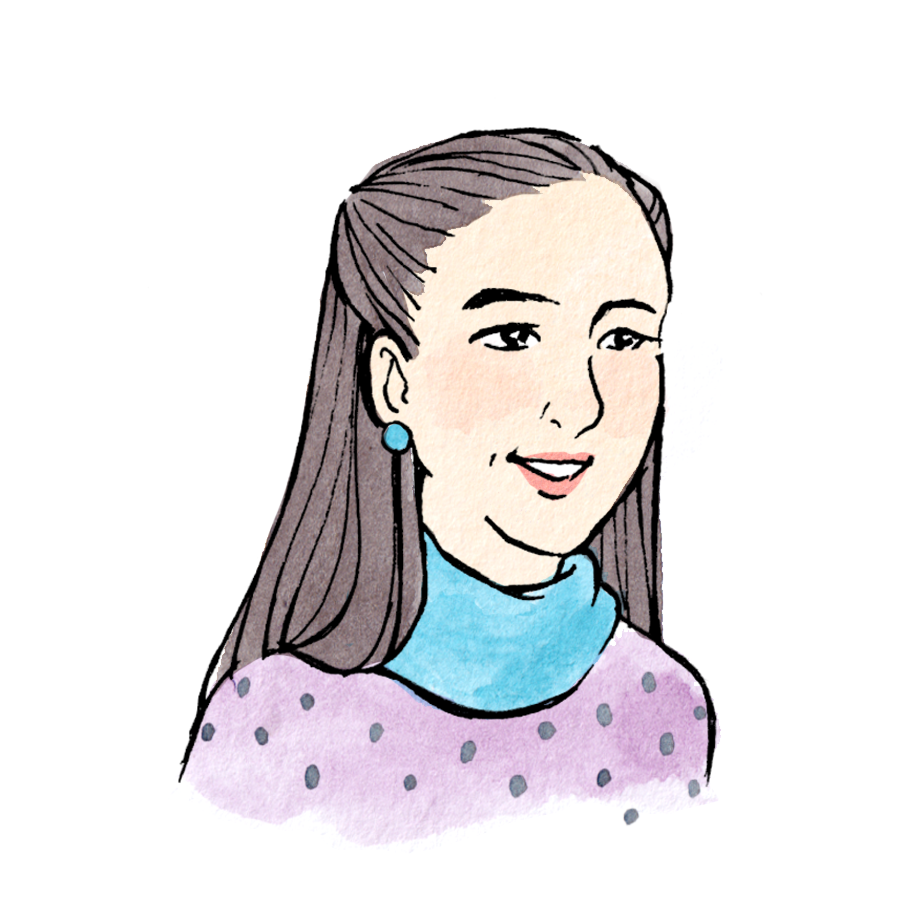
あけみ
仕事と介護もそうですが、自分の家庭や生活が“いっぱいいっぱい”なときもありますからね。それでも、サポートはできるだけしたいですよね。
デイサービスに行きたくない……それぞれの意見
――― お忙しい日々の中で、デイサービスもご利用になっていたそうですね。デイサービス利用中のとしえさんはどのような様子でしたか。

佐山
お義母さんは最初、デイサービスに行くのを嫌がっていました。しだいに慣れてきたのか楽しくなってきたようですよ。デイサービスでの運動やカラオケやお買い物といったレクリエーションや、他の方と会話ができて気分転換になったのかなと思います。
たまに「今日は行きたくないな……」という日もありましたが、行くと楽しんでいたようです。

ひろし
デイサービスに行くことは、祖母にとっても、私たち家族にとっても良いことだったと思います。「家で介護が大変だから行ってもらった方がいい」というわけではないですよ。デイサービスの介護のプロによるレクリエーションや脳トレが祖母にとっていい刺激になり、家族も“イキイキ”とした祖母の姿がみられました。
認知症になってから、祖母はいろいろな不安があるのか、ふさぎ込んでしまったんですよ。しっかりとして頼りがいのある祖母の弱っていく姿を見て、私もどうしたらいいのだろうと思いました。でも、デイサービスに行くようになってから、近所の知り合いの方も同じ施設だったこともあって、毎日にハリが出てきたように思いました。
もちろん、ふさぎ込むことが無くなった訳ではありませんが、楽しそうにデイサービスでの出来事を話す祖母を見て嬉しかったです。
――― デイサービスを利用していい影響がとしえさんにあったのですね。一方で困ったことはありましたか。

佐山
帰りの送迎のときに、自宅で私が待っていないと嫌だったみたいで。いただいた送迎表の時間よりも帰りが早いときもあるんですよ。デイサービスの送迎のバスが自宅に来る時間を見計らって、買い物や銀行や自分の病院に行くのですが、先にお義母さんが自宅に着いているときがあって。私がいないときは誰かしら家に居たのですが、それではお義母さん満足しないようでした。
娘と買い物に出かけたときも、自分の部屋で小言をブツブツと言っていたときもありました。
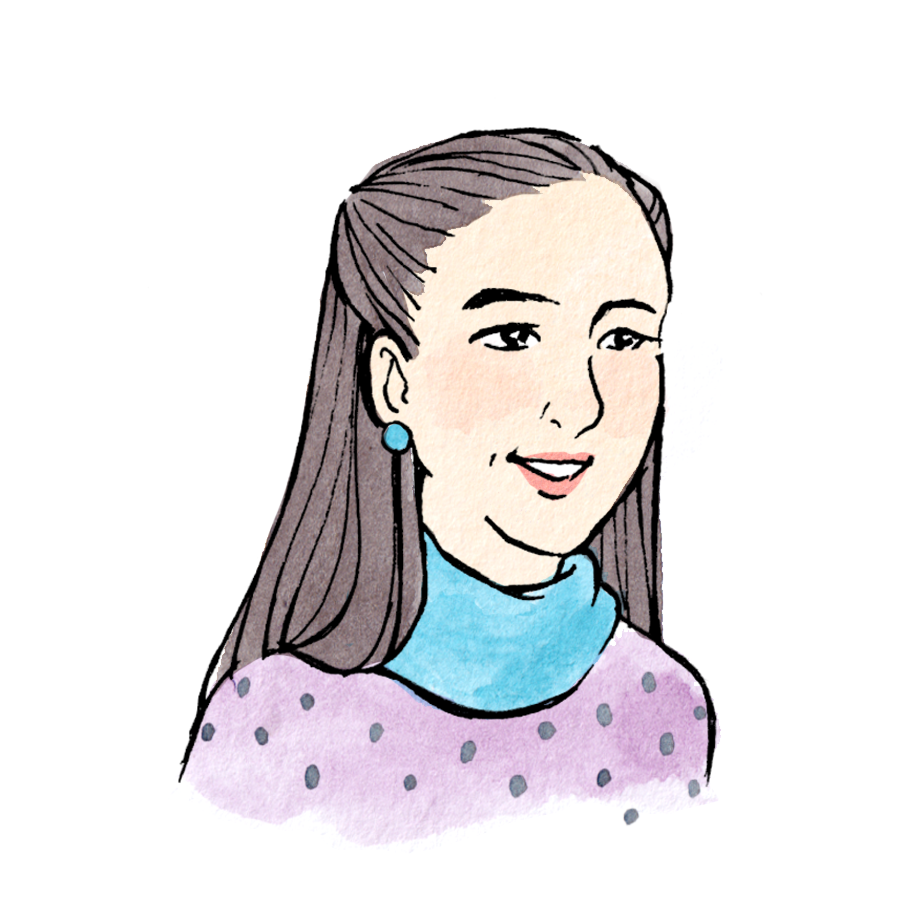
あけみ
おばあちゃん、焼きもちをやいていたのかな。かわいいですね

佐山
今ならお義母さんの“かわいい”エピソードだけどね。当時はお義母さん機嫌が悪くなるから帰ってくる時間にとても神経を使ってました。デイサービスをお休みした方がいると、お義母さんの帰ってくる時間が予定外に早くなるんですよ。自宅で待っていた家族から帰ってきたと連絡をもらって、急いで出先から帰ることも何度もありました。
今にして思えば、介護に必死でしたね。

ひろし
祖母は、母に感情をぶつける事ができたのでしょうね。母は嫌だったと思いますが、祖母にとって母は甘えられる存在だったのかもしれないです。
――― 利用していた施設は、デイサービスだけでしたか。

佐山
本当はお義母さんが検査入院していたときに、退院したらショートステイも利用しようと計画はしていました。しかし、検査入院先の病院で亡くなってしまって利用はしなかったです。
――― ショートステイのことはとしえさんに伝えていましたか。

佐山
ショートステイになると施設に宿泊することになるので、嫌だったようです。「本人の意思の尊重」もありますので無理には進めませんでしたが、だんだんと私たち夫婦や夫のきょうだいの年齢も上がり、介護がつらくなる場面も出てきたんです。息子のひろしも仕事があり、お嫁さんのあけみさんも幼い子供がいて妊娠中でもありました。娘も家庭を持ち子供もまだ幼ない、などの理由があってショートステイの利用を考えるようになりました。

ひろし
自宅から離れる入院も祖母は嫌だったようです。お見舞いに行くといつも「早く帰りたい」と言っていましたから。
ショートステイも利用が決まるまで、母や介護をしている者の言い分と祖母の言い分が割れてしまいました。中間の立場だった父は悩んだと思います。ときどき、私も父から「本人がショートステイは嫌だと言っているし…」と考えていることを聞いたことがありました。

佐山
結局、利用はしませんでしたが、お義母さんにショートステイの話を聞き入れてもらいました。
いつかは終わりが来る介護生活
――― 介護を終えた今だから思うことがありましたら、最後にお伺いできますか。

佐山
私は義理の母の介護だったので、最初は気を使いました。ですが、月日が経つにつれて、自然にお義母さんと打ち解けることができたと思います。
結婚後、同居生活をしてから自分の身内よりも長く生活を共にしてきました。楽しかったことや嫌な思い出もいろいろありましたが、私なりに一生懸命に介護をしてきたと思います。後悔はありませんし、今になって振り返ると全てがよい思い出です。お義母さんも幸せだと思ってこの世を去ってくれたことを願います。

ひろし
私は日頃、仕事をしているため、祖母の介護に関わることが少なかったです。ですが、介護を終えてみるともっとできることは、あったのではないかと感じます。一緒に居られる時間は限られています。共有できる貴重な時間を大切にしていればと、今となっては思います。
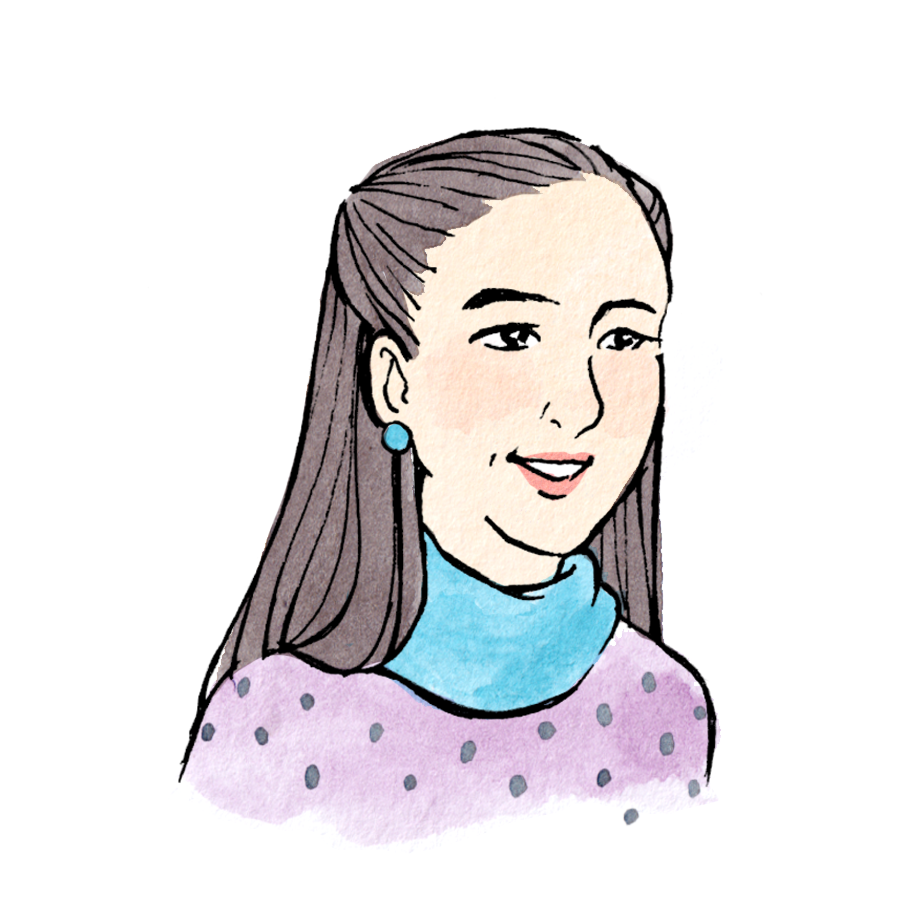
あけみ
介護中は大変なことが多いかと思います。でも一人で抱え込まずに、周りに声を上げて助けを求めた方がいいですよ。当時は悩んでいる夫の母や実の母の間で、介護の仕事をしてきた身としてできるだけのことをしましたし、話も聞いてきました。周りを巻き込んで介護に向きあってもいいと思います。
私も夫も予期せず大切な人の介護生活が終わってしまい、後悔が残りました。介護は長期戦ですが、終わりも来ます。無理をして頑張らなくてもいいので、後悔のない介護生活を送っていただけたらなと思います。
大変なときは周囲の協力を求めてみんなで少しずつ、できることから介護に協力する。 日々の慌ただしい生活の中で、懸命に介護をしてきたみなさんだからこそ、いろいろなお気持ちをお伺いすることができました。介護という苦しい渦から離れると、全てが思い出になるのかもしれません。

取材・文:中島順子
「みんなの介護座談会」へご参加頂ける方を募集しています
「みんなの介護座談会」は読者の皆さまに参加して頂く新企画です。皆さまの日々の介護に対する思いをぜひ座談会で語ってください。
以下のフォームより、ご応募をお待ちしております。
参加フォームはこちらをクリックしてください



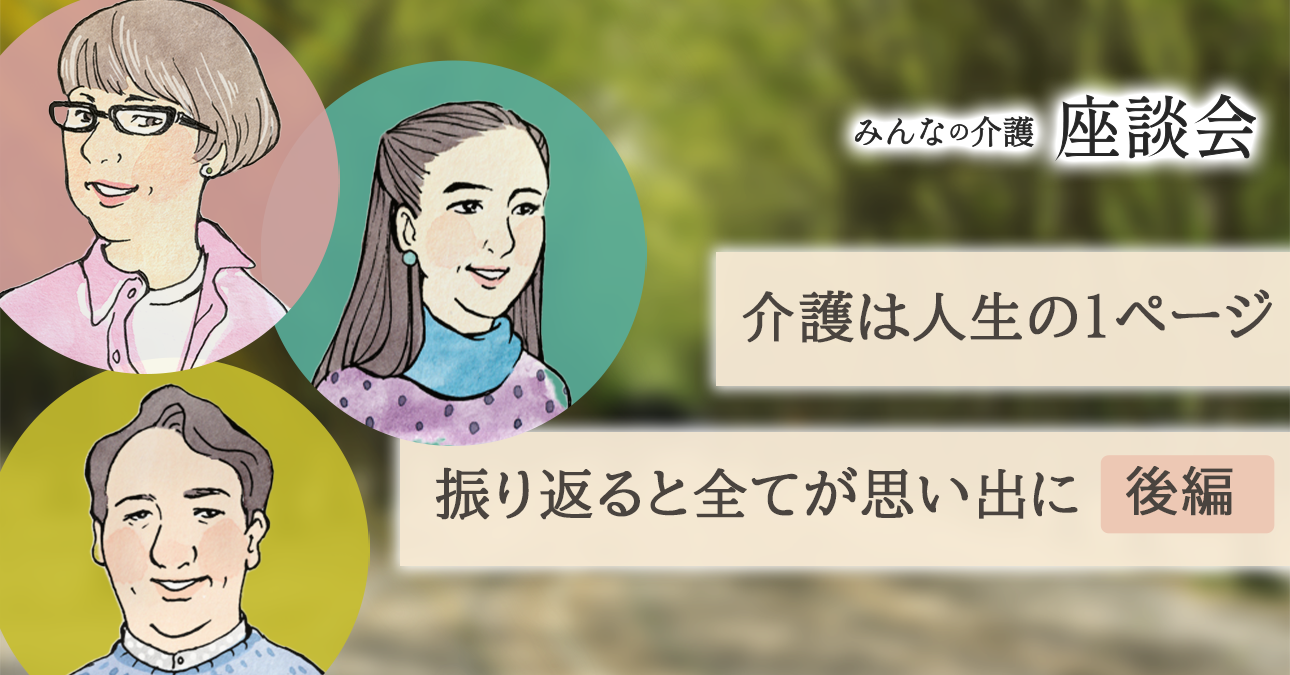
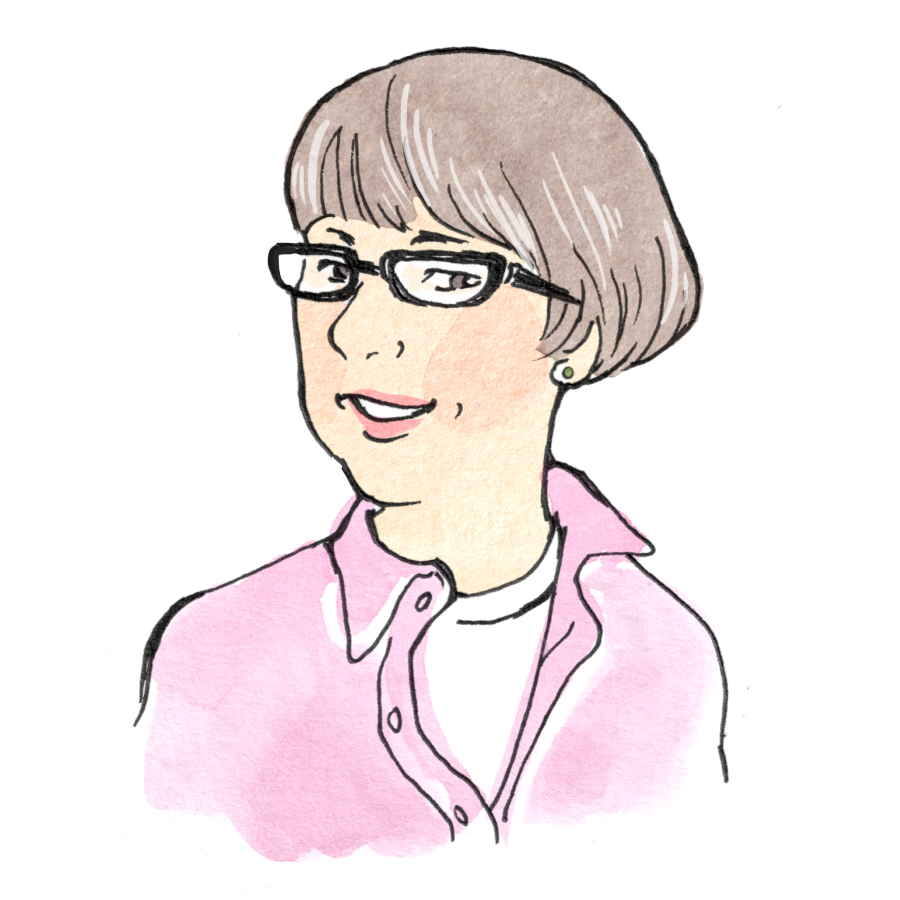
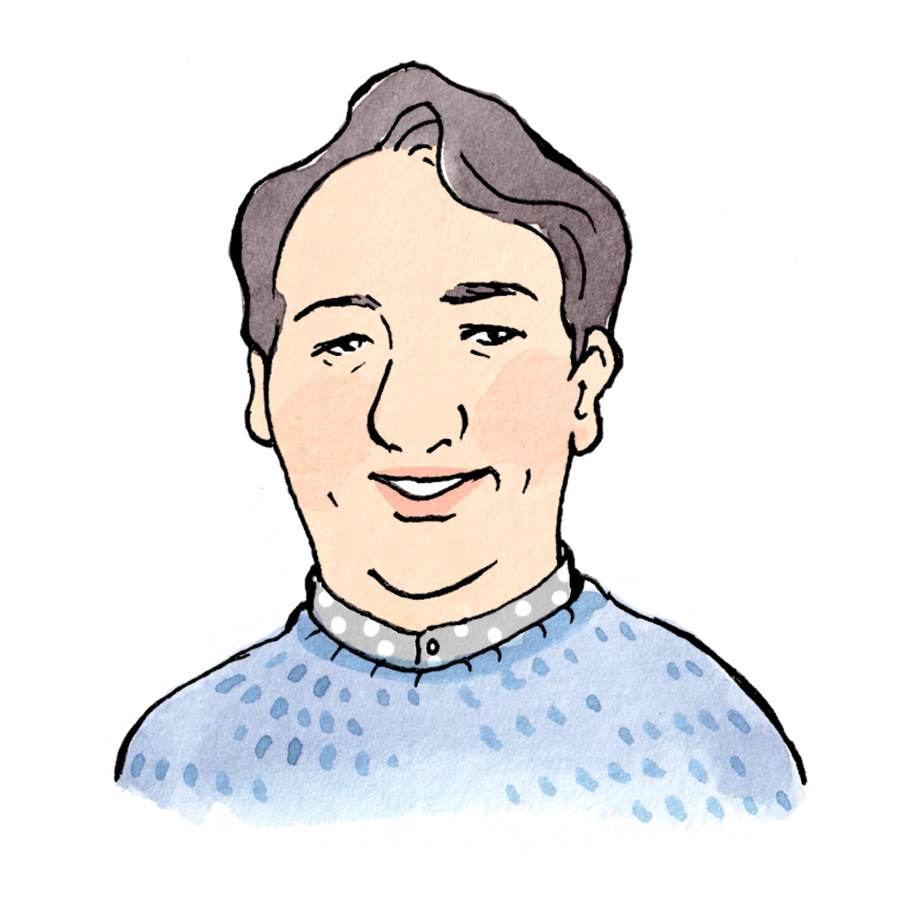
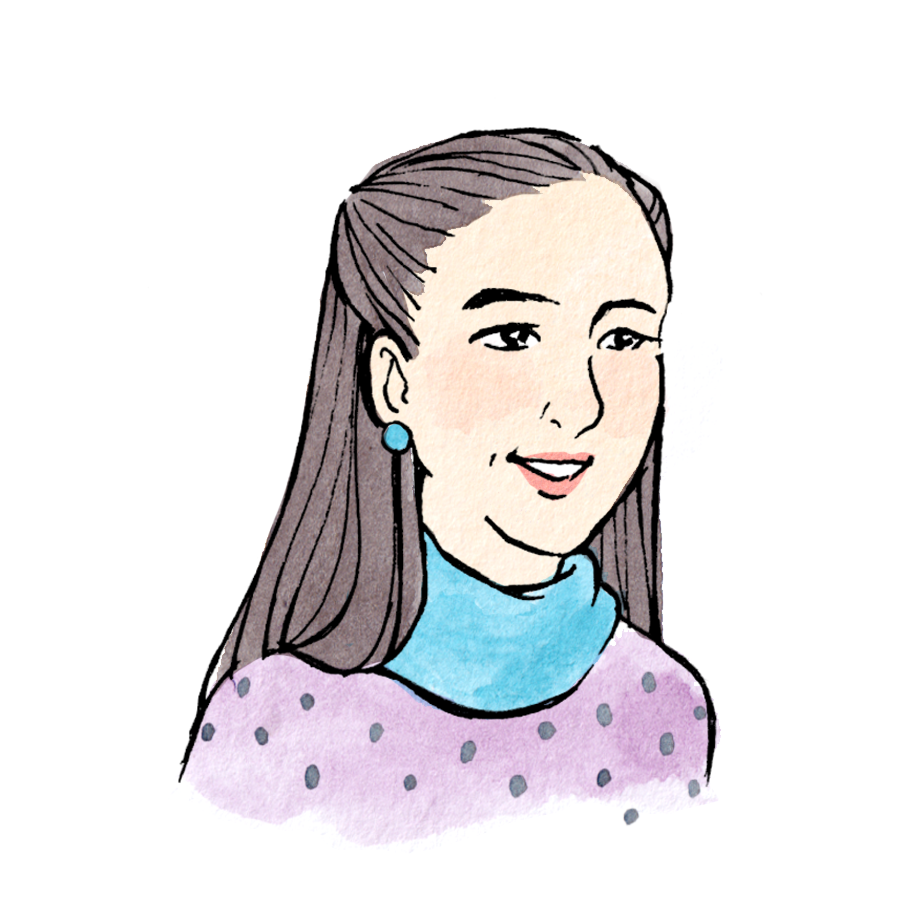
 ひろし
ひろし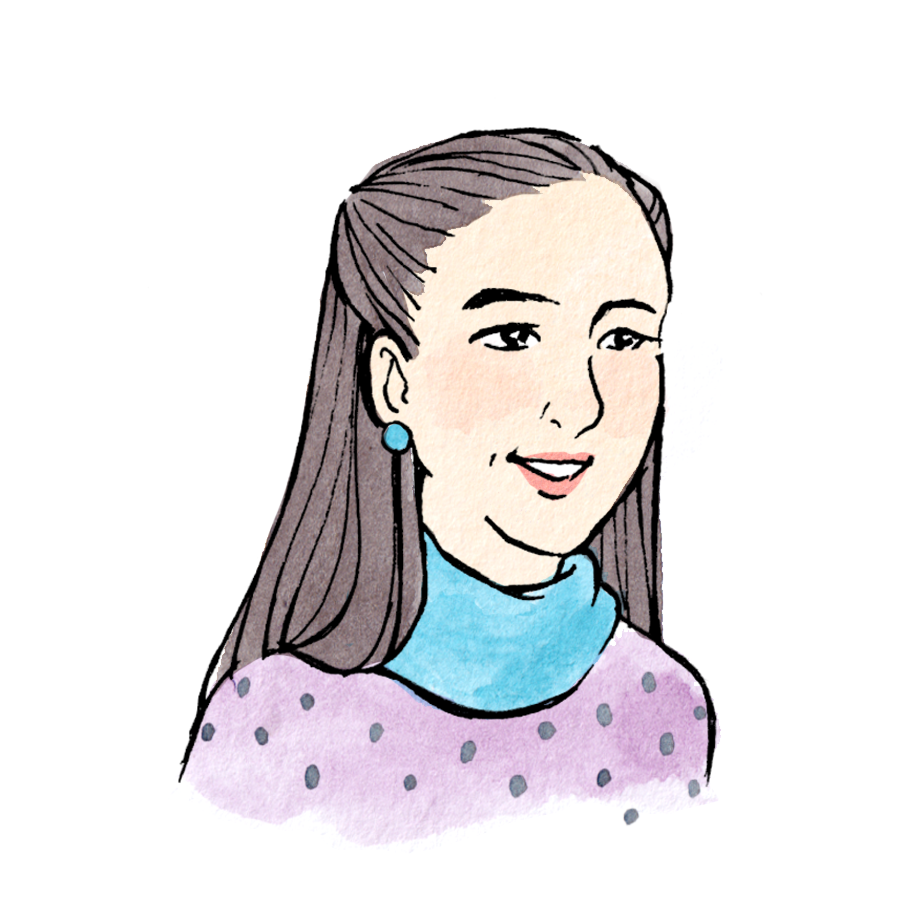 あけみ
あけみ 佐山
佐山