「学校」をコンセプトにした高齢者ケアとして注目される「おとなの学校」大浦敬子代表に、介護の現場での学習の楽しみと効用についてお聞きする。医学博士でもある大浦代表は実家の病院経営を引き継いだときから高齢者医療や介護のあり方について様々な取り組みを続けてきたという。
監修/みんなの介護
【ビジョナリー・大浦敬子の声】
「学校」がコンセプトのデイサービスで
高齢の方も学生の頃の気持ちに戻る

「おとなの学校」は、「学校」をコンセプトにした高齢者ケアのシステムです。朝礼や授業などの学校生活を再現することで、高齢者の皆さんが学生に戻り、元気に学べる場になっています。
私は32歳で実家の病院経営を引き継いだときから、高齢者を元気にする高齢者施設の運営について試行錯誤を繰り返してきました。高齢者が楽しめることを「遊び」や「仕事」などのテーマで、それはもういろいろ試してきたんです。
でも、あるときに公文(日本公文教育研究会)の認知症当事者や認知症予防のための学習療法に出会い、高齢者の学習意欲に気づきました。現在、90歳前後の方は、戦争などで学校に行きたくても行けなかった方が多く、「学校に行きたかった」という思いが強いんですね。学校に通っていた方も、「あの頃は楽しかった」「あの頃に戻りたい」と考えていらっしゃるので、学校なら楽しく参加していただけると思ったのです。
普段はデイサービスを嫌がる方でも、教室に入ったとたん、生徒になりきりますよ。
教科書を使った8教科の授業
「おとなの学校」は、大浦代表の地元・熊本県で2006年に学校形式の介護施設として設立され、2011年に株式会社化、介護施設などへ教科書を導入する事業を開始している。教科書導入施設では校歌や制服も制定している。事業の主軸は、デイサービス施設などで使用するオリジナルの教科書の発行だ。2015年に創刊された月刊の教科書『おとなの学校メソッド』は、2019年末現在で全国の通所介護施設などを対象に約1万部が発行されている。

この教科書を使い、各施設の介護スタッフが先生となって授業を進める。教科書は国語・算数・理科・社会・音楽・家庭科・保健・体育の8教科で、それぞれ30分ずつ行われる。図工は多くのデイサービスで工作やぬり絵が実施されているという理由で、設定していない。
1日のカリキュラムは施設ごとに設定され、1日1コマだけの施設も、朝から昼食をはさんで午後まで授業を続ける施設もある。

大浦代表は「どこの施設でも、皆さんとても楽しそうです。重度の認知症の方でも、『起立、気をつけ、礼、着席』が普通にできる方は多いですね。もちろん『手は膝の上』に置いたまま、30分間授業を聞いて、積極的に手を挙げて発言しています」と笑顔を見せる。
クラスメイト同士の助け合いが生まれる
学校形式のレクリエーションを行うメリットは、「クラスメイト」として利用者同士の交流が望めることもある。教科書を見ながら予習や復習をしたり、重度の認知症の生徒に対して「同級生」たちが気遣ったりと、助け合いが生まれるのだ。
「おとなの学校では、『みんなが優等生』なんです」と大浦代表。
「花マルもいっぱいつけますし、学ぶことを楽しんでいただいています。皆さんが一生懸命に勉強する姿を見ると、かつての悪ガキもみんな優等生になりたかったんだなということがよくわかります」

事前に「親は重度の認知症なので、授業をきちんと受けられる自信がない」とご家族から問い合わせを受けることも多い。しかしほとんどの利用者が、離席や居眠りもせずに問題なく授業を受けている。
自ら発言したり行動したりすることが
高齢者の認知症予防につながる

おとなの学校は、「回想法」が授業の中心です。昔のことを思い出して、「懐かしい!」と心が動くだけで、脳の血流量が増加して認知機能が高まるんです。これを利用した認知症セラピーが「回想法」です。
教科書は、おとなの学校のスタッフが毎月製作、発行しています。「先生用」と「生徒用」で内容を変えていて、「先生用」には毎日の暦や出来事、授業のテーマに沿ったトリビアを載せています。でも、先生はそれを全部話さなくていいんです。
例えば、授業の最初に生徒さんたちに「今日は〇〇の日ですね」と話したら、その後は生徒さんたちがいろんな話をして「脱線」していきます。この脱線がいいんですよ。重度の認知症の方でも、昔のことならどんどん思い出して、話してくれます。
「授業」をすることで、生徒さんたちは自発的に話したり、動いたりするので、自然に脳と身体の動きが活発になるんです。
「介護しない介護」が高齢者を元気にした
おとなの学校のもうひとつの特徴は、「介護しない介護」であることだ。
「介護」とは、「身体上又は精神上の障がいがあることにより日常生活を営むのに支障がある者」について、「心身の状況に応じて行う」ものと定義されている(社会福祉士及び介護福祉士法)。 これに対して、おとなの学校では、授業を進めるだけで生徒たちが元気になり、自然な機能訓練を行えることから、いわゆる「介護」ではないという。
大浦代表は、「重度の認知症の方も真剣に授業を受けられています。今後も多くの認知症の方々に体験していただきたいです」と目を輝かせる。「生徒」が元気になれば介護職員や家族の負担が減り、授業を担当しない職員は、授業中に別の業務を進めることができる。
「こうして現場が楽になると、介護職員のやりがいや定着率も高まります。これがおとなの学校の特徴であり、ほかの施設と違うところです」
かつてグループで運営していた介護老人保健施設では、多くの利用者の要介護認定レベルや失禁率が低下しており、在宅復帰率は18.6%から67.7%に上がっている。
多くの教科書導入施設で高齢者に良い変化が
実際に「おとなの学校メソッド」を使用している施設に聞くと、メソッドはとても好評だ。以下のように、現場の声からも利用者の変化がうかがえる。
「若い頃に通った学校と同じように一人ずつに教科書があり、先生がいて日直もいて、黒板に向かうことで、いくつになっても『学ぶ』楽しさを持ち続けられる。また、教科書に書き込んで、復習もできるので、活気、やる気が出ている」(サービス付き高齢者向け住宅 兵庫県加東市)
「今までテーブルで居眠りをしたり、数分おきにトイレに行ったりしていたご利用者様が進んで自ら授業に参加し、ご利用者様同士で授業について話すことも多い。また、漢字を書く機会も増え、発語が少ないご利用者が手を挙げて発言して表情も明るくなるなど、変化を感じている」(介護老人保健施設 東京都足立区)
また、利用者の家族からも「帰宅後に家族の前で歌を歌うことが増え、活気も出ている」と喜びの声が上がっている。
さらに茨城県のデイサービス利用者の中には、「勉強したことを家族に教えてあげた」「授業に間に合うように入浴などを早めに済ませたい」など家族との関係が良好になったり、生活面でいい変化があったりしたケースもあるという。
自分が高齢者になったときに
されて嫌なことは利用者にもしない

亡くなった母から経営を引き継いだ1990年代前半、高齢者医療はひどいものでした。高齢者は24時間おむつを着用、服も簡単に着脱のできないツナギ(介護衣)だったんです。
私は現場を見て、「これはダメでしょう」と思いました。
当時のスタッフに「自分たちも歳をとったら、こういう風にさせられるけど、いいの?」と問いかけるところから改革を始めたんです。そして、高齢者をただ寝かせていた「儲かる病院」をやめて小さい病院の経営を始め、リハビリテーションや緩和ケア(ホスピス)などに変えていきました。「こんなのはイヤだ」が、私の原動力になったのです。
孔子の言葉に「己の欲せざる所は人に施す勿れ」とありますが、自分が高齢者になったときにされて嫌なことを他人にしてはダメ。そうやって信頼関係をつくってきました。
高齢者にとってベストな介護を考え続けてきた
おとなの学校を開校するまで、「何が高齢者にとってベストなのか、死ぬほど考えてきました」と大浦代表は明かす。拘束だけの医療を廃止し、ADL(日常生活動作)向上などのためのレクリエーションにもトライしてきた。
「本当にいろいろやりましたよ。施設内にビールサーバーを2機置いて、『夜のデイサービス』と称して飲み会をしたり、利用者さんと一緒に糠漬けやクッキーをつくって地域のコミュニケーションセンターで売ったり。クッキーにはメンバー全員の年齢を足して『製造者年齢 1300歳越え』と書いたりしていました。お酒を飲んだり、働いたりするデイサービスは、最近こそ増えていますが、私が『先駆け』だと自負しています」

そんなときに公文の学習療法に出会い、遊びや労働より学習がいいとひらめいた。
「生徒だった『あの日』に帰っていただき、いろいろなことを思い出せば、脳が活性化されていきます。脳は使えば使うほどよくなるんです」
在宅介護を支援する新しいサービスを開始
2019年末には、「おとなの学校メソッド」を家庭でも使える「かぞくの教室」も発売されている。メソッドの教科書を高齢者と家族が読み、内容について話すことで、介護や介護予防とともに家族の絆を強める狙いもある。
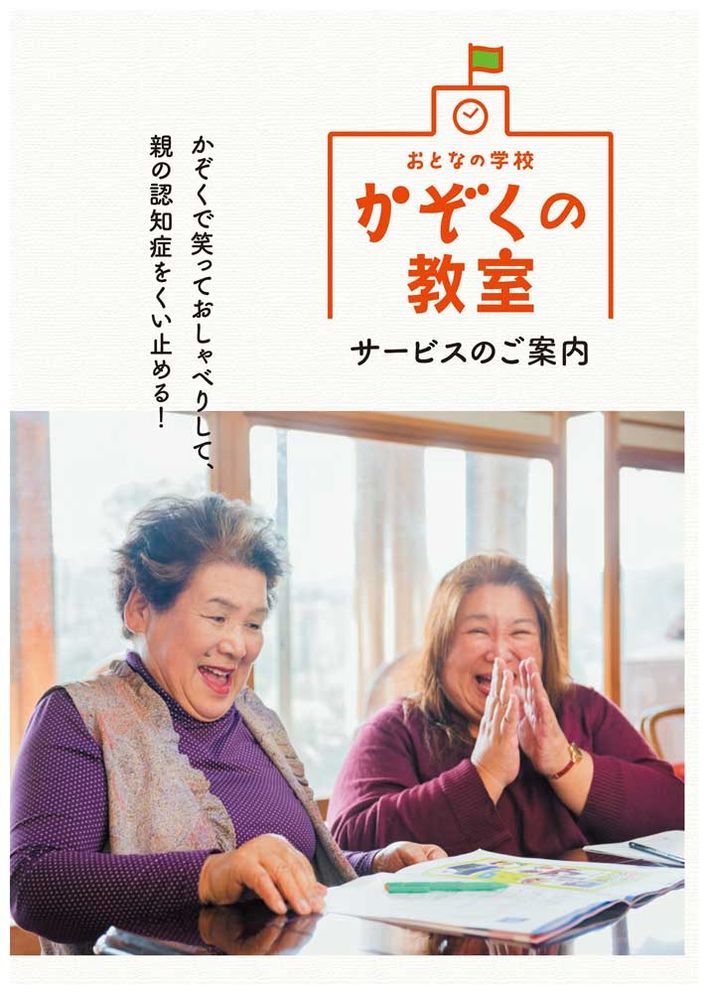
「在宅介護を行うご家族などからのリクエストで始めたサービスです。106歳で亡くなった祖母との対話がヒントになりました。私という孫と話すだけで祖母が元気になるのを見て、対話が大切だと再認識したのです。祖母とは決して仲がいいわけではなかったのですが、晩年はいい関係になれました」大浦代表はこう振り返る。
対話が脳を活性化することは科学的にも根拠があり、介護予防にも効果があるとされている。
「ご家族と家族の歴史をまとめてみることもいいですね。会話をしながらその内容を書き出してみることもおすすめです」
さまざまなアイデアを実現してきた大浦代表は、「私自身がおとなの学校に取り組む頃には、もっとよくなっていると思います。教科書のデジタル化など、今後もいろんな取り組みを続けます」と自信を見せた。
※2020年6月26日取材時点の情報です
撮影:丸山剛史



 この記事の
この記事の