筋ジストロフィーという障害を抱える鹿野さんと、それを支えるボランティアの方々を描いたノンフィクション『こんな夜更けにバナナかよ』の著者、渡辺一史さんをお迎えしてます。
早速ですが、本を書いたきっかけからお聞きしてよろしいですか?
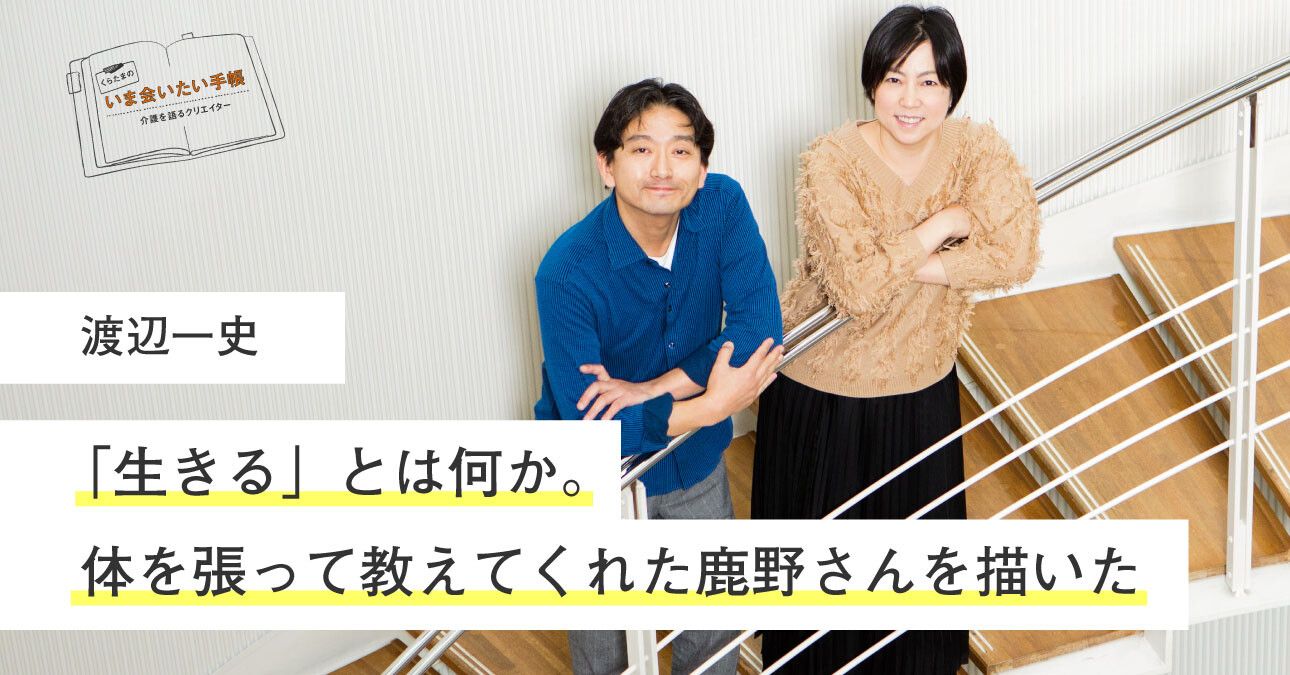
今回は渡辺一史さんをお招きし、筋ジストロフィーという障害を抱える鹿野靖明氏と、彼を支えるボランティアを描いたノンフィクション「こんな夜更けにバナナかよ」を取り上げます。家族介護の在り方や障がい者の方々が持つ役割、これからの福祉に求められることは何かを教えていただきました。
筋ジストロフィーの鹿野靖明氏と、彼を支える20代学生や主婦などを中心としたボランティアとの交流を描いたノンフィクション。日本の在宅福祉・医療の充実を目指して声を上げ、福祉制度が今よりずっと未整備だった時代に、ボランティアの力を借りて「自立生活」を行っていた鹿野氏。なぜボランティアは、彼の元に集まるのか?大宅壮一ノンフィクション賞と講談社ノンフィクション賞をダブル受賞した名著で、2018年12月に主演・大泉洋、高畑充希、三浦春馬など豪華キャストで映画化され大きな話題となった。
 くらたま
くらたま筋ジストロフィーという障害を抱える鹿野さんと、それを支えるボランティアの方々を描いたノンフィクション『こんな夜更けにバナナかよ』の著者、渡辺一史さんをお迎えしてます。
早速ですが、本を書いたきっかけからお聞きしてよろしいですか?
 渡辺
渡辺もともと僕は、大学時代にキャンパス雑誌の編集にのめり込むうちに、大学を中退して23歳のときフリーライターになったんですね。
それから10年くらいたった32歳のときに、たまたま北海道新聞という地方新聞社の出版センターの編集者からこのテーマで本を書かないかと声をかけられたんです。

 くらたま
くらたま新聞社からのご依頼だったんですね。障害者福祉は、もともと興味がある分野だったんですか?
 渡辺
渡辺正直に言うと、当初はあまり興味はなかったです。「そんな重くて深刻な世界に入っていけるんだろうか」と不安でしたし、愛と感動の美談みたいなものを想像して、ぜんぜん乗り気ではなかったですね。
私は尻込みした。あまりに重くて、深刻なテーマに思えたからだ。それに、福祉・医療はまるで未知の分野だった。
私の太刀打ちできそうな範囲を超えていると思えた。
「タイヘンそうな世界だねー」
新聞記事をあらためて斜め読みしながら、私はのんきな声でいっていた。
(『こんな夜更けにバナナかよ』P10より引用)
 くらたま
くらたまなるほど。障害者とボランティアの方の取材となると、つい“美談”というイメージを持ってしまうかもしれないです。
 渡辺
渡辺ただ、初めて鹿野さんに会ったときから、「困難に負けず、けなげに一生懸命に生きている人」とか「聖人君子」といった、障害者の方に対する一般的なイメージとは程遠い人でした(笑)。
欲望全開で「あれしろ、これしろ」と容赦なくボランティアに要求してくるような人でしたし、「どうして、この人のところに、若いボランティアが集まってくるんだろう?」と逆に興味が湧いてきました。
 くらたま
くらたまこれは、よくある愛と感動の美談では語ることができないぞと。
 渡辺
渡辺そうですね。一方で、ボランティアの人たちも、最初は“善良で献身的な若者たち”というイメージしかありませんでしたが、こちらも実際は全然違っていて。
たとえば、よく遅刻してくる人がいたり、鹿野さんが介助の仕方を何回教えても上手にならなくて、「もう来なくていい!」って鹿野さんに言われるような人もいたり。
そういう姿を見て、「この人たちは、なんでボランティアをやっているんだろう」という興味も持つようになりましたね。
 くらたま
くらたまボランティアと言えば、東日本大震災などの被災地に行かれる学生ボランティアのみなさんの存在は、よく知られていますよね。
被災地のように「大勢に働きかける」ボランティアと、鹿野さんのケースのように「一人をガッツリ支える」ボランティアでは、まったく違う意味合いがあるような気がします。
人が人を介助するって何なんだ。ワガママって、いったい何なんだ。ボランティアはボランティアであるという理由から、たえずそうした問いを自分自身に問いかけなければならない。「仕事だから仕方ない」という“言い訳”が成り立たないからだ。
(『こんな夜更けにバナナかよ』P40より引用)
 渡辺
渡辺基本的には、災害ボランティアも、NGOみたいに国際的な支援活動をする人も、動機自体はそんなに変わらないのではないかと思います。
一人ひとり、どうしてボランティアをはじめたのかを聞いてみると、「たまたま募集のチラシを見た」とか「友だちの紹介で」とか、直接的な理由はたわいもないことが多いです。
でも、「なぜそのチラシに目が行ったのか」とか、「なぜサークル活動とかアルバイトではなく、ボランティアをはじめようと思ったのか」とか、質問を掘り下げていくと、だんだんそれぞれの内的な理由が見えてきます。一つには、承認欲求というのがやはり大きな要因としてあるでしょうね。
 くらたま
くらたまう〜ん。確かにボランティアをする理由としては、わかりやすいですね。
 渡辺
渡辺それが見えやすい人もいれば、見えにくい人もいて、一概には言えませんが、たとえば、生い立ちを聞いていくと、けっこう問題を抱えた家庭で育ったりとか、「自分が生きる意味って何だろう」と深く思い悩んでいる人もいたり。
結局、ボランティアをすることで自分の不遇感を埋め合わせようという側面が、多かれ少なかれあるのではないかと。でも、そこで気付かされたのは、誰しも「人を支えている」という実感がないと生きていけないんだな、ということです。
これはボランティアに限らず、仕事一般にも言えることだと思いますが、人は「誰かの役に立っている」という実感があって、はじめて生きていけるところがあるでしょう。結局、人は「誰かを支えること」によって、逆に支えられている存在なのではないかと。

 くらたま
くらたま誰かを支えていなければ、生きていけない。本当にその通りですね。
多くのボランティアたちを取材するうちに見えてきたことがあった。それは、「ボランティアすることに依存する」「障害者を助けることに依存する」という健常者心理の裏側だった。おそらく誰の心のうちにもあり、正常と異常の境界線は紙一重だと思えるところがある。
(『こんな夜更けにバナナかよ』P450より引用)
 渡辺
渡辺それから、普段、私たちは「支える人」と「支えられる人」というふうに分けて、障害者や高齢者は、つねに「支えられる人」の側だと考えがちです。
でも、考えてみると、「支える人」ばっかりが世の中にいてもしょうがない。「支えられる人」がいてくれないと、「支える人」だって力を発揮できないし、その存在価値を失ってしまいます。
たとえば、本来、お医者さんは患者さんがいるからこそ成り立つ職業です。研修医や医者になって間もない頃には、緊張で注射を打つ手が震えたりして、「患者さんが自分を医者にしてくれているんだ」という謙虚な気持ちで患者と向き合っていたはずです。
それがいつのまにか、本来の関係性を忘れ、謙虚さも失って、「どうして、こんなにも次から次に患者が来るんだ」と(笑)。ボランティアというのは、そうした普段は忘れがちな人間関係の原理をとても見えやすくしてくれるところがあります。
 くらたま
くらたまなるほどなぁ。鹿野さんを支えていたボランティアの人たちもいつの間にか、支えられていたんですね。
 渡辺
渡辺「支える人」と「支えられる人」は、つねに逆転しうる関係にあるということですね。鹿野さんは1983年、23歳のときに、それまでいた障害者施設を飛び出して、ボランティアたちとの生活をはじめました。
当時は、いまの「在宅福祉」にあたる制度は皆無といっていい時代でしたが、「どんなに障害が重くても、地域で普通に生活できるような社会にしたい」という思いから、命がけで施設や親元を出る障害者が、全国に少なからずいたんです。
鹿野さんもその一人でした。とはいえ、筋ジストロフィーで手も足も動かないわけですから、たくさんのボランティアを自分で集め、自分で育て、彼らに介助をしてもらいながら生きていきます。こうした生活スタイルのことを「自立生活」といいます。
 くらたま
くらたま今でも、鹿野さんのように、ボランティアのみなさんと生活している方はいるんですか?
 渡辺
渡辺いえ、鹿野さんは2002年8月に42歳で亡くなりましたったが、くしくもその翌年の2003年から「支援費制度」という新しい仕組みができて、それまで「措置制度」と呼ばれていた障害福祉の制度が大きく前進しました。
その後、「障害者総合支援法」という現在の法律に引き継がれて、今では、介助をボランティアに頼らなくては生活できないという状況はほとんどなくなりました。ひとえに、地域に出た障害者たちが、長年、運動や交渉を積み重ねてきた成果です。
ただし、法制度が整っても、行政というのは財政難を理由に“制度の使い惜しみ”をしますから、1日24時間の介助が必要な障害者が地域で生活しようと思ったら、その都度、行政と交渉して「介護給付」を勝ち取るという涙ぐましい努力が必要なのは昔も今も変わりません。
だいたい単純計算すると、1人の重度障害者が地域で生活しようと思えば、介護報酬単価を1時間2,000円と見積もっても、1日24時間で計48,000円、1年365日で計1,750万円と、2,000万円くらいのお金がかかる計算になります。
 くらたま
くらたま2,000万円! 大きい額だなあ。
 渡辺
渡辺ただ、よく誤解されるのは、介護報酬というのは、障害者のフトコロに入るのではなく、居宅介護事業所がそのお金をもらい、介助者の人件費や運営費にあてているわけですからね。
構造的には、地域の雇用を生み、経済活動を支えているという意味で、公共事業と同じです。
1日24時間、1年365日をどう人で埋めるか。この問題は深刻だ。
鹿野の一日の介助には、「昼」(午前11時~午後6時)と「夜」(午後6時~9時)が1人ずつ、「泊まり」(午後9時~翌朝11時)が2人の、合計4人による3交代制で行われている。
単純計算しても、月のべ120人、年間のべ1460人もの介助者が必要だということになる。
(『こんな夜更けにバナナかよ』P28より引用)
 くらたま
くらたまそう考えると、あっという間になくなっちゃうお金ですね。
 渡辺
渡辺それはそうですけど、でも地域に障害者がいるからこそ、居宅介護事業所が運営できて、そこで働くヘルパーさんたちが収入を得て、そこから所得税や住民税、社会保険料などを支払います。そして、ヘルパーさんたちがその地域に住んで家庭をつくり、日々の消費を生み出すわけですから、地域経済にとっては非常に意味があるお金です。
障害者が施設に入所したとしても、同じくらいのお金がかかりますけど、地域ケアのシステムというのは、健常者が何かあったときにも助けてくれるシステムですし、一生健常者でいられる人などいませんよね。障害者を施設に閉じ込めておくよりも、ずっと意味のあるお金の使い方だと思います。
2016年7月に相模原市の障害者施設で、入所者19人が殺害され、26人が重軽傷を負うという事件が起こりました。元施設職員だった犯人の動機を簡単にいうと、“重度の障害者を生かしておくには莫大なお金がかかるから、日本のために彼らを安楽死させるべきだ”というものです。
でも、現実的に物事を見ていくと、24時間の介助が必要な重度障害者というのは、人口の0.1%にも満たない人数ですし、すべての障害福祉サービスにかかるお金を合わせても、国の一般会計の1%くらいの額です。
『なぜ人と人は支え合うのか』(ちくまプリマー新書)という本に、そういうことを丁寧に書きましたが、僕はその後、事件を起こした植松聖被告と横浜市の拘置所内で面会を重ねるようになりました。結局のところ、彼はそういう現実をまったく知らないままに、ただ漠然と「障害者にかかるお金はムダ」と思い込んでいるに過ぎないですね。
 くらたま
くらたま使われたお金は、泡のように消えるわけじゃない。ヘルパーさんを始めとする、たくさんの人たちの生活を支えているんですね。

 くらたま
くらたま障害者の方のお世話って、ご家族が行うケースも多いと思うのですが、渡辺さんはどのようにお考えですか?
 渡辺
渡辺たいてい日本では、障害児が生まれたら、家族で責任をもって介護しろよと。とくに母親が一生かけて面倒をみるのが当たり前だ、という考え方が根強いですよね。
つまり、「介護」というのは家族の責任であって、社会は責任を持たないぞと。
 くらたま
くらたま高齢者に関しても、長男の嫁が責任を持てよ、という風潮がありますよね。
 渡辺
渡辺そうですね。そういった考え方を「日本型福祉社会論」と呼んだりします。
ところが、1960〜70年代に、障害児を抱えた親が、我が子を殺してしまうという事件が多発しました。当時は今よりずっと世間の目が冷たかったし、障害者差別も露骨な時代でした。また、施設に預けようにも施設自体が少ない時代でしたから、障害児を育てているお母さんなんかは本当に大変だったんですね。
だから、障害のある我が子の将来を悲観し、「この子を楽に死なせてあげられるのは自分だけだ」という思いから、愛する我が子を殺害してしまうという事件が頻発したんです。それに対して、社会はどう反応したかというと、「そこまで追い詰められたお母さんはかわいそうだよね」と。
 くらたま
くらたまあぁ〜。社会は、加害者であるはずのお母さんに同情してしまうんですね。
確かに共感しやすいのは、同じ健常者として介護をしている母親かもしれません。もし我が子が障害者だったら、なんて想像したりして。
 渡辺
渡辺だから、お母さんの刑をどうにかして軽くしてあげられないか、という「減刑嘆願」の署名がたくさん集まったりしたんです。
ところが、それに異を唱えたのが、「青い芝の会」という重度の脳性まひの人たちの団体でした。
「青い芝の会」は、日本の障害者運動の出発点として有名な団体ですが、「お母さんが可哀想だというなら、殺された子はいったいどうなるのか」と。お母さんの刑を軽くすることは、障害者の生きる権利を否定することにつながってしまう。そう言って徹底した抗議行動を展開したんです。
 くらたま
くらたま確かに、障害者を殺しても罪が重くならない、なんてことになったら大変ですよね。それで、障害者の方々が立ち上がったんですね。
 渡辺
渡辺でも、それとそっくり同じことが最近も起こりましたよね。2019年6月に農林水産省の元事務次官だった父親が、長年ひきこもりだった息子を刺殺してしまった事件です。
そのときの社会の反応も、「お父さん大変だったね」というのが大半で、お父さんに同情的でしたよね。一方で、殺された息子に同情を寄せたり、彼のことを理解しようという雰囲気はほとんどなかった。むしろバッシングされるような状況でした。
 くらたま
くらたまそうですね。本来は加害者であるはずの親に、同情してしまう構図は今も変わっていませんね。
 渡辺
渡辺認知症ケアの世界も同様だと思います。実際に、認知症になった妻を夫が殺したり、認知症の親を子どもが殺したり、そういう事件が頻発しています。でも、「認知症だったら無理もないよなあ」と、ついそう思ってしまうところがある。
家族のことを愛していて、よくわかっていればこそ、「何度言ったらわかるんだ!」とか「こんなこともできないのか!」とか、つい感情的になりがちで、あげくの果てに、認知症になった家族から「どちらさまですか?」と真顔で聞かれたら、ショックを受けない人はいないでしょう。「こんなふうになった家族を殺してあげないとかわいそう」などと思い詰めてしまうかもしれない。
日本の殺人事件の55%は親族間で起こっていて(2016年警察庁発表)、国際比較しても突出して高い数字ですが、その要因のひとつとして、家族に介護を押し付けている日本社会特有の構造があると思います。
 くらたま
くらたま家族だからこそ、抱いてしまう感情なんでしょうね。
 渡辺
渡辺それともう一つ、障害者の場合、考えなくてはならないのが、「親の愛」からどう逃れるかという問題です。
障害児の親というのは、子どもを愛すればこそ、苦労させたくないという思いから、つい頑張りすぎてしまったり、その子の人生に何でも口を挟もうとする。鹿野さんの場合でも、ボランティアと生活している場に、お母さんがやって来てはボランティアの仕事を先回りして取ってしまったり。
でも、鹿野さんからしてみると、そんなことをされてはボランティアが育たない。だからこそ、いつもありがとうと感謝をしながら、手紙で「僕とボランティアの関係は失敗を繰り返しながら徐々に作っていくもので、その場でうまくやって終わりというものじゃないんです。お母さん、どうかこの点はわかって欲しいです」という気持ちを伝えていました。
これは障害のある人に共通する、親への気持ちだと思います。

 くらたま
くらたまなるほどねぇ。自分がやらないと、と思ってしまう親の気持ちもすごくわかるんですけどね。
 渡辺
渡辺子どもにしてみても、障害が重ければ重いほど、親なしには生きていけないという思いがありますから、なおさら強く言いづらい。だから、障害者の自立って、まずは自分を守ってくれる「親の愛」という壁の外側にどう出られるか。その後、はじめて社会とか他者と直接向き合うことができる。
 くらたま
くらたま家族介護になると危ないけど、外に出るために立ちはだかる壁もまた、家族なんですね。
 渡辺
渡辺ですから、そういう社会の構造的問題にいち早く気づいて、介護は障害者だけの問題ではない、介護は社会全体の問題じゃないかと、1970年代から問題提起をしてくれたのが、先ほど言った「青い芝の会」や、鹿野さんのように地域に出た障害者の人たちなんです。
彼らの試みというのは、家族でもなく、施設でもなくて、地域に自分たちの居場所をどう切り開いていけるか、そのための実践を命がけで行った人たちです。そうやって、地域で介助を受けながら「普通に」生活するという「第三の道」が切り開かれていきました。
2000年に高齢者の介護保険制度ができたときに、「介護の社会化」という言葉がキーワードとして使われるようになりましたが、それは地域に出た障害者が70年代から率先して訴え続けていたことなんです。
介護は家族だけの問題ではない、介護は社会全体の問題であり、家族介護のままだと全員が困る時代が来ると。
「親とは一緒に暮らさない」と鹿野が決意したのは、1983年(昭和58年)、23歳のときだった。(略)
しかし、当時の身体障害者の生きる道はほぼ2つしかなかった。一生親の世話を受けて暮らすか、あるいは、身体障害者施設で暮らすか、である。
鹿野は、そのどちらでもないイバラの道へと足を踏み出した。重度身体障害者が挑んだ「自立生活」への挑戦だった。
(『こんな夜更けにバナナかよ』P28より引用)
 くらたま
くらたまお話を聞いていると、家族の介護エピソードを美談的に語るのって、あんまり良くないんじゃないかなって思いました。あれを良い話として受け取るのは、どうなんだろう?
 渡辺
渡辺まあ、家族を介護することで、大きな発見や成長につながったなら、それはそれで良いことだとは思います。ただ、その裏側に介護殺人という現実もある。その両面があることを忘れてはいけないですよね。
 くらたま
くらたまそうですよね。うまくいっている人たちが称賛されちゃうと、大変な思いをして介護を行っている家族が追い詰められちゃうかもしれない。
 渡辺
渡辺それに、日本特有の「家族介護」への信仰がいつまでたってもなくならないですよね。
 くらたま
くらたまこのコンテンツでも、ただ素敵な本ですねって取り上げるだけじゃなくて、他人を入れた方が良い場合もありますよってことも、どんどん発信していかないと。
 渡辺
渡辺鹿野さんだって、ずっと親元にいて、両親だけに介助されていれば、単に「手のかかる息子」で終わったでしょう。だけど、他人が介助に入っていくことで、状況がまったく変わってくる。
地域に出た鹿野さんは、自分の体を教材にしながら、ボランティアを集め、集まった学生や主婦、社会人などいろんな人たちに、「生きるとはどういうことなのか」を身をもって教えてくれた。
単に「手のかかる息子」ではなく、他者との関係性をもつことで、はじめて障害というものに役割が生まれ、多義的な意味が生まれ、そして、人と人とを結びつける結節点にもなりうる。

 くらたま
くらたまそういう「他人が入る」ことや、「役割を担う」という考え方が、当たり前になってくれば良いですね。
渡辺さんの本の中でも、鹿野さんのことを最初は、「こんな夜更けにバナナが食べたいって、家族にも言わないようなことを他人に求めるなんて、図々しいなあ」って思ってしまいました。
でも、そうじゃない。他人に「助けてよ」って言うことは恥ずかしいことじゃない、言って良いんだっていうことが描かれていましたね。
他人による24時間介助を必要とし、ベッドからほとんど動くことのできない鹿野にとって、自分の欲求を口に出し、介助者にものを頼むことが「生きること」であり、自己の存在を他に示す、ほとんど唯一の手段であるということだ。
(『こんな夜更けにバナナかよ』P361より引用)
 渡辺
渡辺自分でできるなら、そもそも他人に頼まないですよね。自分でできないから頼んでいるんです。でも、そんな単純なことにも気づけないで、「なんだ、このわがままな障害者は!」と思って、すぐ辞めていくようなボランティアもたくさんいました。
そんななか、鹿野さんは本当にわがままんだろうか、そうじゃないんじゃないか、わがままだと思ってる自分のほうが間違っているのかもしれない…そうやって自分自身に“問い”を向けられる人は、ボランティアが長続きしますし、人間的にも驚くほど成長していきます。
そして、他者との接し方も変わるだろうし、人生そのものが大きく変わっていく。僕は2000年4月に鹿野さんの取材をはじめたのですが、2002年8月に亡くなったので、生身の鹿野さんとのお付き合いは、たかだか2年4ヵ月に過ぎません。
でも、その2年4ヵ月がなければ、本も書けなかったし、賞ももらえなかっただろうし、自分の書いた本が映画化されて、こんなふうに倉田さんとの対談が舞い込むなんてこともなかった(笑)。
大学院とかカルチャーセンターに何年か通うより、よほど大きなことを学んだと思いますね。自分の人生がこれほど激しく変わったことはありませんから。そして、そういう体験をした人は、僕だけじゃなく、たくさんいるということです。
このことは障害者に限らず、要介護のお年寄りだって同じではないかと思います。家族だけで死にもの狂いで介護して、家の中に閉じ込めておくのではなく、いろんな他者とかかわることで、はじめて“奇跡”というのは起きるんだということですね。
 くらたま
くらたまいろんな人に取り囲まれるって良いな。これから時間がかかっても、そんな制度ができれば良いなって思います。

渡辺一史(わたなべ・かずふみ) 1968年名古屋市生まれ。札幌市在住のノンフィクションライター。2003年刊『こんな夜更けにバナナかよ』で大宅壮一ノンフィクション賞と講談社ノンフィクション賞、2011年刊『北の無人駅から』でサントリー学芸賞、地方出版文化功労賞などを受賞。当記事でも取り上げた相模原市の障害者施設における殺傷事件などをテーマにした『なぜ人と人は支え合うのか』を2018年に刊行。