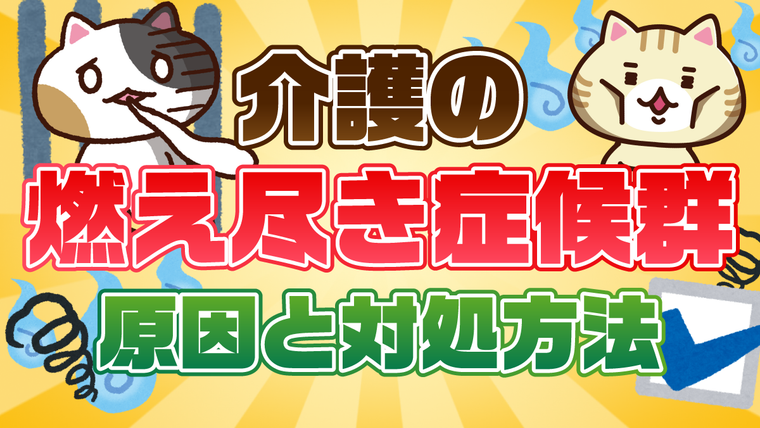みんなの介護アンケート
| ある(1078件) | |
| ない(588件) | |
| わからない(210件) |
燃え尽き症候群(バーンアウト)とは?

別名「バーンアウト」と呼ばれることもある燃え尽き症候群は、仕事に真面目かつ精力的に取り組んできた人が、突然仕事への意欲や情熱をなくし、燃え尽きたような状態になってしまう症状です。
さまざまな職業で見られる症状ですが、特に医療や介護の現場で働く人に多く見られることがあります。
その原因のひとつが、「人」を相手にする職業ということです。
物を相手にする、または物を取り扱う仕事とは異なり、人を相手にする職業では成果が目に見えず、結果を得ても実感しづらいことがあります。
そのため、真面目に仕事に取り組む人はつい努力をしすぎてしまい、自分自身に大きな精神的・肉体的負担を与えてやすくなり、その結果燃え尽き症候群になりやすいのです。
燃え尽き症候群の症状が出たことにより、仕事を退職するケースも考えられます。人材不足をより深刻にさせてしまうこともあるため、医療や介護の現場における燃え尽き症候群対策は必要不可欠といえるでしょう。
燃え尽き症候群の症状
燃え尽き症候群の症状は、身体的なものと精神的なものの2種類があります。
身体的な症状には、不眠やイライラのほか、食欲不振や吐き気、頭痛などの他の病気の症状としても出やすい症状が出ます。
また、場合によってはアルコール摂取量が増えたり、胃腸障害や高血圧などが起こったりすることもあります。
精神的な症状としては、それまで熱心に仕事に取り組んでいた人が、突然仕事に対する意欲をなくすのが特徴的です。
そこに至るまでには、仕事相手との関係構築へ費やす意欲がなくなり、かかわりを持たなくなることがあります。
中には、人間関係が薄くなり、人との関係そのものが苦痛に感じることや相手の気持ちを無視するような行動を起こすケースもあります。
その結果、職場でのサービスの質が低下し、望むような結果や成果が得られない環境で自信を喪失し、離職につながるというのが、燃え尽き症候群の主な症状です。
うつ病との違い
燃え尽き症候群と似た症状を持つ病気に、「うつ病」があります。
どちらも、無気力で落ち込んだ気分になるという点が似通っています。しかし、燃え尽き症候群とうつ病は異なるものです。
うつ病は落ち込んだ気分が一貫し、怒りや責め、罪悪感を自分自身に持つものです。それに対し、燃え尽き症候群は怒りや責めを自分自身のほか、ほかの人も対象にする点に大きな違いがあります。
また、燃え尽き症候群の人は罪悪感よりも喪失感、絶望感などの方をより大きく感じるのも特徴です。さらに、他分野での活動に対する不安感や自分への評価をしてくれる人へのあこがれなどの感情を持つことも、うつ病にはない違いです。
なりやすい人の特徴は「真面目な頑張り屋」

前述の通り、燃え尽き症候群の原因は、個人要因と環境要因の2種類に分けられます。
個人要因は、その人の性格や経験に関係してきます。何事にも真面目に取り組む熱心さを持つ人は、特に燃え尽き症候群になりやすいといわれます。
まだ仕事経験が浅く、かつ仕事に対する理想が高い人も、実際の仕事とのギャップを感じやすいため、燃え尽き症候群になりやすいと考えられます。
環境要因は、仕事環境が大きく影響します。長時間労働や残業、キツいノルマなどを課される職場のほか、介護の現場で多い介助などの肉体的な負担の大きさも、原因とされています。
これだけの環境で働いているにもかかわらず、見合った評価を得られないことも、燃え尽き症候群になる大きな原因の一つです。
医療や介護の現場で働く人に限らず、在宅介護をしている介護者も燃え尽き症候群になりやすいことがあります。
介護者が、この介護に人生を捧げる、一人で介護をやりきるなど発言しているときは、燃え尽き症候群の危険がある状態といっていいでしょう。
このような発言をしている介護者がすべて燃え尽き症候群予備軍とまでは言えませんが、その発言がどのような場面で出たものなのかを、本人の体調の変化などとともに注意して見守る必要があるでしょう。
チェックリスト
燃え尽き症候群は、症状が悪化するとあらゆることに対するやる気や意欲がなくなり体調不良などにより、離職する事態になりかねません。
しかし、自分自身では燃え尽き症候群になっていることに気づきにくいことにより、症状悪化を深刻化させてしまいます。
以下に挙げるチェックリストを参考に、自分がこの中に当てはまっていないか、周囲の人に客観的に見てもらいましょう。
- 一人でいたい、人に会いたくない
- 食欲不振や不眠などで、健康へ悪影響が出ている
- 集中力が落ちている
- 気が短くなりやすい
- 日常生活、または仕事でやるべきことに対して関心がない
- 何事に関しても飽きっぽい
- 気分が晴れない
- ネガティブな気分が続き、打開策が何もない気分が続く
- いつも疲労感を感じている
- 他人や物への関心が薄れる
- やっていることがすべて不十分な気がする
- 自分自身を人として欠陥があると感じる
- 頭痛や風邪のような症状が長く続く
- これらの症状が起こっていることを信じたくない
これは自覚症状を比較的多く挙げているチェックリストですが、実際に燃え尽き症候群になっている当人は、気づかないものです。
普段付き合いがある周囲の人にチェックリストを確認してもらい、自分に対する客観的な評価を知ることが、燃え尽き症候群の症状緩和につながります。
立ち直るための3つの改善方法
自分の状態を受け入れる
燃え尽き症候群から立ち直るためには、まず、自分の状態を受け入れることが重要になってきます。
自分自身が燃え尽きるまで努力した、やりきったという事実を認め、その感情を自分で感じて受け入れます。
燃え尽きるまでひとつのことに対して打ち込めることができる人というのは、とても真面目で几帳面な部分を持ち合わせています。
燃え尽きた後、すぐに何かを別のことを始められない状態が続き、できない自分を責めて、追い詰めてしまいがちです。
しかし、心身ともに疲れている状態では、頑張ることはできません。
ときには、頑張っている自分を褒めてあげてはいかがでしょうか。
いつもと違う新しいことをする
燃え尽き症候群から抜けだけない原因は、毎日同じ変化のない生活を繰り返し送っているからかもしれません。
なぜなら、燃え尽きた後は、決まったこと以外をする気力がないからです。
そこで、いつもと同じこと以外に何か新しいことをしてみましょう。
例えば、毎日同じ駅を使って電車通勤しているのならば、エスカレーターをやめて歩いてみたり、違う車両に乗ってみるのもいいかもしれません。
いつもと違うことをしてみれば、視界が開け、変化が期待できます。
気長に変化を待つ
燃え尽き症候群を改善するための一番の方法は、自分のやる気が出るまで焦らずに待つことです。
激務が終わった瞬間に燃え尽き症候群になった人は、その後休暇で旅行にでかけて心をリセット。
例として、「会社でもしばらくぼーっとする期間がありましたが、しばらくすると、だんだんとやる気が取り戻した」という報告もあります。
思い切って環境を変えて、緊張が続いていた体を休ませ、心もリフレッシュすると、自然と燃え尽き症候群は落ち着いてくるでしょう。
何もしない時間は決して無駄ではないのです。
ワーク・エンゲージメントによる回復

ワーク・エンゲージメントとは、燃え尽きている(バーンアウト)とは反対の状態で、社員が仕事に対して誇りややりがいを感じ、仕事から活力を得ている心理状態のことです。
燃え尽き症候群の主な要素は疲弊です。
上記3つの、立ち直るための改善方法を参考に、疲労回復する機会を十分設けて回復した状態になれば、ワーク・エンゲージメントを活用していきましょう。
ワーク・エンゲージメントを高めると、燃え尽き症候群の予防にもつながります。
また、介護職員が心理的ストレスを受けることが減るので、人間関係も良好になり、離職する方が減るといった効果もあります。
2015年12月の「労働安全衛生法」改正により義務化されたストレスチェックが、ワーク・エンゲージメントに活用可能です。
ただ、現在のストレスチェックは社員50人以上の事業所が対象なっているので、介護施設で働く職員全員がストレスチェックを受けられるようにする体制の準備も必要です。
燃え尽き症候群にならないために・予防方法は?

燃え尽き症候群は、症状を完治させる薬が存在しません。ですが、普段の生活や仕事の取り組み方を改善すれば、予防ができます。
運動や睡眠など生活習慣を整える
まず、生活習慣を正しくしましょう。
朝きちんと起きて、適度な運動を行いましょう。運動による疲れで夜ぐっすり眠ることができ、気持ちよく朝目覚められるようになるので、生活リズムが正せます。
夜勤がある人は、夜に眠れないこともあるでしょう。そんなときは、休日に運動をして身体を動かすと、夜に眠りやすくなります。
規則正しい生活を心がける
規則正しい生活を送るためにも、食事をしっかり食べることも大事です。
燃え尽き症候群になる人は、あらゆることに無気力になってしまいます。食事にすら関心が薄くなってしまい、偏った食事が続くと体調も悪化します。
食事は生活をするうえでの基本なので、食事内容が偏ってきたな、と感じた時は、バランスの取れた食事内容に修正するようにしましょう。
自分を客観視する
そして仕事においては、取り組んでいる仕事を客観的に見ること、職場での役割と自分の役割と区別して考えること、職場内だけではなく職場以外の場で相談できる人を見つけておくことも必要です。
正しい生活を送りながら、ほかの人に頼りつつ仕事を進めていくことが、燃え尽き症候群予防の基本となるでしょう。