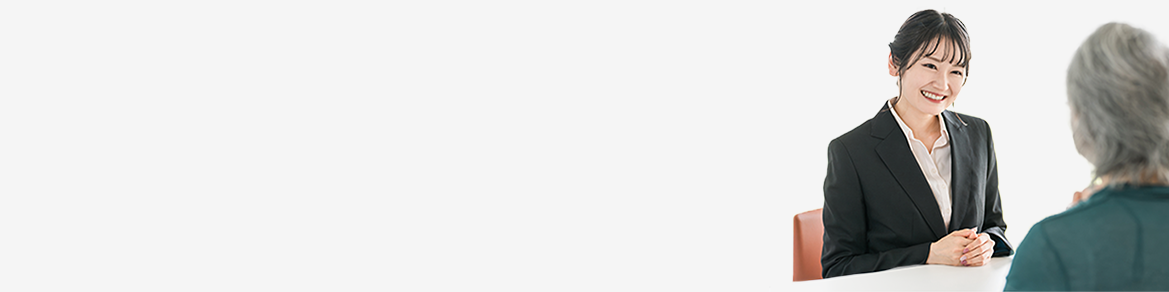関節症・リウマチでも対応が可能な施設特集
関節症・リウマチ患者は適切な運動ができる生活を

老化により、軟骨がすり減ることで関節が変形することによって起こるのが変形性関節症。また、免疫の仕組みに異常が生じることで起こる、慢性的な間接の炎症による痛みのある関節リウマチも併せて、痛みを悪化させないようにしながら適度に運動をすることで筋力が衰えないようにすることも大切です。だからこそ関節症・リウマチ患者の方は、体の症状に合わせた適切な運動プログラムに取り組める体制を整えた介護施設を選ぶことがおすすめです。
リウマチ・関節症の高齢者の老人ホーム選びについて
リウマチ・関節症は高齢者に多い病気のイメージがありますが、40~60代に発症のピークがみられます。男性よりも女性の方が約3倍も発症率が高いといれています。40~60代の女性はとくに注意してください。「若いから大丈夫」とは必ずしも言えません。
リウマチ・関節症は関節の内部にある滑膜(かつまく)で炎症がおこることで発症すると考えられています。自己免疫疾患の一種で、本来自分の体を守るべき免疫が、なんらかの理由で自分自身の正常な細胞まで攻撃、破壊することで起こります。病気の正確な原因はわかっていないため、残念ながら完全な予防法はありません。
病気の症状としては、初期のうちに食欲不振、熱っぽさ、体のだるさなどを感じ、さらに体がこわばって、動かしづらさを覚えるようになります。体に力が入りにくいことも。ただ体を動かしているうちに、動かしづらさが消えるなどの症状がでると、リウマチ・関節症の初期症状である可能性が高くなります。その後、関節リウマチ独自の症状が出始めます。指や手首などの関節に腫れ(炎症)やこわばり、痛みが。最初は小さな関節の痛みから始まり、だんだん全身へと炎症や痛みがひろがっていきます。
リウマチ・関節症の高齢者が老人ホームに入所する際には、老人ホーム側が病気に対してしっかり対応できるかどうかのチェックが重要です。みんなの介護に掲載されている老人ホームは約9,000施設ですが、そのうち5,822の施設でリウマチ・関節症高齢者の受け入れが可能となっています。施設の特徴をよくみると、日中看護師常駐・理学療法士勤務・24時間介護士常駐・作業療法士勤務など医療面のケア、リハビリケアの行き届いた老人ホームも少なくありません。老人ホームの種類としては住宅型有料老人ホーム、介護付有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、高齢者住宅など。なぜ医療面やリハビリの充実した老人ホームが多いのでしょうか?
リウマチ・関節症の患者は、無理のない範囲で体を動かし、固まった関節や筋肉をほぐす運動をおこなう必要があります。関節が固くなったからそのままで良い、というわけではないのです。理学療法士が勤務する老人ホームなら、定期的に関節をやわらかくする運動指導や補助、ストレッチなどの指導をうけることができます。
リウマチ・関節症の患者は体が冷えると痛みが増すため、温熱療法でしっかり対応してくれると体も楽になります。リウマチ・関節症は介護保険制度を利用できるので、積極的に利用しましょう。リハビリが強化された老人ホームはリウマチ・関節症の高齢者受け入れが可能ですし、実際に入所しても満足感が高いもの。老人ホームへ入所を希望するときは、リハビリがどれくらい充実しているのかをチェックしましょう。
リウマチ・関節症とは?原因・症状・治療法・後遺症について
前項でも少しふれましたが、リウマチ・関節症の原因ははっきりとわかっていません。この病気の原因としては免疫異常が考えられていますが、どのような原因で自己免疫系に異常がおこるのかはわかっていないのです。原因が特定できないため、効果的な予防法や根本的な治療法がないのが現状です。これは認知症などでも同じことです。
リウマチ・関節症の症状は手足の指の関節、手首の関節など小さな関節が腫れる、こわばる、痛いなどの症状からはじまり、膝関節や頸椎、肘関節、股関節、顎関節など全身に炎症や痛みがひろがっていきます。なかには突然、膝関節の痛みや炎症から病気がはじまる事例も。初期には熱っぽさや体のだるさ、食欲不振などの症状がでます。「いつもと体調が違う」と思ったら、無理をせずにしばらく様子をみましょう。
病気を発症しても放置してしまうと、炎症やこわばりが全身の関節にひろがるだけに留まりません。関節炎の痛みだけではなく関節が破壊されるため、血流が悪くなることによる痛みや筋肉痛も加わることに。関節炎や筋肉の痛みで体を動かさないようになると、次第に筋力が衰え、日常生活に支障がでます。関節の痛みだけではなく、全身のだるさや疲労感、微熱などの症状がつづき、体調不良に。食欲不振になると脱水症状や低栄養の状態に注意しなければなりません。
関節の炎症だけではなく、目や肺、血管、などに炎症が起こることも。目の炎症は痛みや視力低下などの症状があらわれ、同じく自己免疫疾患のシェーグレン症候群を併発すると、目が乾いてかゆみを感じます。肺の血管に炎症が起こると胸膜炎や間質性肺炎を引きおこすことも。血管が炎症を起こすと、体全体に酸素や栄養素を補給することがむずかしくなり、臓器が全体的にダメージを負います。自己免疫疾患のためなかなか完治させることができず、悪性関節リウマチとなり難病指定されています。
リウマチ・関節症の治療法としては薬物療法が中心となります。さらにリハビリテーションや症状の重い方は手術による治療も。薬物療法では関節の炎症をおさえる「抗炎症剤」を服用することで痛みを軽減させます。ただし副作用として胃腸障害や不眠、血圧上昇、食欲不振、だるさなどの症状がみられることも。異常を感じた場合はすぐに医師に相談しましょう。薬物治療にはほかにも「抗リウマチ剤」や「生物学的製剤」などがあります。
病気の治療には薬物療法だけではなく、リハビリテーションも併用されます。関節の痛みやこわばりにより体を動かさなくなると、筋力の衰えや委縮により機能低下を起こし、体が動かなくなってしまいます。機能低下を防ぐためにも、リハビリで無理なく体を動かし、関節の可動域をひろげ筋力の維持をはかります。このリハビリテーションには運動療法はもちろん、物理療法や作業療法、装具療法などがあり、患者の痛みをとり、スムーズな日常生活を支援するためのものとなっています。
リウマチ・関節症は一度発症し、関節や骨、靭帯にダメージを負うと、その状態が元にもどらない不可逆性の病気です。そのため素早い診断・治療が必要となります。病気の後遺症としては、関節の痛み、関節の可動域の制限、変形などがあげられます。リハビリ(運老療法や物理療法・作業療法)で関節の可動域をひろげ、筋力の低下をふせぐことでできるだけスムーズな日常生活、自立した生活をめざします。
リウマチ・関節症の方の施設選びのポイント
リウマチ・関節症は若い方でも発症する可能性が高く「高齢者特有の病気」ではありません。リウマチ・関節症は症状がすすまないうちに診断を受け、早いうちから治療を開始することで進行を最小限に防ぐ。これが最良の対策となります。
リウマチ・関節症の高齢者が老人ホームを選ぶときのポイントは、やはりリハビリが充実しているかどうか。理学療法士など専門の指導員が常駐し、適切な運動リハビリや物理療法が受けられる施設を選ぶことです。リウマチ・関節症の患者は起き上がれないほどの痛みを感じることもあり、痛みの緩和として温熱療法やマッサージを施してくれる老人ホームを選ぶと体がかなり楽になります。温熱療法だけではなく、炎症が激しいときは冷却療法が効果的であると言われています。患者の体の状況にあわせて、さまざまな療法をつかいわけてくれる老人ホームを選びましょう。
老人ホームでは運動療法や物理療法だけではなく、作業療法を提供している施設も。リウマチ・関節症の患者は手指の関節にも炎症が起き、上手く動かせなくなることも少なくありません。そこで作業療法士の指導をうけながら、絵手紙や絵画、書道、編み物、手芸、木工、竹細工など指先をつかうリハビリをおこないます。一人で作業をするのではなく、ほかの入所者と一緒に作業をするので孤独感を覚えにくく、楽しく作業ができるのがメリット。リウマチ・関節症の高齢者が老人ホームを選ぶときには、リハビリの充実度、そして医療体制がどこまでしっかりしているのかも確認しましょう。
みんなの介護では約9、000もの介護施設が紹介されていますが、そのうち体験入居が可能な物件は5,822か所となっています。全体の約8割以上の老人ホームで体験入居に応じてもらえます。気になる施設が見つかったときは、遠慮なく体験入居を申しこんでみましょう。
身元保証人なしでも入れる施設特集

核家族化が進む現代では、「一人暮らしで身寄りがいない」「家族はいるが頼むことができない」といった問題を抱えている高齢者の方も多数。一方で老人ホームでは、ほとんどの施設で身元保証人や身元引受人を必要とする場合が多く「身元保証人がいないと老人ホームへの入居はできない」と考えている方も少なくないのではないでしょうか?
確かに、基本的に老人ホームへの入居には身元保証人が必要ですが、ここでご紹介するのは、それが必要ない施設ばかり。入居後のサポートや身柄の引き受けなどさまざまなサービスがあるのでご安心くださいね。
身元保証に関してのサービスも充実!

「介護施設に入りたいけれど、身元保証人がいないから…」と悩んでいる人もいるでしょう。しかし、今は身元保証人の代わりとなるシステムが確立されていますので、地域包括支援センターや社会福祉協議会で相談してみると良いでしょう。
老人ホームによっては成年後見制度などに基づき、法定代理人を定めることを入居条件にしています。法定代理人とは、認知症などで判断能力が低下した人の代わりに、代理人が月額利用料の支払いや、通帳などの財産管理を行うシステムです。
判断能力がある人も「月額利用料の支払いなどが理解しづらくて辛い」といった場合、任意後見人を定められます。このような後見人は、身上監護(依頼人が幸せに暮らせているかどうか状況を把握する業務)や、福祉サービスの手続きサポートなども行うため、入居後も依頼人は安心して暮らせます。
依頼人の連絡窓口にもなるので、施設で何かあったときも後見人に連絡が行くシステムです。老人ホームが、「身元保証人がいない場合は後見人を付けること」を条件としているのはこのようなサポートがあるからです。
後見人に必要な報酬はどのくらい?
成年後見制度を利用する方法
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申し立てることになります。地域包括支援センターや社会福祉協議会などが相談窓口となっており、申し立てのサポートをしてくれますので、まずはこれらの機関に相談をしてみると良いでしょう。
ちなみに身元保証人は一般市民や一般社団法人、NPO法人などさまざまですが、自分で選ぶのではなく、社会福祉協議会などが選定するので安心です。最近は身元保証会社も出てきており、身元保証人がいない人のために、保証代行を行っています。しかも身元保証にオプションとして、生活支援サービスや死後の事務支援サービスが付けられるので便利です。
後見人に必要な報酬はどのくらい?
後見人を頼む際に老人ホームに入居後のことや、亡くなった後のことなども取り決めますので、危篤状態などの緊急時にも本人の意向が尊重されます。認知症などで判断能力が低下した際も安心です。
しかし、「後見人って高いんじゃないの?」と心配する人もいるでしょう。確かに、後見人に金銭管理などの代行サービスを頼むと料金が発生します。サービスにもよりますが毎月数千円といった程度で、そこまで高額ではありません。
後見人は身元の保証はできませんが、老人ホームの月額利用料の支払い代行などをしてもらえるので、老人ホーム側としても安心。金銭のことでトラブルを起こさずにすむため、老人ホームと信頼関係もしっかりと築けるでしょう。
後見人に必要な報酬はどのくらい?
身元保証会社にかかる費用
身元保証会社を利用する場合は、申し込むサービスの量によって金額が違います。生活支援や死後の手続きなど、代行サービスを沢山申し込んだ場合、生涯で支払う金額が数百万円になる場合も。
しかし、身元保証会社は少々費用がかかる場合もありますが、身元保証をしてもらえるので頼もしい存在です。「30年間生きた場合で、どれくらい支払うのか?」といった長期利用の計算をしておきましょう。
身元保証会社の選び方
身元保証会社に身元保証を頼んでおけば安心ですが、「どの会社が良いのかわからない」という人も多いと思います。こういった契約は内容が難しく、支払う料金も預託金や月額利用料などさまざまです。
一人での契約は少々厳しいかもしれませんので、家族などに同行を頼み、一緒に契約内容を理解してもらいましょう。こういったサービスの申し込みに関しても、地域包括支援センターや社会福祉協議会に相談可能です。
ちなみに預託金は一般的に依頼した本人の葬儀代などに使いますが、予め「預託金などは何に使うのか?」といった詳細をしっかりと聞いておくと良いでしょう。
後見人と身元保証会社の違いは?
成年後見人と身元保証会社の違いは、成年後見人は依頼主の身元保証人にはなれませんが、身元保証会社は身元保証が行えることです。成年後見人は公的な立場なので、料金も法外になることはありません。一方、身元保証会社は一般会社なので、料金は会社によって違いますし、サービスによっては少々料金が高くなるでしょう。
しかし、こういった制度を利用すれば、身元保証人がいなくても老人ホームに入居できます。ちなみに老人ホームによって身元保証に関するルールが違います。見学時などに確認しておくと安心です。