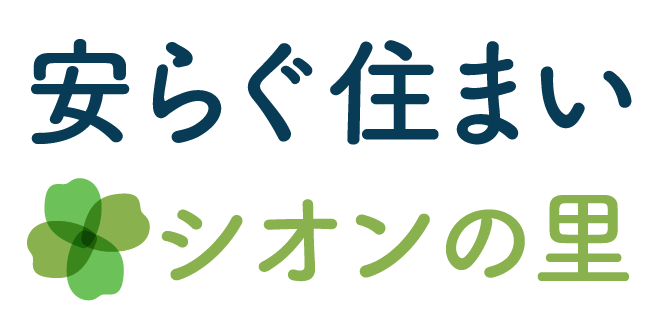結核患者でも入居可能な施設特集
今の高齢者は結核菌を知らぬ間に保有している可能性がある!?

結核とは、結核菌を吸い込むことによって起こる感染症のこと。感染すると咳やたん、発熱を起こすなど肺を中心とした症状が起こりやすくなりますが、実は全身に炎症を起こすこともある病気です。特に現在の高齢者は、結核菌が蔓延した時代を生きており、その結核菌を体内に保有していることも。そのうち、免疫力や抵抗力が抵抗した頃合いに症状が出始めることもあり、今が健康だからといって、決して安心できません。きちんと検査を受けると同時に、介護施設でも感染・被感染しないように注意したいものですね。
結核菌を保有した入居者から、老人ホームでも感染する可能性が!?
結核は過去の病気というイメージがありますが、決してそのようなことはありません。2015年に日本全国で新たに結核患者として登録された患者は約18,300名となっており、予想以上に患者がいることがおわかり頂けると思います。また2015年に結核で亡くなった患者は約2,000名。結核による死亡者数は減少傾向となっていますが、注意するべき感染症であることは変わりありません。
今も注意すべき感染症、結核ですが、とくに免疫力の落ちた高齢者は注意が必要です。結核は患者の咳やたんのなかに混ざった結核菌が空気中に飛びちり、その結核菌を同じ空間にいる人が吸いこむことで感染します。空気感染するため、結核を発症した患者が排菌(菌を排出すること)している場合、ほかの方に感染させないために隔離する必要があるのです。
体内に入りこんだ結核菌ですが、まず鼻やのど、気管支の繊毛によって外に排出されれば感染することはありません。体内に入った場合、結核菌と免疫との戦いになります。結核菌が勝利すると体内で増殖し半年から2年程度の潜伏期間を経て発症します。結核を発症すると咳や痰、発熱など風邪に似た症状がでます。ただ結核と風邪の症状に大きな違いがないため、結核を発症していることに長期間気がつかないケースも。
もし結核菌が体内に入っても、免疫によって結核菌の増殖がおさえられた場合、病気を発症することはありません。8~9割の感染者が一生結核を発症しないと言われています。このケースでは結核菌は体内で死滅、または長い冬眠状態に入ります。
問題は残り1~2割の感染者。結核菌の感染から数年~数十年という長い時間が経過してから発症します。つまり結核という感染症は「病気を発症していなくても体内に結核菌を保有し、長い年月をかけて発症する(既感染)ケースがある」ことを理解しておかなければなりません。数十年という長い眠りから覚めた結核菌が一度発症すると体内で菌が増殖、咳や痰から結核菌が排出される(排菌)ようになります。このような状態にならないよう、早めの治療が必要なのです。
老人ホームの場合、集団生活をしていることや高齢者自身がすでに結核に感染している可能性が高いこと、免疫力が低下しており結核に感染しやすくなっていることなどいくつかのリスクが重なっています。集団生活ではリビングやダイニング、トイレ、浴室など共有するスペースが多く、結核の発症者と日常的に接触するため感染リスクがかなり高いと認識したほうが良いでしょう。そのため排菌している結核患者が一人いるだけで集団感染をおこしやすく、看護・介護職員による注意が必要になります。
結核の症状や感染について
結核菌が体内にはいり、さらに免疫によってその力を封じることができない場合は結核を発症することになります。結核を発症すると、以下のような症状がでます。
- 咳やたん、微熱がつづく
- 食欲が落ちる、体重が減る
- 体がだるい
- 胸に痛みがある
このような症状がでたとき、また周囲に結核患者がいる場合などは早めに医療機関を受診し、診察をうけましょう。結核は過去に「不治の病」と呼ばれていましたが、今は適切な服薬治療で治る病気となっています。むやみに怖がることはありません。ただ結核菌が咳やたんのなかに排出されているケースでは、周囲の方々への感染を防ぐために入院治療をおこないます。排菌が確認されていない場合は隔離などの必要はなく、通院によって治療をおこないます。
結核の治療には3~4種類の薬を使います。最低でも半年の服用が必要ですが、その間に自己判断で薬の服用を中断したり、量を減らすなどすると結核菌に耐性ができる、症状が悪化するなど悪い影響が及びます。医師から指示されたとおりに薬を服用することが完治の基本です。
体内に結核菌がはいりこんでいても、具体的な症状がない場合は「潜在性結核感染症」と呼ばれ、周囲の方々に病気をうつすことはありません。「潜在性結核感染症」の患者は服薬することで発症リスクをおさえることができるため、イソニアジドとよばれる薬を最低半年服用します。薬を服用することで発症リスクを大幅に下げることができるのです。
老人ホームで結核が出た場合の対処法は?
老人ホームには基礎疾患により免疫力の低下した入所者がいるため、とくに感染症への対策は十分におこなう必要があります。平常時から感染症の予防が重要です。そのためには、入所時の健康診断や定期健康診断、日頃のバイタルチェックで利用者の健康状態を把握します。
入所時は胸部X線検査を実施して、異常があるかないかをしっかり記録することが重要です。検査の結果「潜在性結核感染症」であったとしても、発症していなければ周囲の方々に感染させることはないため、入所を拒否することはできません。また結核の治療中であっても結核菌を排出していなければ集団生活にも問題ありません。老人ホームへの入所後には、定期健康診断をおこないます。胸部X線検査の結果、結核感染のおそれがある入所者に対しては精密検査を受けてもらうなどの措置が必要です。
結核に感染した高齢者の場合、結核症状でみられるせきや痰、微熱、体のだるさなどをあまり訴えないこともあります。日頃のバイタルチェック(体温、体重、食欲などの観察)から異常の有無を見落とさないようにします。結核はほかの病気とおなじく、早期発見・早期治療が基本です。せきや痰などの呼吸器障害がなくても、微熱がつづく、体重が落ちる、食欲がないなどの症状がみられた場合、すぐに胸部X線検査などで検査をおこないます。その結果、利用者が結核に感染し菌を排出していることが判明した場合は以下のような対処法をおこないます。
まず患者にはサージカルマスクを着用させ、一般利用者とは隔離し医師の指示にしたがいます。患者を診断した医療機関は保健所に感染症の発生を報告。老人ホーム側は管轄の保健所と連携して、患者に対して適切な対応をおこないます。検査の結果、結核菌を排出している利用者は結核専門病棟に入院し、一般利用者と完全に隔離したうえで治療を開始します。ただ結核に感染していても排菌がみられない場合は隔離の必要はなく、一般利用者と同じ施設内で生活し通院によって治療をおこないます。
ここで問題になるのは結核菌を排出している患者と接触した一般利用者や職員です。感染のおそれのある方は「接触者健診」を受診し、結核に感染しているかどうかを検査します。この接触者健診をおこなう際には、入所者やその家族にむけて説明会をおこなう決まりとなっています。
結核菌を排出している利用者が病院で治療をおこない、完治すれば施設で通常通りの生活を営むことができます。このとき結核を治療した利用者が不当な差別を受けないように、職員も結核に対する正しい知識を身につける必要があります。
結核は不治の病と言われていましたが、今は服薬によって完治させることができる感染症になっています。施設職員が正しい知識をもち、いたずらに動揺せずに冷静に対処することが利用者の安心や安全につながります。