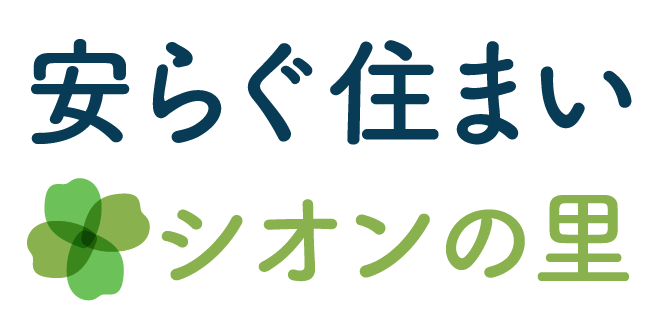梅毒(ばいどく)でも入居可能な施設特集
梅毒(ばいどく)は昔と違い怖い病気ではなくなった!?

梅毒(ばいどく)とは、梅毒トレポネーマと呼ばれる病原体に感染することで、全身の様々な部位に障がいを起こす感染症です。今の高齢者世代では、過去に“不治の病”として流行していたことを思い出す方も少なくないでしょう。しかし、1942年に抗生物質・ペニシリンが実用化されると梅毒へも大きな効力を発揮し、死亡者数は激減しました。現代では恐れる病気ではなくなったのは確かですが、高齢者の感染事例がないわけではありません。しっかりとした感染対策を取っている介護施設に入居することで、安心して暮らしたいものですね。
梅毒感染者が急増中!老人ホーム選びも慎重に
「梅毒」という病気を聞くと「昔の病気」というイメージがわいてきます。衛生状態の悪い時代、抗生剤などの治療薬がなかった時代には、この病気で命を落とした方がかなりいたようです。「不治の病」とも呼ばれていました。ところが抗生剤・ペニシリンの登場により梅毒は治療できる病気となり、現場の医師でも患者さんを治療する機会はほとんどなくなり「梅毒は教科書にのっているだけの病気」とも言われていました。梅毒患者数は減少傾向にあったのですが、2011年をさかいにして患者数が増加しています。
東京都感染症情報センターが発表した「梅毒患者報告数の推移」グラフをごらんください。2006年の梅毒患者数は112名でしたが、2011年には患者数が248名になり約2倍の増加、さらに2013年には507名に、そして2014年には1,044名と急増。患者数が1,000名を超えており、2006年当初からみると約10倍の伸びとなっています。梅毒は男性の多い病気、とされていますが、2014年以降は女性患者の割合が増加傾向にあります。女性も男性同様、十分な注意が必要なのです。
| 2006年(112人) | |
| 2007年(162人) | |
| 2008年(205人) | |
| 2009年(196人) | |
| 2010年(173人) | |
| 2011年(248人) | |
| 2012年(297人) | |
| 2013年(419人) | |
| 2014年(507人) | |
| 2015年(1044人) | |
| 2016年(1673人) |
「年齢階級別患者報告数の推移」をみると、男性は30~39歳、40~49歳、そして女性の場合は20~29歳、30~39歳の方に梅毒感染が多くみられる傾向です。比較的若い世代、働き盛りの世代に多くみられる梅毒感染ですが、男性の場合60~69歳の患者も微増傾向にあります。病気予防のためには「梅毒は若い人の病気、高齢者には関係ない」という思いこみは捨て、十分に注意を払うことが必要ですね。
梅毒は感染症となるため、老人ホームの入所に制限がかかるケースも十分考えられます。みんなの介護に掲載されている老人ホームのうち、梅毒患者の受け入れが可能な介護施設は約2,100か所、全体で約7,000もの施設が掲載されているので、全体のうち約3割の施設で受け入れが可能ということになります。梅毒の場合はカテーテルの管理や頻繁な血液検査、特殊な医療器具の操作、頻繁な通院などが必要ないため、比較的受け入れやすい疾病のようです。
ただし介護スタッフに「梅毒に対する正しい知識」がないと、ちょっとした接触だけで「梅毒が感染する」と怖がる職員もいるようです。老人ホームは梅毒患者の受け入れが可能であることはもちろん、梅毒患者の受け入れ実績と病気に関する知識をもつ介護施設を選ぶことが重要ですね。
梅毒とは?
ここでは梅毒という病気についてご説明しています。ぜひご参考にしてください。梅毒の原因となる病原菌は「梅毒トレポネーマ」と呼ばれる人の目にはみえない細菌です。らせん状の形をしています。感染力が非常に強いのが特徴ですが、空気感染することはありません。感染者の近くにいるだけで病気がうつるということは一切ありませんので、必要以上に避けるのは患者のこころを傷つけることになります。
主な感染ルートは梅毒感染者と性交渉をおこなうこと、そして母子感染することも知られています。この病気、感染すると皮膚に赤みやしこりが発生する、リンパ節が腫れるなどの症状がでますが、さまざまな症状が長く続かないのも特徴。皮膚の異常やリンパ節の腫れは一時的なもので「病気になっている」という自覚がもちにくく、治療しないまま放置する危険性も。
ではここから梅毒に感染したあと、具体的にどのような症状がでていくのかを見ていきましょう。梅毒の症状には第1期~4期までのステージがあります。性交渉などで梅毒トレポネーマが体内に侵入すると、小さな傷口から血管へと病原菌がひろがっていきます。感染後3週間ほどすると第1期症状が出現します。感染した場所に小豆くらいの大きさの赤く硬いしこりが発生します。痛みがないため自覚症状がもてない方も。しこりを放置すると症状がおさまる患者もいますし、しこりの表面に炎症がおこり湿り気をおびることも。
感染後約3か月程度経過すると、第2期症状があらわれます。梅毒トレポネーマが血液にのり全身にひろがるため、全身の皮膚や粘膜に発疹や赤い斑点が。これらはバラ疹とよばれ、背中や胸、手足、お腹など全身にみられます。左右対称にあらわれるのも特徴です。さらにリンパ節が腫れていきます。リンパ節は脇の下や首、足のつけ根など。この第1期から第2期までは梅毒トレポネーマが皮膚の近くにいるため、かなり感染力強くなっています。この時期の梅毒患者との性行為は非常に危険なのです。
感染して3年以上、第3期になると梅毒トレポネーマは皮膚から体の奥深くまではいりこみ、深刻な症状を引き起こします。心臓や脳がおかされ、錯乱やマヒ、また認知症の症状がでることも。深部組織を破壊するゴム腫やしこりがあらわれますが、このゴム腫とは柔らかく弾力のある腫瘍のこと。顔や背中、肩、胸などにこの腫瘍が広がります。今はペニシリンの登場で第3期・第4期まで症状がすすむ患者はいなくなったと言われています。
この第3期に手を打たないと最終段階、第4期へと突入します。感染から10年以上経過すると、梅毒トレポネーマは中枢神経に侵入。神経炎・血管炎などの症状のほかにも、腫瘍が臓器に転移して臓器がくさるという末期的症状も。脳や中枢神経、脊髄などに梅毒トレポネーマが侵入していますので、認知症や神経障害などの症状が引きおこされます。
梅毒で鼻が落ちるという状態は、鼻にできたゴム腫が腐ることを暗示しています。第3期~第4期は梅毒トレポネーマが患者の体内の奥へと入りこんでいくため、感染力は非常に低くなっています。
梅毒は病気の原因が特定され、さらに特効薬が開発されています。初期のうちに病気に気づき、早めに治療をすれば完治させることが可能。決して怖い病気ではありません。ただ第3期~4期まで進行してしまうと根本治療がむずかしいのが現実です。早めの受診・治療が重要ですね。
老人ホームでの感染力は弱そうだけど…「梅毒可」の施設の対応は?
梅毒患者が老人ホームに入所するときは、病気の進行度を介護スタッフが把握することが重要です。第1~2期では、梅毒トレポネーマの感染力が強い状態なので、入所者の体液や血液などに触れることは避けましょう。入所者の飲んだカップに、さらに誰かが口をつけないように十分な注意が必要です。ただし梅毒も第3期~4期、つまり感染してから5年以上経過すると感染力はかなり低下しています。必要以上に気をつかって接する必要はありません。
「梅毒可」の老人ホームでは、施設スタッフが梅毒に対する知識をもち、患者に対する接し方の教育を受けています。過去に梅毒患者を受け入れている施設であれば、対応マニュアルや介護に関するノウハウも蓄積されているはずです。基本的に梅毒は性交渉やそれに類するような行為により感染しますので、患者の体にさわった程度では問題ありません。施設によってはワンケア・ワングローブを徹底している施設もあるため、排泄物の処理や入浴などのケアに手袋を使用し、衛生面の管理や感染対策をする施設もあります。
梅毒は血液・体液を介して感染する病気なので、注射器のまわし打ちは厳禁です。老人ホームでは感染が広がらないように、患者の行動については見守りをおこないます。第3~4期は感染力が低下、ほとんどないと言われていますが、ほかの入所者、また介護・看護スタッフに感染しないよう配慮されています。