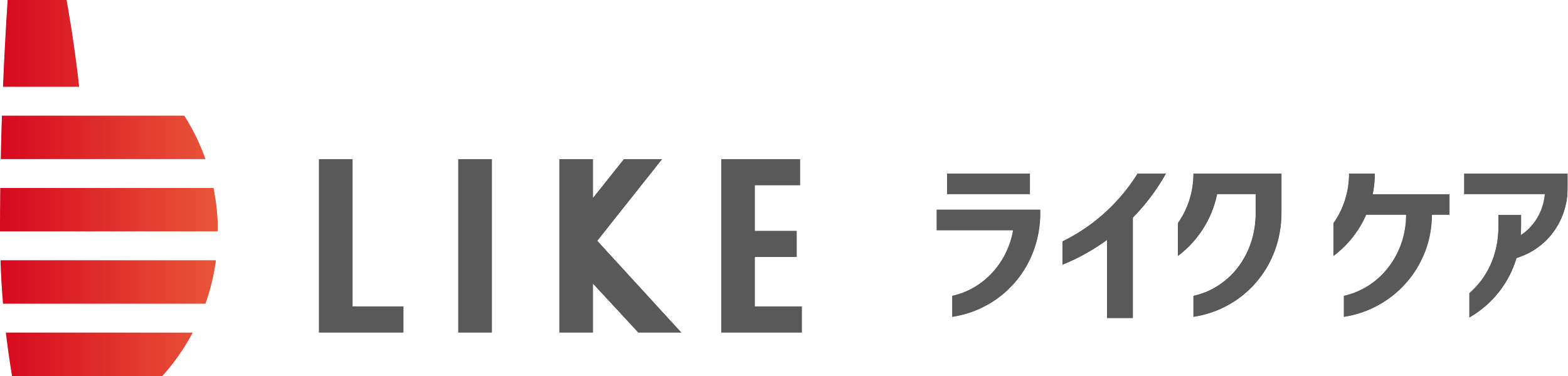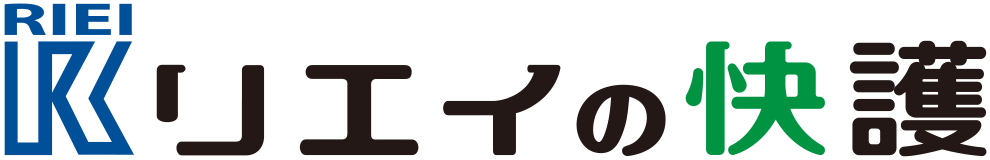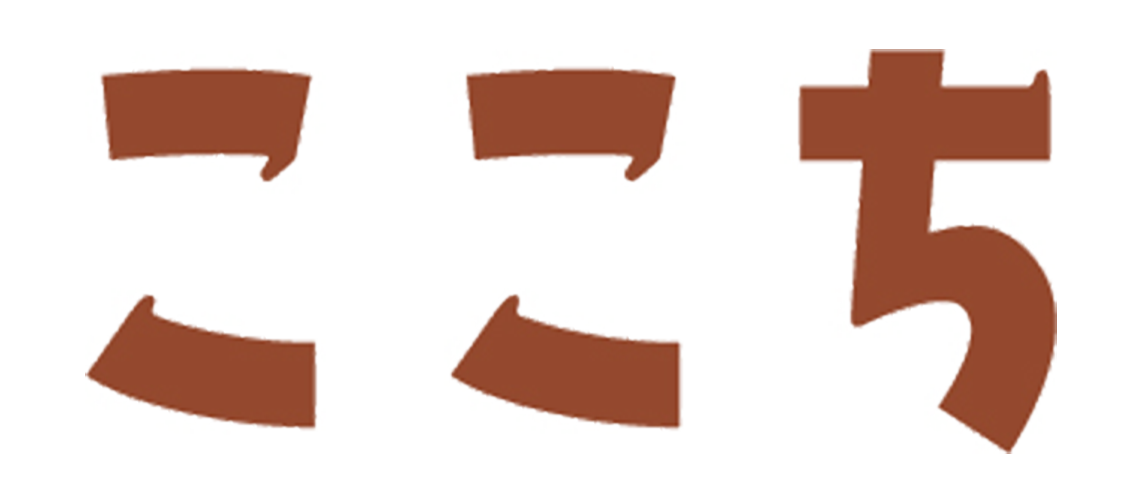病院・クリニック併設の施設特集
持病がある方や健康に不安がある方こそ、病院・クリニック併設の施設は大きなメリット

高齢になればなるほど、持病があったり、健康状態に不安を抱えたりする方が増えるのは当然のこと。介護施設への入居にあたって、健康に関するサポート体制の充実した施設選びをしたいなら、病院やクリニックを併設した施設がオススメです。日常的にドクターによる治療や看護師によるケアを受けることができ、いざ容態が急変した場合も迅速に処置してもらえるというメリットがあります。緊急時の対応だけでなく、日々の健康管理や診療、治療などにも便利な病院・クリニック併設タイプの施設なら、医療面でのサポートも充実しているので安心して毎日を過ごせます。
定期的な検診だけでなく、万が一のときにもすぐに受診できる
高齢になるとなにかしらの持病を抱えているケースが多く、普段から病院やクリニックに定期的に通院していることも決してめずらしくはありません。持病が糖尿病だけの場合もあれば、糖尿病に高血圧、腎臓病(人工透析)など複数の病気をもっていることも。持病が増えれば増えるだけ健康管理にはかなりの注意が必要です。
高齢者の健康上の問題点は持病だけではありません。一度脳梗塞を起こした方のなかには、再び同じ場所で脳梗塞が発生することもあります。高血圧であれば血管系の病気を起こす可能性も高まります。健康面に不安をもつ高齢者にとって、老人ホームに病院やクリニックが併設されていることは大きな安心につながります。
認知症を発症し、自身で健康管理がきちんとできない高齢者も、病院・クリニック併設の老人ホームに入居すれば問題点も解消できます。定期的に健康診断を受けることで医師や看護師が小さな変化に気付き、早めに対応可能です。認知機能の低下で本人の病気の自覚がなくても、血液検査やMRI検査で病気の早期発見も期待でき、早めに治療をはじめることもできます。急変時にはそのつど医師が診察をおこない、適切に対応してくれる安心感はやはり格別です。
病院・クリニック併設の老人ホームは、老人ホームと同じ建物内に病院が開設されているケース、また病院と老人ホームが渡り廊下でつながっているケース、老人ホームと同じ敷地内に病院が開設されている場合など、入居者がすぐに診察や定期健康診断を受診できるように配慮されています。渡り廊下でつながっている場合は、夜中でも雨や雪の日でも、さらに車椅子やストレッチャーを利用した場合であってもスムーズに病院に搬送できるメリットがあります。クリニックは日曜日や祝日がおやすみのところがほとんどですが、病床数の多い大規模総合病院と老人ホームが提携していれば24時間365日、いつでも診察が受けられる安心感があります。
病院・クリニック併設の老人ホームは医療法人が運営していることが多く、医療面はかなり充実しています。そのかわり、ほかの老人ホームにくらべて、月額利用料や入居一時金が割高になっていることが多い傾向です。安心して暮らすための対価として考えるべきでしょう。
老人ホームに併設された病院に入院していた患者が、退院後にすぐに併設の老人ホームに入居できるのも、医療体制が強化された老人ホームの魅力であり強みです。病院を退院したあと、入居できそうな老人ホームを見つけることができずに病院を転々とする例もありますが、病院と老人ホームが相互に提携していれば「退院後の行き先がない」と心配することも少なくなります。これは精神的な安定につながります。
総合病院と提携している老人ホームなら、人工呼吸器や人工透析、中心静脈栄養(IVH)患者、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者など、一般的な老人ホームでは受け入れがむずかしい高齢者も、安心して入居できます。
病院・クリニック併設の介護施設は少ないのが現状!?
医療面での安心感がとても大きな病院・クリニック併設の介護施設。やはり大きなメリットは、入居者の急な体調変化に対して迅速に対応できることでしょう。高齢者の場合、昨日は体調が良くほかの入所者と元気にレクリエーションを楽しんでいたとしても、明日は急に体調を崩し、ベッドで一日中横になることもあります。そんなとき、病院やクリニックが併設されていれば、医師が本人の居室を訪問して診察してくれることも可能です。さらに容体が悪いようなら、施設の整った大きな病院に検査や入院ができるようにすぐに手配してくれます。健康面に不安を抱えている高齢者にとって、医療面が充実した老人ホームはとてもありがたいものです。
老人ホームは3大介護(食事・入浴・排泄)と生活支援を行っていればいい、という時代もありましたが、今は利用者も増えてニーズも広がり、さまざまなケースに柔軟に対応できなければ生き残れなくなりました。身体介護と生活支援だけではなく、手厚い医療面のケア、心のケア、生きがいづくり、ほかの入所者との触れあいなど、プラスアルファのサービスを加え、老人ホームの特徴や魅力を発信していかなければほかの事業所との競合に勝てません。老人ホームの運営側にとっては厳しい時代となっています。「費用は少々高くなってもいいから、医療面を充実させてほしい」というニーズも当然ありますので、その声ににこたえるべく誕生したのが病院・クリニック併設の老人ホームなのです。
では医療体制の充実した老人ホームは、一体どれくらいあるのでしょうか?
全国に9,000か所以上ある老人ホームのうち、病院・クリニック併設の介護施設は約563か所。全体の6%程度にとどまります。そのなかでもとくに病院・クリニック併設の老人ホームが多いのが大阪府の60か所。つぎが東京都の49か所、神奈川県の47か所、福岡県の42か所、愛知県の30か所、千葉県の27か所、埼玉県の25か所、北海道の22か所とつづきます。政令指定都市のある地域(人口の多い場所)には病院・クリニック併設の老人ホームが多く開設している傾向です。都市部に住んでいる方には喜ばしい状況ですが、裏がえして考えれば、地方には医療体制のととのった老人ホームが少ないということにもなります。
病院やクリニックが併設された老人ホームだけではなく、距離は少し遠くても提携する病院があり、入所者が急変した場合にすぐにオンコールで医師や看護師が駆けつけてくれる老人ホームも安心して入居できます。特定の持病をもつ高齢者は、老人ホームの入居前にどこまで医療面の対応が可能かを、じっくり打ち合わせると安心です。
人工呼吸器、簡易人工呼吸器の患者は受け入れ不可でも、在宅酸素療法の患者は受け入れ可能な施設もあります。一般には受け入れがむずかしい人工透析患者や中心静脈栄養(IVH)患者、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者も、提携しているクリニックや病院で治療が受けられる場合は入居できる場合ももちろんあります。「人工呼吸器の患者だから……、人工透析だから……」と老人ホームへの入居をあきらめる必要はありません。
日常的な医療行為が必要な高齢者こそ病院併設の老人ホーム選びを
高齢になると糖尿病や高血圧症、腎臓病、床ずれ、結核、肝炎、認知症、パーキンソン病、うつ病、統合失調症、リウマチ・関節症、骨粗しょう症、心臓病、狭心症、動脈硬化など、さまざまな持病をもつ可能性が高くなります。このなかでも日常的な医療行為が必要な高齢者には、きめ細かい医療ケアサービスが受けられる「病院・クリニック併設型の老人ホーム」がおすすめです。
糖尿病でも服薬と通院で血糖値をコントロールできる患者と、インスリン注射を1日に3回注射しなければならないうえに、認知症を発症しており自分で注射が打てない患者とでは、その深刻さにも違いがあります。後者の方がより医療・看護体制のととのった老人ホームを選択しなければなりません。
糖尿病以外にもさまざまな病気があり、とくに人工透析患者やストーマ(人工肛門・人工膀胱)を造設しているオストメイト、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者、中心静脈栄養(IVH)患者、人工呼吸器を使用している患者、結核、疥癬、鼻腔・経管栄養の患者は受け入れ可能な老人ホームが少ない傾向にあります。高い医療技術や管理が必要なのです。
病院やクリニックが併設された老人ホームなら、一般的に受け入れがむずかしい病気を患っていても、施設で対応できる可能性が高くなります。医療機関が同じ建物にある、渡り廊下で通える、歩いて数分の場所にあれば介護職員や看護師、家族が病院へ付き添いをする負担もかなり軽減されます。
介護施設の利用者が通院する場合、ひとりで外出できなければ介護職員や看護師に付き添ってもらうケースもあり、これを外出解除と呼んでいます。この外出介助も無料ではなく、介護保険でお願いしなければなりません。場合によっては介護保険の適用外になります。もし片道1時間以上かかる病院への通院を希望すると、看護にかかる時間を超えてしまい契約時間を完全にオーバーしてしまいます。外出介助にかかる時間を短縮するために、より老人ホームに近い病院へ変更してもらうこともあり得ます。
病院やクリニック併設の老人ホーム、提携病院が近くにある老人ホームなら、外出介助にかかる時間がゼロ、またはかなり短くなります。外出介助にかかる費用を心配し、病院を変更する必要はありません。この点でも病院・クリニック併設の老人ホームは有利と言えます。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)の対応が可能な施設特集
専門的で高度な医療技術が整っています
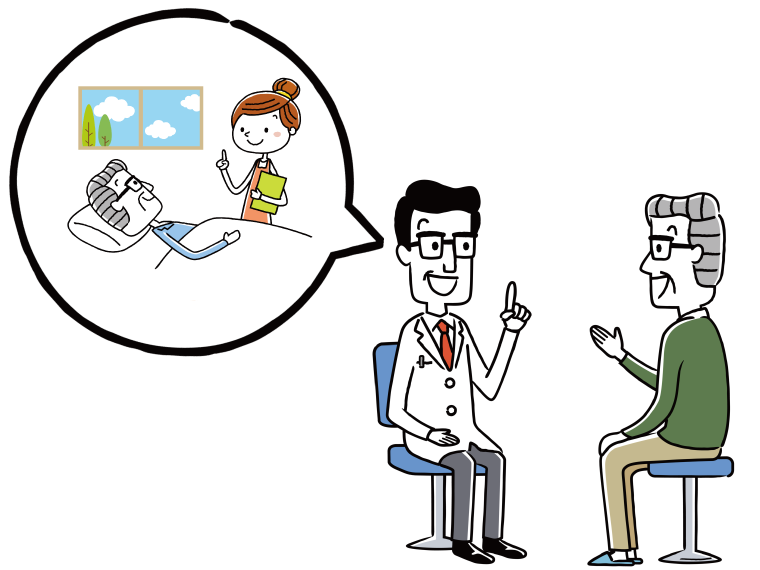
原因不明の指定難病である筋萎縮性側索硬化症(ALS)では、身体機能の低下によって胃ろうや中心静脈栄養(IVH)が必要になったり、気管切開が必要になるケースもあります。非常に専門的で、なおかつ高度な医療・看護の技術を要するため、受け入れを行なっている介護施設も限られてきます。有料老人ホームへの入居を考える際には、24時間看護が徹底していたり、医療施設に併設しているなど、医療と密接に連携しているところを選ぶと良いでしょう。
ALS患者の受け入れ可能な老人ホームには、専門的で高度な医療技術が
筋萎縮性側索硬化症(Amyotrophic Lateral Sclerosis:ALS)という病名、効き慣れない病名だと感じる方も多いでしょう。肺炎やインフルエンザ、胃炎、糖尿病など私たちの身近にある病気のイメージではありません。この病気は50~70代の方に多くみられ、とくに65~69歳の方が多く発症しています。男性と女性を比べると、男性の方が1.5倍患者数が多いという統計もあります。職業により発症の偏りもみつかっていません。主婦だから発症しにくい、肉体労働者だから発症しやすい、という傾向はありません。誰でもこの病気にかかる可能性があります。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者数は1975年には214名でした。それから年々患者数は増えつづけ、2014年には9,950名と1万人近くの患者が治療を受けています。日本の国民病と呼ばれる糖尿病の患者数が316万人以上いることを考えるとメジャーな病気とは言えませんが、誰でも発症する可能性があるため注意が必要です。この病気は1974年に特定疾患として認定された指定難病で、現在の医学では完治させることは困難です。この病気の原因については「グルタミン酸過剰説」「環境説」「遺伝性説」などいくつかの仮説はありますが、いずれも仮説の域を出ていません。原因はいまだに不明です。また根本的な治療法も見つかっていないため、進行を遅らせる治療しか選択できません。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)の初期の症状としては「箸が持ちにくい」「重いものが持てない」「筋肉が痛い、つっぱる」「舌の動きが悪くなり発音しにくい」「食事が飲みこみのくい」など。このとき自身がALSを発症していることを自覚できないことも多く、整形外科や一般内科を受診する方も少なくありません。そのため病気の診断・治療が遅れることになります。ALSの診断や治療ができる診療科目は「神経内科」です。
その後症状が悪化すると、全身の筋肉がおとろえ、自力で立ちあがり運動することができなくなり寝たきりの状態へ。さらに呼吸をおこなう筋肉も低下するため、夜眠っても十分な酸素が体内に供給されず「朝起きると頭痛がする」「スッキリしない」などの症状があらわれます。呼吸筋の力が低下することで呼吸困難になり、最終的には人工呼吸器を装着することになります。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者が老人ホームへの入居を希望する場合、高度な医療技術がそなわった介護施設を選定しなければなりません。医師や看護師が24時間常駐し患者の容体をつねに観察し、服薬管理はもちろん患者の状況によっては胃ろう、たん吸引、人工呼吸器の管理は不可欠。胃ろうやたん吸引は研修をうけた介護職員でも対応できますが、人工呼吸器は専門的な医療ケアになるため医師や看護師の管理が必要です。筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の受け入れが可能な老人ホームは、高度な医療ケアが提供できる環境、また老人ホーム内に医療施設があり、たえず医療スタッフのバックアップが期待できる施設でなければなりません。
みんなの介護に掲載されている約9,000か所の老人ホームのうち、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の受け入れが可能な施設は約1,507か所。受け入れ可能な老人ホームは少なめです。老人ホームの傾向を見てみると、24時間医療機関と連携できる環境、24時間看護師常駐、日中看護師常駐など、医療面の強化を謳う施設が多くなっています。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の老人ホームの受け入れ体制は?
筋萎縮性側索硬化症(ALS)は筋肉が少しずつ委縮し、やがて日常生活に支障がでる神経性の病気です。難病指定されており、病気の原因特定や治療法はまだ確立されていません。筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者が老人ホームへの入所を希望する場合、施設側の受け入れ態勢がととのっていなければ不可能です。
有料老人ホームにおけるALS患者の受け入れ割合は全体の約18%となっており、入居先はかなり限定されます。筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の受け入れに難色をしめす老人ホームが多いのは、さまざまな医療ケアが必要になるためです。筋肉の委縮は体にさまざまな障害をもたらします。
食事や水分の摂取が困難になる「嚥下障害」では、介護食の提供や食事介助が必要ですし、口から栄養が摂取できなければ胃ろう造設や中心静脈栄養の導入になります。
体中の筋肉が衰えるため「寝たきり」になると床ずれ防止の体位変換やオムツ交換、入浴介助、急変時の対応など介護職員にもかなりの負担がかかります。ALS患者の受け入れ実績のある老人ホームでは、患者に対するケアのノウハウが蓄積されています。実績のある老人ホームを選ぶことで、入居者はもちろん、その家族も安心できるでしょう。
介護・看護職員はALSという病気に対する理解や対応の方法、さらに患者に対する心のケアも必要です。ALSと診断されると、気持ちが落ちこんだりうつ状態になる方が大勢います。施設職員はALSの患者がこのような精神状態になることを把握し、必要に応じて話しを聞く(カウンセリング)や、薬物療法などで対応します。
さらに患者のうち約2割の方に、高次機能障害や前頭側頭型認知症の症状がでることがわかっています。これら病気の発症によって、同じ行動や言葉を何度も繰りかえす、同じ食べ物ばかり食べたがる、特定の物事に固執する、精神的に不安定になるなどの症状がでます。老人ホームのスタッフは患者の症状をみながら、体だけではなく精神的なケアも同時におこないます。
老人ホームに入所すると何かと不安なことが多いもの。けれど介護施設の職員は介護や看護のプロ。とくにALS受け入れ実績のある老人ホームなら安心です。プロがおこなうケアに期待したいですね。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)とは?
筋萎縮性側索硬化症(ALS)とは、一体どのような病気なのでしょうか。
この病気は脳神経細胞(運動神経細胞)が侵されることで発症する病気です。運動神経細胞が機能しなくなると、脳や末梢神経からの指令が筋肉へと伝わらなくなります。「右手を動かして箸を持って食事を食べなさい」という脳の指令は出ても、運動神経細胞が機能しないため筋肉への信号がうまく伝わりません。このため患者の体が動きにくくなる、また動かなくなります。
このとき、腕や足の動きに異常を感じた患者の74.2%が、整形外科や一般内科、脳神経外科などを受診しています。
| 一般内科、整形外科など(74.2%) | |
| 神経内科(25.8%) |
さらに、舌の動きが悪くなり話しにくくなる、食事の飲みこみが悪くなるなど舌やのどの筋肉が低下する「球麻痺」で受診した方の61.5%が、一般内科や耳鼻咽頭科、整形外科などの診療科目を受診しています。筋萎縮性側索硬化症(ALS)の診断・治療ができるのは「神経内科」だけです。もし整形外科や内科を受診しても症状が1か月以上治らない場合は、神経内科を受診しましょう。
| 一般内科や耳鼻咽頭科、整形外科など(61.5%) | |
| 神経内科(38.5%) |
では、筋萎縮性側索硬化症(ALS)発症すると、その後どうなってしまうのでしょうか。病気のため筋肉がどんどんやせ細っていき、立つ・歩く・座るなどの日常生活動作に問題がではじめ、最終的には寝たきりの状態になります。
ただ、この病気は運動神経細胞のみ侵されるだけで、知覚神経や自律神経には異常がみられないため、五感(視覚、聴覚、臭覚、味覚、触覚)や認知機能、知性に関しては問題ありません。ALSの患者は皮膚がかゆいという感覚はありますが、かゆい皮膚を掻くための動作ができなくなります。ALSは体中の筋肉が萎縮する病気ですが、心臓や胃腸の動きは自律神経によってコントロールされているので内臓機能には問題はありません。ただし「呼吸」は呼吸筋と自律神経でコントロールされているので、病気の進行とともに呼吸がしにくくなり、最終的には人工呼吸器をつけることになります。
この病気は比較的早く進行すると言われていますが、進行速度に関しては個人差があります。4~5年で症状がすすむ患者がいる反面、10年かけてゆっくり症状が進行することも。早めの診断と治療によって、すこしでも病気の進行を遅らせることが重要です。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療には服薬がありますが、運動療法や栄養管理、呼吸管理などによって生活の質(QOL)の低下をおだやかにできることがわかっています。とくに運動療法は病気の進行を遅らせ生存期間の延長が期待できると言われているため、老人ホームでもALS患者の体調や病気の進行度をみながらリハビリをおこなうことも。筋トレよりもゆったりした有酸素運動の方が効果が高いため、無理なくゆっくり体を動かすことが病気の進行防止には役立ちます。