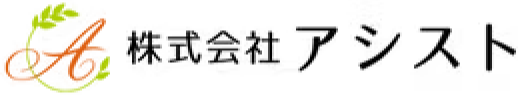カテーテル・尿バルーンの対応が可能な施設特集
施設内での交換が可能な施設もあります

前立腺肥大をはじめ、手術による麻酔や薬剤の影響などで排尿が難しい人に対して行われる処置が、カテーテル・尿バルーン。衛生管理のために定期的な交換が必要です。そのためには定期的な通院が必要ですが、カテーテル・尿バルーンへの対応が可能な介護施設では、医師や看護スタッフによって交換してくれる場合も。医療機関との協力体制が充実していたり、また24時間看護などのサービス体制が整っていたりと、ご入居者様にとってこの上ない安心が、そうした施設には待っています。
カテーテル・尿バルーンを施設内で交換できる施設もあります
カテーテル・尿バルーンとは、カテーテルを尿道口から膀胱へと差しこみ、尿を体外に自動的に排出させることです。
このような医療的処置がとられるケースと考えられるのは、まず手術後。術後はすぐに体を動かし活動することはできません。傷口が開く可能性もありますし、痛みもあります。手術後はベッド上で安静にするのが基本です。体を動かすことができないため、トイレにも行けません。そこでカテーテル・尿バルーンを尿道口から膀胱へと差しこみ、膀胱内にたまった尿を自動的に体外に排出させるのです。
ほかにも前立腺、膀胱腫瘍の術後等にカテーテル・尿バルーンを留置します。創部安静のためにおこなう処置となります。さらに末期がん患者や症状の重い患者の場合は、正確な水分管理が必要なためにこの処置をおこないます。尿量を管理しながら輸液を補充するためです。もしも尿量が極端に減ってしまった場合は、腎臓になんらかのトラブルが起きている証拠。尿量を管理することで体の異常をすばやく察知できるのです。
カテーテル・尿バルーンの挿入や引きぬきは医療行為です。医師や看護師などの有資格者でなければ処置ができません(例外として患者本人とその家族がバルーンの挿入をおこなうことができます。その場合は医師から十分な指導・説明を受けることが条件となります)。無資格者である介護職員がカテーテルの挿入をおこなうのは違法行為となります。もしカテーテル・尿バルーンの高齢者が老人ホームへの入所を希望した場合、看護師や医師がカテーテル管理可能な施設を選ばなければなりません。
みんなの介護では、全国の介護施設、約9,000施設の情報が網羅されていますが、カテーテル・尿バルーンに対応できる老人ホームは約5,263か所。半数以上の老人ホームで対応可能となっています。これはカテーテルや尿バルーンを一度挿入すると、約3週間から1か月程度はそのまま様子をみることができる、という理由もあるでしょう。中心静脈栄養ほどの厳しい衛生管理、医療ケアは必要ありません。
もちろんバルーンを留置しているあいだに「尿の色に異常がみられる」「尿量が急に減る」「カテーテルが抜ける」「発熱する」などの異常がみられたときは、すぐに医師や看護師が対応しなければなりません。そのため看護師が24時間常駐、または日中看護師常駐、夜間はオンコールで即時に医療対応が可能な老人ホームでなければ、カテーテル・尿バルーンの方は入所できません。
有料老人ホームにおける尿バルーンの患者の受け入れ割合は約58.4%。約半数の老人ホームで受け入れが可能となっています。もし老人ホームへの入所を希望する場合は、比較的スムーズに受け入れ先を見つけることができるでしょう。
カテーテル・尿バルーンとは?
カテーテル・尿バルーンは先ほども少しご説明しましたが、尿道口から導尿用のカテーテルを膀胱まで挿入し、尿を体外へと(蓄尿バックへと)排出させます。カテーテルは透明なので、外から尿の排出状況を確認できます。尿がしっかり排出されていることを確認したあと、蒸留水(滅菌水)をいれたバルーンを膨らませることでカテーテルが外れにくくなります。バルーンは、尿カテーテルを膀胱内に留置させるための方法なのです。尿カテーテルを挿入するとバルーンを膨らませることになるため「尿バルーン」と「尿カテーテル」はセットになっていると考えてください。
この処置が必要な患者は、厳密な水分管理が必要な患者、手術後に絶対安静が必要な患者、尿毒症や尿閉等など全身の感染症や腎機能低下防止のため、血尿の患者、前立腺肥大症、尿道狭窄等など慢性的な尿閉の症状がでている患者等、になります。この尿カテーテルは手術後におこなうことが多いので、経験された方も多いのではないでしょうか。
女性の尿道は4~5センチなのでそれほど違和感はないのですが、男性の尿道は15センチ前後あり、さらに前立腺による抵抗のため挿入が多少むずかしくなります。男性の方が違和感や痛みが起こりやすいようです。挿入時に痛みを感じにくいように、カテーテルの先にゼリー状の潤滑油を塗ります。排出された尿は蓄尿バック内に集められますが、尿を見られるのは気恥ずかしいという患者の気持ちを考慮し、カバーで覆って尿が見えないように配慮されているケースもあります。蓄尿バックは尿の逆流を防ぐために、つねに患者よりも低い位置に設置します。
膀胱や尿管は基本的に無菌ですが、体外に排出した尿には細菌が入りこむ可能性があります。菌で汚染された尿が患者の体内に逆流すると、感染症(敗血症など)を起こすリスクが高まります。尿カテーテルの挿入時は「体内に菌を入れないこと」が絶対条件です。尿道口やその周辺を消毒することはもちろん、カテーテルを挿入する看護師や医師の手指もきれいに消毒しなければなりません。
尿カテーテル留置でもっとも気をつけなければならないことは、やはり尿路感染症です。もしも雑菌が患者の体内に入りこむと腎盂腎炎や膀胱炎、敗血症を引きおこす可能性も。衛生面には十分な管理が必要です。
カテーテル・尿バルーンを装着している高齢者の老人ホームへの入居ではここに注意!
尿カテーテル・尿バルーンを留置している高齢者が老人ホームへの入居を希望する場合は、まず、医療体制がととのっているかどうかを確認しましょう。カテーテルの挿入や抜去、尿量管理などは医療行為になりますので、医師や看護師などの医療従事者でなければ対応できません。
万一、尿路感染が起きると抗生剤の投与など専門的な治療が必要です。医師や看護師が24時間常駐、または日中常駐の老人ホームかどうか、尿カテーテル患者の受け入れ実績があり、きちんとした対応が可能かどうかを確認したところです。夜間・早朝に異常がおきた場合、オンコールですぐに医師や看護師が対応できる老人ホームできるかも重要です。尿量やカテーテルの管理、緊急時の対応など、もしものときに医療機関と連携できていない老人ホームでは困ります。
これらの条件をクリアし、尿バルーン留置の高齢者の受け入れ可能な老人ホームであっても「いくつか注意」が必要です。認知症や統合失調法などの病気で「カテーテルを本人が勝手に引き抜く((自己抜去)行為)が頻繁にあると、入居を断られるケースも。カテーテルを自己抜去すると尿路が傷つく可能性もあり、観察や医療的措置が必要になることもあります。とくにグループホームの場合は要注意。本人が尿カテーテルを抜去しなくても、ほかの入居者が興味半分で抜いてしまう可能性もあるようです。尿カテーテル患者がグループホームに入居する際は事前によく話し合いをおこないましょう。
尿カテーテルは衛生面も考慮し、一定の間隔で取りかえる必要があります。取りかえには泌尿器科クリニックを受診する必要があるのか、それとも施設常駐の医師や看護師で対応可能かどうかの確認をおこないましょう。施設内でカテーテルの取りかえができるなら外出する必要はありません。通院の必要がある場合、クリニックまで介護タクシーを利用するのか、職員が送迎をおこなうのか、通院の頻度などがネックになることがあります。クリニックに何度も通うことが想定される場合は、送迎の費用や職員の対応などについて事前に話しをしておきましょう。老人ホーム入所後に高額な介護タクシー代などを請求されて揉めるケースもあります。