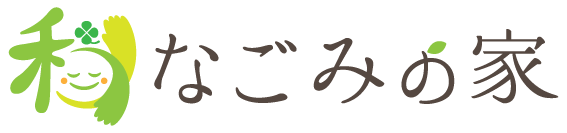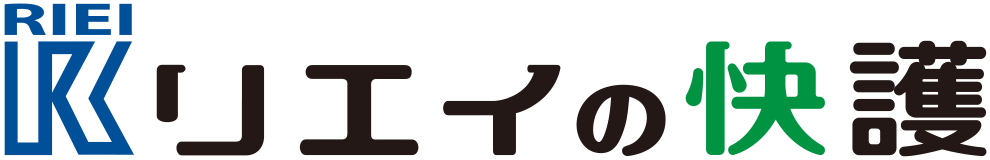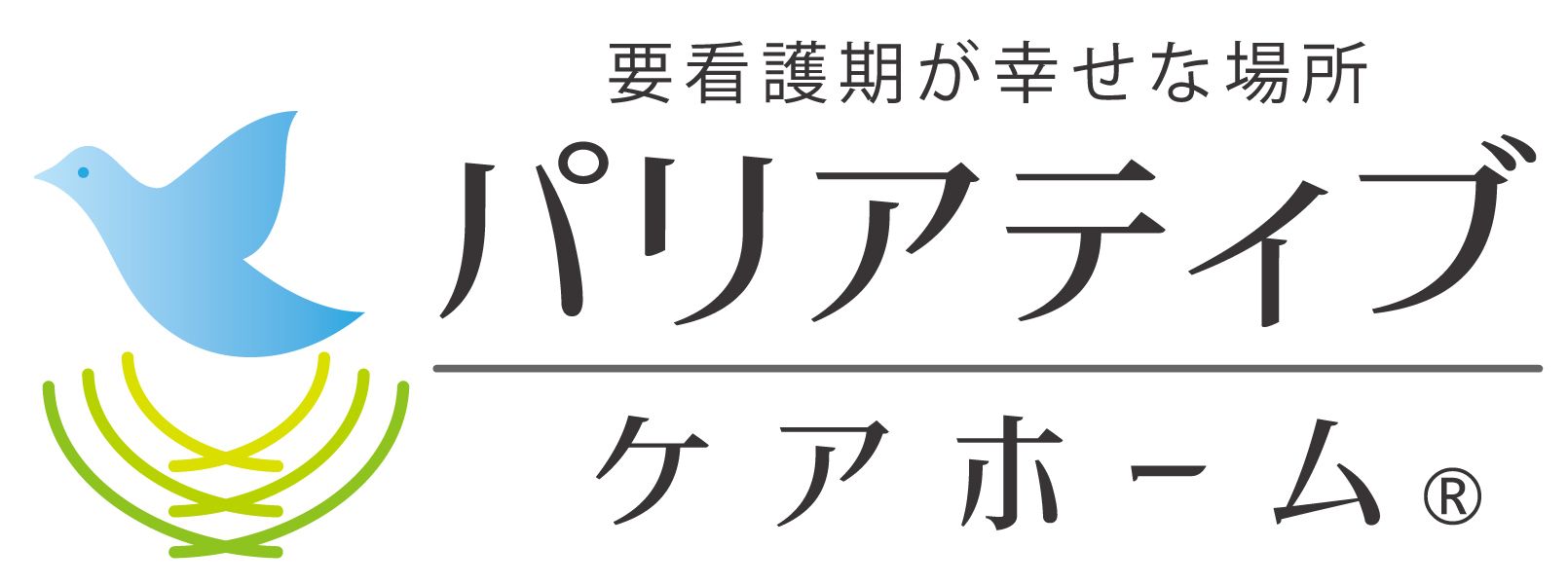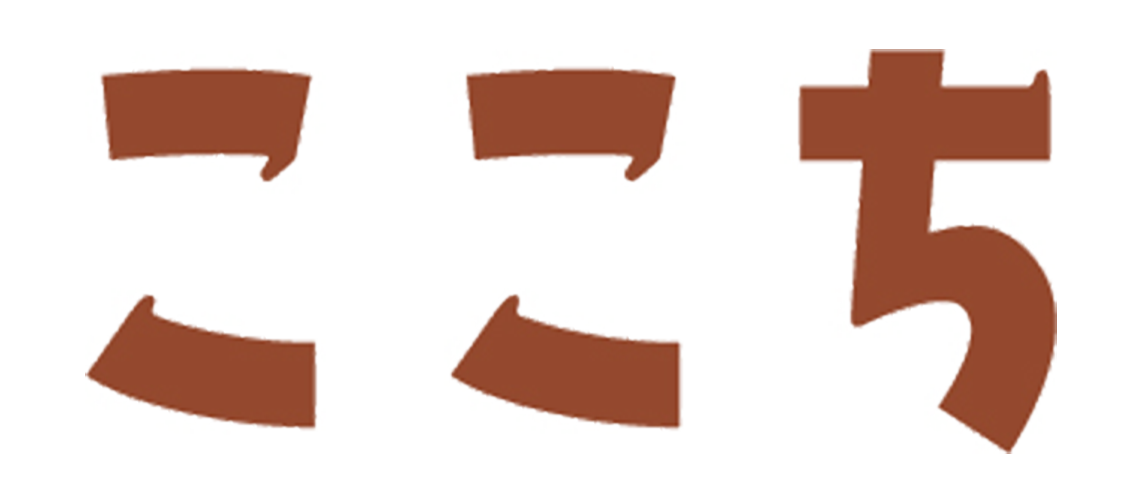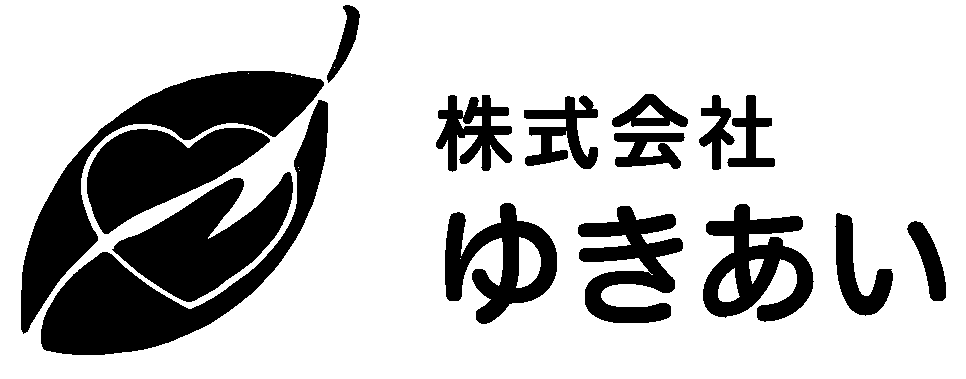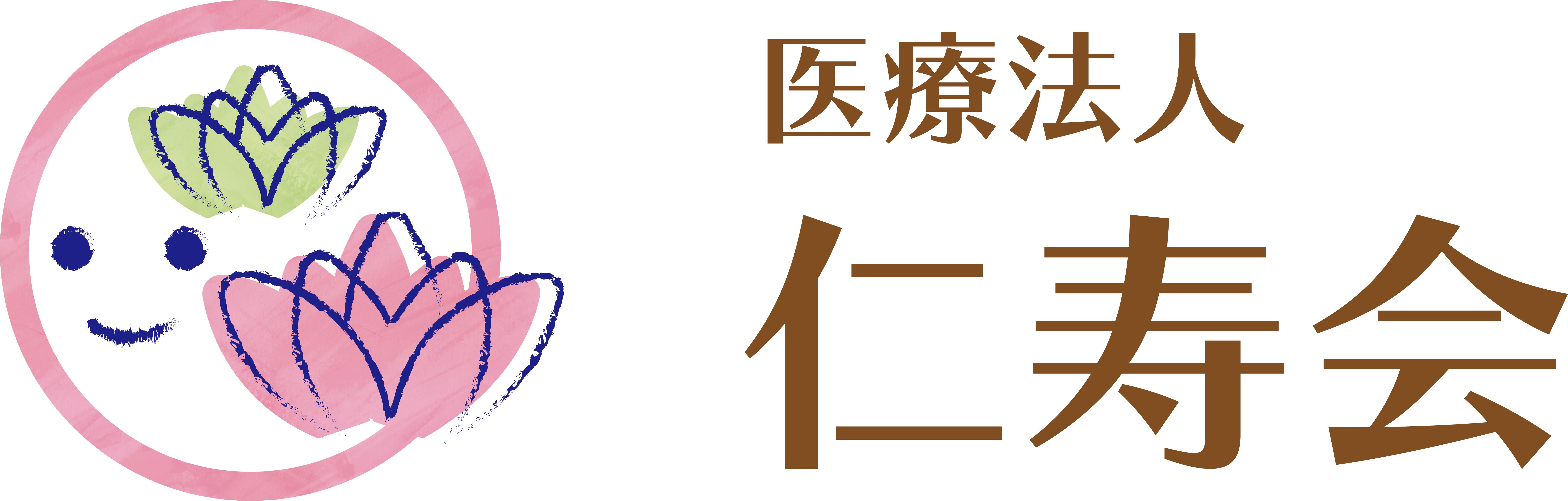看取り・終末期・ターミナルケアの対応が可能な施設特集
QOLを重視した医療ケアも万全の施設です

例えば末期がんの患者などは、それ以上の治療を行わないというケースもあるでしょう。そんな時こそ、終末期対応可・ターミナルケアのある施設への入居を考えてみてはいかがでしょう? 「介護・看護に関して24時間体制が整っているか」「すぐに連絡が取れる提携の医療機関があるか」。この2点を確認しておけば、ある程度は施設側の姿勢も見えてくるもの。医療ケアがしっかりとした施設ばかりで、来るべき日までの生活を、どれだけ自分らしく送れるかという“クオリティ・オブ・ライフ”を重視しているため、きっと充実した余生を送れるはずですよ。
看取りに対応した老人ホーム・介護施設は、QOLを重視した介護が特長です
最期を迎えたい場所として一番多かったのが「自宅」の54.6%であるというアンケート結果が、内閣府が全国55歳以上の男女を対象にしておこなった「高齢者の健康に関する意識調査(平成24年度)」によって明らかになりました。ついで「病院などの医療施設」が27.7%、「特別養護老人ホームなどの福祉施設」が4.5%、「高齢者向けのケア付き住宅」が4.1%となっています。多くの方が自宅で最期を迎えたいと望んでいるにも関わらず、実際にその希望がかなえられるケースは少なく、ほとんどの方が病院などの医療施設で亡くなっています。
日本人の死因は悪性新生物(がん)や心疾患、肺炎、脳血管疾患が多くを占めており、全体の約64%もの方々が病気によってこの世を去っています。自宅で安らかな死を迎えたいと願っても医療施設で最期を迎えざるを得ない状況です。
最近は介護福祉施設で最期を迎えたいと望む方が増えています。この背景には「看取り・ターミナルケア対応」の老人ホームが増加していることがあげられます。
平成18年に介護報酬が改定され「看取り加算」が可能になったことから、一部の老人ホームでは看取りの定義やケアの方針をしっかり定めたうえで看取りを希望する入居者を受け入れています。看取り・ターミナルケア対応の老人ホームでは、入居者の人生の質(QOL)を充実させ、より満足できる生活を送ってもらうことを重視しています。看取り可能な老人ホームでは治療を受けても病気回復の見込みがない入居者に対して、穏やかな死を迎えられるようにさまざまな取り組みを行っています。
ある看取り対応の老人ホームでは、入所者の好きな音楽を流したり、栄養摂取に時間をかける、職員が業務の合間にできるだけ本人に語りかけ寂しい思いをさせないなどの配慮を行っています。看取り・ターミナルケアが可能な老人ホームでは看取りのための介護スタッフ研修が定期的に実施され、看取りに対する心構えや必要な措置を学んでいます。看取り期にあらわれる入居者の変化(急変時ふくむ)に適切に対応し、安心して生活してもらうために各老人ホームで努力していますので、安心して利用して頂きたいと思います。
看取り可能な老人ホーム・介護施設で受けることができる介護サポート
看取り可能な施設では、終末期をむかえた入居者に対して手厚い介護がおこなわれます。その具体的な例をあげてご紹介しましょう。
まずはボディケアです。これは安らかな死を迎えるために環境を整えることから始まります。相部屋であれば、家族との面会がしやすい個室に移動することもあります。利用者が過ごしやすいように室温を調整し、お花を飾ったり好きな音楽を流す、好みの絵画を飾るなどして過ごしやすい環境にします。終末期には食事量が減っていく傾向が見られますが、できるだけ好きなメニューを提供し食べやすいようにとろみをつけて時間をかけ、栄養摂取を心がけます。体を清潔にすることも重要です。ただ蒸しタオルで体を拭くだけではなく、できる限りお風呂に入ってもらうことを心がける老人ホームもあります。体がきれいになることで気持ちもさっぱりするものです。ほかにも病気を患った入居者への疼痛緩和のためのマッサージや温シップ、排泄介助などさまざまなものがあります。
ボディケア以外にも入居者へのメンタルケアも行います。終末期は入居者の精神的な苦痛をとりのぞくために、できる限り本人に話しかけ、寂しい思いをさせないようにします。手を握ったりマッサージを行うなどのスキンシップで寄り添うことを重視した介護サービスを提供。また職員同士の連絡を密にして、夜間の急変時にそなえます。
終末期にはメンタルケアだけではなく、入居者への医療ケアも必要です。医師の指導のもと、酸素吸入や点滴、疼痛緩和のための処置などを行います。看護職員は医師や介護スタッフと連携して、入居者の体調変化や容体の急変に対応します。
看取りケアでは本人だけではなく、家族への精神的ケアにも対応しています。この先入居者がどのような経過をたどるのか、現状に対してスタッフがどのように対処していくのかを説明し、看取りへの不安を解消できるように努めます。家族と入居者の面会時間をできるだけ長くとれるように配慮し、最期のときを家族も心穏やかにともに過ごせるように、介護・看護スタッフが24時間体制で介護や見守りを行います。家族としては先の見えない状況で不安や迷いがあるかと思いますが、分からないことがあれば介護スタッフに声をかけ、その都度解消していくことが精神的な安定につながります。
どのように看取りを行うか?老人ホーム・介護施設入居前には同意書への確認を!
看取り・ターミナルケア対応の老人ホームでは、まず入居時に家族に対して「本人の容体が急変したときには救急搬送を行うのか、それとも何もしないのか」ということを確認します。高齢者は急に体調を崩してしまうこともあるため、入居時に家族の看取りに対する気持ちを確認します。
このとき「緊急時に病院搬送してほしい」という要望であれば医療施設での看取りになる可能性が高くなります。看取り対応の老人ホームであっても、こちらを希望して構いません。また「緊急時に病院搬送しないでほしい」ということであれば、老人ホーム内でできることとできないことなどを施設側が説明します。老人ホーム内でできる医療行為には限界があり、積極的に治療することはできません。その点をよく頭にいれ、急変時の対応を決めていきましょう。入居時には「病院搬送しないでほしい」と伝えたとしても、その後、本人や家族の気持ちに変化があれば老人ホーム側は柔軟に対応しますので安心してください。
老人ホームへの入居後、入居者が終末期にあると医師が判断した場合、また食事の量が少なくなる、元気がなくなった頃に老人ホーム側から「看取り看護・介護についての同意書」へのサインを求められることになります。書面で看取りの意志を確認すると、老人ホーム側では医師の指導を仰ぎながら生活相談員や看護師、介護士、管理栄養士、理学療法士などのスタッフと連携し「看取り介護計画書」を作成。この計画書は老人ホームが一方的に作成するものではなく、入居者本人やご家族の意向や要望も反映されます。
一旦作成された看取り介護計画書ですが、入居者本人の健康状態や意思の変化などにより適宜見直しを行うことができます。不安なことや疑問、迷いがあるときは遠慮なく老人ホームの介護スタッフに相談しましょう。
施設への報酬となる「看取り介護加算」と家族の「同意書」の関連とは?
老人ホーム側の報酬となる介護保険での「看取り介護加算」ですが、どのような施設や状況であっても加算がとれるわけではありません。いくつか条件があります。
まず看取りに関する職員研修を行うこと、常勤の看護師を1名配置すること、看護職員と24時間いつでも連絡がとれる体制を整えること。これらの条件は看取りに関する職員教育や看護体制についてのものです。職員が看取りや看護のことについて無知では、安心して家族をあずけることができません。個室、または静養室を設置した老人ホームであることも条件です。多床室だけの老人ホームでは、本人や家族も落ち着きません。
また看取りに関する指針を定め、入居者やその家族に対して指針の内容を事前に十分確認し、同意を得られているかどうかも重要です。老人ホームの看取り方針に同意できた場合「看取り看護・介護についての同意書」へ入居者と家族(身元引受人)がサインをします。この同意書を受領してから4~30日以内は144単位の看取り介護加算となり、死亡日の前日及び前々日は680単位、さらに死亡日は1日につき1,280単位を加算すると介護保険で定められています。つまり介護・看護スタッフの教育や配置が十分であっても「同意書」がなければ看取り介護加算をとることができないのです。
このときの看取り介護加算額に対し、一部が入居者の自費費用となります。自費費用分に対しては事前に老人ホーム側から説明があります。あとで揉めないためにも話の内容をきちんとメモし、わからない部分は遠慮なく質問して頭にいれておきましょう。
脳卒中・脳梗塞・クモ膜下出血でも対応が可能な施設特集
重度の後遺症があっても、有料老人ホームなど介護施設なら安心

脳梗塞やクモ膜下出血、脳出血を合わせて脳卒中と称します。それぞれ高齢者に多い脳の疾患。軽症であれば後遺症も軽く済みますが、重症になると半身マヒが残ったり、はたまた失語症にかかったり…。要介護認定も高くなるケースが多く、そうなると自宅での介護も大変です。そんな方のために、有料老人ホームなどの介護施設は手厚い介護サービスが用意されていますので、入居を検討してみてはいかがでしょうか。
脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血の方の老人ホーム選びについて
脳梗塞や脳出血、クモ膜下出血などにより後遺症が残ってしまった場合には、介護施設を探す際に発症からの時期を基準に老人ホームの種類を考えてみるといいでしょう。
発症から半年以内など発症してからの時期が短い場合は、リハビリに取り組むことで後遺症が回復することもありますので、リハビリ病院やリハビリテーションが充実している介護老人保健施設がいいでしょう。脳疾患系の病気による後遺症は、リハビリをはじめるのが早ければ早いほど回復しやすいとも言われています。
急性期病院からリハビリ病院ではなく介護施設に入ることを考えているなら、介護老人保健施設でも介護保険申請をしなくてはいけないので入院中に介護保険申請の手続きをしておきましょう。
急性期後のリハビリテーションにより、ある程度症状が安定し、後遺症が残っている場合には、介護付き有料老人ホームなど安心して長く暮らせる老人ホームへの入居もしくは自宅での生活を考えることとなります。老人ホームなどの施設に入る際には、日常生活においてできることや必要なケア内容を整理し、どのような生活をしたいのかを考えて条件を決めるといいでしょう。
例えば心臓疾患・高血圧など脳卒中にかかった人が持っていることの多い慢性疾患をお持ちなら、医療体制が充実している老人ホームやクリニック併設型などがオススメ。自宅に近い環境でゆっくり過ごしたいのか、レクリエーションやリハビリテーションの充実を望むのかなど希望される生活スタイルは様々でしょうから、ご本人の希望なども聞きながら、安心して過ごせるホームを探しましょう。
また、脳卒中の後遺症として精神症状が出られている場合には、介護施設や老人ホームへの入居は難しい可能性があります。興奮状態にあり、転倒してしまえば怪我の原因にもなりますから、せん妄症状などの精神症状が見られる場合には速やかに医師に相談し、精神科などでの薬物治療を始めることが大切です。
脳梗塞とは? その原因、そして気になる後遺症について
医学用語で脳血管障害と呼ばれる脳卒中には、脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血などがあり、発症した場合には命の危険や後遺症が残る恐れがあることはよく知られていることです。
なかでも脳梗塞は、脳卒中患者の75パーセントを占めています。さらに脳卒中の死亡率と受領率を見てみると、脳梗塞は死亡率でもトップを占めており、とても危険な病気です。
脳梗塞とは脳の血管が詰まってしまう病気で、詰まった血管の先端にある脳が酸素不足により損傷を受けてしまい、損傷を受けた場所によって言語障害、運動麻痺、意識障害と言った局所的な症状がみられます。万が一、脳の広い範囲で損傷を受けてしまった場合や速やかに治療を受けなかったときにはさらに命を落としてしまう危険性まであるからこそ、早い段階での治療が何よりも大切です。
脳梗塞は3つのタイプに分類され「アテローム性脳梗塞」「ラクナ梗塞」「心原性脳梗塞」があります。ひとつめのアテローム性脳梗塞とは血管の壁に脂肪、脂質といった不要なものが付着し徐々に血管の内部を狭め、最終的に血管が詰まってしまう脳梗塞です。また、ラクナ梗塞は高血圧により引き起こされることが多く、日本人の脳梗塞発症患者の中で最も多いタイプです。
初期症状としては片側の手足のしびれやめまい、ろれつが回らなくなる、歩けない、片側の目が見えにくくなる、言葉が出てこない・理解できない、頭痛、吐き気や嘔吐、激しい眠気などが挙げられ、異変を感じたらすぐに医師にかかることがその後の回復においてとても大切です。
気になる脳梗塞の後遺症は、脳が血管の詰まりにより壊死してしまうことが原因で、神経障害や高次脳機能障害、感情障害といったタイプがあります。
なかでも神経障害は、体の左右どちらかが全くもしくは少ししか動かなくなる片麻痺・半身麻痺と呼ばれるものが有名です。このほかにも「手で字を書く」などの細かい作業ができなくなったり、喋ろうと思ってもうまくしゃべれないなどの運動障害が見られることもあります。その他にも神経障害として「感覚障害」「視覚障害」「嚥下障害」「排尿障害」など日常生活に大きく支障をきたすのが神経障害です。
もう一つ、後遺症のタイプとして挙げられる高次脳機能障害は、記憶障害や注意障害、認知障害などが挙げられ、認知症とは異なるものの、非常に認知症と似た症状がみられることがあります。
最後の感情障害は、性格の変化やうつ・不眠、無気力などが挙げられ、身体的に後遺症が残ってしまったことからくるショックなども合わさり、精神的に不安定になってしまうことがあります。
後遺症は人によって異なりますから、家族や介護者は十分に後遺症を理解し、ケアにつなげていくことが大切となってきます。
脳梗塞の方を介護する時に注意したいポイントは?
脳梗塞は、症状の度合いなど様々な要因で患者さんごとにあらわれる後遺症が少しずつ違います。比較的軽症で、すぐに治療を開始したことなどが要因となり、後遺症がない方もいらっしゃいますし、半身不随など日常生活に大きな影響を与えてしまう後遺症が残ってしまう方も多くいます。
回復期におけるリハビリテーションによって、ある程度後遺症が改善することが期待できますが、それでも脳梗塞によって損傷を受けてしまった脳の機能は再生されませんので、家族や介護者はどのような後遺症が出ているのかをしっかりと理解・把握した上で介護を行うことが必要となります。
患者さんの視点に立ち、できていたことが突然できなくなることからくる精神的なダメージに対しても十分な配慮をすることは何よりも大切です。
また、すべて身の回りのことを介助者がやってしまうのではなく、残された残存機能を生かしながら本人が少しでも自立ある暮らしを送れるような環境づくりをしてあげることが、本人の前向きな気持ちを後押しすることにもなります。また、できることを自分ですることで、体の動く部分の機能維持にもつながります。
近年インターネット技術の発展・普及によってパソコンを使う高齢者の方も増えていますが、パソコンの利用は脳梗塞により後遺症が残ってしまった方にとっても生活を大きく変える可能性を秘めています。
例えばソーシャルネットワークなどに参加することで、新しい人間関係や交流が生まれたり、情報発信する機会が創造され、患者さん本人の居場所作りにもつながります。また、インターネットを使える、パソコンを使える、ということは本人の自信にもつながり、新たな趣味へと気持ちを一歩踏み出すきっかけにもなりえます。さらに、パソコンは脳を活性化させる効果があることも注目されており、脳血管障害により半身麻痺が残ってしまった方が、ブログを始めたことがきっかけでリハビリテーション効果があったことなども報告されています。
いずれにせよ、脳梗塞の方の介護においては、本人が明るい気持ちで過ごせるような環境やきっかけ作りもとても重要となってきます。家族が介護をする場合には、一人に負担がかからないよう家族間で協力し合うなど負担が大きくなりすぎないようにしましょう。老人ホームでは同じ境遇の方に会える可能性もあり、本人にとってもいい影響を及ぼす可能性がありますから、在宅にこだわりすぎないことも大切かもしれません。
脳梗塞の方の老人ホームの受入れについて
突然の発症により要介護状態になってしまうケースも多い脳梗塞。病院でのリハビリなどを経た後に自宅ではなく老人ホームでの暮らしを選ぶ方も少なくありません。
脳梗塞による後遺症で要介護になった方が老人ホームへの入居を考えるにあたって、候補として上がってくるのが「特別養護老人ホーム」や「介護付き有料老人ホーム」です。また、最近では訪問介護事業所を併設した「サービス付き高齢者向け住宅」や「住宅型有料老人ホーム」も増え、受け入れをしている施設もあります。
特別養護老人ホームに入居する場合、介護度や家族の状況などが加味され、必要性の高い方から入居が決定していきます。そのため、費用面から特別養護老人ホームを希望しても、入居待ちにより待機期間がある場合もありますから、老人ホーム探しは早い方がベターです。
こうした場合の待機期間中の住まいとして有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を活用している方も多数いらっしゃいます。また、長期間入居することを前提に有料老人ホームを探している方もいらっしゃるかもしれません。
有料老人ホームの入居の受け入れの可否については、脳梗塞による後遺症の程度や、全身状態、病歴などが総合的に判断されて入居を受け入れるかどうかが最終決定されますので、気になる施設は実際に相談してみましょう。
また、入居先を選ぶ際には、健康管理面で安心な看護師常駐の施設や、リハビリの受けられる施設などがオススメです。それぞれの老人ホームで特色も大きく違いますから、環境・サービス・医療サポートなどの提供サービスをしっかりと確認してみましょう。