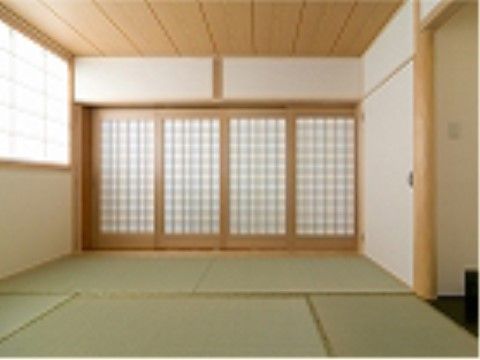終身利用可の施設特集
終身利用可の有料老人ホームなら入居後追加の一時金の支払いは不要

有料老人ホームには、「終身利用可」とされている施設があります。これは、入居時に支払う初期費用の中に「終身にわたって居室や共用スペース、各種サービスを利用する権利」、つまり終身利用権を購入する費用が含まれているということになります。最近では、終身利用権が付与された高額な入居一時金をなくし、高齢者が気軽に入居できるように入居一時金を安く設定したり、そもそも入居一時金をなくしたりする有料老人ホームも増えてきました。所有権ではないため譲渡や転売、相続などはできませんが、長く安心して住み続けることができます。
入居一時金が安めの老人ホームへの入居検討を
有料老人ホームを探す時、亡くなるその時まで安心して入居できるホームがいいと思う人はたくさんいるでしょう。「終身利用可」の老人ホームを探すと満足いくホーム探しになります。でも、「終身利用可」というのは具体的にはどのようなことなのでしょうか。
「終身利用可」とは、亡くなるまで居室・共有スペース・各種サービスを利用できるという意味です。多くの老人ホームは、入居するときに入居一時金を払う仕組みになっていますが、終身利用可の老人ホームでは入居一時金に終身利用権を購入する費用が含まれています。つまり、入居後追加で一時金を支払う必要はなく、月額の費用を払うことで終身に渡り老人ホームで暮らすことができるのです。
最近では、入居一時金を払わなくてもいい、また入居一時金が安い老人ホームも出てきています。終身利用可でありながら入居一時金の負担が少ない老人ホームを選ぶのもひとつの手だと言えます。また、入居一時金が安くても月額費用が高い場合もありますので、注意が必要です。入居一時金や月額費用は、利用者の経済状況によっても支払える金額が異なりますので、無理のないプランかどうか調べておくのがよいでしょう。
終身利用権は、所有権とは違います。つまり、譲渡・転売・相続などはできないのです。しかし、終身利用可の老人ホームは生涯に渡って安心して住めるということに間違いないでしょう。また、後に述べるように終身利用可でも退去しなくてはならない場合もあるので、しっかり確認しておきましょう。持ち家を売ったお金で入居金を作り、終身利用可の施設を終の棲家として契約する人もいます。その意味でも有料老人ホームに対する期待というのは高いと言えます。後で後悔しないように、契約内容はしっかりと把握しておきたいものです。
終身契約でも終身入居を確約するものじゃない!?
老人ホームの契約には、終身契約と一定期間の契約があります。終身契約は、亡くなるまで退去しなくてもよい契約で、一定期間の契約は一年や二年ごとに契約をし直す契約です。そうすると、終身契約はどんな場合でも看取りまで行ってくれるかのようですが、違う場合があります。終身利用可の老人ホームに終身契約をして入居しても、退去しなくてはならないケースがあるのです。退去の条件は老人ホームによって違いますので、よく確認することが必要です。退去の理由で多いのが病気になった時と迷惑行為がある場合でしょう。具体的に説明します。
まず、医療面で昼夜を問わないサポートが必要になった時があげられます。例えば、点滴や痰吸引などを夜間も行う必要がある場合です。老人ホームには看護師が常駐しているところもありますが、その多くは24時間常駐ではなく日中常駐です。したがって看護師がいない夜間にも医療行為が必要な場合、退去せざるを得ないという場合があるのです。
次に、認知症や精神疾患によって他の入居者に迷惑行為を行ってしまう場合です。暴言や暴力、そして夜間に大声を出すなど、共同生活ができないと判断されると退去しなくてはならない施設が多いです。これらのことがあれば終身契約をしていても退去理由になる場合があるでしょう。
また、入院が長引く場合、特別養護老人ホームなどは退去しなくてはならなくなる可能性が高いですが、民間の有料老人ホームの場合は月額費用を払えば退去はしなくてもよい場合が多いです。
また、入居時に嘘の申告をしていた場合も退去理由になります。例えば、認知症で徘徊が多いのにその旨申告をしていなかったとすると、発覚した場合退去を迫られます。終身契約で一生涯安心して老後を暮らしたい場合は、その施設の退去条件をよく調べておくのが得策だと言えるでしょう。
利用権方式と賃貸借方式。契約方式の違いは?
老人ホームの契約にはいくつか種類があります。利用権方式と賃貸借方式、そして終身建物賃貸借方式です。ひとつずつ説明していきましょう。
利用権方式とは、多くの有料老人ホームが採用している方式です。この方式がとられている場合、入居時にまとまったお金を払うことで、多くは終身に渡って居室や共有スペースを利用できます。また、介護費用や生活支援等のサービス料も一緒になっているという点が特徴です。終身利用可の老人ホームがこの方式をとっている場合、一生涯その老人ホームで暮らせますが、購入しているのはあくまで利用権なので、相続・譲渡・転売などはできません。
賃貸借方式は、一般的な賃貸マンションや賃貸アパートのように、月々家賃や管理費を支払う方式です。こちらは介護や生活支援等のサービス利用料は居住費用とは別になっている場合が多いです。借地借家法によって守られており、入院が長期に渡ったり介護度が高くなったりしても退去を迫られることはありません。
終身建物賃貸借方式は、賃貸借方式のうち特約で死亡により契約終了となるものです。「高齢者の住居の安定確保に関する法律」と借地借家法によって守られています。「高齢者の住居の安定確保に関する法律」に基づき「終身建物賃貸借業」との認可が下りたら名乗ることができます。こちらも相続・譲渡・転売などはできませんが、夫婦のどちらかが死亡した場合には生きている方が住み続けられるという特色があります。自治体の厳しい検査に合格しなくてはこの方式では運用できないので、とても少ないのが実情です。
どの方式でも、終身に渡って利用したい場合は必ず退去条件などを確認しておくことが必要です。前に述べたように、終身利用権を購入しても退去しなくてはならない場合が多々あります。資料請求・施設訪問などを通して調べておくのがよいでしょう。
| 利用権方式 | 賃貸借方式 | 終身建物賃貸借方式 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 入居時に入居一時金を支払い、終身利用権を得る契約方式。 所有権ではないため相続にはならない |
一般の賃貸住宅同様に月々の家賃・管理費を支払う契約方式 | 賃貸借契約の内容であることに加え、契約終了が契約者の死亡によるもの |
| 契約でカバーされるもの | 居住部分、介護・生活支援等のサービス | 居住部分と介護等のサービスは別契約 | 居住部分と介護等のサービスは別契約 |
| 特徴 | 入居時にまとまったお金が必要な場合が多い。 終身利用が可能。 月々の利用料が抑えられる |
入居時に必要なのは敷金・保証金等のみなので初期費用が抑えられる | 終身住み続けることができる 夫婦の場合は契約者が死亡しても配偶者が引き続き住む権利がある |
| 根拠法 | なし | 借地借家法 | 借地借家法 高齢者の住居の安定確保に関する法律 |
もしも「退居」となっても、クーリングオフ制度が強い味方に!
老人ホームの費用は様々ですが、高額な入居金を支払う場合が多いです。私たち消費者にとって大きな買い物になる場合もあるので、有料老人ホームにもクーリングオフ制度が適用されています。
もしも有料老人ホームに入ってから「退居」となった場合でも、90日以内であればクーリングオフ制度が味方になってくれるのです。クーリングオフ制度とは、契約解除や申し込み撤回を無条件で行える制度です。ただし、支払った高額な入居一時金が全て戻ってくるかどうかは都道府県によっても違います。入居時にしっかりと確認しておくのがよいでしょう。
また、クーリングオフ制度が適用になるかどうか、それ自体も下調べしておく必要があります。老人ホームの入居金は高額な場合が多いので、契約してしまってから「しまった」とならないようにしたいものです。
そのほか、有料老人ホームの契約に関して注意したいのが、保全措置があるかどうかです。有料老人ホームは民間の会社が運営しているので、倒産しないとも限りません。その場合に、500万円を上限に前払い金を保全しているホームもあるのです。これがあるのとないのでは安心感が大分違いますので、しっかり確認しておくことが必要です。保全措置がとられる老人ホームは平成18年4月以降に設置届けを出したホームです。それ以前のホームでは保全措置をとることは努力目標であり必須ではないので、注意が必要です。
「終の棲家」を期待し、持ち家を売却してから老人ホームに入る場合もあります。そういう場合も含め、老人ホームの倒産により新たな施設を探さなくてはならなくなる場合は困難を極めることでしょう。そのための保全措置なので、まずは保全措置があるかどうか、金額はどのくらいかなどを確認することが必要です。また、倒産によるリスクを避けるために、経営状態が悪い老人ホームへの入居は避けるなどの対策が必要です。
身元保証人なしでも入れる施設特集

核家族化が進む現代では、「一人暮らしで身寄りがいない」「家族はいるが頼むことができない」といった問題を抱えている高齢者の方も多数。一方で老人ホームでは、ほとんどの施設で身元保証人や身元引受人を必要とする場合が多く「身元保証人がいないと老人ホームへの入居はできない」と考えている方も少なくないのではないでしょうか?
確かに、基本的に老人ホームへの入居には身元保証人が必要ですが、ここでご紹介するのは、それが必要ない施設ばかり。入居後のサポートや身柄の引き受けなどさまざまなサービスがあるのでご安心くださいね。
身元保証に関してのサービスも充実!

「介護施設に入りたいけれど、身元保証人がいないから…」と悩んでいる人もいるでしょう。しかし、今は身元保証人の代わりとなるシステムが確立されていますので、地域包括支援センターや社会福祉協議会で相談してみると良いでしょう。
老人ホームによっては成年後見制度などに基づき、法定代理人を定めることを入居条件にしています。法定代理人とは、認知症などで判断能力が低下した人の代わりに、代理人が月額利用料の支払いや、通帳などの財産管理を行うシステムです。
判断能力がある人も「月額利用料の支払いなどが理解しづらくて辛い」といった場合、任意後見人を定められます。このような後見人は、身上監護(依頼人が幸せに暮らせているかどうか状況を把握する業務)や、福祉サービスの手続きサポートなども行うため、入居後も依頼人は安心して暮らせます。
依頼人の連絡窓口にもなるので、施設で何かあったときも後見人に連絡が行くシステムです。老人ホームが、「身元保証人がいない場合は後見人を付けること」を条件としているのはこのようなサポートがあるからです。
後見人に必要な報酬はどのくらい?
成年後見制度を利用する方法
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申し立てることになります。地域包括支援センターや社会福祉協議会などが相談窓口となっており、申し立てのサポートをしてくれますので、まずはこれらの機関に相談をしてみると良いでしょう。
ちなみに身元保証人は一般市民や一般社団法人、NPO法人などさまざまですが、自分で選ぶのではなく、社会福祉協議会などが選定するので安心です。最近は身元保証会社も出てきており、身元保証人がいない人のために、保証代行を行っています。しかも身元保証にオプションとして、生活支援サービスや死後の事務支援サービスが付けられるので便利です。
後見人に必要な報酬はどのくらい?
後見人を頼む際に老人ホームに入居後のことや、亡くなった後のことなども取り決めますので、危篤状態などの緊急時にも本人の意向が尊重されます。認知症などで判断能力が低下した際も安心です。
しかし、「後見人って高いんじゃないの?」と心配する人もいるでしょう。確かに、後見人に金銭管理などの代行サービスを頼むと料金が発生します。サービスにもよりますが毎月数千円といった程度で、そこまで高額ではありません。
後見人は身元の保証はできませんが、老人ホームの月額利用料の支払い代行などをしてもらえるので、老人ホーム側としても安心。金銭のことでトラブルを起こさずにすむため、老人ホームと信頼関係もしっかりと築けるでしょう。
後見人に必要な報酬はどのくらい?
身元保証会社にかかる費用
身元保証会社を利用する場合は、申し込むサービスの量によって金額が違います。生活支援や死後の手続きなど、代行サービスを沢山申し込んだ場合、生涯で支払う金額が数百万円になる場合も。
しかし、身元保証会社は少々費用がかかる場合もありますが、身元保証をしてもらえるので頼もしい存在です。「30年間生きた場合で、どれくらい支払うのか?」といった長期利用の計算をしておきましょう。
身元保証会社の選び方
身元保証会社に身元保証を頼んでおけば安心ですが、「どの会社が良いのかわからない」という人も多いと思います。こういった契約は内容が難しく、支払う料金も預託金や月額利用料などさまざまです。
一人での契約は少々厳しいかもしれませんので、家族などに同行を頼み、一緒に契約内容を理解してもらいましょう。こういったサービスの申し込みに関しても、地域包括支援センターや社会福祉協議会に相談可能です。
ちなみに預託金は一般的に依頼した本人の葬儀代などに使いますが、予め「預託金などは何に使うのか?」といった詳細をしっかりと聞いておくと良いでしょう。
後見人と身元保証会社の違いは?
成年後見人と身元保証会社の違いは、成年後見人は依頼主の身元保証人にはなれませんが、身元保証会社は身元保証が行えることです。成年後見人は公的な立場なので、料金も法外になることはありません。一方、身元保証会社は一般会社なので、料金は会社によって違いますし、サービスによっては少々料金が高くなるでしょう。
しかし、こういった制度を利用すれば、身元保証人がいなくても老人ホームに入居できます。ちなみに老人ホームによって身元保証に関するルールが違います。見学時などに確認しておくと安心です。