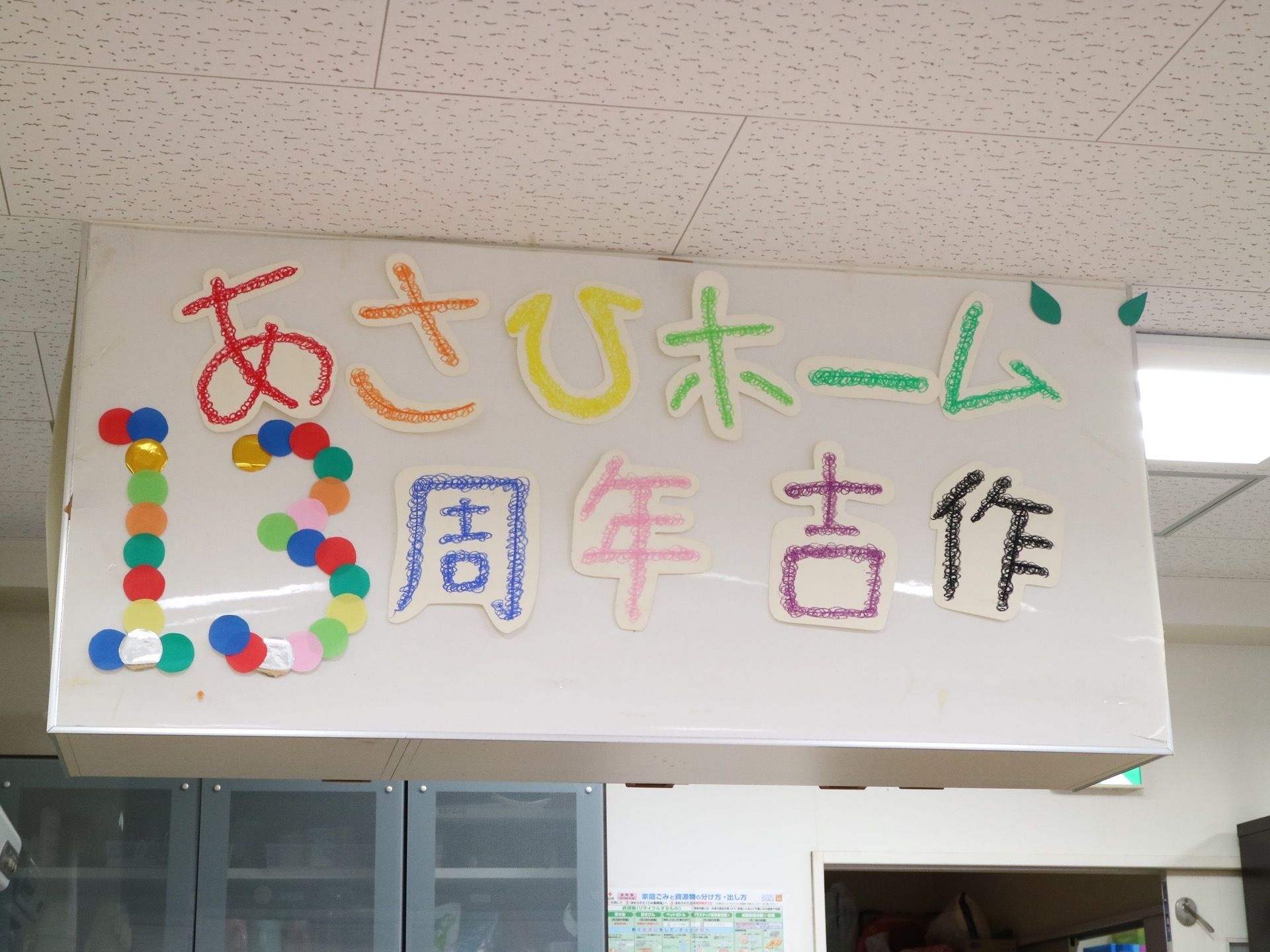入居一時金0円でも入れる施設特集

「退院後すぐに入居できる施設を探している」「特別養護老人ホームに入居できるようになるまでのつなぎに」etc…。お急ぎの方や、一時的な入居を検討している方にピッタリなのが、入居一時金0円プランです。考え方によっては、特別養護老人ホーム(特養)への入居待ちをしている間の生活の場として、入居一時金0円の施設であれば、少ない負担で済むとも考えられます。入居時の費用面の負担が軽く、その安心感は絶大。設備やサービスも多種多様なので、多くの選択肢から理想の施設をお選びください。
“入居一時金0円”はどう活用する?
老人ホームの入居時はなにかと物入り。入居一時金のほかにも引っ越し費用や、家具やベッドの買い替えなどをするとさらに出費がかさみます。細かい日用品を購入しているとあっという間に費用が膨らむことも。住居が変わるときには、意外とお金が飛んでいくものです。そのため「できるだけ初期費用をおさえて老人ホームに入居したい」とお考えの方も多いと思います。
では一体どうすればいいのでしょか。その方法のひとつが「入居一時金0円」の老人ホームを選択することです。
老人ホームへの入居時には、数十万円~数百万円の入居一時金を支払う必要があり、これが利用者の負担になっています。ところが入居一時金0円の老人ホームなら、入居時の出費をかなりおさえることができます。それまで高い費用がネックとなり老人ホームへの入所をためらっていた高齢者にとって、入居一時金0円の老人ホームは入居のハードルが低くなるのでとても魅力的です。
特養に入居するまでのつなぎとして老人ホームへの入居を検討している高齢者にとって、初期費用をおさえて生活できるのは将来的な安心につながります。「退院後、すぐに入居できる老人ホームを探している」「できるだけ早く入居したい」など、すぐに入居先を決めたいと思っている方にも、入居一時金0円の老人ホームはおすすめです。
「自宅を改修し終わるまで、一時的にお世話になりたい」といった短期間の入居であれば、さらに入居一時金0円のメリットが生きてきます。短期間の入所に数百万円もの入居一時金を支払うのは、金銭的にかなり高いハードル。また、一度支払った入居一時金は初期償却などですぐに目減りしていきます。短期入所を希望するなら、迷わず入居一時金0円の老人ホームを選択しましょう。「無駄に償却される入居一時金」をカットできます。
入居一時金0円の老人ホーム、そのメリットとデメリットとは?
入居一時金0円の老人ホームですが、そのメリットとデメリットをご説明しましょう。まず注意していただきたいことは「入居一時金0円」を謳う老人ホームだからと言って、本当に入居一時金が無料ではないということです。
「利用権方式」で契約する場合は、施設の利用権を取得するために入居一時金が必要となります。この一時金を入居時にまとめて全額支払うのか、それとも毎月の家賃や管理費に上乗せして分割して支払うのかを選べるようになっており、後者を選ぶことで「入居時の経済的な負担が軽くなるメリット」を享受できるのです。
ただし同じ老人ホームに長期間入所する場合は、入居一時金を一括して支払う方が有利です。入居一時金0円で月額利用料が25万円、毎月受給できる年金が15万円であったと仮定します。このケースでは毎月10万円の赤字となり、5年間この生活を続けると600万円の貯金を使い果たすことになります。20年間入居期間が続くと2400万円もの赤字となり相当な貯蓄が必要となります。
ところが入居一時金を600万円支払い、月額利用料が15万円となった場合は事情が変わってきます。入居一時金を支払うため最初は大きな金額がかかりますが、月額利用料が年金でまかなえることになりますので5年後に必要な費用は600万円。20年経ってもそれ以上費用がかさむことはありません。入居一時金0円で得をするかどうかは「入居期間」次第です。
| プラン | 前払金 | 月額利用料 | 年金額 | 切り崩し額 | 入居年数 | 切り崩し額+前払金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0円 | 25万円 | 15万円 | 10万円 | 5年 | 600万円 |
| 0円 | 25万円 | 15万円 | 10万円 | 20年 | 2400万円 | |
| B | 600万円 | 15万円 | 15万円 | 0円 | 5年 | 0円 |
| 600万円 | 15万円 | 15万円 | 0円 | 20年 | 0円 |
もし同じ条件を設定し1年で退去した場合、120万円の貯蓄切り崩しが必要になります。ところが入居一時金600万円を支払うケースでは、初期償却や減価償却で約260万円の大金が「たった1年」で目減りしてしまいます。返却される入居一時金は340万円となり、利用者としてはとても納得できない気持ちになるでしょう。
「入居一時金0円プラン」や入居一時金全額一括納入」に対しどういう人が向いているのかは、入居期間の長さがその明暗をわけることになります。2~3年程度の短い入居であれば、入居金0円を選択する方がメリットが大きくなります。
老人ホームの契約方式をチェック!利用料の支払い方式にも違いがある
入居一時金を考える際には、老人ホームの契約方式も知っておく必要があります。これには「利用権方式」「建物賃貸借方式」「終身建物賃貸借方式」の3種類があり、この中でもっとも多い契約方法は「利用権方式」。施設にある居室(専用部分)や食堂や機能訓練室、トイレ、浴室(共有部分)などを利用する権利を購入します。
| 契約方式 | 概要 |
|---|---|
| 利用権方式 | 居室(専用部分)や食堂や機能訓練室、トイレ、浴室(共有部分)などを利用する権利を購入します。利用権購入のために「入居一時金」というまとまった費用を支払う必要があります。支払った入居一時金は、各老人ホームが決めた償却期間・償却率によりどんどん目減りしていき、最終的にはゼロになります。 ここで注意したいのは、取得できるのはあくまでも「利用権」であり「所有権」ではないということです。契約者本人が何らかの理由で退去した場合、利用権は消滅します。親族に遺産として相続させることはできません。また運営者が変わったときは施設を退去しなければならないこともあります。入居時に契約をしっかり確認しましょう。 |
| 建物賃貸借方式 | 一般的な賃貸住宅と同じ契約で、毎月家賃や管理費を支払う方法です。つまり、利用料を毎月支払います。利用権を購入する必要がないため入居一時金は必要ありません。賃貸住宅と同じ扱いなので、老人ホームによっては敷金を請求されることもあります。この敷金ですが老人ホームによって0円から数百万円までかなりの差が。後々のトラブルを防止する意味でも、事前に敷金の金額をハッキリ確認しておきましょう。借地借家法により借家権が設定されているため、事業者が変わったからと言って強制的に退去させられることはありません。 |
| 終身建物賃貸借方式 | 先ほどの建物賃貸借方式と基本的には同じです。ただ契約者が死亡することで契約が終了する点に差異があります。夫婦入居の場合、契約者が先に死亡しても配偶者が生きていれば住み続けることができます。 |
老人福祉法の改定で「入居一時金」の今後はどうなる?

老人ホームの入居時に支払った「入居一時金」はその後、一体どうなってしまうのでしょうか。多くの老人ホームでは入居時に初期償却として20~30%が償却され、その後、5~10年をかけて均等に償却される方式が採用されています。
償却完了後に入居者が退去すれば入居一時金は返還されませんし、償却期間内に退去すれば未償却部分が返却されます。分かりやすく具体的な金額をしめして説明しましょう。
もし入居一時金を100万円支払った場合、まず初期償却で20万円が償却され残りは80万円となります。その後10年かけて償却すると仮定すれば1年間に8万円の目減り。入居者が5年で退去すると約40万円の入居一時金が返還されます。償却期間や初期償却の割合は各老人ホームによって違いますので、事前によく確認しておきましょう。
短期間で老人ホームを退去しても、思ったほど一時金が戻ってこないことも多々あります。事業者と利用者との間でトラブルになることも。この入居一時金については国民生活センターなどに苦情や相談が多く寄せられたため、2011年6月に老人福祉法が改正されています。
老人ホームの事業者が受けとる前払金は「家賃や敷金、介護のために必要な費用」のみに限られ「権利金」名目での受領が禁止されました。以前は、老人ホームの入居一時金に「権利金」が設定されており、この費用がかなり高額だったのです。権利金がカットされることで、現在は入居一時金が安くなっています。利用者にとってはメリットのある法改正だったのです。
入居者の金銭的な負担が軽くなることは非常に喜ばしいことです。また法改正により、入居一時金の算出根拠を明示することも義務付けられています。「入居一時金が高い」と感じられるときは、その根拠を開示してもらい納得したうえで契約を結びましょう。
入居年齢相談可の施設特集

多くの介護施設において、入居に関しては65歳以上という年齢制限が一般的。介護保険の適用が65歳以上ということで(第1号被保険者)、当然と言えば当然かもしれません。
しかし、中にはそれよりも低い年齢から入居できる施設も。40歳以上65歳未満の人が対象となる第2号被保険者は、施設によって受け入れを行なっているところもあるので、気になる方はぜひお問い合わせください。
入居後、他のご入居者様との触れ合いなどを考えると、年齢が近い方が良いという方も多いでしょう。そんな方のためにご用意した、入居年齢相談可の施設特集です。
老人ホーム探しを始める年齢

老人ホームは体力や判断力があるうちに探しておくと安心です。実際に老人ホームへ見学に行くのが一番ですが、見学には時間も体力も必要。契約に関する説明なども、理解力や判断力がないとうまく理解できないことがあります。
要支援・要介護状態になりやすいのは、一般的には75歳以上とされているため、その前に探しておけるとベスト。60~65歳以上から受け入れる老人ホームも多いので、できるだけ早いタイミングで老人ホームを探しておくと、希望通りの施設に入居できる可能性が高まるでしょう。
若年齢者向け老人ホームは多くない
基本的には入居条件を「65歳以上の人」としている老人ホームが多く、64歳以下の人が入居できる老人ホームは全国的にも多くはないのが現状。老人ホームに入居する64歳以下の人は多数派ではないことがその大きな理由となっています。
また、老人ホームに入居する人の平均年齢は85歳前後と言われており、64歳以下の人が入居すると、「周りの人との年齢差が大きいため、コミュニケーションが取りにくい」といった問題もあるようです。
若年齢者の料金は比較的高い
現在のところ、64歳以下の人(第2号被保険者)が老人ホームに入居する場合、長期入居が想定されることもあり、入居金が高めになる場合が少なくありません。老人ホームの入居金は基本的に「前払い家賃」であり、想定入居期間に合わせて入居金を設定することが高い入居金の理由です。
例えば、入居時の年齢が65歳の場合は、5年分の前払い家賃相当である入居金800万円を支払います。償却期間は5年です。一方、入居時の年齢が55歳の場合は、10年分の前払い家賃相当である入居金1,600万円を支払います。償却期間は10年となります。老人ホームによって想定入居期間は違いますが、入居時の年齢が若いほど高くなるシステムです。
第2号被保険者の施設探しで気をつけるべき点

64歳以下の第2号被保険者が老人ホームを探す場合、64歳以下の人を受け入れている老人ホームが少なく、ご自身で見つけるのは難しいかも知れません。みんなの介護では、年齢だけでなく、それ以外のご要望を踏まえて一人ひとりに最適な施設を紹介していますので、お気軽にご相談くださいね。
前もって準備すること
老人ホームの入居にあたっては、予算の計画をしっかり立てておくことが何よりも重要です。64歳以下で入居すると入居期間が長くなる可能性が高く、病状が悪化するなどの状況変化が起きても医療費や月額利用料を支払えるよう、しっかりと計算をしておきましょう。特別養護老人ホームは利用料が比較的安いので、要介護3以上の人はぜひ検討してみてください。
また、特殊な病気の場合、大学病院でなければ治療が難しい場合もあります。「自分が通院している病院との連携があるかどうか?」あるいは「老人ホームと連携している病院に転院できるか?」「送迎などの通院介助サービスはあるか?」などを、入居前に確認しておくと安心です。
施設探しのポイント
老人ホームを探す際にチェックすべきポイントはいくつかありますが、とりわけ重要なのが「自分の病気を受け入れる体制があるかどうか」です。また、医療体制が充実しているかどうかも肝心です。「病状が悪化しても対応してもらえるか?」は事前に必ず確認しましょう。
可能であれば早いうちに一度見学し、施設の環境を確かめておくことは無駄ではなさそうです。