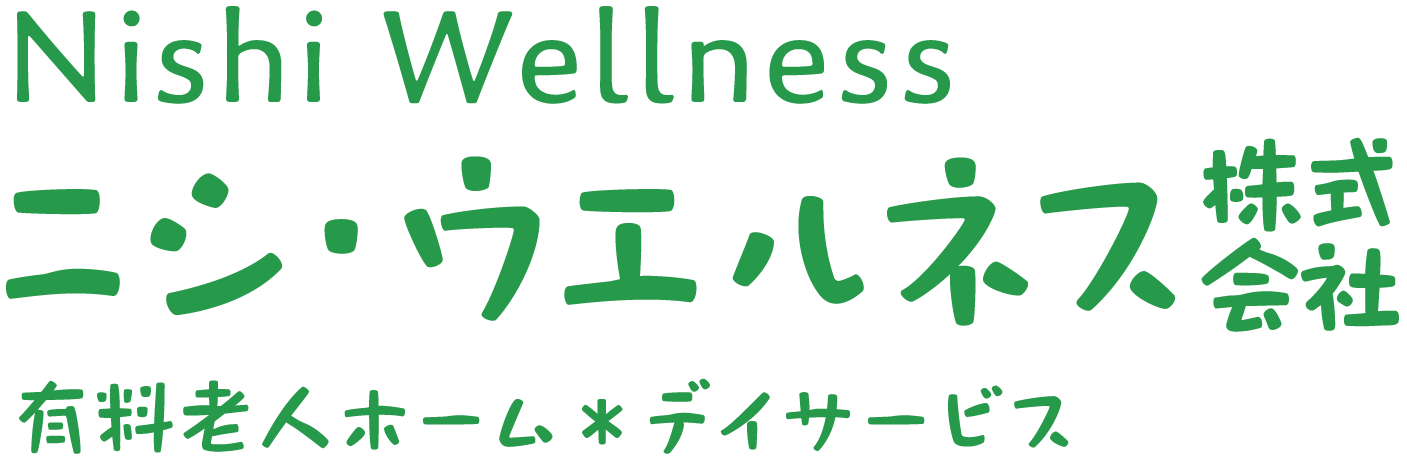喫煙スペースありの施設特集
館内に喫煙スペースを設けて、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境づくりが進行中
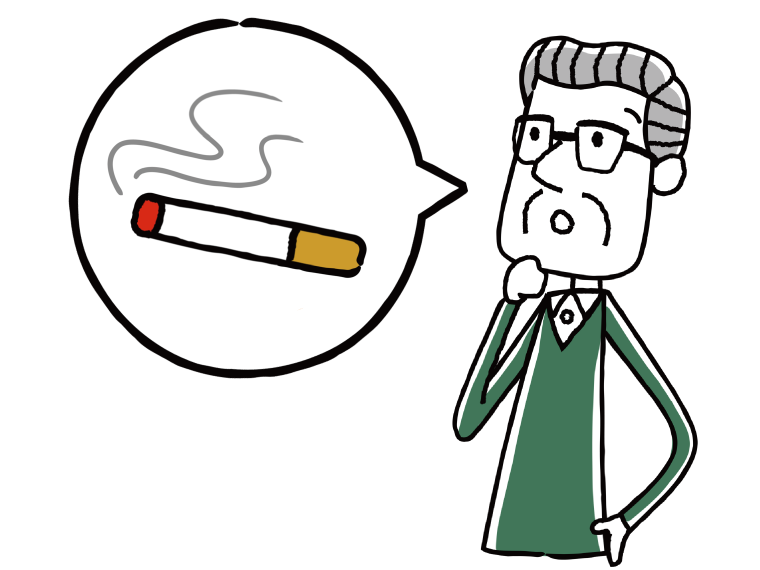
喫煙スペースの有無というのは、実は介護施設を選ぶ際に大きなポイントとなるかもしれません。というのも、激動の高度経済成長期を生き抜いてきた現在の高齢者には喫煙者が多く、一方で、健康のために禁煙した人も多く、その両者が快適に暮らすために必要不可欠なスペースだから。ひと昔前であれば“フリースモーキング”も一般的でしたが、禁煙が声高に叫ばれる昨今では、館内に喫煙スペースを設け、タバコを吸う人と吸わない人とが共存できる環境づくりが進んでいます。そこでここでは、館内での喫煙がOKという介護施設をご紹介していきます。
愛煙家の高齢者のための環境も整っている
喫煙愛好家の方々にとって、最近はとくに肩身のせまい思いをすることが多いのではないでしょうか?
日本ではタバコによる受動喫煙のリスクを避けるために「健康増進法」が成立、以後、公共の場では確実に禁煙が広がり、レストランや喫茶店でも分煙がすすんでいます。公共の場だけではなく、自宅でも家族に気を遣ってベランダや玄関先でひとりタバコを吸う「ホタル族」の姿も多々みられます。このホタル族に対してもマンション住民から「受動喫煙の危険がある」という厳しい意見もあり、気軽にタバコが吸えない状況です。さらに追いうちをかけるようにタバコの価格自体も少しずつ上昇しており、喫煙愛好家にとっては安心してタバコが吸えない状況になっています。
公共の場だけではなく、老人ホームでも禁煙スペースと喫煙スペースを設ける「分煙」がすすんでいます。居室では喫煙可能であっても、共有スペースでは喫煙禁止の老人ホームがある一方、居室も共有スペースも全面禁煙となっており、施設の決まった場所に喫煙スペースを設置していることも。施設内ではなく施設外に排気設備つきのコンテナハウスを設置し、そこを喫煙スペースにしているケースもあります。喫煙愛好家にとってタバコは趣味や楽しみのひとつ。入居を希望する老人ホームでどこまで喫煙できるのかを確認しておきましょう。
認知症を発症している入居者の場合、火の取り扱いにはとくに厳しい管理が必要です。老人ホームによってはライターやタバコを施設職員があずかり、好きなときに喫煙できないようにしていることも。認知症の場合どのような行動をとるのかわからないこともあり、原則として自由に喫煙することはできません。老人ホームへの入所時には喫煙スペースの有無だけではなく、認知症の状況などもきちんと職員に伝える必要がありますね。
非喫煙者の場合、できるだけ禁煙スペースの広い老人ホームを選ぶことが重要です。喫煙者の多い老人ホームでは、居室や共有スペースにタバコの臭いが感じられることも。タバコの臭いは壁紙やカーテン、ソファーの生地などに移りやすく、いつまでも残ります。タバコの臭いが苦手な方は「全館禁煙の老人ホーム」または「きちんと分煙された老人ホーム」を選ぶことで快適な生活をおくることが可能です。
みんなの介護に掲載されている約7,000施設のうち、喫煙スペースありの老人ホームは約2,600施設。全体のうちの約4割の老人ホームに喫煙スペースがあります。喫煙愛好家の方は喫煙スペースが設置された老人ホームを選びましょう。
60歳以上男性の4人に1人は喫煙者!?
日本たばこ産業株式会社(JT)が調査した「2016年全国たばこ喫煙者率調査・年代別喫煙者率」のグラフによると、喫煙者が一番多いのは40代の男性で38.2%とかなり高い数値です。40代男性のじつに3人に1人が喫煙愛好者となっています。
では60代以上の高齢者の場合はどうでしょうか。喫煙者率(男性)は22.0%、女性は5.7%であることが判明しています。この結果から、60歳以上の男性の約4人に1人は喫煙者と考えてもよい状況です。喫煙愛好家の数は予想以上に多いことがわかります。
健康増進法施行により公共施設での禁煙、分煙がかなりすすんでいますが、潜在的な喫煙者数が多いため、都市部の一部公共施設では喫煙化エリア外でタバコを吸う例もあり「禁煙部分にまでタバコの煙が流れてくる」とトラブルになることも。くれぐれもマナーを守って楽しんでもらいたいものです。
また、10年以上の喫煙歴のある60歳以上の高齢者のうち、じつに97%もの方に「「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」の疑いがあるとも言われています。COPDは、タバコなど有害な煙を長期間吸いこむことで発症する、炎症をともなう呼吸器の病気の総称です。気管支炎や肺気腫もCOPDの一種です。この病気の最大の原因は喫煙で、禁煙すれば病気の発症をおさえることができます。
病気の症状としては歩行時や階段の昇り降りで息切れがする労作時呼吸困難や、せき、たん、喘息など。
治療の基本は当然禁煙ですが、禁煙以外にも気管支拡張薬の使用(吸入薬)、肺炎球菌ワクチンやインフルエンザワクチンの接種、呼吸リハビリテーションの実施などで症状をやわらげ、病気の進行をおさえます。もし血中の酸素濃度が低くなってしまった場合は、在宅酸素療法をおこなうことも。症状が改善せず呼吸不全がつづく場合は小型の人工呼吸器やマスクを着用したり、症例によっては肺の切除をおこなうことも。甘くみるとこわいCOPD、禁煙を心がけることで病気の発症や進行をある程度おさえることができます。
ニコチン依存はCOPDだけではなく、うつ病やうつ病様症状をも引きおこすことが指摘されています。「健康のためにも禁煙を」という言葉にはきちんとした裏付けがあるのですね。いつまでも元気に暮らせるよう、できるだけ禁煙を心がけましょう。
喫煙可の老人ホームは少ない!?その理由とは?
健康増進法(受動喫煙防止法)施行後、禁煙や分煙に配慮した老人ホームが増えています。
老人ホームは宿泊のための施設ではなく「生活の場」であるため、個人の嗜好や趣味、楽しみを老人ホーム側が制限することはできません。ところがタバコは受動喫煙によるリスクや害が指摘されており、タバコを吸うことで同じ部屋にいる入所者の健康を害する可能性があります。老人ホームで分煙や禁煙がなされていない場合、非喫煙者であってもタバコの煙を吸いこむ可能性はゼロではありません。受動喫煙により心筋梗塞や狭心症で死亡する可能性が1.3~2.7倍に跳ねあがることが指摘されていますし、心臓の病気だけではなく、気管支炎の悪化、脳卒中、動脈硬化などの原因になるといわれています。
このような背景があり、非喫煙者から老人ホームへ「分煙、喫煙」の要望が寄せられるようになりました。本人の意思とは関係なく受動喫煙のリスクにさらされるのは、やはり迷惑なものですね。老人ホーム側としては非喫煙者の意見や健康増進法施行の影響を考慮して、入居者の喫煙を全部、または一部制限していることが多くなっています。これが喫煙可の老人ホームが少なくなっている理由です。
社会的には「禁煙」への流れが主流となっていますが、そうは言っても長年楽しんできたタバコをある日急にやめるのはむずかしいもの。とある老人ホームでは施設内に喫煙スペースをもうけ、喫煙愛好者にはそのスペース内でタバコを楽しんでもらえるように配慮しています。喫煙スペースは完全に密閉されているうえに分煙装置が設置されており、スペース内の煙が施設内に流出する心配は一切ありません。入所者のなかには「食後の一服がないと、やっていられない」と感じる方もいます。施設職員や面会者のなかにも喫煙愛好者がいるため、喫煙スペースを設置するケースも多いようです。
密閉された喫煙スペースや分煙装置を施設内に設置出来ない場合は、施設外に専用のスペースをつくり、そちらで喫煙してもらうケースもあります。この場合、施設内は完全禁煙となるため、非喫煙者にとってはこちらの方が好ましいでしょう。
老人ホームを選ぶときには、施設内が完全禁煙なのか、施設内に喫煙スペースがあるのかを確認することをおすすめします。喫煙可の老人ホームは少なくなっていますが、現状の喫煙者数を考えれば今すぐに老人ホーム内の完全禁煙は実現しにくいと考えられます。探せば喫煙可の老人ホームは必ずあります。
身元保証人なしでも入れる施設特集

核家族化が進む現代では、「一人暮らしで身寄りがいない」「家族はいるが頼むことができない」といった問題を抱えている高齢者の方も多数。一方で老人ホームでは、ほとんどの施設で身元保証人や身元引受人を必要とする場合が多く「身元保証人がいないと老人ホームへの入居はできない」と考えている方も少なくないのではないでしょうか?
確かに、基本的に老人ホームへの入居には身元保証人が必要ですが、ここでご紹介するのは、それが必要ない施設ばかり。入居後のサポートや身柄の引き受けなどさまざまなサービスがあるのでご安心くださいね。
身元保証に関してのサービスも充実!

「介護施設に入りたいけれど、身元保証人がいないから…」と悩んでいる人もいるでしょう。しかし、今は身元保証人の代わりとなるシステムが確立されていますので、地域包括支援センターや社会福祉協議会で相談してみると良いでしょう。
老人ホームによっては成年後見制度などに基づき、法定代理人を定めることを入居条件にしています。法定代理人とは、認知症などで判断能力が低下した人の代わりに、代理人が月額利用料の支払いや、通帳などの財産管理を行うシステムです。
判断能力がある人も「月額利用料の支払いなどが理解しづらくて辛い」といった場合、任意後見人を定められます。このような後見人は、身上監護(依頼人が幸せに暮らせているかどうか状況を把握する業務)や、福祉サービスの手続きサポートなども行うため、入居後も依頼人は安心して暮らせます。
依頼人の連絡窓口にもなるので、施設で何かあったときも後見人に連絡が行くシステムです。老人ホームが、「身元保証人がいない場合は後見人を付けること」を条件としているのはこのようなサポートがあるからです。
後見人に必要な報酬はどのくらい?
成年後見制度を利用する方法
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申し立てることになります。地域包括支援センターや社会福祉協議会などが相談窓口となっており、申し立てのサポートをしてくれますので、まずはこれらの機関に相談をしてみると良いでしょう。
ちなみに身元保証人は一般市民や一般社団法人、NPO法人などさまざまですが、自分で選ぶのではなく、社会福祉協議会などが選定するので安心です。最近は身元保証会社も出てきており、身元保証人がいない人のために、保証代行を行っています。しかも身元保証にオプションとして、生活支援サービスや死後の事務支援サービスが付けられるので便利です。
後見人に必要な報酬はどのくらい?
後見人を頼む際に老人ホームに入居後のことや、亡くなった後のことなども取り決めますので、危篤状態などの緊急時にも本人の意向が尊重されます。認知症などで判断能力が低下した際も安心です。
しかし、「後見人って高いんじゃないの?」と心配する人もいるでしょう。確かに、後見人に金銭管理などの代行サービスを頼むと料金が発生します。サービスにもよりますが毎月数千円といった程度で、そこまで高額ではありません。
後見人は身元の保証はできませんが、老人ホームの月額利用料の支払い代行などをしてもらえるので、老人ホーム側としても安心。金銭のことでトラブルを起こさずにすむため、老人ホームと信頼関係もしっかりと築けるでしょう。
後見人に必要な報酬はどのくらい?
身元保証会社にかかる費用
身元保証会社を利用する場合は、申し込むサービスの量によって金額が違います。生活支援や死後の手続きなど、代行サービスを沢山申し込んだ場合、生涯で支払う金額が数百万円になる場合も。
しかし、身元保証会社は少々費用がかかる場合もありますが、身元保証をしてもらえるので頼もしい存在です。「30年間生きた場合で、どれくらい支払うのか?」といった長期利用の計算をしておきましょう。
身元保証会社の選び方
身元保証会社に身元保証を頼んでおけば安心ですが、「どの会社が良いのかわからない」という人も多いと思います。こういった契約は内容が難しく、支払う料金も預託金や月額利用料などさまざまです。
一人での契約は少々厳しいかもしれませんので、家族などに同行を頼み、一緒に契約内容を理解してもらいましょう。こういったサービスの申し込みに関しても、地域包括支援センターや社会福祉協議会に相談可能です。
ちなみに預託金は一般的に依頼した本人の葬儀代などに使いますが、予め「預託金などは何に使うのか?」といった詳細をしっかりと聞いておくと良いでしょう。
後見人と身元保証会社の違いは?
成年後見人と身元保証会社の違いは、成年後見人は依頼主の身元保証人にはなれませんが、身元保証会社は身元保証が行えることです。成年後見人は公的な立場なので、料金も法外になることはありません。一方、身元保証会社は一般会社なので、料金は会社によって違いますし、サービスによっては少々料金が高くなるでしょう。
しかし、こういった制度を利用すれば、身元保証人がいなくても老人ホームに入居できます。ちなみに老人ホームによって身元保証に関するルールが違います。見学時などに確認しておくと安心です。