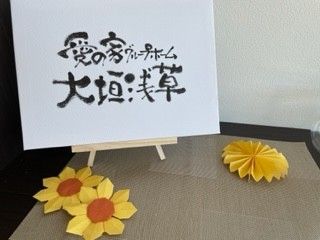寺社仏閣が駅から1キロ圏内に数ヶ所あります
 岐阜県内で第二の人口を抱える大垣市。県内西部の中心的存在であることを自負する動きも顕著です。人口減少が全国的に叫ばれる時代にありながら、近年の人口が横ばいに近く人口流失を本格的に起こしていないことも、評価に値するでしょう。水質のよさや史蹟や寺社仏閣が多く残っているといった点でもよく引き合いに出されます。友江駅の周囲はそのような市の特長を端的に表しているエリアだといえそうです。友江駅の周辺は、駅からす至近距離にあるというわけではないもののさまざまな自社が集まっています。その中でも宝光院は、毎年2月に開催される祭事で有名になりました。友江駅の周りは基本的に静かな土地ばかりで建物や人口の密度はかなり低いですが、美しく澄んだ空気や水、そして日光などを毎日たっぷりと味わいながら暮らしていける土地柄です。友江駅は、名神高速道路に比較的近く、さらにこの道路を介して東海環状自動車道へのアクセスも容易な場所に所在する駅です。タクシーやマイカーを使うときはこれらの幹線道路を使って遠方に出かける住民が少なくないようです。友江駅は、2007年から養老鉄道の養老線の管轄となっています。管内で見ると、最寄りの乗り換え駅は3区間離れた大垣駅です。大垣駅ではJRの東海道本線と樽見鉄道の樽見線に接続しています。なお発着駅である桑名駅までは距離がありますが、この駅まで行くとJRの関西本線や近鉄の名古屋線などに乗り継ぐチャンスが発生します。友江駅は小規模な駅のため、需要は自然と限られたものになっています。しかし通勤ないし通学で常用する旅客が駅の周辺に確実に残っており、安定感は見られます。1日あたりの乗降客数は、30年くらい前からあまり変わっていません。データを参照すると、500~700人の間で推移している様子を確認できます。友江駅の周辺は、ずっと昔から閑散とした土地が広がっています。介護施設などを建てるときに適した土地はかなり残っているようですが、駅のすぐ目の前に位置する施設を見つけることはかなり困難。そこで、2キロくらい離れたあたりをまず探してみることをおすすめします。その次に、4~5キロ離れたあたりをじっくりと探してみましょう。施設の区別については、グループホームがかなり増えていますが、それ以外の施設についてはほぼ均等に建設されてきたようです。費用体系は一部の例外を除外すると、安価なところが大半を占めています。
岐阜県内で第二の人口を抱える大垣市。県内西部の中心的存在であることを自負する動きも顕著です。人口減少が全国的に叫ばれる時代にありながら、近年の人口が横ばいに近く人口流失を本格的に起こしていないことも、評価に値するでしょう。水質のよさや史蹟や寺社仏閣が多く残っているといった点でもよく引き合いに出されます。友江駅の周囲はそのような市の特長を端的に表しているエリアだといえそうです。友江駅の周辺は、駅からす至近距離にあるというわけではないもののさまざまな自社が集まっています。その中でも宝光院は、毎年2月に開催される祭事で有名になりました。友江駅の周りは基本的に静かな土地ばかりで建物や人口の密度はかなり低いですが、美しく澄んだ空気や水、そして日光などを毎日たっぷりと味わいながら暮らしていける土地柄です。友江駅は、名神高速道路に比較的近く、さらにこの道路を介して東海環状自動車道へのアクセスも容易な場所に所在する駅です。タクシーやマイカーを使うときはこれらの幹線道路を使って遠方に出かける住民が少なくないようです。友江駅は、2007年から養老鉄道の養老線の管轄となっています。管内で見ると、最寄りの乗り換え駅は3区間離れた大垣駅です。大垣駅ではJRの東海道本線と樽見鉄道の樽見線に接続しています。なお発着駅である桑名駅までは距離がありますが、この駅まで行くとJRの関西本線や近鉄の名古屋線などに乗り継ぐチャンスが発生します。友江駅は小規模な駅のため、需要は自然と限られたものになっています。しかし通勤ないし通学で常用する旅客が駅の周辺に確実に残っており、安定感は見られます。1日あたりの乗降客数は、30年くらい前からあまり変わっていません。データを参照すると、500~700人の間で推移している様子を確認できます。友江駅の周辺は、ずっと昔から閑散とした土地が広がっています。介護施設などを建てるときに適した土地はかなり残っているようですが、駅のすぐ目の前に位置する施設を見つけることはかなり困難。そこで、2キロくらい離れたあたりをまず探してみることをおすすめします。その次に、4~5キロ離れたあたりをじっくりと探してみましょう。施設の区別については、グループホームがかなり増えていますが、それ以外の施設についてはほぼ均等に建設されてきたようです。費用体系は一部の例外を除外すると、安価なところが大半を占めています。